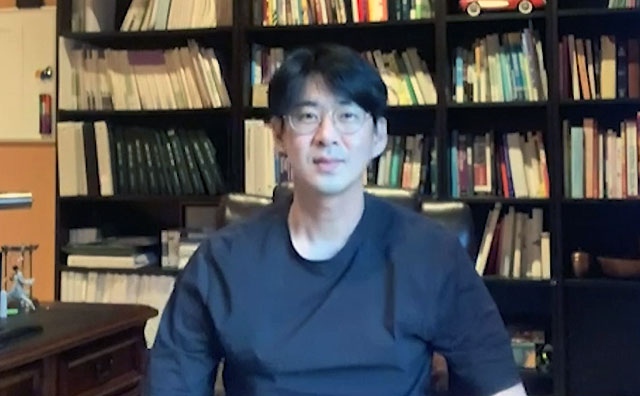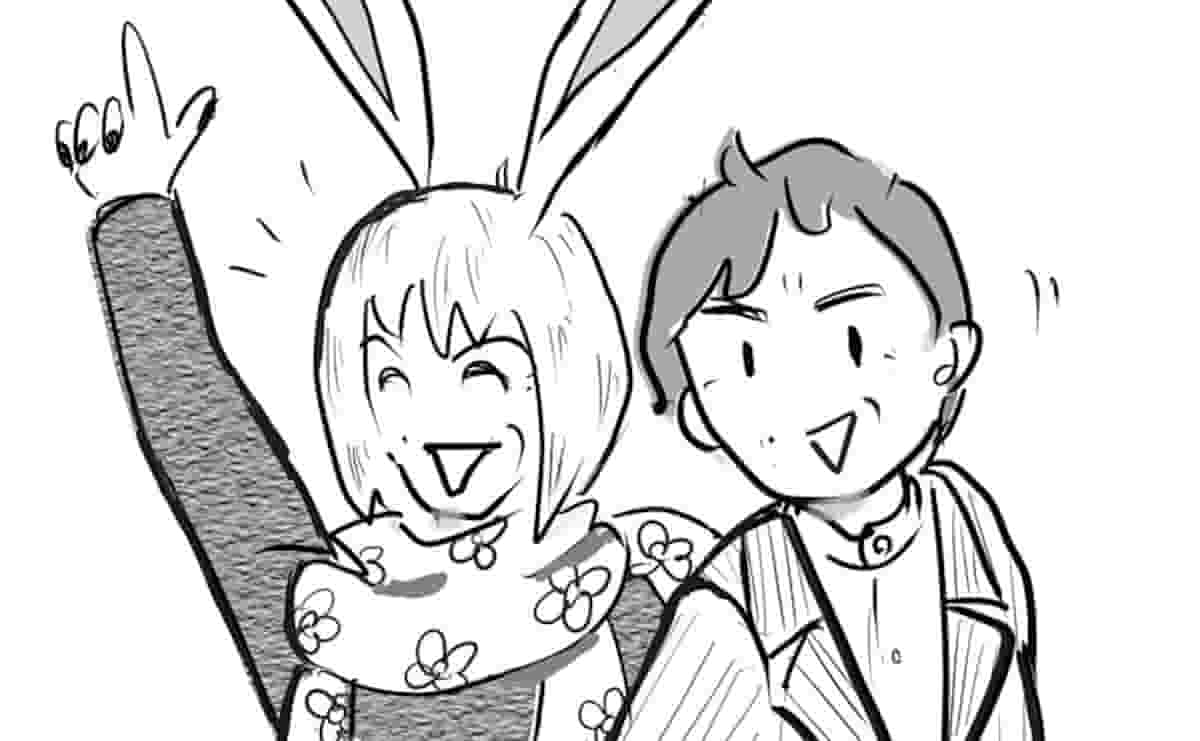あらゆる関係はS-Mである
2008年12月25日 公開 2022年11月07日 更新
野球漫画を変えた「おお振り」
その意味で、本作における、より決定的な先行作品はひぐちアサの『おおきく振りかぶって』(以下『おお振り』、講談社)ではないだろうか。
『おお振り』は野球漫画に革命をもたらしたとされる作品である。
物語の設定は、無名の新設野球部から甲子園優勝をめざす高校球児たちという、いわば野球漫画としては定番中の定番である。しかし本作は、そのあまりにも 斬新な描写で「野球漫画に新風を吹き込んだ」と高く評価された。読みはじめてすぐに驚かされるのは、ヒーローであるはずの投手が弱気で卑屈な性格であると いう、およそ野球漫画の主人公としてはありえないような性格造形である。
もちろん本作は、単純なトラウマとその癒しが描かれるような、悪い意味での心理主義的な作品ではないし、「スポ根」もいっさい登場しない。しかし、従来 のスポーツ漫画では考えられないほどの繊細な心理描写や、選手の日常の細やかな描写ぶりなどが新鮮であると高く評価され、2006年の手塚治虫文化賞「新 生賞」、2007年第31回講談社漫画賞一般部門など、数々の受賞歴がある。
本作の画期性には全面的に賛同しつつも、私が『おお振り』にいまひとつのめり込めなかったのは、一部で指摘されているような「やおい・BL」的なムード ゆえである。そうした要素そのものが受け入れがたいのではなく、この作品をBL野球漫画的な方向で売ろうという意図を最初に感じさせられてしまったことが 大きかった。
実際にそうした意図があったかどうか、いまとなっては定かではない。しかし少なくとも、某有名書店が本作のBL性を強調するような売り方を試みて批判さ れたことは事実としてあった。売る側の意図はともかくとして、本作が「やおい・BL」的文脈でも十分に楽しめる作品であることは間違いない。この事実は示 唆的である。
先にも述べたとおり、「やおい・BLカルチャー」の本質は、関係性の快楽という点に極まる。その意味で『おお振り』の画期性は、心理主義的描写などでは なく、スポーツ漫画にはじめて「関係主義」を全面的に導入したという点に集約されるのではないだろうか。少なくとも私が『おお振り』を『少女ファイト』の 先行作品とみなすのは、この文脈をおいてほかにない。
だとすれば日本橋ヨヲコは、『おお振り』を参照しつつも、かなり慎重に、自作から「やおい・BL」的要素(あるいは「百合」〈=レズビアン〉的要素)を 排除しようとした可能性がある。あるいはここに、描写が「二者関係」に輻輳しやすい「野球」と、同じく「三者関係」以上に展開していかざるをえない「バ レー」との決定的違いが反映されているのかもしれない。
才能=トラウマ
閑話休題。『少女ファイト』に戻ろう。
先述したとおり、主人公の大石練は、姉の死というトラウマを負っている。そのつらさを紛らわすために、バレーの練習に没頭するのだが、その没頭ぶりと才 能があまりにも突出していたために、周囲のメンバーがついていけず、結果的に彼女は孤立してしまう。そう、トラウマは姉の死ばかりではない。日本橋の作品 にあっては、過剰な才能すらも、ある種のトラウマのように扱われることになるのだ。
この姿勢は、漫画そのものをテーマとした日本橋の佳作『G戦場ヘヴンズドア』(小学館)の時点から一貫している。天才的な漫画の才能をもつ主人公・長谷 川鉄男は、その才能ゆえに癒されない苦痛を抱え、ただ漫画のためではなく、手段としての漫画を描きつづける。ここには姉の死を忘れるための手段として、ひ たすらバレーに没頭する大石練の姿が重なるだろう。
『G戦場~』が特異なのは、それがたんなる天才の栄光と挫折という展開には決してならないところだ。鉄男はペンを捨て編集者になるのだが、その姿は挫折 としては描かれない。彼は堺田町蔵や菅原久美子をはじめとする仲間たちとの関係のなかで、おのれの才能と発展的に決別していくのだ。
くりかえそう。日本橋の作品においては、才能はほぼトラウマと同等の位置に置かれることになる。さらに、関係性がそのトラウマを癒していく過程がきわめて説得的に描かれるのだ。
それゆえ『少女ファイト』の最大の魅力は、なんといってもその入り組んだ群像劇にある。一般に女子におけるバレー漫画の人気は、プレーヤーが実際に多い こともさることながら、タカラヅカ的な凛々しい女の園という魅力を抜きにしては語れない。しかし日本橋は、果敢にも大量の男性キャラを物語に投入し、女性 キャラとのカップリングを積極的にはかろうとする。それぞれのキャラが背負っているものがていねいに描かれているので、こうしたキャラクター操作がまった く御都合主義に見えない。
溶け合うキャラたち
キャラクターといえば、『少女ファイト』で特筆すべきは、その絵柄の変化である。本作と過去の日本橋作品とのあいだには、技術的にもスタイルとしても大 きな断絶がある(単行本の表紙を比較してみるだけでそれはわかる)。これはたんなる「進化」ではない。過去作品の描線にかすかにかいま見えた「迷い」のよ うなものがみごとに払拭されている。そう、『少女ファイト』にいたって日本橋ヨヲコは、まったく独自のデフォルメの文法を確立したのである。
それはあまりにも独特なので、彼女1人のオリジナルスタイルに留まるか、大量の模倣者を生み出すのか、現時点ではいずれとも予測がつけにくい。いずれに せよ、漫画を読む愉悦は「輪郭線の快楽」に極まるという個人的見解からすれば、彼女の描線は文句なしにすばらしい。
その大胆にデフォルメされた描線からある程度予測可能なことではあるが、日本橋はキャラの類型性を恐れていない。これほど複雑な群像劇を描きながら、 『少女ファイト』のキャラたちは、性格的にも絵柄的にもきわめて輪郭のはっきりした、よい意味でシンプルなキャラばかりなのだ。たとえば伊丹志乃など、ど こへ出しても恥ずかしくない典型的な「ツンデレ」キャラである。
『G戦場~』などの過去作品とくらべてみても、「キャラの類型化」は、いっそう確信的に練られていることがわかる。この戦略は正解だ。日本橋は漫画が何 よりもまず「感情のメディア」であることを知悉している。だからこそ漫画においては、類型的なキャラこそが最も輝くということも。むしろ漫画においてあえ て類型化を忌避すること(「複雑なキャラクター」だけを描くこと)は、しばしば「文学性」への擦り寄りという危険を冒すことになるだろう。
キャラが類型的なぶんだけ、その関係性のネットワークは、恐ろしく緻密に設定されている。おそらく作者の仕事場には、キャラクターの設定表やキャラ間の 緻密な相関図が壁一面に貼られているのではないだろうか。私はすでに本作を5回以上通読したが、この複雑に張りめぐらされた関係性のネットワークを、いま だ完全に把握するにはいたっていない。
もちろん、まだ描かれていない部分もあるし、一部のキャラは他作品と重なっているため、関係性の外周はどこまでも広がっていく。そこにかいま見えるのは 「自分がつくりだしたキャラクターの生をまっとうしてやりたい」という作家の誠実さであり、キャラクターという存在への愛にほかならない。
ところで、作者が経験者であるという以上に、本作で「バレー」が選択されるほかなかった経緯については、大石練と亡き姉・真理とのやりとりからもうかがえる。
――「姉ちゃんは 何でそんなに バレーが 好きなの?」
「うーん 何だろ 試合中さ 極限まで いくと 人との 境目が なくなるの」(中略)
「人も ネットも コートも ボールも 自分の 一部になった 気がするの」
「こんなに 溶け合えるもの ほかにないわ」(『少女ファイト』1巻)
これがバレーに対する一般的な見解かどうかはわからないが、少なくともこのくだりを読めば、本作が決して「魔球」を描かず、「1人の天才」だけに焦点を あてようともしない理由がはっきりする。この主題は、1巻のクライマックスともいえる決定的シーンで、もう一度反復される。
ふとした誤解から白雲山中学バレー部を退部になった大石練が、姉の墓前で泣き崩れているところへ、黒曜谷高校バレー部の監督・陣内笛子が現れる。彼女は 真理の死に責任を感じており、以来ずっと喪に服したまま毎日の墓参りを欠かさずにいたのだ。笛子は練に「生き方が雑だ」と言い放ち、さらに言葉を続ける。
「生きている意味が 全て噛み合う その瞬間を 味わいたいのなら」
「丁寧に生きろ」
と。
「溶け合う」ことと「噛み合う」こと。その瞬間を描くためには、たしかに「バレー」しかなかったのかもしれない。「天才」でも「根性」でもなく、「関係 性」を描くこと。スポーツ漫画におけるその可能性は、まず、ひぐちアサの『おお振り』によって見出された。しかし日本橋は、それとはまったく異なる関係性 の様相を、『少女ファイト』において描き出そうとしているかのようだ。
「決断主義」から「関係主義」へ
批評家の宇野常寛は、近著『ゼロ年代の想像力』(早川書房)において、「決断主義」を批判している。「決断主義」とは――宇野独特の用法でいえば――小 泉純一郎や漫画『デスノート』(大場つぐみ、小畑健、集英社)の主人公・夜神月のように、「何が正しいかは政治的に勝利した人間が決定する」という世界観 に基づく「動員ゲーム」を指している。それは現実世界と虚構世界のいずれにも見られる傾向だ。彼はこうした決断主義を乗り越えるべく、「コミュニケーショ ン」の重要性を主張する。
「家族(与えられるもの)から疑似家族(自分で選択するもの)へ、ひとつの物語=共同性への依存から、複数の物語に接続可能な開かれたコミュニケーショ ンへ、終わりなき(ゆえに絶望的な)日常から、終わりを見つめた(ゆえに可能性にあふれた)日常へ――現代を生きる私たちにとって超越性とは世界や時代か ら与えられるべきものではない。個人が日常のなかから、自分の力で掴み取るべきものなのだ」(『ゼロ年代の想像力』)
この、宇野本来の挑発性から見れば、意外なほど穏健な主張を支えるのは、神学者ラインホールド・ニーバーによる「静穏の祈り」の文句である。
「変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気をわれらに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さ を与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、識別する知恵を、われらに与えたまえ」
カート・ヴォネガットもみずからの小説中に引用した、この有名な文句には、私もかつて感銘を受けたことを告白しておこう。しかし、いまは必ずしも当時の 私に賛成できない。あえて嫌味な言い方をすれば、私はもう、それほどナイーブな発想が困難になったのだ。
私はこの「祈り」に、努力目標を聞かれた優等生が答えがちな言葉、「短所は改め、長所はより伸ばしていきたいと思います」的な空疎さを感じてしまう。決して間違いではない、しかし……という違和感。それは何に由来するか。
「長所」と「短所」とはしばしば同一物だ。たとえば「社交性」と「没個性」、「自立心」と「頑なさ」が表裏一体であるように。それゆえ「短所は改 め……」式の発想は、つねに本質的な矛盾を抱え込むことになるし、突き詰めれば平均化こそが最善、という抑圧的な発想につながりかねない。
同じことは「変えられるもの」と「変えられないもの」の区別についてもいえる。私は人間性について、「変われば変わるほど変わらない」という基本的な認 識を一貫して堅持している。これは言い換えるなら「変革」こそが「保守」の要件、という意味でもある。
それゆえこの2つの区分は、つねに事後的にしか見出しえない。「変わりたい」意志と「変わりたくない」意志、これに加えて「変われと強く言われれば変わりたくない」意志などのせめぎあいがあり、その結果としてしかこの「区分」は見出しえないのだ。
これは決して、何を意志しようとなるようにしかならない、という意味ではない。むしろその正反対である。「意志を放棄すれば、人は人の形を保てなくな る」という意味だ。それゆえニーバーの祈りに関していえば、「勇気」も「冷静さ」も、同じ1つの意志の事後的な形式を示すだけだし、「知恵」は文字どおり 「後知恵」でしかありえない。もう一度くりかえすが、これはニヒリズムではない。
ニーバーの祈りを支えるものは「コミュニケーション」への信頼である。本来「祈り」は「不可能性」が前提であろう。それが不可能であるときにこそ、なさ れるものが「祈り」なのだ。またそうでなければ、それは「祈り」ではなくたんなる「願望」だ。ニーバーの「祈り」は、「CHANGE!」と叫ぶオバマのよ うに、その可能性へと人をそそのかす。
「話し合えばわかりあえる」と信ずる者にとって、「変わりうるもの」と「変わりえないもの」の区分は単純だ。それは「話が通じる/通じない」という区分 とぴったり重なるだろう。そのような区分は、まさに「自分自身」のなかにもありうるだろう。しかし私は、このような区分に反対する。なぜならそこにあるの は「話は通じない」という、たった1つの真理だけなのだから。
そう、ラカンを持ち出すまでもない。話は通じない、それだけだ。もともと言語という、きわめて文脈依存度が高く不安定なコード・システムを獲得した時点 で、そのことは決定づけられていた。また、だからこそ言葉巧みな人間が未熟さを抱え込んだままだったり、寡黙な人間が驚くべき成長を遂げるといった逆説が 起こりうる。この逆説とコミュニケーションは関係がない。煎じ詰めればあるのは「関係性」ばかりである。
『少女ファイト』の世界もまた、「話の通じない」世界ではある。大石練の躓きの石は、まさにコミュニケーションの齟齬がもたらした、誤解と思い込みである。ときとして「才能」もまた、こうした齟齬をもたらすことを、日本橋は仮借なく描き出す。
コミュニケーションに傷つけられた大石を癒すのは、幼馴染みの式島兄弟であり、バレーの仲間たちとの関係性だ。そう、日本橋は知っている。「コミュニ ケーション」の対義語が「関係性」であることを。人が溶け合い、意味が噛み合う瞬間は、意志と関係性なくしては、決してありえないということを。
すでに社会を覆い尽くしているコミュニケーション至上主義は、明らかに宇野の言う「決断主義」の背景を成している。コミュニケーション主義こそは、それ が変わりうるものであることがこれほど明らかであるにもかかわらず、不動の壁としてわれわれの前に立ちふさがり、変化への意志を果てしなく萎えさせる当の ものだ。
しかし「あきらめる」(大石練と長谷川留弥子が忌み嫌う言葉だ)ことはない。われわれにはまだ「関係主義」が残されている。それがどんなかたちのもの か、まだ想像もつかないが、『少女ファイト』において、その希望の輪郭線がすでに描かれつつあることは間違いない。