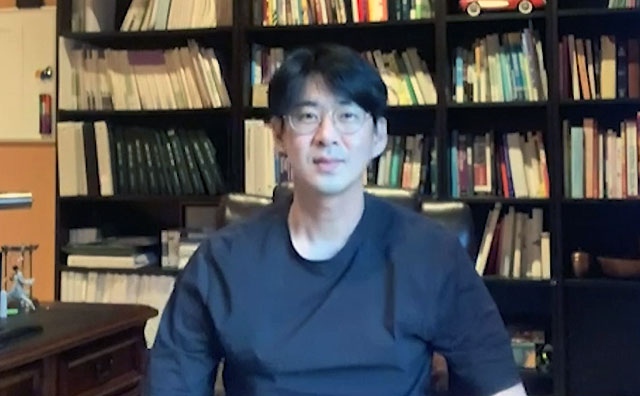ザックJAPAN、ブラジルへの道
2011年03月28日 公開 2022年08月17日 更新

“不敗神話”は保たれたまま
すべての動作がまるでスローモーションのようだった。
左サイドから長友佑都のクロスが上がる。中央では、完全フリーの李忠成が待ち構えていた。李がダンスを踊るように左足を振り抜く。その直後、ボールはマーク・シュワルツァーの守るオーストラリア・ゴールに突き刺さっていた。
『キャプテン翼』の一場面をみているようなスーパーゴール。その劇的なゴールの十数分後、ウズベキスタンのラフシャン・イルマトフ主審の試合終了のホイッスルが鳴り響くと、日本代表のアルベルト・ザッケローニ監督は何かを大声で叫びながら、何度も拳をドーハの夜空へと突き上げた。その拳には、母国イタリアで勝てない日々に苦しみ、「もはや終わった監督」というレッテルを貼られた男の熱い思いが込められていたにちがいない。
指揮官の周りに彼の新しい教え子たちが次々と集まり、歓喜の輪が広がっていく。“激闘”を制した男たちの最高の笑顔……。中心には、日本代表をまだ半年も率いていないにもかかわらず、チームをアジアの頂点へと導いたザッケローニの姿があった。
2022年、この中東の小国はW杯のホスト国となることが決まっている。ドーハの夜空では、新都心に立ち並ぶ高層ビルから漏れる明かりと日本の勝利を祝うカリファ・スタジアムからの歓声が、まるで何かを暗示するかのようにシンクロし合っていた。
2004年の中国大会以来、4度目のアジア制覇だった。ただ、その栄光までの道のりはまさに苦難の連続だった。
大会を通じての成績は、5勝2分け。ただ「90分間で」という条件がつくと3勝4分けということになる。いわゆる“完勝のゲーム”は大会3戦目にあたるサウジアラビア戦(5―0)のみであり、グループリーグのシリア戦、ホスト国カタールとの準々決勝で記録された2勝は、いずれも10対11という数的不利をはね返しての辛勝だった。
おそらく、日本でテレビ観戦していたファンは、逆境をものともせず劇的に勝ち上がる日本代表の姿に大きな興奮と喜びを覚えたことだろう。しかし、十分な準備期間を与えられず、それでも優勝を半ば義務付けられていた選手たちにとっては、ほんとうに厳しい戦いだったようだ。カタール戦後、多くの選手が「10人になり1―2とリードされたときには、正直、負けを覚悟した」と本音を漏らしている。
ともあれ、8月末の就任以来、ザック・ジャパンは一つの敗北も喫していない。“不敗神話”はいまだ保たれたままだ。イタリア人傭兵隊長に率いられたサムライ軍団は、どんな道を歩もうとしているのだろうか? 指揮官が口にしたいくつかの言葉の意味を考えながら、私なりにザック・ジャパンの向かうこれからの道すじを模索してみたいと思う。
日本人指導に適した“平等主義”
コンパッテッツァ(compattezza、コンパクトさ、一体感)、エクイリーブリオ(equilibrio、バランス)、コラッジョ(coraggio、勇気)、そしてテンポ(tempo、時間)……。この4つの言葉は大会中、とくにザックが好んで口にしていたものだ。私は、これらの言葉に指揮官のチームづくりにおける信念をみるような気がする。
決勝直後のインタビュー、ザッケローニはまだ興奮した様子で次のように述べている。「(この代表は)偉大なコンパッテッツァを備えた偉大なチームだ!」と。たしかに、アジアカップでの日本は、非常によくまとまっていた。ザッケローニは、実績や年齢に関係なく選手を一律平等に取り扱う指揮官として知られている。昨年2月、イタリア随一の名門チーム、ユヴェントスの監督に就任したとき、彼は強い口調でこう宣言している。「ベテランと若手を区別して扱うことはできない。フロントのなかには、それをする人がいるかもしれない。しかし、一監督として私にはそういう区分はできない」。
ただ、その一方で、イタリアでの彼はいわゆる“お山の大将”的なスター選手との確執に何度も苦しめられてきた過去をもつ。ザックはプロ選手としてプレーした経験をまったくもたない。10代のとき大病を患い、若くしてプロへの道を閉ざされたからだ。その後、「選手がダメなら監督で」と弛まぬ情熱と探究心を武器にカルチョ(イタリア語でサッカーの意味)の一線へと這い上がってきた人物である。ただ、選手として十分な経験がないぶん、イタリアでは「大物の扱いが下手」という指摘が少なからずあった。
ミラン時代には天才肌のスヴォニミール・ボバン、インテル時代には当時のイタリア代表のエース、クリスティアン・ヴィエリと衝突。昨シーズンのユヴェントスでも、現役ブラジル代表のフェリーペ・メーロ、チームのシンボルであるアレッサンドロ・デル・ピエロとピッチ上で口論することもあった。ラツィオ時代に彼の指導を受けたあるスター選手は、FWとして現役時代華々しい実績をもっていたロベルト・マンチーニがザックの後任に決まったとき、はっきりとこういったという。「彼(マンチーニ)なら俺たちの気持ち、苦悩を理解してくれるはず。本だけでサッカーを学んできた“誰かさん”とは違う」。
今回、カタールでのザックは控え選手に非常に気を使っているようにみえた。決勝直後の会見、あるいは翌日の囲み会見でも、「この勝利は全員で勝ち獲ったもの」であることを強調していた。一度も出場機会のなかったDF森脇良太、GK権田修一の名を何度も挙げ、彼らの陰の貢献をしきりに称えていた。名を挙げられた森脇は、「監督は僕たちサブ組にもいつも声をかけてくれていた。練習でも『みてくれているんだな』という安心感があり、モティベーションが落ちなかった」と語っている。チーム内に“アンタッチャブルな存在”をつくらないザックの“平等主義”を裏づける証言である。
もしかすると、この方法は、日本人を指導するのに適しているのかもしれない。イタリア人は個性をことさらに重んじる人種である。表向きでは「チームのために」を強調しても、心では強烈なエゴを隠し持っている。逆にいうなら、そうでなければ、イタリアのサッカー界で頭角を現わすことは難しいだろう。
そうした集団をまとめるには、指揮官に周囲を圧倒するようなカリスマ性があるか、とんでもなく高度な権謀術数を備えているかしかない。たとえばチームの顔ともいうべきスターを味方につけ、彼を通じてチームをまとめ上げるとか……。ともあれ、必ずしも平等主義が機能する土壌ではないのだ。
一方、日本では(いまのところ)その方法が非常にいいかたちで機能しているように思う。選手を平等に扱うことにより、サブ組のモティベーションが上がり、それが力となってチームに強固なコンパッテッツァが生まれたのではないだろうか。
ただ、ここでもう一つ記しておきたいことがある。これは、大会中、つねにピッチ上にいた知り合いのカメラマンから聞いたことなのだが、チームが円陣を組むとき、ザッケローニはほぼ毎回、本田圭佑の脇に入っていたという。たとえ遠くにいてもわざわざ回り込むようなかたちで……。もしかしたら、ただの偶然かもしれない。
しかし、私はそこに指揮官の“特別な意図”が働いていたように思えてならない。表では徹底した平等を謳い、さりげない態度でエース格の選手に「おまえがこのチームの中心なんだ」というメッセージを送る。アジアカップの代表が無類のコンパッテッツァを誇るチームになれたのは、けっして偶然のことではないと思っている。