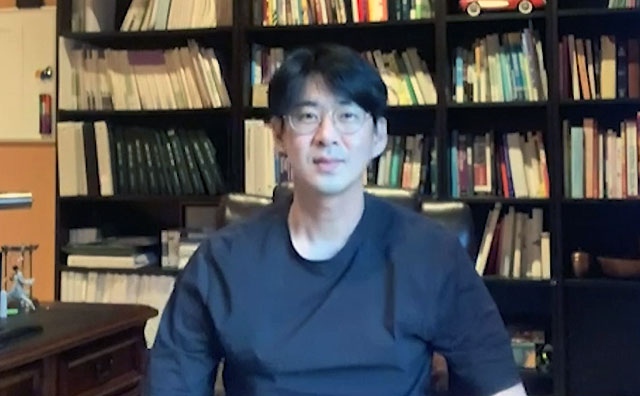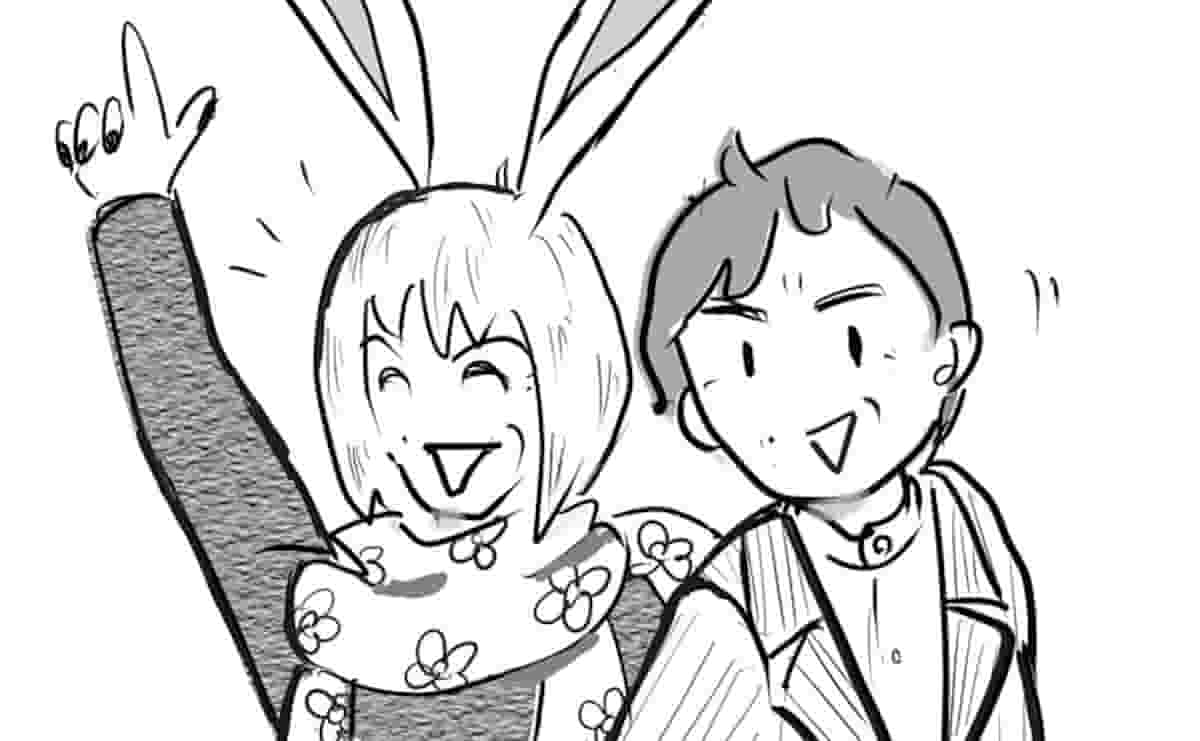円高報道、4つの留意点
2010年11月08日 公開 2022年10月13日 更新

企業や消費者のマインドを冷やすマスメディア
「メディアは事態がどれほどひどいかを伝え続けており、消費者はそれらを再び信じ込み始めている。『米国の経済が二番底のようなリセッションに陥るかもしれない』、あるいは、ある記事が見出しで伝えていたように、『恐慌にさえ陥るかもしれない』といった報道が集中的に出てくるまでは、事態は改善し始めていた。
経済は3~4%のペースで成長してきており、大きな数字ではないものの、昨年に比べればずっとましだ。メディアがいまの姿勢をあらためることだけを、私は望んでいる」
これは、『チーフ・エグゼクティブ・マガジン』という企業経営者向けのメディアが毎月実施している景況感調査に回答するにあたって、ある米企業のCEO(最高経営責任者)が寄せたコメントである。
彼らの景況感を示す米企業CEO信頼感指数は、上記のコメントが寄せられた7月の調査で79.8になり、前月比26.5ポイントの急低下を演じた。昨年11月調査(76.2)以来の低い水準である。
『チーフ・エグゼクティブ・マガジン』は、7月の結果を「ドラマティックな急低下」と形容した。内訳を構成している5つの指数(現況信頼感指数、将来信頼感指数、ビジネスコンディション指数、投資信頼感指数、雇用信頼感指数)がいずれも、7月は悪化した。
企業活動に最終的な責任を負っているトップのマインドが悪化すると、設備投資の上積みや新たな雇用といった、景気回復を推進する原動力になる前向きな動きは、どうしても鈍くなってくる。
実際、米国の設備投資をみていくうえで重要な先行指標である非国防資本財受注(除く航空機)の7月分は、前月比▲7.2%という大きな落ち込みとなった。減少したのは3カ月ぶりのことである。筆者は上記のCEO指数の急激な落ち込みを、すぐに思い出した。
では、金融市場の7月の動きはどうだったか。ニューヨークダウ工業株30種平均が、7月2日にかけて7日続落して9,700ドルを割り込むなど、株価の下落が上旬にみられたという事実がある。ただし、株価はその後、7月下旬にかけては、10,500ドル台へと切り返す動きだった。また、日本でも話題になった、セントルイス地区連邦準備銀行のブラード総裁による、米国経済が「日本型デフレ」に陥るリスクについての言及があったのは、月末近くの7月29日であり、7月分のアンケートへの回答全体に大きな影響を及ぼしたとは考えにくい。
そこで浮かび上がってくるのが、冒頭に引用したCEOコメントにある、厳しい経済状況についての度重なる報道内容による影響である。
マスメディアによる報道の内容が企業や消費者のマインドを冷やすルートは、1990年バブル崩壊後の日本でも、何度か話題になった。米国でもいま、そうした現象が観察されているなら、じつに興味深い話である。
経済が大きな苦境に陥ると、消費者は全体の状況を把握しようとする際に、報道機関に依存せざるをえない。すると、上記のCEOコメントが指摘するような一種の悪循環が生じる可能性があることは否定できない。
7月調査には、次のようなコメントも、あるCEOから寄せられていた。
「現在、高い信頼感はどこにも見当たらない。ほとんどの人が『ハンカーダウン』モードに入っている」
「ハンカーダウン」モード(“hunker-down”mode)というのは、ひざを抱えてしゃがみこむ、危険を回避しようとする姿勢のことである。
その後、米企業CEO頼感指数の8月分が発表された。結果は89.2(前月比+9.4ポイント)。同指数の落ち込みにはいったん歯止めがかかったことが明らかになったわけである。しかし、7月に急低下するよりも前、5月に記録していた直近ピーク(109.9)までは、かなりの距離がある。
5つの内訳指数のなかでは、投資信頼感指数が96.9(前月比+17.9ポイント)で、リバウンドがもっとも目立った。8月にかけて長期金利が大きく低下したことが、社債を発行できる大企業の設備投資意欲を、ある程度刺激したものと考えられる。
ただし投資意欲の改善は、あくまでも大企業を中心とした話だろう。銀行からの借り入れに依存している度合いが高い中小企業の場合、金融環境が引き続き厳しいことは、今回の調査の発表資料でもしっかり指摘されていた。
一方、リバウンドがもっとも鈍かったのが、雇用信頼感指数である。8月は79.1(前月比+2.5ポイント)にとどまった。調査に参加したCEOからは、次のようなコメントが寄せられていた。
「政府は景気刺激のアイデアを使い切ってしまったが、米国の経済はなお悪い状態にある。彼らが即座に焦点を当てるべきだったのは雇用の数字であり、それは経済の残りの部分を押し上げていただろう。雇用は『列車効果(traineffect)』のようなものであり、機関車を修理すれば、列車の残りの車両はついてくるだろう」
けれども、企業に雇用を増加させようとオバマ政権が努力を続ける際に障害になっているのが、(1)米家計の過剰消費構造が崩壊したことによる需給ギャップの拡大、(2)雇用創出力が高い新たな産業分野の欠如、(3)歳出増加に強く反対している議会共和党の存在および11月に行なわれる中間選挙での与党・民主党の敗北見通し、などである。
大きなバブルが崩壊した直後に雇用を増やすという仕事は、誰が米国の大統領でも、そう簡単には実現できない話であろう。一方的な米国経済の悪化は、いまのところ起こっていない。
かといって、米国経済が順調な回復軌道に乗っていく見通しが立ったわけでもない。バブル崩壊後の構造調整圧力ゆえに、「不安定な低空飛行」と筆者が形容している米国経済の状況は、まだしばらく続きそうで、市場のムードは楽観と悲観のあいだを、今後も振り子のように揺れ動き続ける可能性が高い。
米国やユーロ圏が「日本型デフレ」に突入する?
マスメディアの報道内容についての話をもう少し敷衍すると、日本国内においても、最近の経済報道の内容について違和感を覚えることがしばしばある。
たとえば、「通貨安戦争」「通貨切り下げ競争」という、最近目にするフレーズ。これは言葉のイメージよりも、かなり割り引いてとらえておく必要がある。また、円売り介入の実行は、本来、そう簡単な話ではない。筆者がぜひとも確認しておきたい点は、以下の4つである。
(1)米国やユーロ圏が自国通貨を安くしようと「誘導」している事実はない。とくに米国では、為替政策の主導権を握っている米財務省が、自国の債券・株式市場が動揺するリスクをとってまで、「強いドル」政策という為替政策の「看板」を放棄してまでドル相場の下落を促すとは考えにくい。
(2)市場の動きを「容認」する、すなわち自由な取引を経て市場で形成された相場水準を尊重するのが、通貨当局者が通常とるべき姿勢である。市場の動きに対して口先介入的なトークを発するほうが、むしろ例外的な動きである。
(3)為替相場は「相手のある話」であり、いわゆるゼロサムゲームである。それでもある国が為替介入実行を辞さずに自国通貨安に固執するならば、G7による政策協調ないし紳士協定を逸脱することになってしまう。
非公式会合に衣替えする前に公表されていたG7の共同声明には、混乱状態にある市場を落ち着かせるための為替介入(いわゆるスムージングオペ)を実施することができる条件として、「過度の変動や無秩序な動き(excessvolatilityanddisorderlymovements)」が、ほぼ毎回明記されていた。むろんこの考え方は現在でも生きている。9月15日実施の円売り介入は、「過度の変動」を大義名分にしたものだった。
(4)そもそもの話として、市場での取引規模が大きい主要国の為替相場は、人為的にコントロールするのが困難である。為替介入の効果は限定的であり、持続性もない。円売り介入を実施すればなんとかなる、といった意見は、ある意味、無責任である。
最近の新聞報道をみていると、ドル/円相場が世界の為替取引の中心だと誤解しているかのようなものさえ散見される。
「円高」局面ではあっても「ドル安」局面ではないケースは、実際には少なくない。対ユーロや対カナダドルで、あるいは貿易取引のウェイトに基づいて加重平均した実効レートでみてドルが上昇しているにもかかわらず、ドル/円での円高ドル安進行という現象だけしか考えずに「通貨安戦争」といった記事を書くとすれば、事実に基づいた正しい報道とはいえないだろう。
そうした記事を書いている記者は、世界経済において日本経済の地位が着実に沈下しているという事実から、あえて目をそらしているのだろうか。なお、世界の為替市場でもっとも取引量が多いのは、いうまでもなく、ユーロ/ドル相場である。
このほか、人口動態、賃金上昇率、期待インフレ率の様相が日本とまったく異なっているにもかかわらず、バブル崩壊と需給ギャップ拡大だけを根拠に、米国やユーロ圏が「日本型デフレ」に突入するだろうという見方を前面に出すのも、かなり乱暴な議論である。
デフレというのは通常、IMF(国際通貨基金)の定義に従い、2年以上にわたる持続的な物価下落現象を指している。ところが最近は、バブル崩壊後に景気が長期間低迷することを「デフレ」とみなして議論を展開している報道やコメントが見受けられる。
現在のように、経済には大きな構造変化が生じているのではないかと感じるとき、マスメディアによる報道内容への依存度を、人びとは高めやすい。
正しい状況認識に基づいた、しかもバランスが取れた経済報道の重要性は、いくら強調しても、しすぎだということにはなるまい。そうした報道内容自体に、企業や家計といった経済主体の先行きの行動を左右する潜在的可能性があるのだから。
"