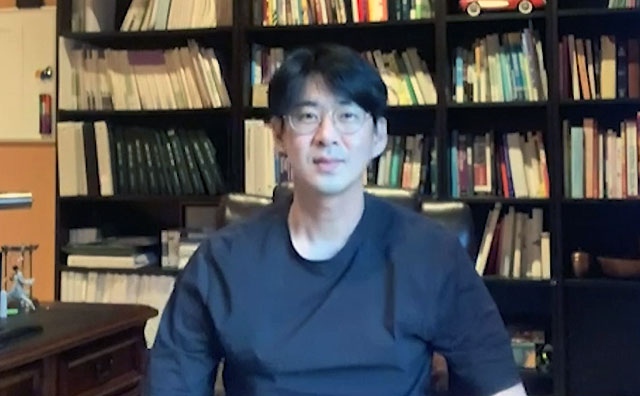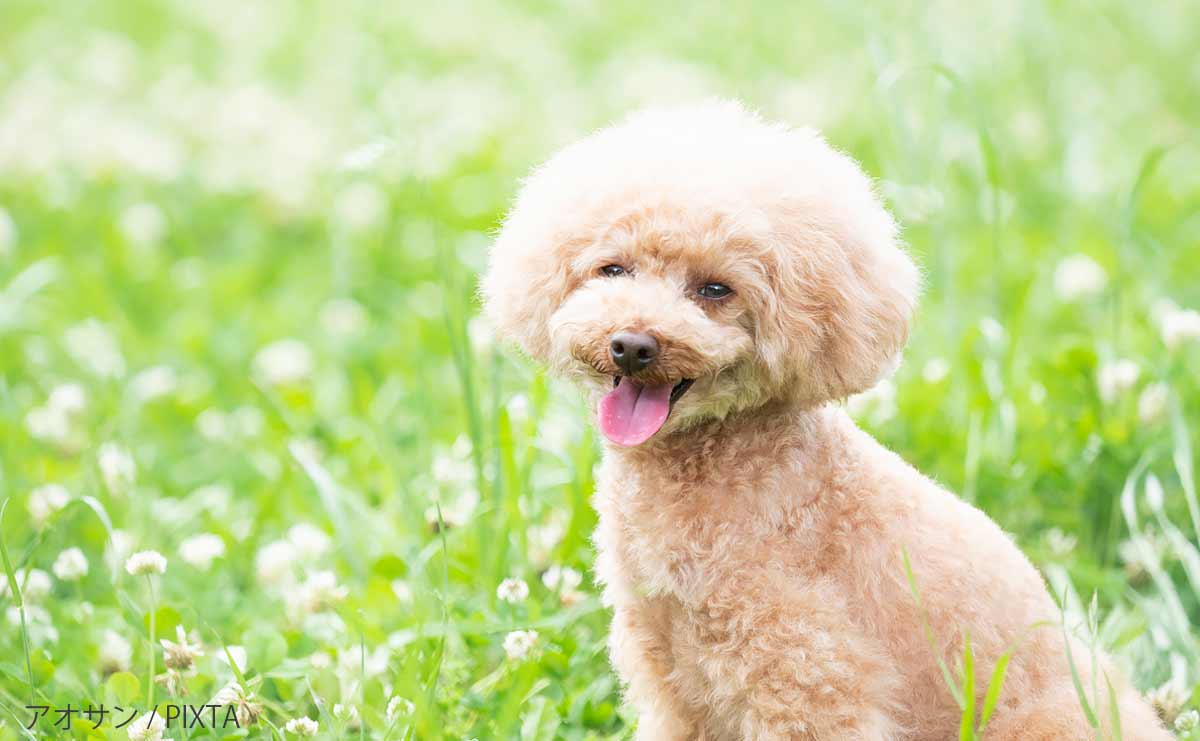[甦る戦争の記憶]硫黄島戦没者慰霊式を訪ねて〔2〕
2014年05月19日 公開 2023年01月12日 更新
《『Voice』2014年6月号[特集:甦る戦争の記憶]より》
遺骨収集の現状
日本側の代表者の1人として参加し、スピーチも行なった岸信夫外務副大臣に自身と硫黄島の関わりについて聞いた。
岸氏は今回が4回目の硫黄島訪問で、初めて訪問したのは超党派議連の一員として参加した2005年の60周年記念のときだったという。
「そのときは、慰霊のため、島を周回して栗林さんがおられた司令府壕などにも入ることができました。かなり奥深くまで入ったのですが、地熱がすごくて、50度くらいになるんです。実質サウナと同じですから、こんなところに1カ月以上もこもって、国のため、家族のために圧倒的不利で孤独な状況に耐えておられたのかと思うと、声も出ませんでした。追悼式典において、あれほど熾烈な戦いを行なった2カ国が合同で英霊に対する敬意を共有するというのは世界的にも珍しいことだと思います」
岸氏が硫黄島に深く思いを寄せられるようになったのは国会議員になってからだった。
「正直なところ、国会議員になるまで硫黄島のことをほとんど調べたこともありませんでしたし、特別な思いもありませんでした。現地に行くに際していろいろな資料を読み、あらためて熾烈な戦いの実相を知ったのです。そして、その恩讐を乗り越えたからこそいまがあるという意義を感じました」
3月下旬には、政府のレーダー調査によって滑走路に隣接した地区で、新たに遺骨が眠っている可能性が確認されたが、外務省としてはどのような対応を考えているのだろうか。
「今回、米国側から新しい資料が出てきたことが、新たな遺骨調査につながりました。現時点で、まだ半分以上のご遺骨が帰還を果たしていないのが現状です。気候も厳しいですし、時間がたてば風化していきますから、このままではいけないということは強く感じております。現実問題として滑走路は使用中ですが、その下に多数のご遺骨が埋まっている可能性が高いので、まずは滑走路の周辺から調査が始まっています。
基本的には厚生労働省の管轄に属する話ですが、情報提供などに関しては米国との連携も必要ですし、滑走路の運用や移設は防衛省にも関係します。滑走路は現在使用中ですから、訓練を絶やすわけにはいきません。島全体が戦闘の場となり、個別に埋葬された場所もあるでしょうから、すべてのご遺骨のご帰還を果たすまでに、そうとうに時間がかかるのは確かです。
同じく激烈な地上戦が行なわれた沖縄と決定的に違うのは、沖縄には民間人が住んでいますが、硫黄島には基本的には自衛隊員しかおらず、ご遺族といえどもなかなか訪問できないという状況のなか、ご遺骨収集だけに集中することはできないということはご理解いただきたいです」

〈写真:上陸する米軍を迎え撃つため、海岸に設置されたトーチカ跡〉
帰還兵たちの苦しみ
海兵隊に招待されて式典に参加した関係から、式典中、筆者は米国側のテントに座った。その際に隣同士になったシェリル・マック氏は、亡き父親が硫黄島の生き残りだったという。生前に子供たちにこの戦いについて語ることはなかったのか、と私は尋ねた。
「いえ、父は硫黄島の思い出についてはいっさい語ることがありませんでした。おそらく、“悪夢”でしかなかったのだと思います。戦後に結婚した母から聞きましたが、父は真夜中に何度となくうなされては飛び起き、叫び声を上げたこともあったそうです」
これは、米軍の硫黄島経験者においては決して珍しい現象ではない。かの摺鉢山の頂上に星条旗を掲げた6人の兵士の1人、ジョン・ブラッドリー氏の息子であるジェイムズ・ブラッドリー氏が関係者や遺族を取材して書き上げたベストセラー『硫黄島の星条旗』(文春文庫、原題:Flags of Our Fathers)のなかにもまったく同じ記述がある。
「しかし、ジョン・ブラッドリーには、忘却は簡単には来なかった。忘れるのには、しばらくかかった。彼は初めてのデートのとき、エリザベス・ヴァン・ゴープに7、8分間つまらなさそうに硫黄島の話をしたが、母の話では、結婚したあと、父は夜寝ているときにすすり泣いた。4年間、すすり泣いていたという」(p.426、筆者註:『硫黄島の星条旗』には近代日本史に関する基本的な間違いが多々見られるが、一般の米国兵とその家族の心情を知るうえで格好の1冊であることは確かである)
「『Flags of Our Fathers』に書いてあるとおりなのですね」
マック氏はうなずいた。
「だから、1つお願いしていいですか? ここにいるヴェテラン(帰還兵)の人たちに、あまり凄惨な戦闘や流血の話は聞かないでほしいのです」
「了解です。ところで、あなたのお父さんは精神科医へ相談に行かなかったのですか?」
マック氏は大きく目を見開き、そんなこと絶対にありえないと強調するように強く首を振った。
「4、50年前のアメリカは、現代とはまったく違います。まして、父が暮らしていたのはカリフォルニアの農村でした。もうわかるでしょう? そういう小さなコミュニティのなかで、精神科医に行ったなんていう話が伝わってしまったら……」
「村八分」は、決して日本だけの話ではない。誰もがお互いの顔と名前を知る小さな村社会においては、全世界どこにでもある話なのだ。現代なら精神科医にトラウマの治療を受ければいいが、当時は「トラウマ」という言葉すらない時代だった。そんななかで、帰還兵たちは戦後も苦しみを負っていたことを感じさせる証言だった。
<<次ページ>> レーションの味