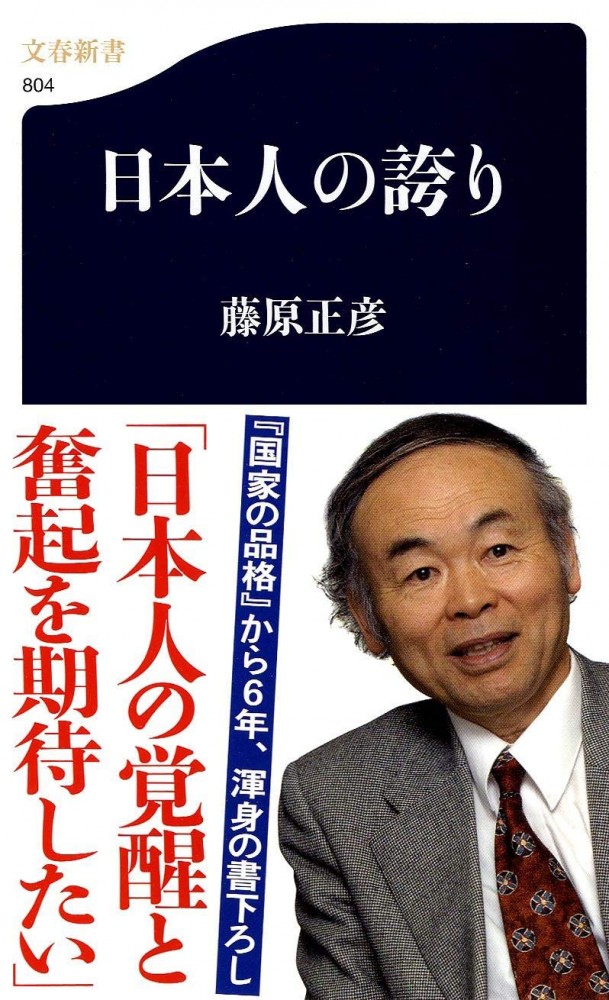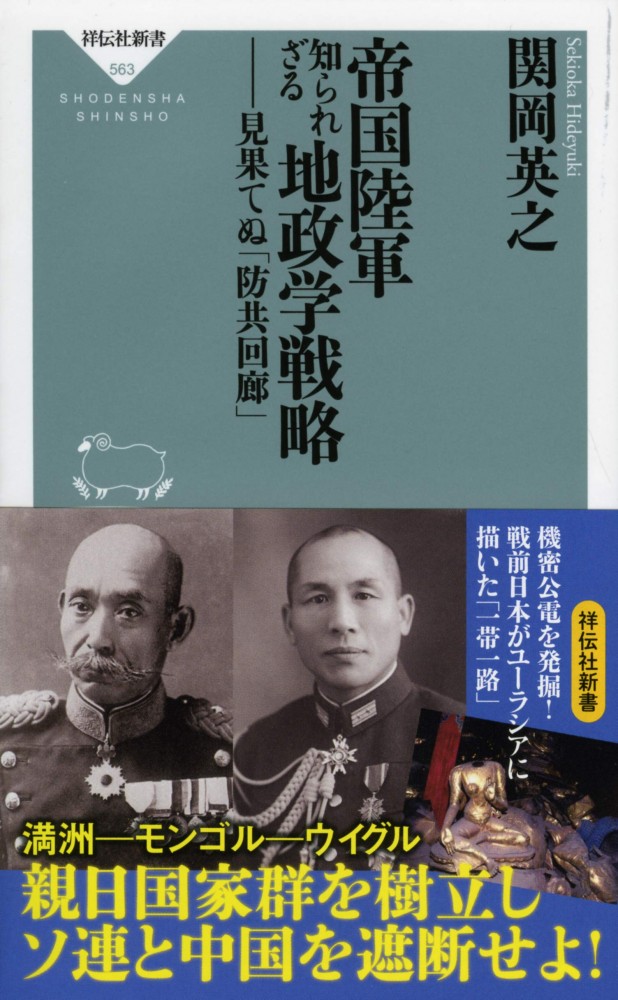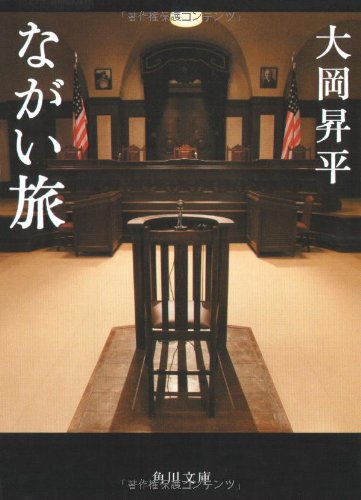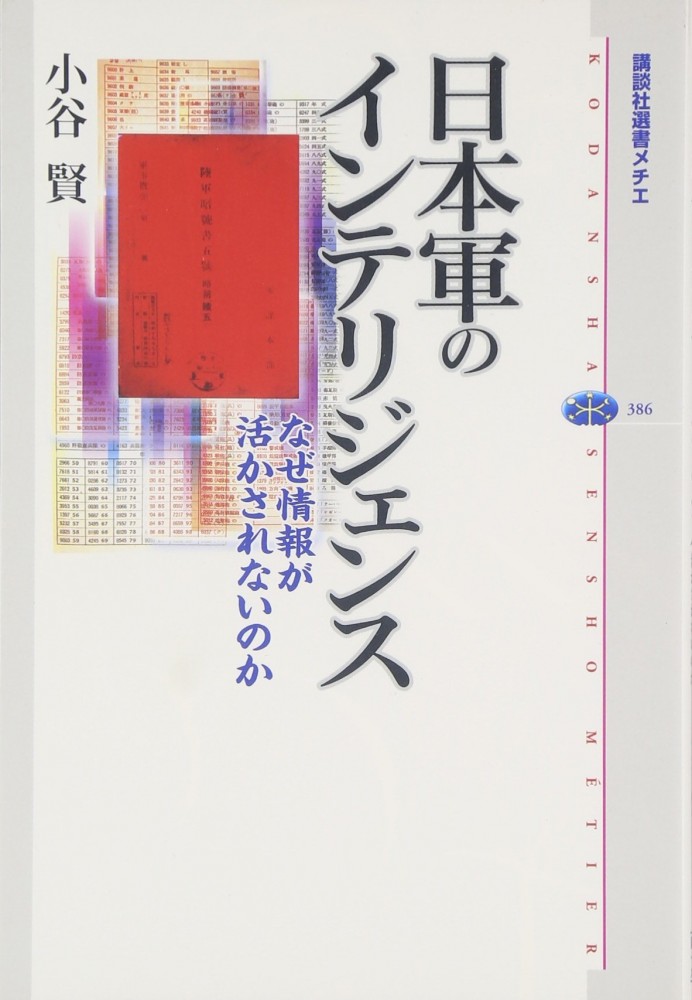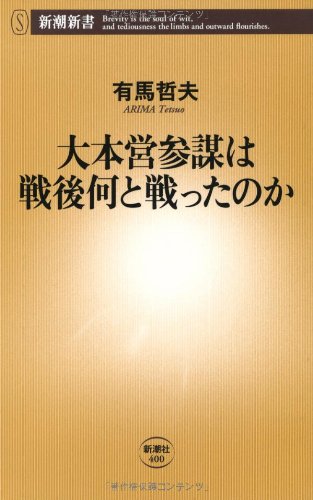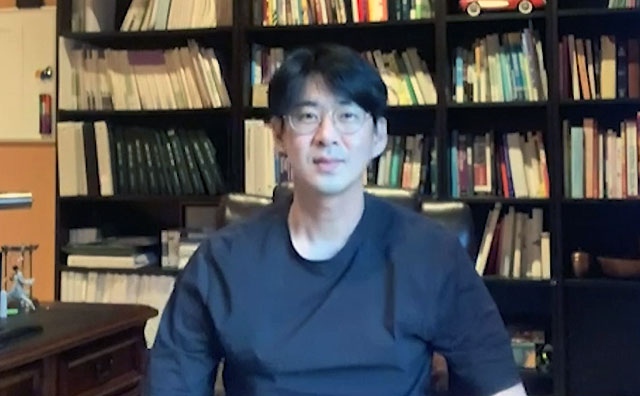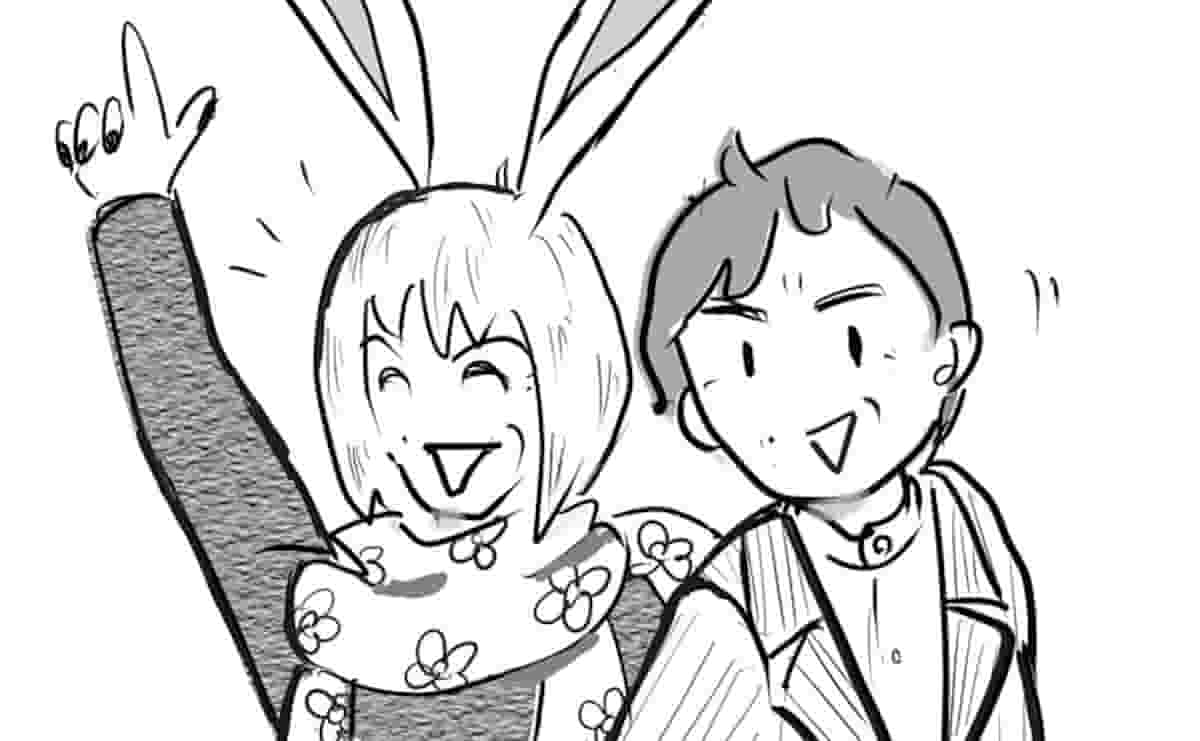大東亜戦争が終結して65年余りが経過し、日本人のあいだでも戦争の記憶は風化しつつあるといわれる。しかしその一方で、毎年夏がくれば、あの戦争をテーマにした評論や評伝、戦記などが出版され、書店店頭を賑わす。
こうした現状をみれば、大東亜戦争に対する日本人の関心は、近年むしろ高まっているともいえる。周辺諸国との相次ぐ外交問題の勃発は、かえって敗戦で失われたナショナル・アイデンティティーを喚起しているかのようだ。まず、この総論部分では、前の戦争の「歴史観」を形づくるうえで、参考になる書を挙げる。
今回の震災で戦後日本は最大の危機を迎えたとされるが、国民が一丸となって復旧・復興を成し遂げることが重要だ。いまこそ日本人は長い眠りから覚め、この危機に対していかに戦い、乗り越えていくかを世界に示さなければならない。
『日本人の誇り』(藤原正彦著)
こうした感情にストレートに訴え、現在ベストセラーになっているのが、藤原正彦著『日本人の誇り』である。
著者は定年前の十数年間、勤務先のお茶の水女子大学の新入生を対象に「日本はどういう国か」と尋ねていた。すると多くが「恥ずかしい国」「胸を張って語れない歴史をもつ国」といった否定的な答えを述べたという。戦前の日本は帝国主義、軍国主義、植民地主義にひた走り、アジア各国を侵略した恥ずべき国と学校教育のなかで教わってきたからだ。その結果、祖国への誇りをもてないでいる。
その主要因を著者は、敗戦後、GHQ(連合国軍総司令部)すなわちアメリカが行なった「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム(WGIP=戦争についての罪の意識を日本人に植えつける宣伝計画)」に求める。それは、日本の歴史を全否定することで、日本人の魂の空洞化を狙ったものであった。そして、その隙間に歴史への贖罪意識を植え付けようとした。いわゆる自虐史観といわれるものが、それであろう。
だが、著者はいう。ペリー来航の1853年からサンフランシスコ講和条約が発効する1952年までの「100年戦争」で日本は多くの間違いを犯したが、日本が「100年戦争」をしなければ、世界はいまも白人支配のままであった、と。胸を張ってそういえるようになることが、日本人としての「誇り」をもつ、ということなのであろう。
『帝国陸軍見果てぬ「防共回廊」』(関岡英之著)
関岡英之著『帝国陸軍見果てぬ「防共回廊」』は、帝国陸軍が推進した「防共回廊構想」の実像に迫った労作。「防共回廊構想」とは、戦前日本のユーラシア戦略を指す。1932年の満洲国建国に続き、内モンゴル、寧夏・甘粛・東トルキスタン(新疆)の独立運動を支援、反共親日国家群を樹立してソ連の南下を防ぎ、また中国共産党への補給を遮断し、東アジアの赤化を阻止するという、地政学に基づく壮大な戦略論であった。
この構想は、「多民族国家」中ソの国家解体を誘発しかねない、あまりに正鵠を射たものだった。それゆえに戦後、徹底したタブーとして抹殺され、歴史の闇に封印されてきたという。それをいま解くことは、日本人が世界に向けて歴史の正当性を訴えていくことにもつながる。
『ながい旅』(大岡昇平著)
戦争中、空爆を行なったB29搭乗員の処刑を命令した容疑で、B級戦犯として起訴された第13方面軍司令官兼東海軍管区司令官・岡田資中将。大岡昇平著『ながい旅』は、米軍の無差別爆撃を立証しようと法廷で戦った岡田の姿を描いたノンフィクションである。
東京裁判に代表される戦後の戦争裁判は、戦勝国による一方的な裁きといわれることがある。それは、しょせん勝者の復讐劇であり、茶番にすぎない。しかし岡田は、この戦争裁判を本土決戦の象徴として捉え、法廷で徹底的に戦おうとした。
もっとも、岡田の目的は無罪を勝ち取り、自分が生きることではなかった。岡田の主眼は、自分一人が責任を被り、部下たちの命を救うことにあった。さらに、「世界民族の為」として無差別爆撃を憂え、現国際法の修正を訴えたのである。岡田は熱心な日蓮宗信者であり、平和を希求する気持ちが非常に強かったという。
だが結局、岡田は法廷で死刑判決を受けることになった。このとき、傍聴席にいた妻に対して、ただひと言「本望である」と語ったという。立派な人がいたとの感慨を抱く。われわれ日本人は岡田の義憤を公憤に変え、その思いを幾世代にも受け継いでいくべきであろう。
『山口多聞』(松田十刻著)
戦争という究極の非常時において、不確定な情報に基づき、冷静な判断を迅速に下せるリーダーのことを、人は「名将」と呼ぶ。とくに大東亜戦争という未曾有の国難において、そうした名将たちの姿に学ぶことは、本来あるべきリーダーシップを知るための、最良の"疑似体験"となりうるかもしれない。
松田十刻著『山口多聞』は、大東亜戦争時の日本海軍きっての名将、また闘将として、アメリカの歴史家からも評価の高い軍人の生涯をまとめた評伝である。
1942年6月5~7日、大東亜戦争の転機となったミッドウェー海戦。日本海軍は真珠湾攻撃のあと南方で華々しい戦績を残しながら、結果的には油断や怠慢、驕慢といったことが重なり、圧倒的に有利と思われていたこの作戦でアメリカ軍に惨敗を喫する。このとき、味方空母3隻が一瞬の虚を突かれ、敵機の攻撃で被弾炎上するなか、残る1隻を率いて乾坤一擲の精神で反撃を開始したのが、山口多聞である。
不屈の闘将の指揮により、わずかな日本攻撃隊は犠牲を顧みずに米空母1隻に連続攻撃せしめ、ついに航行不能に陥れるが、山口座乗の空母も敵機の攻撃で炎上した。しかし、山口は艦からの脱出を潔しとせず、艦と運命を共にしたのである。言行一致。危機に臨んで率先してわが身を捧げる覚悟があるリーダーは、日本人が描く名将像の一つにほかならない。
『零戦撃墜王』(岩本徹三著)
岩本徹三著『零戦撃墜王』は、日本海軍戦闘機隊のトップ・エースとして活躍した撃墜王が残した空戦記。日中戦争から敗戦までのじつに8年間、第一線で戦いつづけたエースは、まず岩本以外に存在しない。
岩本の信条は、「空の勝敗は、指揮官の判断一つで決まる」であった。岩本自身は単機の格闘戦に絶対的な自信をもっていたが、中隊長として編隊を率いた場合、部下たちにはけっして無理をさせず、優位からの一斉攻撃を心がけていた。一方、未熟なパイロットが特攻機で突っ込んでいく様子を目の当たりにして、「髪の毛の逆立つ思いであった」と心情を吐露している。
大東亜戦争時、連合国を畏怖させた岩本のような有能な戦闘機隊長の多くが、まだ20代の若者であったことには驚く。今回の震災対応では、日本は再びこうした若者の正義感、行動力といったものに復興を託すしかないのではないか。60歳以上の老人たちが国を危うくする様子をいつまでもみせられるのは、もう御免である。
工藤美代子著『大東亜戦争の指揮官たち』は、軍人のみならず、皇族、政治家、外交官にも視野を広げ、リーダーのあり方を論じた本。売れ筋の昭和人物伝には当時の指導者層を断罪するものが多いが、東京裁判史観からの決別を訴える本書は、その点、異色な存在である。
『日本軍のインテリジェンス』(小谷賢著)
2007年、小谷賢著『日本軍のインテリジェンス』の出版は歴史界の話題をさらった。戦前の日本がどのような情報活動を行なってきたのか、体系的に論じた研究書がそれまでほとんどなかったからだ。なお、インテリジェンスとは、情報、諜報、情報機関などを含む広い概念であり、秘密工作や暗号解読などもそこに含まれる。
戦前の暗号戦については、日本は連合軍に完敗したという印象だけが根付いている。しかし、本書が明らかにするのは、日本陸軍が暗号戦においてけっして米英に引けをとらない戦いをしていた事実だ。1941年を通じて行なわれた日米交渉の折に、日本側の外交電報が米側に筒抜けになっていたことはよく知られている。だが、日本側も米軍の外交暗号を解読していた。その能力の高さは、米暗号専門家の陸軍士官が、敗戦後、占領軍の尋問中に米軍の暗号を実際に解読してみせ、相手を驚愕させたことでも証明されたという。
問題の本質は、情報がなかったことではなく、活かされなかったことにある。本書は戦前の教訓を踏まえたうえで、現在の日本のインテリジェンスをみた場合、情報部の地位の低さや防諜(カウンター・インテリジェンス)の不徹底、情報集約機関の不在、セクショナリズムといった問題点を挙げている。
『謎解き「張作霖爆殺事件」』(加藤康男著)
近年、新史料の発見や公開に基づき、戦前の日本が対中国戦略を誤った原因として、モスクワからの指令に基づくコミンテルンの謀略(陰謀)が指摘されるようになった。とくに1928年の張作霖爆殺事件に、コミンテルン(正確にはソ連軍諜報部)が関与していたかどうかという論争が、ここ数年、論壇誌を中心に巻き起こった。
改めてこのテーマを徹底検証したのが、加藤康男著『謎解き「張作霖爆殺事件」』である。本書は、これまで昭和史研究家が扱ってこなかった意外な盲点を見事に突いている。従来、同事件の爆心は河本大作大佐が指揮する関東軍の一部が仕掛けた「線路脇」とされてきたが、著者は一次史料を再検討した結果、爆心がじつは「客車内」にあった可能性を指摘する。
かくて「河本首謀説」は矛盾にさらされることになるのだが、事件の真相は? 本書は同事件にコミンテルンと、さらに張作霖の実子・張学良が関与していた可能性を指摘。昭和史がもたらす深い闇に、思わず目まいを覚える。
『大本営参謀は戦後何と戦ったのか』(有馬哲夫著)
有馬哲夫著『大本営参謀は戦後何と戦ったのか』は、CIAファイルから読み解く戦後裏面史。敗戦とともに大本営参謀の一部は地下に潜り、GHQに対して面従腹背を貫きつつ、国内の治安維持や防共活動、インテリジェンス機関の整備に動いた。日本を再び強い国にするためであった。戦前と戦後の歴史の連続性を強く感じさせる内容だ。