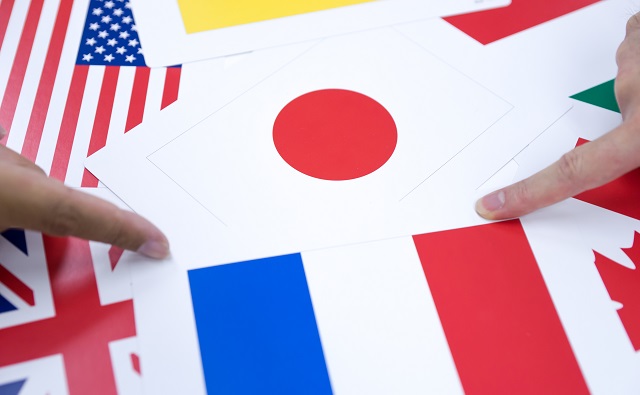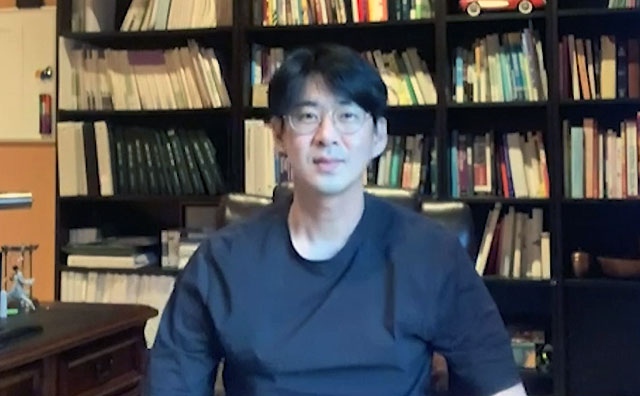1930年代への逆戻り? 自国第一主義の妖怪たちによる世界経済の「大激転」を阻止せよ
2017年06月08日 公開 2022年11月02日 更新
リーマンショック直後の時期、各国首脳は君富論モードに
親分不在の簡単越境時代においては、誰もがみんなのために本気になって考えなければならない。それをしないで、誰もが自分のことだけを考えて右往左往していると、みんなで足を引っ張りあいながら、奈落の底まで落ちて行く。誰もが、ひたすら自分のためだけの部分最適を追求してばかりいたのでは、とてつもない全体不最適を生み出してしまって、みんなが不幸になって行く。こんなにバカげた話はない。
このバカげた話が現実になることを、「合成の誤謬」という。一人一人にとっていいことを合成しても、全体にとっていいことをもたらすことが出来るとは限らない。これが合成の誤謬だ。日本の我々は、東日本大震災の直後にそれを目の当たりにした。あの時、物資不足の到来を懸念した人々が買いだめに走った。お米・トイレットペーパー・乾電池・水・パスタ・卵等々々々……。何もかもが、スーパーやコンビニの棚から消え失せた。
個々人や個別家庭の観点からみれば、危機に際して物資を備蓄するのは、いたって合理的な選択だ。個人や個別家庭という「部分」にとって、買いだめは最適化をもたらす。だが、個々の誰もがこれをやりだすと、全体としてみれば物資不足という著しく不最適な結果を生み出してしまう。これが合成の誤謬だ。
パックス誰でもないグローバル時代は、この合成の誤謬問題を我々にかつてなく鮮明に示してくれる。その意味で、みんなが君富論モードに入りやすい。そのことが、それなりにはっきり現れたのが、2008年のリーマンショック直後の時期だったと思う。あの時、G20の緊急会合に集まった国々の首脳たちは、合成の誤謬の脅威をひしひしと実感したに違いない。金融危機がすさまじい勢いでグローバル経済を席巻して行く中で、誰もが「自分さえ良ければ」だけを考えていたら、お互いにお互いの首を絞めながら集団的ショック死に突入して行くことになる。そのことを実感する中での会合だったから、この手の集まりにしては珍しく、危機意識の共有度が高い印象が残った。
すぐお気づきの通り、これもしょせんは「情けは人のためならず」タイプの君富論ではある。だが、それでも、丸出し僕富論のぶつかり合いよりは、はるかにマシだ。そして、君富論を一度やってみたものは、それがもたらす感動と温かさを忘れることが出来ないはずだ。そこから、本当の共感社会、本当に人のために泣ける人々の世界に向かって、扉が開いていく希望が芽生える。
「全体最適」ではなく「全員最適」
ここで、1つ注意を要することがある。全体最適という言葉には気をつけなければいけない。これさえ実現していればいい。そのように思い込んでしまうと、実をいえば、そこに激転妖怪たちの侵入を許す隙間をつくってしまうことになる。全体最適は、ダボス人間たちが好きな概念だ。グローバル経済は、常にグローバルな全体最適をもたらす。だから、グローバル経済は黄金だ。彼らは、そう考える。
だが、全体がよければいいだろうというこの発想こそ、反グローバルの掛け声の下に国家主義が鎌首をもたげることにつながる。全体的にハッピーなのと、全員がハッピーなのとは違う。たった一人でも、不幸な人がいれば、みんながその人のために泣く。そのたった一人の人が幸せになるまで、誰も本当の幸せ感は味わえない。この感覚がないと、グローバル経済さえどんどん成長していれば、その陰で格差と貧困が広がってもいいという論理に陥る。すると、このダボス人間的世界観への反発が、激転妖怪たちが振りかざす僕富論に息吹を吹き込んでしまう。全体最適だけでよしとしていてはいけない。理想は全員最適だ。
理想無き者に現実は変えられない
というわけで、くしくも理想という言葉に到達した。君富論は、確かに理想論だ。そして理想論は正論だ。正論のどこが悪いか。正論は正しいから正論なのである。それを現実的ではないからという言い方で否定するとは、何たる不心得。何たる勘違い。理想形を見極めることが出来ないものに、現実を評価することは出来ない。無定見に現実を肯定し、無力感を噛み締めながら現実に振り回されるばかりだ。理想無き者に現実は変えられない。
理想形に到達することは、確かに大変だ。人類にとって、それは不可能なことなのかもしれない。だが、不可能を可能にする気概がなければ、敗北主義の泥沼に飲み込まれていくばかりだ。理想はあそこにある。どうすれば、あそこに行けるか。それを常に考えていると、思わぬ時にぐっと理想に近づける可能性がある。だが、理想を掲げていなければ、話にならない。理想は厄介だ。難しい。だが、理想を示すのが、真の預言者たちの仕事だ。
ニセ預言者たちは、厄介なことはいわない。難しいことを語らない。彼らはとても二元対立的で、二次元的で、二者択一的だ。この単純さと単調さが、彼らの最大の特徴であり、最大の弱点だ。トラ鬼さんも、「やるぜ!」と大見得を切っていたことが、さしあたり、何一つ出来ていない。妖怪アホノミクスも、発信するメッセージを随分変えなければいけなくなった。分配に目を向けているフリをしなければいけなくなった。同一労働同一賃金の追求を掲げざるを得なくなった。焦りがこの妖怪の姿勢を一段と過激で露骨にしていく。
「ポピュリズム」という言葉の本来の意味
ここで、改めて、ポピュリズムという言葉に思いが及ぶ。端的にいえば、今、我々がポピュリズムと呼んで警戒しているものは、本当のポピュリズムではない。ニセ預言者たちが掲げるニセポピュリズムだ。
ポピュリズムを日本語でいえばどうなるか。今日的には、それは「大衆迎合」だということになっている。これはおかしい。そもそも、大衆迎合という言い方は、大衆に対して失礼だ。いかにも、大衆は軽佻浮薄で、その軽佻浮薄なる集団の機嫌を取るのがポピュリズムだといっている観がある。あたかも、ニセ預言者どもの出現が大衆の犯罪であるかのイメージになる。大衆の存在が諸悪の根源だという結論につながることになりかねない。
せめて、「大衆扇動」と言ってもらう方が、まだいいだろう。
だが、いずれにせよ、ポピュリズムという言葉の本来の意味は、大衆迎合でも大衆扇動でもない。人民主義。人本主義。人民本位。こんなところがその本来の意味に近いだろう。この辺は、筆者もまだこれから探求する必要が大いにある。したがって、ここで結論めいたことをいうわけにはいかない。だが、謎解き的直感からいえば、我々はニセポピュリズムを排して真のポピュリズムを蘇らせることによって、純度の高い君富論の世界に踏み込むことが出来るのではないか。ひとまず、このようなところまで筆者の発想は到達した。
ここが、次の探求の出発点になるのだと思う。不可能を可能にするための理想論の旅が、ここからまた始まって行く。
真のポピュリズムと真の君富論が出会う場所。そこが、我々が目指すべきところだ。