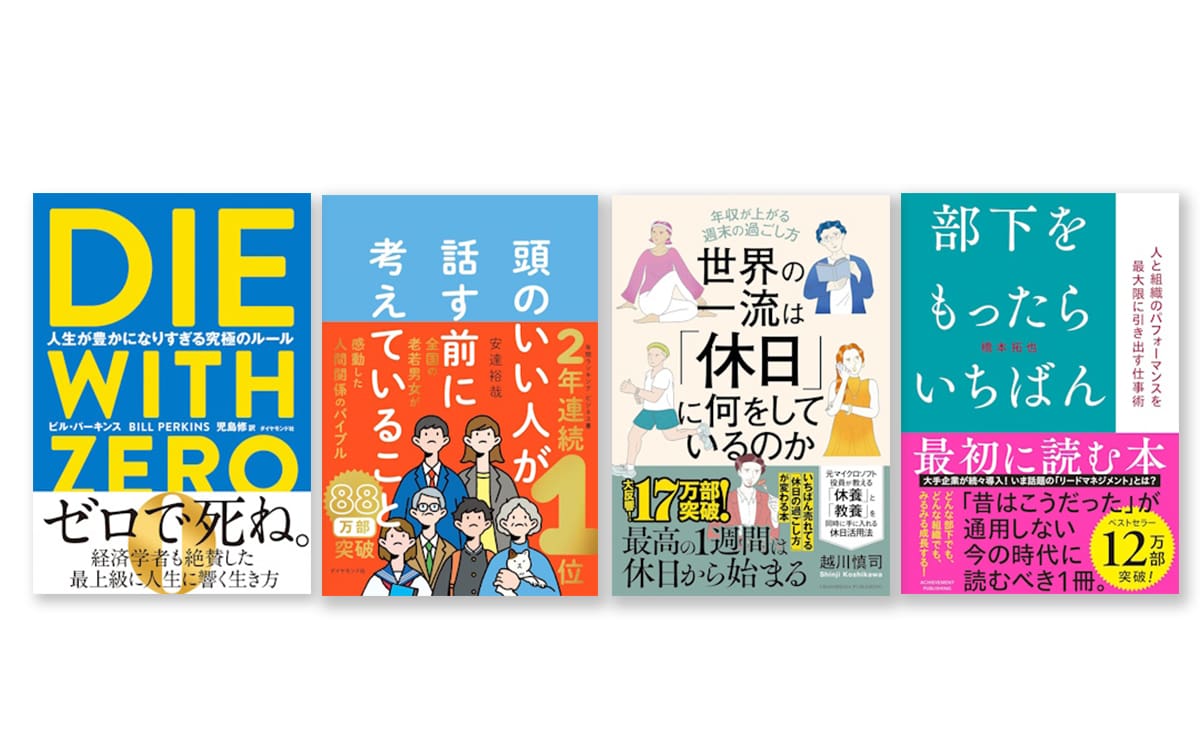ふるさとを守ることの大切さ/桜ノ博士・三好 学
2012年03月20日 公開 2024年12月16日 更新

※本稿は、吉田健二著 『「桜ノ博士」三好学物語』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
環境があって、そこに人間が存在する。 三好 学
◆ふるさとを守ることの大切さ
郷土保護(ふるさとを守る)とは、近年、海外諸国、特にドイツで唱えることで、大きくいえば一国、小さくいえば一州、一郡、一村などの土地の保護である。ここでいう「保護」は、いわゆる軍備によって外敵の侵入を防ぐことではなく、その土地固有の特徴が滅びることを防ぐことである。
1つの土地には、おのずから特徴がある。
まず地勢からいえば、山岳、丘陵、湖、川、原野など、古代からその土地の特徴を表しているものがあり、その上に森林などの草木、いろいろな鳥や動物、虫や魚、化石、鉱物など、その土地固有の天産物として見るべきものがある。
また、その土地には、昔からの歴史をはじめ、風俗、言語にいたるまで、それぞれの特徴がある。これらの特徴は、一口でいえば「風景」「天然物」「歴史」の三つになるが、細かく分けると、たくさんの項目がある。
1つの郷土としての特徴を表すためには、その歴史、名勝、天然物の保存を行い、その特徴が消滅しないようにしなければならない。しかし、世の中の変化に従い、名勝・旧跡もしだいにわからなくなり、人に忘れられ、また固有の天然物も壊され、あとかたもなく消えてしまい、その郷土の特徴がなくなってしまう。
これを防ぐために、近世になってヨーロッパでは郷土保護の事業が盛んになってきた。その事業は、まず、その土地の特徴である史跡、名勝、天然物についての調査をして、その結果を報告し、さらにくわしい「郷土誌」の編さんを行い、また、一方では郷土記念の材料を集めて陳列する「郷土博物館」を作り、土地の人びとにふるさとの特徴を知らせる。その他、土地の学校では、中学校、小学校で「郷土誌」に関係あることを教え、いわゆる「郷土学」の講習をおこたらない。
外国では、各地で「郷土誌」ができ、また「郷土博物館」も設けている。大きい町の博物館には世界的な材料が集めてあるが、その一部には、郷土の歴史、天然物に関する物品が陳列されている。また、「郷土誌」も、簡単なものから、よりくわしいものまで著されている。近年、フランスの各州では、くわしい
「郷土誌」の編さんが行われて、すでに大分できた。2冊、3冊ぐらいの大本で、郷土に関する一切の事柄を分類的に記してある。歴史、地理、政治、経済などの部分と動植物、地質、鉱物、気候、物産等に関する部分を分けて立派に編さんされている。
このような「郷土誌」は、その郷土の利益となるもので、もとより局部的(地域的なもの)である。しかし、このような記録が全国を通してできると、それによってその国一般のくわしい記録ができあがることになる。
わが国では、江戸時代には「名所図会」や各藩の郷土的書類があって、名勝、歴史、伝記、産物などに関する事がらはかなりくわしく書いてあるが、博物学やその他の科学についてはおおざっぱで、不正確で、決して完全な郷土誌にはなっていない。これから郷土誌を編さんする場合は、決して一方の材料にかたよることなく、各方面にたいして一様にくわしく、かつ正確に書かなければならない。
…(中略)…
郷土保護の考えは、わが国にも昔からあり、今日では小学校などでも「郷土学」を教えているが、しかし、たんに学校ばかりでなく、地方の公共団体において郷土保護のために尽力しなければならない。市町村の公職にある人びと、また土地の名望家、有志家は、みんなこの考えで郷土の歴史を明らかにし、名勝、天然物を保護し、その土地の特徴を表す天然記念物および人造記念物を永遠に残す方法を講じ、一方で郷土愛護心の涵養をはかり、他方においては、これらの特徴を世に紹介して、その土地の誇りとすることに努めなければならない。
―― 三好学著『天然記念物』より
三好学(みよしまなぶ)博士の業績
三好学博士は何をした人?
三好学博士は、植物学の世界では広く知られる植物学者になりましたが、名前は聞いたことがあるけれど、実際に何をした人か、どのような業績を残した人か、よく知らないという人も多いと思います。
日本の桜と花しょうぶの研究で世界的に有名な植物学者で、「桜博士」と呼ばれていたこと、約3年間という短い間でしたが小学校の先生もしていて、『授業日誌』というくわしい記録を書いていました。博士の書いた『授業日誌』は、日本で学校教育が始まったばかりのころに、どのような教育がされていたのかを具体的に知るための、唯一といっていいほどの貴重な史料にもなっています。
このほかにも博士はいろいろな業績を残していますが、博士を語るときに忘れてはならないふたつの業績がありますので紹介しましょう。
◆日本に近代植物学をもたらした人
三好学博士は、明治時代にドイツに留学して、進んだ植物学を学んで帰国し、日本に近代植物学をもたらし、その基礎をきずきました。
世界中同じですが、植物学というのはもともと、薬草を探すことから始まった学問です。中国では、「本草学」といって、6世紀ごろに、野山の草木の中から薬になるものを集めて、薬草として分類して記録・整理したのが始まりだといわれています。この「本草学」が奈良時代に日本に伝わって以来、日本の植物学も「本草学」として発展してきました。
明治時代になってもそれは同じで、当時の植物学研究は、いろいろなところから植物を採集してきて、その植物がどんな種類の植物かを明らかにして分類し、記録する、「分類学」でした。1877年(明治10年)、東京大学に理学部が作られ、生物学科ができたときも、
そこで研究したのは植物の分類学でした。数年後、アメリカから帰国した矢田部良吉博士が一般植物学を大学で講義するようになって初めて、植物学が系統だった学問になったのです。三好学博士が植物学の道を歩み始めたのはそのような時代のことでした。
しかし、ドイツではすでに、植物そのものを科学的に研究する植物生理学や、その植物が自然の中で、周囲の環境とどのようにかかわりあいながら生息しているかを研究する植物生態学が始まっていました。植物学が、分類する学問から科学的に研究する学問へと大きく変わっていたのです。その第一人者が、博士がドイツ留学のとき師事したペッファー教授です。
博士は、この進んだドイツの近代植物学を日本にもたらし、研究をしたのです。留学先のドイツから実験用器具や器械、参考書や資料を持ち帰り、自分自身でも研究し、学生たちにも教えました。明治、大正時代以降のほとんどの日本の植物生理学者、植物生態学者が博士の弟子だといわれますから、「日本の近代植物学研究の父」といっても言い過ぎではないでしょう。
ちなみに、今では普通に使われる「生態学」や「景観」といった言葉を最初に使ったのは、三好学博士でした。また、人間も自然の一部である以上、人間の営みと植物の関係をしっかり研究しなければならないと、「人生植物学」を提唱しました。
自然保護運動のさきがけとなった人
また、博士は、自然保護運動の先駆者の一人でもありました。明治維新以降、日本には近代化の波がおしよせてきました。国中が、「文明開化」と「殖産興業」にわきたちました。しかし、その一方で、各地で自然が急速に破壊されていき、昔からある名木や名勝・旧跡がどんどんなくなっていきました。近代文明がもたらす便利さ・快適さの裏で、自然が壊されていったのです。
植物学者としてそのような日本の状況を博士はうれえていました。そして、1906年(明治39年) に『東洋学芸雑誌』という雑誌に「名木の伐滅ならびにその保存の必要」という論文を発表したのを最初に、いろいろな雑誌や新聞で、天然記念物保存の大切さを訴えました。また、日本各地の名木や名勝・旧跡の調査を行い、海外の進んだ事例を研究するなど、精力的に活動しました。また、民間の心ある人を動かして、政府にも働き掛けました。
博士のこの努力は、1919年(大正8年)に「史蹟名勝天然記念物保存法」として実を結び、翌年には、岐阜県中津川市坂本のハナノキ自生地など10件が天然記念物に指定されました。この法律は、現在の「文化財保護法」や「自然環境保全法」の先駆けとなるものですが、法律の公布と同時に、博士は、史蹟名勝天然記念物調査委員に就任。その後、この世を去る直前まで、全国各地を調査して歩くなど精力的な活動を続けました。博士が亡くなる3年前の1936年(昭和11年)には、史跡691件、名勝93件、天然記念物566件が国指定となり、そのうち430件が植物関係だったといいますから、博士の活動がいかに精力的だったかがわかります。
吉田健二(よしだ・けんじ)
漫画家
1975年(昭和50年)、山口県田布施町生まれ。岸信介、佐藤栄作と2人の内閣総理大臣を出す町で育つ。
『週刊少年マガジン』(講談社)でデビュー。現在『がっつりラーメン戦記 ふろむJ』(ホーム社)をWeb連載中。
他の主な作品に『日本国大統領 桜坂満太郎』(新潮社)『幕末英雄伝 坂本龍馬 上・下』(ポプラ社)『沖縄美ら海水族館物語~ジンベエとマンタが教えてくれたこと』(PHP研究所)などがある。