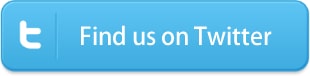ミッドウェー海戦、空母「飛龍」乗組員の証言
2017年06月05日 公開
2022年06月28日 更新

今日は何の日 昭和17年6月5日
ミッドウェー海戦で南雲機動部隊が壊滅的な敗北
昭和17年(1942)年6月5日(現地時間6月4日)、ミッドウェー海戦があり、南雲忠一司令長官率いる4隻の空母から成る機動部隊が敗北を喫しました。今回は「歴史街道」編集部が当時、空母「飛龍」に乗艦していた方を取材をした際に、直接伺ったお話を紹介します。
まずは元空母「飛龍」機関長付少尉であった故・萬代久男さんです(取材は2000年)。萬代さんは海戦当日、艦底の機関部に詰めており、戦況は艦橋の司令部から艦内電話で知らされるはずでしたが、甲板まで上がってはじめて3空母が炎上していると聞いて愕然としたそうです。その後、飛龍が被弾すると、猛烈な火災のため通信が杜絶、人が直接艦橋まで出向かなくてはならなくなります。しかし通路は、ミッドウェー島占領後用にと積み上げていた米俵に火がついて通ることはできず、艦橋との連絡手段がなくなりました。一方、艦橋側も同じく艦底に降りられず、連絡も途絶えたため機関部全滅と判断し、飛龍処分を決めるのです。ところが実際は飛龍の機関部は健在で、艦橋と連絡さえつけば帰還することができたのです。萬代さんが強調されたのは、「ダメージ・コントロール」でした。もし、飛龍に当時米空母が備えていた油火災を鎮火できる万能ノズル、酸欠状態でも活動を可能にする酸素自給機、そして電源が落ちても通信可能な無電地電話があれば、みすみす空母を失うことはなかった、と。飛龍が魚雷処分で沈む時、艦底の約100名の機関科員が脱出を図りますが、艦外のカッターにたどり着いたのは39人でした。そして2週間の漂流の末、米軍に救助されて捕虜となったのです。漂流中に2人の仲間が落命していました。
もうおひと方は、元空母「飛龍」雷撃隊の丸山泰輔一等飛行兵曹(当時、後に少尉、故人)です。丸山さんは九七式艦上攻撃機(魚雷を射つ雷撃機で3人乗り)の偵察員を務め、真珠湾で戦艦オクラホマ、ミッドウェーで空母ヨークタウン、南太平洋海戦で空母ホーネットへの雷撃に成功して生還した方です。寡黙な丸山さんはこう語ってくださいました。「雷撃は単機で成功するものではありません。大切なのは他機とのチームワークです。敵艦は必ず回避運動をとります。そこで敵艦の動き、スピード、長さ、我が魚雷のスピードを勘案し、魚雷が有効な角度から撃たなければなりません。もちろん90度が理想ですが、その位置につけば、たちまち猛烈な対空砲火で撃墜されます。そこで他機とともに左右から挟撃するのです。敵が一方に気を取られている隙に、反対側から射ち込む。この辺はサッカーのゴールと似ています。つまり雷撃成功は仲間の犠牲の上に成り立つものであり、決して単機の功績などではないのです」と、仲間の献身的な協力と犠牲の上に現在の自分があることをお話しくださいました。そして最後に「私は戦争を、軍人の本分を尽くして戦ってまいりました。しかし現在の日本人は、はたして本分を尽くした仕事をしているのか、という気持ちになります。不測の事態が起きた時、見て見ぬふりをするのか、それとも毅然と対処するのか。その差は『自分の本分を尽くそう』という姿勢の有無から生まれてくるものではないでしょうか」。
この言葉は2002年の瀋陽総領事館事件直後のことですが、今でも、その重みは何ら変わっていないのではないでしょうか。
なお、7月6日発売の「歴史街道」8月号では、「山口多聞とミッドウェー海戦」を総力特集します。決定的な敗北の中、強烈な輝きを放った男たちの戦いをご紹介する予定です。
歴史街道 購入
アクセスランキング(週間)
更新:04月17日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 細川ガラシャの辞世~ちりぬべき時知りてこそ世の中の 花も花なれ人も人なれ
- ユダヤ人はなぜ、ナチス・ドイツの標的にされたのか
- 豊臣秀吉、天下人の辞世~露と落ち露と消えにし我が身かな
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 陸軍兵力・軍艦数で劣る日本が、日清戦争で勝てた理由
- マッカーサーを感動させた、昭和天皇のお覚悟と天真の流露
- 小田原参陣前、伊達政宗は弟・小次郎を殺してはいなかった!?
- 第六潜水艇遭難~教科書にも載った佐久間勉艇長の遺書
- 日本と朝鮮半島の交流史~今だからこそ知っておきたい!
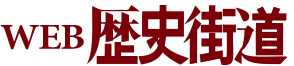




.jpg)