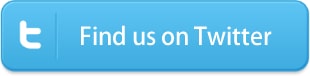夫・半藤一利の最後の言葉

新潟県長岡市内を流れる信濃川
疎開先の新潟で眺めた、巨大な炎の柱
さてさて、夫より5歳年下の私は、その時何をしていたのでありましょうか。新しい環境と豪雪の脅威、それから想像を絶する空腹と闘っていました。
私たち一家は、昭和19年(1944)11月に住み慣れた東京を離れ て、新潟県長岡市の郊外の父の生家の近くに疎開しました。11月は越後で最も悪い季節です。雨期なのです。
みぞれ混じりの冷雨が連日降り続き、やがてそれが雪に変わるのです。ここは豪雪地帯として有名でありますが、一晩で一メートルも積もる日もあります。既に二階建ての家屋がすっぽりと埋まってしまうほど、雪が積もっているというのに。
そういう朝には、母と二人でシャベルやコスキで新雪を払いのけ小さな段 をきざみ(これも大仕事)、上級生に両手で雪の上に引っ張り上げてもら い、下からは母にお尻を押し上げてもらって、やっと道に出て学校に行きました。
小学校三年生の女の子にはかなりこたえる作業でありました。何よりも耐え難かったのは、空腹です。当時はとにかく食べるものがなく、というのは、周囲に住む農家の人々が排他的で「よそ者に売るものはない」と言って母に米や野菜を売ってくれなかったのです。
私は目がギョロギョロとして、やせ細っていました。私にとっての戦争というものは、飢餓との闘いでした。空腹ほど辛いものはない、と今でも思うのです。
もちろん、殴られたり蹴られたりするのも辛いことでしょう。でも、空腹とは一種の暴力であることを、戦争は私に知らしめました。それでも、夫が経験したように、火に追われたり溺死寸前になったりする恐怖とは比べ物になりません。
ただ、私も一度、田んぼに囲まれたこの村で、幸か不幸か、太平洋戦争を、それも実戦を見る機会を得たのです。私が見たもの、それは長岡空襲の凄絶な戦火でした。以下、私の著書『夏目家の糠』に収録された「大空襲の夜」を抜粋し、少し読みやすく書き直しながら、ここに写すことをお許しください。
「その日、父母と姉と私は、父の生家、村松の本覚寺を訪れていた。盆参りという、寺としては一年中で一番大きな行事が催されたからである。夕食後、父は一人で帰宅した。
当時中学生であった兄は勤労動員で、その夜、北長岡の軍需工場で働いていた。夜勤明けで帰宅する兄を出迎える者がいなくてはかわいそうだと、父は一里(四キロ)の道を歩いて帰ったのである。
その夜、私たち三人は早々と眠った。どのくらい経った頃か、周囲が騒々しくて目が覚めた。空襲警報のサイレンや飛行機の轟音で目が覚めたという記憶はない。窓を開けると闇夜を旋回している色とりどりの電光がまず目に入った。星の数ほど無数に見えた。
時々赤い火を噴いて、焼夷弾が自在に飛び交う電光から降ってくるのが見えた。なぜ爆撃機B29が赤青黄緑とさまざまな色の光を放ちながら爆撃していたのか、今もわからない。私にはB29が陽気に焼夷弾をまき散らしているように見えた。
地上からはメラメラと燃えたつ巨大な炎の柱が天を射るようにそびえ立ち、闇夜を真っ赤に染め上げた。街全体が炎に包まれるのを私は初めて見た。
あの大空襲で命を落とされた方、命からがら逃げまどっていた方を思えば不謹慎も甚だしいが、その規模といい、華やかさといい、後にも先にもあれほど壮観な光景を私は見たことがない。息をのむほどに美しい眺めであった。
兄があの火の中で死んでしまったに違いない、と母が言った。誰も哀しいとは思わなかった。肉親の死にも麻痺して何も感じない異常な時代であった。私は怖いとも悲しいとも感じなかったが、歯の根が合わず全身が小刻みに震えていつまでも止まらなかったのをおぼえている。昭和20年8月1日、私が11歳の時であった」
太平洋戦争が終わったのが昭和20年8月15日ですから、長岡空襲は終戦の直前ということになります。まるで見通しのよい観客席に座って、じっくりとつぶさに、あたかも芝居やオペラを観賞するように、戦争、それも実戦を観る機会を得られたことは、私の人生にとって非常に大きな経験でした。
夫は空襲の体験者ですが、私はその目撃者とでもいうのでしょうか。今の長岡名物、花火で有名な8月の長岡まつりは、もともと長岡空襲の悲しい日を長岡市復興へのバネにするため、長岡市戦災復興祭として始まったと聞いています。
戦争で中断した長岡の花火も空襲の翌年の夏には再開されたように思います。長岡にいた頃、私も何回か夜空に開く華を見ました。しかし三尺玉だろうとスターマインだろうと、あの空襲の夜の強烈な華やかさには遠く及びません。
長岡まつりの季節になると、私は花火よりも先に、大空襲の夜の悲しい美しさを思い起こしてしまいます。それが悲惨な戦争を経験した者の、辛い性ということなのでありましょうか。
亡き夫も花火は大嫌いでした。花火を見ると、よく二人で不機嫌になったものです。そうそう、長岡空襲で亡くなったかのように思われていた私の兄ですが、実は彼は生きていました。兄を心配した父が宮内駅(長岡駅の隣の駅)に行くと、焼け跡からヨロヨロと兄が現れたそうです。
態度にこそ表しませんでしたが、兄と再会できた父の喜びははかりしれません。その後、戦争も終わり、平和が訪れた頃、兄はある学友を家に招きました。それが、後に私の夫となる半藤一利でした。
夫が残した最後の言葉
夫が亡くなったのは、令和3年(2021)の1月。彼は自分の死期を悟っていたのかもしれません。具合が悪くなるにつれて、「あなたをおいて先に逝くことを許して下さい」と私に頻りに詫びるのでした。
そして、亡くなる日の真夜中、明け方頃だったかもしれません。「起きてる?」と、夫の方から声をかけてきました。私が飛び起きて、夫のベッドの脇にしゃがみ込むと、彼はこう続けました。
「日本人って皆が悪いと思ってるだろ?」「うん、私も悪い奴だと思ってるわ」私がそう答えると、「日本人はそんなに悪くないんだよ」と言いました。
そして、「墨子を読みなさい。2500年前の中国の思想家だけど、あの時代に戦争をしてはいけない、と言ってるんだよ。偉いだろう」それが、戦争の恐ろしさを語り続けた彼の、最後の言葉となりました。
天災と違って、戦争は人間の叡智で防げるものです。戦争は悪であると、私は心から憎んでいます。あの恐ろしい体験をする者も、それを目撃する者も、二度と、決して生みだしてはならない。それが私たち戦争体験者の願いなのです。
歴史街道 購入
アクセスランキング(週間)
更新:04月20日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- ユダヤ人はなぜ、ナチス・ドイツの標的にされたのか
- 陸軍兵力・軍艦数で劣る日本が、日清戦争で勝てた理由
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- マッカーサーを感動させた、昭和天皇のお覚悟と天真の流露
- 日本と朝鮮半島の交流史~今だからこそ知っておきたい!
- 細川ガラシャの辞世~ちりぬべき時知りてこそ世の中の 花も花なれ人も人なれ
- 第六潜水艇遭難~教科書にも載った佐久間勉艇長の遺書
- 世界史における「最強の武人」といえば誰? ランキング
- 小田原参陣前、伊達政宗は弟・小次郎を殺してはいなかった!?
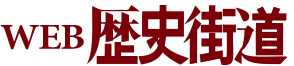
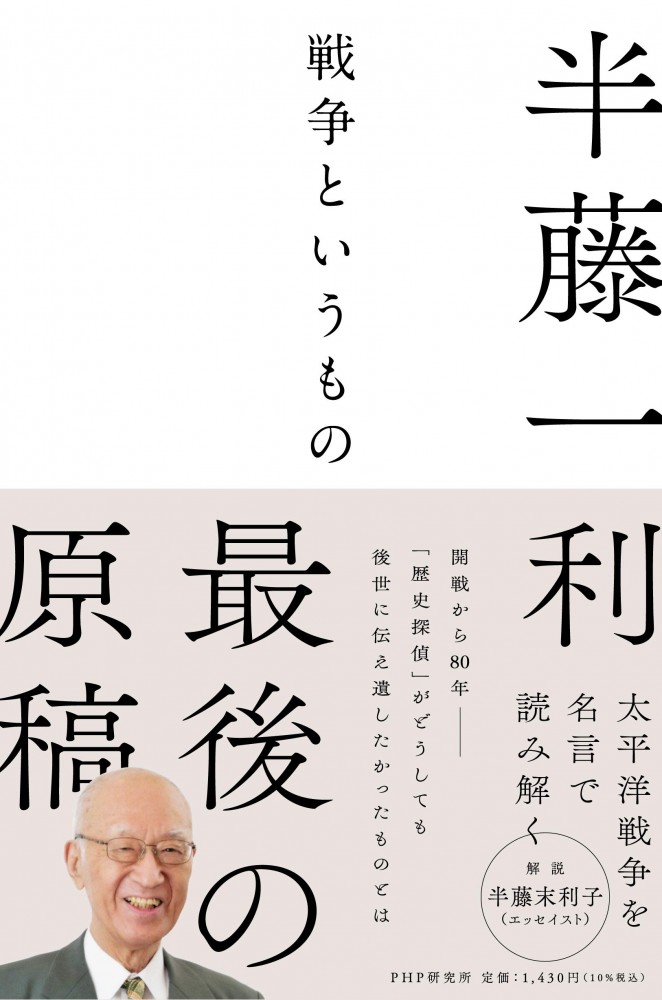


.jpg)