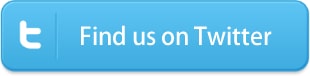武家の時代へ。源氏と平氏、何が明暗を分けたのか

長年にわたって戦いを繰り広げた源氏と平氏。それは貴族の世から武士の世へ、時代の転換を告げる戦いとなった。勝者と敗者を分けたものとはなんだったのか。そして頼朝による武家政権は、日本の歴史に何をもたらしたのか。
昭和30年(1955)、福岡県生まれ。平成2年(1990)、『血の日本史』でデビュー。『天馬、翔ける』で中山義秀文学賞、『等伯』で直木賞を受賞。主な著書に『信長燃ゆ』『レオン氏郷』『平城京』『家康』『迷宮の月』『特攻隊員と大刀洗飛行場』などがある。
武士の誕生、3つのルーツ
平安末期、源氏と平氏というふたつの武家が戦いを繰り広げた。平氏は西国のイメージが強いが、時代を遡ると源氏同様、東国に根を張っていた武士団である。
武士の誕生には3つのルーツがある。
1つは「健児(こんでい)」と呼ばれる兵士で、律令制のもとで国司の配下にあり、各地の治安維持にあたっていた者たち。
もう1つは、律令制の崩壊に伴って、荘園領主たちが、自分の所領の耕作を請け負わせ、武装化していった「田堵(たと)」。
そしてもう1つは、奥州を鎮定する際に捕虜になった蝦夷たち。彼らは「俘囚(ふしゅう)」と呼ばれ、健康で屈強な男たちが多かったため、労働力として各荘園に預けられたが、やがて逃亡し、野盗になるなどしていた。
関東において、こうした者たちが職業武士団として確立していく契機となったのは、対蝦夷政策である。
当時は畿内を中心とする日本と、東北地方の蝦夷は別の国という意識があった。彼らには、蝦夷の侵略を防ぐ、いわば国境警備隊の役割を与えられたのである。
中国では古来、ウイグルや満州など、遠方に警備隊を置く場合、食糧を中央から供給するのは難しいため、彼らに開拓を促し、自分たちで農業をやって生活せよ、といった方策がとられた。
これを日本でも採り入れて、国境警備隊として置いた者たちに、開発領主として農業もやりなさい、なにかあったら奥州に攻めていけ、という体制をとった。
武士団はこうした蝦夷対策によって、成長していったのである。
関東で成長した源氏と平氏、その分かれ目
源氏は当初、摂津や河内など、畿内を中心に活動していた。
最初に目覚ましい活躍をしたのが源満仲で、安和2年(969)、左大臣・源高明が失脚した安和の変に関与し、藤原摂関家の信頼を獲得した。
その子・頼信は、長元元年(1028)に房総地方で起きた平忠常の乱を平定。坂東武士の多くが頼信の配下となり、以後、源氏は関東で大きく伸長していく。
一方の平氏は、平安中期頃から東国に移り住み、天慶2年(939)の平将門の乱などを経て勢力を拡大していった。「坂東八平氏」と呼ばれる秩父氏、三浦氏、千葉氏などはそこから派生した一族である。
その後、源氏が関東を拠点にし、国境警備隊兼開発領主の立場であり続けたのに対し、平氏は伊勢地方へと勢力を伸ばしていく。
当時は、畿内から関東への、兵や物資の輸送は海運が中心で、伊勢湾から伊豆を通って関東へ船で運んだ。平氏はこの海運業に目をつけたのだ。
長元元年の平忠常の乱で一時没落した平氏は、伊勢に進出することによって、活路を見出そうとしたのではないか。これがやがて、伊勢平氏と呼ばれる武士団に成長していく。
彼らは海運で財を築き、清盛の父・忠盛の時には、日宋貿易を牛耳るようにまでなっている。それによって得た資金で、中央政権との結びつきを強めていったのだろう。
源氏が摂関家に接近して力をつけたのに対し、平氏が接近したのが院であった。
承徳元年(1097)、清盛の祖父・正盛は白河法皇に伊賀の所領を寄進し、関係を深めた。父の忠盛も、鳥羽上皇に得長寿院を寄進して接近している。
保元・平治の乱、平氏が勝っていたこと
源氏と平氏の勢力がさらに伸長するきっかけになったのは、保元元年(1156)に起こった保元の乱である。
これは、崇徳上皇とその弟である後白河天皇の争いで、後白河方に源義朝と平清盛がついて勝利へ導いた。
3年後の平治元年(1159)には、二条天皇に譲位し、上皇となっていた後白河の近臣同士の内紛により、平治の乱が起きた。信西(藤原通憲)は平清盛と組み、藤原信頼は源義朝と組んで、互いが牽制しあう構図となった。
同年12月、清盛らが熊野詣で京を留守にしている隙に、義朝は後白河上皇を二条天皇のいる内裏に移して拘束、信西を自害に追い込む。
これを知った清盛はすぐさま京に戻り、天皇を自身の屋敷である六波羅へ移すことに成功、上皇も内裏を脱出した。信頼・義朝討伐の綸旨が出され、源氏は「朝敵」となったのである。
敗れた義朝は、東国へ向かう途中に尾張で討たれた。そして三男の頼朝は、伊豆の蛭ケ小島へ配流となった。
源氏と平氏、両者の明暗を分けた要因の一つは、経済力である。日宋貿易を牛耳っている平氏と、関東にだけ勢力を張っている源氏では、資金力に雲泥の差があった。
そのうえ、清盛には政治力があった。
清盛の継室・時子は二条天皇の乳母で、影響力を行使できる関係にある。また、後白河上皇には、のちに蓮華王院を寄進するなどしている。
後白河上皇と二条天皇が対立する中でも、両方にうまく取り入っているように、優れたバランス感覚を持っていることがわかる。
さらに清盛が時子の妹・滋子を後白河に入内させると、その子が高倉天皇として即位。そして高倉天皇に清盛の娘・徳子が入内し、安徳天皇が誕生するのである。
このように清盛は、天皇家と一体化することによって権力基盤を作っていった。これは藤原道長が娘を次々と入内させ、天皇の外戚となったやり方と同じだ。ある意味、旧来型ともいえる。
相次いで不幸に見舞われた平家
清盛は太政大臣にまで昇りつめ、時子の弟・時忠が「此一門にあらざらむ人は皆人非人なるべし」と言ったと伝えられるほど、平家一門は権勢を極めた。
一方朝廷内部では、反感を持つ者も出てきた。後白河は平家を排除しようと画策するが、治承3年(1179)、清盛によって幽閉される。
しかしこの頃から、平家にはよくないことが相次いで起こり始めていた。
同年、清盛の長男・重盛が死去。治承5年(1181)1月には、政務を担っていた高倉上皇が崩御。そして 閏2月、清盛自身も原因不明の熱病によって没した。清盛の跡を継いで平家を率いたのは、三男の宗盛である。
前年の治承4年(1180)には、後白河の皇子・以仁王が、源頼政らと共に挙兵。「平氏討伐の令旨」を全国に下した。
これに伊豆へ配流となっていた頼朝、源氏の内紛によって木曾で庇護されていた義仲らが呼応した。
義仲は、寿永2年(1183)5月、越中と加賀の国境にある倶利伽羅峠で平家の大軍を破った。義仲軍は京へとなだれ込み、平家は船を連ねて瀬戸内海を西へ逃げていく。
これを契機に、平家は衰亡への道をたどることになる。
圧倒的優位にあったはずの平家が、なぜ義仲軍に負けたのか。
その理由は、清盛亡きあとの平家に、大軍を指揮できるだけの将がいなかったからではないかと思われる。武家として政治権力を掌握した平家だが、朝廷に深く入り込み、貴族化しすぎてしまった。
その上この頃、養和の飢饉という、大飢饉が起こっている。西日本の被害が大きく、関東はそれほどでもなかった。
関東で源氏が着々と戦さに向けて準備を進めている間、平家は兵を動員するにも兵糧がなく、動くに動けなかった。これも敗因の一つだったと考えられる。
義仲と頼朝の人間性の違い
義仲を待ち受けていたのは、荒廃した都だった。
飢饉への対応と治安の回復を期待された義仲だったが、うまくいかなかった。都人からも朝廷からも信用を失い、名ばかりの征夷大将軍となった。
後白河から義仲追討令を受けた頼朝は、異母弟にあたる範頼と義経の軍勢を、都へと差し向けた。彼らは近江粟津で義仲を討ち果たした。
頼朝と義仲は、どちらも似たような身の上ではあった。
この当時、義仲は31歳だったのに対し、頼朝は38歳。この年齢差は大きかったと思われる。
義仲が木曾に匿われるようになったのは2歳のときで、まだ年端もいかない子どもだった。自分の身の上さえ理解していない状態で、「木曾御曹司」と呼ばれて大事にされて育った。
一方の頼朝は、平治の乱のとき、すでに13歳になっていた。京で何が起きていて、誰を信用するべきか、誰を信用してはいけないか、政治とはどういうものかを、ある程度理解していただろう。
しかも、彼は一度殺されかけている。清盛の継母・池禅尼の嘆願によって助命されたものの、伊豆で幽閉されている間も、清盛が「殺してしまえ」と言えば、いつ殺されてもおかしくない状況にあった。
若き日の頼朝は、自分の身の安全を保つために必死だったはずだ。猜疑心や忍耐強さ、慎重さ、相手の心理の裏の裏を読んで人を動かす力、そういったものが培われていったに違いない。
朝廷・寺社に武家を割り込ませる
その後、義経によって平家は、一ノ谷、屋島で敗れ、元暦2年(1185)の壇ノ浦の戦いで滅亡した。清盛の死後、わずか4年のことであった。
一方、頼朝は鎌倉に幕府を開く。その政治体制は、革命に近いものだった。
清盛は朝廷に依存し、旧来型のやり方で権力基盤を作っていった。それに対し、頼朝は朝廷とは距離を置き、畿内の支配から東国を独立させて、武士を中心とする新しい政治をこの国に導入した。
頼朝は元暦元年(1184)にはすでに、公文所・問注所を置き、幕府の原型を築いた。続いて諸国に守護・地頭を設置した。
荘園制の下では、全国の荘園は貴族や寺社の管理下にあったが、そこに武家を割り込ませたのである。頼朝は、幕府・朝廷・寺社の天下三分体制を作ったといえよう。
東国を中心とする武家が、守護や地頭として各地に散らばったことは、商業圏が拡大する契機となった。
そもそもこの時代、日宋貿易の活発化によって、日本の経済構造が変わろうとしていた。宋は商業が発達した国で、そこで流通していた銭が輸入され、日本においても商業が発達し始めていたのである。
それは、政治にも大きな変化をもたらした。
平安時代、朝廷の目は畿内近辺にしか届いていなかったと言っていい。だが経済活動が拡がっていけば、全国各地への目配りが必要になってくる。
幕府が守護・地頭を全国各地に置いたことは、それに対応することにもなった。
建久10年(1199)、頼朝は落馬したことで、突然の死を迎える。跡を継いだ頼家も、その弟の実朝も暗殺され、源氏将軍はわずか3代で途絶えた。その後、幕府の実権をにぎったのが、北条氏だった。
平氏は、東国への航路の出発地である伊勢を押さえたことで勢力を伸ばしていったが、その航路の東、伊豆で力を蓄えていったのが北条氏である。
平治の乱後、清盛が頼朝を流す場所に伊豆を選んだのは、平氏の出であるとともに、この航路におけるパートナーである北条氏に預けるなら安心だと考えたからだろう。
ところが、北条時政の娘・政子が頼朝と結ばれたことから、頼朝は北条氏に担がれるかたちで挙兵、平家を滅ぼすことに成功した。
こうして、東国への航路、そして宋との貿易を一手に担っていた平家が滅んだ結果、全国の主要な港のほとんどは、北条氏が手中に収めたのである。
源氏将軍が3代で途絶え、実権を北条氏が握ったことと合わせて考えると、頼朝は神輿に過ぎず、いらなくなったら捨ててしまってもよい存在だったと捉えるのは穿ち過ぎだろうか。
その後、幕府内で北条氏が敵視し、滅ぼしていく畠山氏や三浦氏もまた、平氏の出であった。
となると、俯瞰して見るならば、源平合戦と言われるものは、平氏の内紛であったかのようにも見えてくるのである。
歴史街道 購入
アクセスランキング(週間)
更新:04月16日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 細川ガラシャの辞世~ちりぬべき時知りてこそ世の中の 花も花なれ人も人なれ
- ユダヤ人はなぜ、ナチス・ドイツの標的にされたのか
- 豊臣秀吉、天下人の辞世~露と落ち露と消えにし我が身かな
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- マッカーサーを感動させた、昭和天皇のお覚悟と天真の流露
- 小田原参陣前、伊達政宗は弟・小次郎を殺してはいなかった!?
- 陸軍兵力・軍艦数で劣る日本が、日清戦争で勝てた理由
- 世界史における「最強の武人」といえば誰? ランキング
- 日本と朝鮮半島の交流史~今だからこそ知っておきたい!
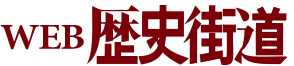




.jpg)