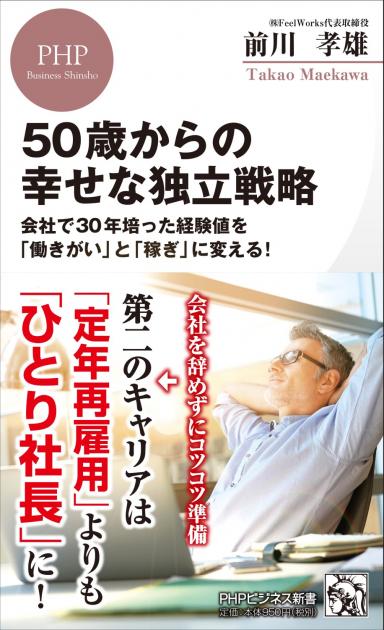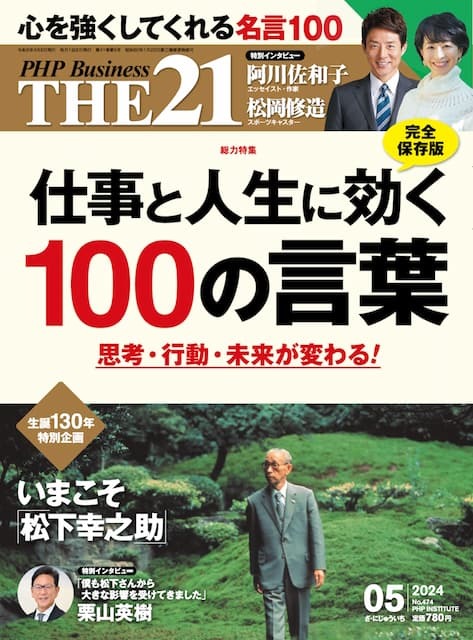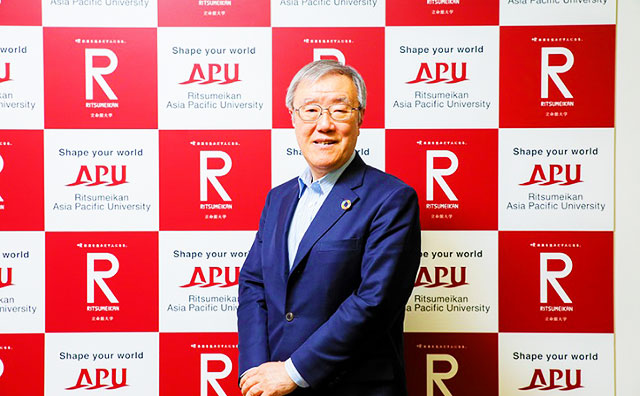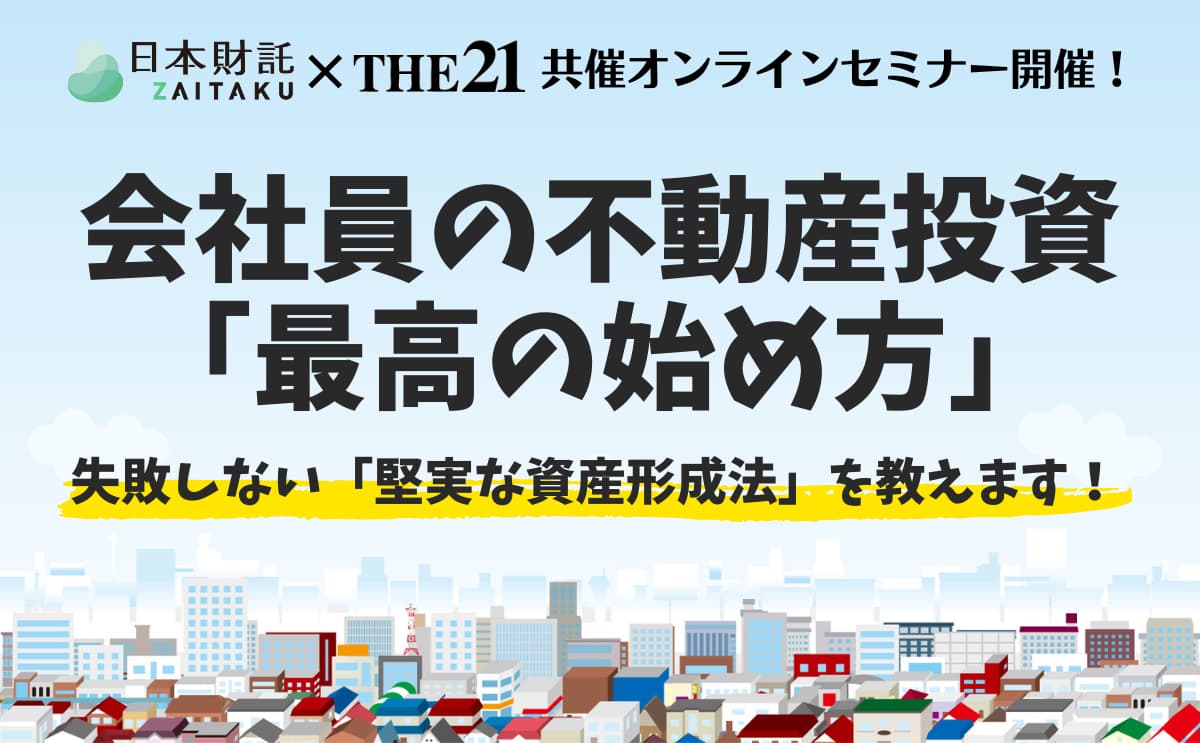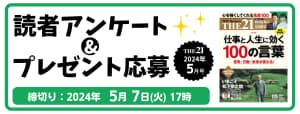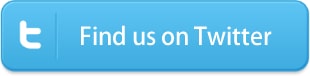50代求人は「若手の16分の1」…ミドル社員が「転職」より「独立」を選ぶべき理由
2021年01月14日 公開
2023年03月31日 更新

一般的には、「独立」よりも「転職」のほうがローリスクのように思える。
しかし、ミドルの転職・独立事情に詳しい前川孝雄氏は、「転職には思わぬリスクがある。これまで真面目に頑張ってきた50代会社員に最もおすすめなのは、『ひとり社長』として独立すること」だという。
※本稿は、前川孝雄 著『50歳からの幸せな独立戦略』(PHPビジネス新書)の一部を再編集したものです。
「リファラル転職」の理想と現実
50代のビジネスパーソンが今の会社を辞めることを検討したとき、一般的には独立よりも先に転職を考える人がきっと多いはずです。正社員または役員としての転職であれば、月々の安定した給与は保証されますから、転職は全般的にリスクが少なく思える選択肢です。
その中でも、今までの実績や能力、人柄などを買われて、知人・友人などから誘われる「リファラル転職」は、自分に向いている仕事での転職も実現可能ですし、うまくいけば報酬アップも期待できますから、魅力的な選択肢の一つです。
実績や能力を買われ、請われて転職するわけですから、経験を活かせる度合いも他の転職に比べれば高くなります。
とはいえ、業界が変わることも多く、転職先企業内での人的ネットワークをゼロから作り上げることも必要なわけで、ケースバイケースですが「経験が活かせる度合い」に関しては中程度と見ておいたほうがいいでしょう。
「エグゼクティブサーチ」は0.1%の世界
次に選択肢として浮上するのが、「エグゼクティブサーチ」です。
人材を求める企業から依頼を受けて、専門のスタッフが該当する人物をリサーチしてヘッドハンティングし、両者をマッチングするサービスですが、あなたが社外でも認知されるような実績をあげていれば、ここでピックアップされる可能性もあります。
実績や能力を評価されて、請われて転職するという意味では、リファラル転職に近く、比較的経験を活かすこともできるでしょう。
しかし、知人・友人を介するリファラル転職や後述する公募転職と比べると、その市場は極少です。標準的なサラリーマンの転職者数が年間約120万人と言われる中、1000人程度。わずか0.1%の世界です。
しかも入社後の評価はシビア。期待されているだけの実績を短期間にあげることができなければ、あっさりと切られてしまうことも多いというデメリットがあります。
「公募転職」は大企業から中小への転職が中心
リファラル転職もエグゼクティブサーチを介した転職も難しい場合は、人材紹介会社や求人サイト、ハローワークあるいは企業のWebサイトなどに掲載されている求人情報をもとに、自分から応募する公募転職がその次の選択肢となります。
公募転職の場合は大企業から大企業への転職は難しいのが現実で、大企業から中小企業への転職が中心となります。かつ、35歳以降、5歳ごとに求人数は半減し、50代ともなれば16分の1まで激減するといわれています。
当然、年収も、例えば700~800万円台から300万円台に半減することも覚悟しておかないといけません。
次のページ
一緒に働くようになったとたんに、人間関係がうまくいかなくなることも >
THE21 購入
アクセスランキング(週間)
更新:04月20日 00:05
- 50代から「キャリアコンサルタント」を目指す! 国家資格の取得で変わった第2の人生
- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック
- 50代からのiDeCoは遅い? 専門家が語る「老後資金」の組み立て方
- 個別株には手を出さない...投資歴25年「パックン流・超堅実な投資術」
- いい年して幼稚な「ベビー社員」に振り回されないためには?
- 老後いくらあれば満足? 60歳でリタイアできる人の“枯渇しない資産”の築き方
- 今からでも遅くない! 40代からみるみる結果が出る「勉強のコツ」
- 40代は“人生の曲がり角”...人事のプロが明かす「出世する人、しない人」
- 40代からの「学び直し」。勉強すべき6つの分野とは?
- 50代で「腐っていく人」「花開く人」の決定的な違い