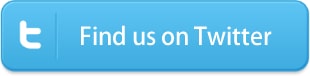反日・反独映画の虚妄――なぜ『アンブロークン』の日本上映を望むのか?
2015年03月16日 公開
2022年12月19日 更新
ドイツ兵を殺しまくる映画『フューリー』
昨年ピットは、第二次大戦時のアメリカ軍戦車兵らを題材とした『フューリー』という映画に主演したが、日本でも公開されたこの映画は徹頭徹尾ドイツ人を殺しまくるという内容だ。ピットは以前にも『イングロリアス・バスターズ』という、ドイツ人を拷問し、殺しまくり、その頭皮を剥ぎ取ることを痛快に描く低俗な娯楽映画で主役を演じている。
『フューリー』の冒頭では、アメリカ軍の戦車に踏み潰されてペタンコになり、あるいはブルドーザーで掻き集められ、ミンチのようになって穴に放り込まれる無惨なドイツ兵の死体が多く映し出される。
ピット演じる主人公はドイツ人を殺すことに異常な執念を燃やしており、「ウォーダディ(戦争オヤジ)」という寒気がするようなあだ名で呼ばれている。こんな戦争オヤジは、まだ戦場に慣れない新兵の腕をつかみ、目の前で家族の写真を出しながら命乞いをする無抵抗のドイツ人捕虜の射殺を強要するかと思えば、通りがかりの民間人の家に押し入り、持参した卵を渡して食事を準備させ、その家の若い女性をして件の新兵に対する「筆下ろし」まで強要する。まさに男の風上にも置けぬ輩であるが、かと思えば、話の途中でほんの数秒だけ苦悩するような表情を見せ、わずかに「人の心」をもっているのだと匂わせる。
当初こんなオヤジを憎んでいた初心な新兵は、上官がドイツ少年兵に撃たれ、また卵をくれたお礼に「愛の手ほどき」までしてくれたドイツ美人がナチスの砲撃で殺されるのを見て目覚め、わずか半日後には「殺戮マシーン」に変身、ドイツ兵らを機関銃で薙ぎ倒すのだ。
ドイツ軍の本物の「ティーガー戦車」が出演するということで、マニアを中心に話題となったこの映画を観た多くのアメリカ人は「じつにリアルだ」と感動したようだし、日本でも一部映画評論家が同じような感想を漏らしていた。
一方、戦車に詳しくない私は、この映画を観てひたすら吐き気を催したクチだ。リアルな残虐シーンに対してではなく、人間性の堕落について開き直ることしかできないその未熟な精神に対してである。
敵国の女性を捕まえて我がものとし、わずか数個の卵で「愛」まで芽生えさせるといった脚本家の石器時代的発想にも恐れ入ったが、それ以上に、無抵抗の捕虜を違法に殺害したピットが、話の途中でほんの少し苦悩する表情を見せることで、自らが犯したすべての戦争犯罪が理解され、許容される(べき)という感覚は、あまりに傲慢であり、甘えている。挙げ句の果てにピットは「歴史は残酷だ」という台詞を吐いて自己正当化の念押しをするのだ。
一方、『アンブロークン』に登場する日本人看守(捕虜を虐待するだけで殺してはいない)には、そんな苦悩とか自己正当化のチャンスは与えられない。もし件の日本人看守が、ピットよろしく苦悩の表情を見せて観客の理解を求め、挙げ句の果てに「収容所は残酷だ」と開き直ったら、それこそブーイングの嵐が吹き荒れるに違いない。なぜなら、われわれは正義のアメリカ白人ではなく、「野蛮で残酷な敗戦国の黄色劣等人種」だからだ。
アメリカによる無差別空襲と原爆投下という「衝撃と畏怖」作戦で対米恐怖症に陥り、占領統治で精神的にも骨抜きにされた戦後日本人の一部は、 あの男らしいサンダース軍曹が機関銃でドイツ兵をバタバタ薙ぎ倒すドラマ『コンバット』を見て育った。だから、同盟国であったはずのドイツ人が無惨に殺される『フューリー』を見て無邪気に感動できるわけだが、自分たちもまたあの戦争オヤジに殺される側にいたのだ、ということにさえ気付かないのだから、おめでたいことこの上ない。
日独の「アラ探し」が大好き
アメリカ政府は冷戦後、「ナチス戦争犯罪開示法」や「日本帝国政府開示法」といった新法を制定し、国防総省やCIA、FBIまでを総動員して一生懸命に日独両国の「アラ探し」に取り組んできた。そしてハリウッドはそれを掩護射撃するかのごとく、戦後70年も経った今日でも反日・反独プロパガンダ映画の製作に励んでいるが、その動機の根底には、日独両国の「強さ」への恐怖感がある。この両国はかつてアングロサクソンに反抗し、最後は国土の隅々まで焦土にされたにもかかわらず、戦後は不死鳥のように復活し、持ち前の勤勉性と規律、技術力と頭脳を駆使して再び大国化したからだ。
たとえば、実質的な植民地であったはずの日本はここ数年、東京裁判史観の呪縛から自らを大きく解き放ちつつあり、これまで日本人の心を支配してきたはずのアメリカにとっては、うかうかしていられない状況になりつつある。
一方のドイツは、低迷する欧州連合(EU)を独り支えることで欧州の経済的覇者となっており、また以前と違って自らのパワーさえ主張し始めている。
EU創設のもともとの発想は「ドイツは強すぎて近隣諸国と安らかに共存できない」と見る旧連合国が、「ドイツ的な欧州ではなく、欧州的なドイツ」(『フィナンシャル・タイムズ』紙、2013年3月26日)をめざすことで、統一ドイツの大国化を防ごうと考えたことに起因する。フランスはそれに乗じて、EU(=ユーロ)の強化を通じ、アメリカ一極集中体制(=ドル基軸体制)への対抗軸としようとさえ考えていた。
そんなドイツでは、最近「バカバカしいEUから脱退すべき」という感情的な声が強まっている。ドイツはこれまでスペインやイタリア、ギリシャなどの財政危機に陥った南ヨーロッパ諸国に対し、数千億ユーロもの支援をしてきたが、相手は何かあるとすぐにドイツを「ネオナチ」と呼び、そのくせいまでも、いざとなればドイツの納税者こそが自分たちを救うべきだと開き直っているように見えるからだ。
むろんEUから脱退などすれば、その新通貨(恐らくマルク)は周辺諸国に対して強くなりすぎ、ドイツは工業製品を輸出できなくなるだろうから、これはあまり得策とはいえない。ならばいっそのこと、通貨ユーロを支配して事実上の「マルク」とし、もってEUにおける経済覇権を確立するほうが手っ取り早い。
これは、いまであれば実現可能かもしれない。なぜなら、かつて欧州的知性の代表者を自負し、仏独同盟がEUを牽引すると信じて疑わなかったフランスが、ここに来て急に影響力を失いつつあるからだ。あとに残った国々など、ドイツにとっては大した相手ではない。最近、ドイツが破綻寸前のギリシャに対して冷淡に見えるのも、腹の中では、あんな余計なお荷物はできれば切り離したい、と考えているからだろう。
<<次ページ>>大国化し、反米化するドイツへの「警告」?
Voice 購入
アクセスランキング(週間)
更新:04月20日 00:05
- 実は「地対艦ミサイル先進国」日本の実力
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- ”米軍は警戒”なのに日本は…中国「史上最強の地対艦ミサイル」の脅威
- アメリカ軍は弱体化している...世界トップに躍り出た「中国海軍の軍事力」
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 専門家が、日本は「日米同盟から離脱すべき」と警鐘を鳴らす理由
- 台湾有事で想定される2つのシナリオ...中国が「米軍を奇襲する」可能性
- 中国史上唯一の女帝にして暴君 則天武后の「残忍政治とその原点」
- ソ連と同じ轍を踏むのか?「アフガン侵攻失敗」にみるロシアの行く末
- 【天才の光と影 異端のノーベル賞受賞者たち】第18回 リチャード・ファインマン(1965年ノーベル物理学賞)




.jpg)