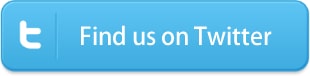バブル崩壊の“後始末”を担ったトッカイの男たち
2019年08月23日 公開
2019年08月23日 更新

バブル崩壊後、金融機関の破綻が相次いだ裏で、破綻処理や債権回収のための国策会社が設立された。とくに悪質・反社会的な債務者を担当したのが「特別回収部」、つまり「トッカイ」だった――。清武英利氏が新聞記者、ノンフィクション作家としてのキャリアをかけて、名もなき男たちの苦悩や生き様をくみ取る。
※本稿は月刊誌『Voice』(2019年9月号)「著者に聞く」、清武英利氏の『トッカイ バブルの怪人を追いつめた男たち』より一部抜粋・編集したものです。
聞き手:編集部
バブルと金融動乱の渦のなかで
――『しんがり 山一證券 最後の12人』(講談社+α文庫)では、自主廃業の真相究明と清算業務を続けた山一證券の社員たち。『石つぶて 警視庁 二課刑事の残したもの』(講談社文庫)では、官邸・外務省の「機密費」という国家のタブーに挑んだ刑事たち。
そして最新作の題材に選ばれたのが、「トッカイ」という異色の集団です。本書で彼らの存在を初めて知りました。
【清武】「トッカイ」という言葉自体、聞いたことがないという人がほとんどでしょう。
バブル経済崩壊後の1999年、日本中の不良債権を回収するために、「整理回収機構(前身は住宅金融債権管理機構)」という国策会社が設立されました。そこで働く面々の多くは、破綻した金融機関の出身者です。
つまり彼らは、「貸し手側」から「取り立てる側」に回ったわけですが、そのなかでも100億円以上などの大口で、しかも悪質・反社会的な債務者を担当したのが「特別回収部」、つまり「トッカイ」だったのです。
――本書は今年4月、つまり平成が幕を閉じる間際に刊行されました。
【清武】90年代の日本人は、バブルと金融動乱の渦のなかにいました。トッカイの男たちは、その象徴的な存在です。自分が選ぶ題材はいつも「世に残すべきもの」であってほしいと思います。
今回でいえば、平成が終わる前に、あの動乱の「後始末」に挑まざるを得なかった人びとの物語を世に残したいと考えました。喜んで挑んだ者など誰一人としていなかったのです。
正直にいえば、トッカイの話に出合ったときには“面倒”なテーマになると思いました。社会部時代にデスクとして取材の指揮をとっていましたが、私たちが知っていたのは、中坊公平氏をはじめ表の人ばかりで、現場の回収人の素顔は知らなかった。
今回の主な舞台は大阪、京都だし、住専マネーの一部はタックスヘイブンに隠されていて、極めて複雑でした。書き終えると精魂尽き果てるな、と思いました(笑)。
――それでも清武さんを奮い立たせた原動力は何だったのでしょうか。
【清武】新聞記者時代には、自分がいなければ明らかにはならなかった事実をつかもうと心がけてきました。人よりも早いだけでは、自分という記者が存在する意味がない。
いまでは「社会のトップランナーよりは後列にいる人を、明日よりは昨日を、手を挙げる人よりは歯ぎしりする人を、満足する人よりは抵抗する人を」、読みやすい文体で書いていこうと思っています。当事者の会話を可能なかぎり復元することが工夫のしどころですね。
大きな成功を収めたような人物は、放っておいても社会の注目を浴び、他の人が書くでしょう。「誰も書かないのであれば」というのが、私たちノンフィクション作家の原点のような気がします。
ある哲学者が、「人生で一番大切なのは、上手くいっているときの自分ではなくて、希望が失われた後の自分だ」と言っています。大事なのは幸運に乗っているときの自分ではなくて、幸運が尽きた後の自分です。
そのように、運が尽きた後に立ち上がる人や、抵抗人を取り上げていきたい。作品を完成させるには取材開始から2、3年はかかりますが、自分自身が尊敬、敬愛できる人であれば書き続けられる。
――ノンフィクション作品はディティール(細部)の勝負なわけですが、清武さんの作品は1行1行に込められている熱量を感じます。
【清武】敬愛する弁護士さんに「面倒なことは大事なこと」と言われて、心にあったことを言い当てられたような気がしました。その言葉を大切にしています。
若い記者だった時代に、「新幹線取材はするな」と言われていました。ぱっと行って表層を取材してさっと帰ってくる。でも、みんなそうしていたのです。
そんな取材で事件の全体像を描けるわけがない。地味で面倒な作業を行なわなくても、新聞記事は何とか書けるのです。
ただそれを繰り返していると、事件の真実など程遠い。まして当事者の苦しみなどわかるわけもない。舞台となった街中を考え考え歩き、1人でも多くの関係者に話を聞く。人に酔うくらいに会ってみる。
そうでなければ、記者として存在する意味がないのです。私たちが心を動かされ、何かを感じられる「人間の心のひだ」のようなものは、“人酔い”するくらいの執拗な取材の先にあるはずです。
Voice 購入
アクセスランキング(週間)
更新:04月20日 00:05
- 実は「地対艦ミサイル先進国」日本の実力
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- ”米軍は警戒”なのに日本は…中国「史上最強の地対艦ミサイル」の脅威
- アメリカ軍は弱体化している...世界トップに躍り出た「中国海軍の軍事力」
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 専門家が、日本は「日米同盟から離脱すべき」と警鐘を鳴らす理由
- 台湾有事で想定される2つのシナリオ...中国が「米軍を奇襲する」可能性
- 中国史上唯一の女帝にして暴君 則天武后の「残忍政治とその原点」
- ソ連と同じ轍を踏むのか?「アフガン侵攻失敗」にみるロシアの行く末
- 【天才の光と影 異端のノーベル賞受賞者たち】第18回 リチャード・ファインマン(1965年ノーベル物理学賞)


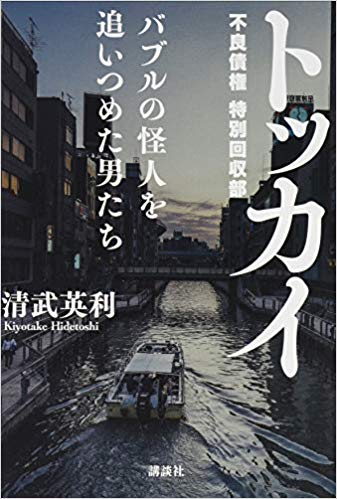







.jpg)