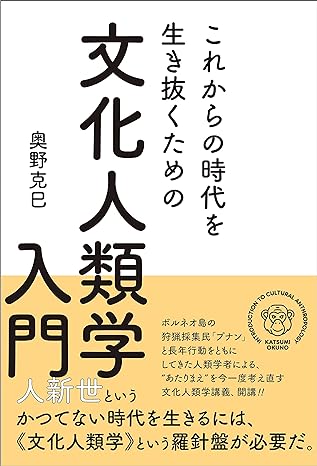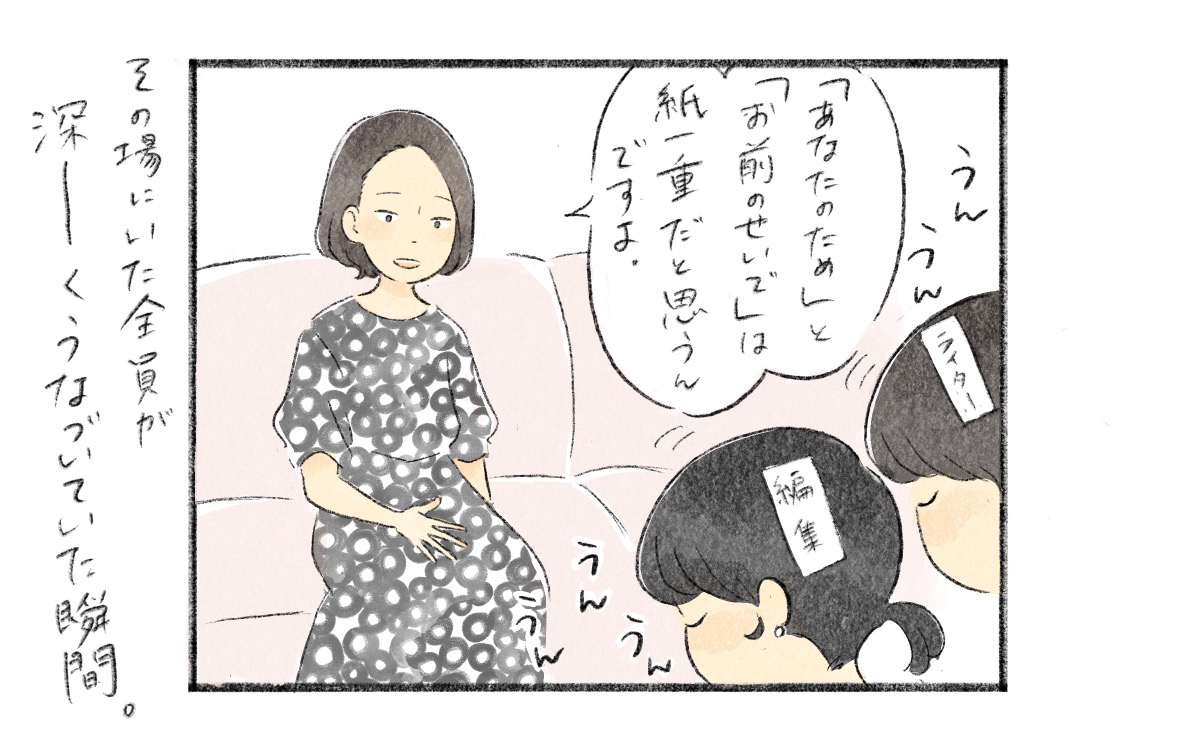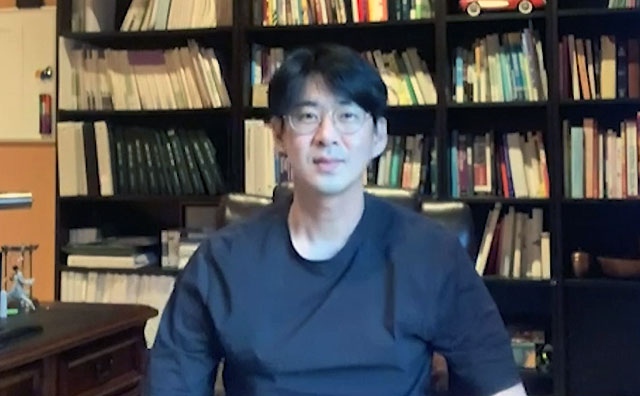Trans-womanであり性社会文化史研究者の三橋順子さんが明治大学文学部で12年にわたって担当する「ジェンダー論」講義は、毎年300人以上の学生が受講する人気授業になっています。その講義録をもとにした『これからの時代を生き抜くためのジェンダー&セクシュアリティ論入門』が刊行されました。
それを記念して、同じ「これからの時代を生き抜くための"入門"」シリーズの前巻である『これからの時代を生き抜くための文化人類学入門』著者の文化人類学者の奥野克巳さんとの対談がジュンク堂書店池袋本店にて行われました。
ジェンダー&セクシュアリティ論と文化人類学はどのように響き合うのか。今回は、その内容の一部抜粋してご紹介します。
後編となる今回は、5つのジェンダーを持つ社会、シャーマンとトランスジェンダーの関係性、そして最後は日本の現状でトークは帰結を迎えます。(構成:斎藤岬)
5つのジェンダーがあると言われるインドネシア・ブギス社会
【奥野】インドの社会はやはり男女二元論がものすごく強いんだと思います。ヒジュラは男性が去勢するんですね。それによって女神に祝福される。そのことで、たとえば子どもが生まれたときに祝福する役割を担ってきた。
ヒジュラはインドの男女二元論の強い伝統の中で培われてきたものであり、さきほど三橋さんがおっしゃったようなもう少し古層の、古い人類のやり方とはやや異なるのかなと思います。
【三橋】インドの特に北部などでは家畜の遊牧に伴う去勢文化があります。これは推論ですが、その技術が人間に適応されて、もともとあった去勢を伴わないサードジェンダー的、あるいは両性具有的な概念と重なり合ったのではないでしょうか。
去勢とジェンダー移行の文化が重なっているのは意外とヒジュラだけですよね。中国王朝やビザンツ帝国、オスマン・トルコ帝国などの宦官は去勢はするけれど必ずしも女性へのジェンダー移行はしません。身体はやや女性的になっても基本的には男性ジェンダーのままです。
奥野さんを前にして私が言うのも変ですが、今見えている文化というのは多層的に重なったものなんでしょうね。より普遍的でベーシックな文化はどんなものか考えると、南太平洋諸島などはそれがわりと残っているのかなと考えています。
【奥野】もう一方の極にあるのがインドネシア・スラウェシ島のブギスだと思います。ブギス社会では5つのジェンダーがあるといわれているんですね。
第3のジェンダーであるチャラバイは去勢が必要なく、結婚に関するビジネスのネットワークを持っています。そのビジネスに加わるために男が「チャラバイになろう」と思ったらその日からなれます。逆に、やめたいときにやめることもできる。ジェンダー固定がないようなんです。
【三橋】流動的といえば聞こえはいいけれど、けっこう商業的だしご都合主義的ですよね。だけどそれを社会が認めているというところがポイントだと思います。
「シャーマンは、普通の人と違う格好をしている」
【奥野】そうですね。祭礼を担っていたファカレイティと同様に、なんらかの社会的な役割が与えられています。つまり緩やかな形でそういう存在が社会の中で認められている。ブギスにはほかに第4のジェンダーとしてチャラライ、そしてビッスと呼ばれる両性具有的な存在がいます。
ビッスはシャーマンであり、宗教的な職を担っています。シャーマンというのはこの世とあの世という2つの世界を股にかけ、あちら側の世界に行って帰ってくることによって何らかの仕事をします。そういう意味で、ブギス社会に限らずシャーマンにはトランスベスタイト(異性装趣味)が多いですね。
【三橋】それでいうと、自分がサードジェンダー的なものに関心を持つ中で、そこにシャーマニズムが接続したのは、大学時代に一般教養で受けた佐々木宏幹先生の講義だったんです。
【奥野】シャーマニズム研究の先生ですね。
【三橋】はい。佐々木先生がこの通りに言っていたかどうかは記憶が曖昧なんですが、「シャーマンは大体、普通の人と違う格好をしている」という話があったんですね。
その格好には2つのパターンがあって、ひとつは鹿の角を被っていたり鳥の羽を着けていたりするような動物と人間が混じった格好、もうひとつが両性具有的な格好だ、と。
それを聞いていたから、日本史の研究をする中で髭の生えた巫女を絵巻に見つけたとき「日本にもやっぱりダブルジェンダー的なシャーマンがいたんだ」と思ったんですね。
あるいは、琉球弧にも女装するユタがいて、かなり近代まで残っていました。トカラ列島の悪石島では1960年代まで女装のシャーマンが3人いた。宗教的役割を担うサードジェンダー的な存在は日本にもいたわけです。
インドやインドネシア、太平洋諸島の話をしてきましたが、その分布に日本も含まれているんですよね。やはりかなり普遍性があるんだな、と。
【奥野】私はボルネオ島に住むカリスという焼畑農耕民のシャーマニズムと呪術をドクター論文のテーマにしていて、1990年代半ばにその地域に2年間住んでいたんです。
人口2000人くらいの集団で、シャーマンは男性女性合わせて10人くらいいました。そこでもやはり男性のシャーマンはトランスベスタイトで、儀礼の際には口紅をつけて普段は男性が着ない赤い腰巻きをつけます。誰から学んだのか聞いたら「先輩の男性シャーマンがそうやっていた」と言っていました。
【三橋】トランスベスタイト、日本では女装者といわれる人たちは化粧や着るものが女性よりも派手なんですよね。ある種、女性性を強調するような部分がある。それは各地の女装のシャーマンも同様ですが、人口が2000人しかいなくて文化交流も盛んではないような地域でも同じだというのはとても興味深いです。
サードジェンダーが社会で果たす役割
【奥野】アメリカでもtwo-spiritsがそうであるように、最も強力なシャーマンはトランスベスタイトあるいはトランスジェンダーですね。
【三橋】やっぱりパワーが強いんでしょうね。だから恐れられるけれど、それはつまりシャーマンとしての能力が高いわけで、トランスベスタイトあるいはトランスジェンダーであることが社会においてマイナス評価にならない。
だからトランスウーマンが社会的に弱い存在であるというのは、まったく汎世界的ではないんですよね。こう言うと我田引水だと批判されますが(笑)、世界の事例や日本の歴史的事例を客観的に見ればむしろパワフルなんじゃないかと思います。
【奥野】そうですね。佐々木先生がおっしゃっていたように、シャーマンが人間であるのに動物をまとったり、男であるのに異性装をしたりするのは、2つの世界を行き来することの象徴的な行動です。
性を越境することは、人間と動物、この世とあの世のバウンダリーを超えるということとパラレルなんですね。現実世界と目に見えない世界を自由に行き来する行為が、シャーマンのパワーの源泉です。
【三橋】こうして奥野さんと話して、自分が見取り稽古的に身に付けた知識で組み立てた話があながち間違っていないとわかってとても心強いです。
これまで私は日本のトランスベスタイトやトランスジェンダーに「あなたたちは社会集団の中で恐れられ尊敬されてきたダブルジェンダーのシャーマンの遠い末裔なんだから、そんなに卑屈になりなさんな。胸を張って生きましょう」とずっと言ってきました。
でもなかなか通じないんですね。「そうは言っても差別がきつい」というのはもちろんわかります。20世紀後半の日本社会を生きてきた自分の経験からしても大変でした。でも、やっぱりそういう見方もしてほしいなと思うんです。
チャラバイの結婚ビジネスへの関与など、サードジェンダー的な存在が社会の中で担う役割の話がありましたが、ほかにもメキシコ南部のフチタン地方ではムシェと呼ばれるサードジェンダーがいて、やはり結婚に関わる役割を請け負っています。
残念ながら私はまだインドとインドネシアとメキシコの3カ所の事例しか知らないんですが、世界ではもっとあるんじゃないでしょうか。
【奥野】いろいろありますね。社会的役割を与えられていて、そのことに誇りを持つという仕組みは各地に存在します。
21世紀になってからLGBTの概念が広がった
【三橋】社会的役割を持っていることがすごく重要なんですよね。トランスジェンダーやトランスベスタイトはどんな社会にも必ず存在します。そういう人を「神の教えに背くから」と手間をかけて殺してしまうよりも、社会的役割を与えて生かすほうがずっと合理的です。
"合理的"というと欧米的・近代的な印象ですが、そうではなくそうした人たちに役割を与えて活かしてきた社会のほうがむしろ普遍的だったと私は考えています。前近代の日本社会もそうだったんだろうな、と。
20世紀の日本の場合、職業はショービジネス(芸能)、飲食接客、セックスワークに限定されていました。私はこれを「ニューハーフ3業種」と言っています。それが21世紀になってからLGBTの概念や人権に関する考え方が社会に入ってきて、トランスジェンダーの人たちが「3業種」以外の職業にもつけるようになっていった。
私が中央大学の非常勤講師になったのは2000年です。たまたまかもしれないけれど、2000年という世紀の区切りのタイミングでそうなったのも、日本社会のひとつの流れだったのかなと思います。
最初に奥野さんがおっしゃっていた「自分語りが嫌いだと言いつつ...」という話は、自分でも書きながら思っていました(笑)。
「言っていることとやっていることが違うな」と思いつつ、1990年代から現在までの約30年の間に今言ったような社会の動きがあって、そういう時代に自分が行き当たったこと自体も偶然だし、ある種の運命だし、もっとかっこよく言うなら、それが私に与えられた役割、天命だったのかな、とこの本をまとめたときに思いました。
【奥野】ジェンダーとセクシュアリティをめぐる問題の中に私たちの現代社会における諸問題が凝縮されている可能性を、今回ご著書を読ませていただいてものすごく感じました。引き続き三橋さんのほかのご著作も読んで勉強していきたいと思います。
【三橋順子(みつはし・じゅんこ)】
1955年、埼玉県生まれ、Trans-woman。性社会文化史研究者。明治大学文学部非常勤講師。専門はジェンダー&セクシュアリティの歴史研究、とりわけ、性別越境、買売春(「赤線」)など。著書に『女装と日本人』(講談社現代新書)、『新宿「性なる街」の歴史地理』(朝日選書)、『歴史の中の多様な「性」―日本とアジア 変幻するセクシュアリティ』(岩波書店)がある。
【奥野克巳(おくの・かつみ)】
1962年、滋賀県生まれ。文化人類学者。立教大学異文化コミュニケーション学部教授。大学在学中から世界中を旅し商社勤務を経て、大学院で文化人類学を専攻。2006年からボルネオ島の狩猟民プナンのもとで定期的にフィールドワークを続けている。著作に『はじめての人類学』(講談社現代新書)、『これからの時代を生き抜くための文化人類学入門』(辰巳出版)などがある。