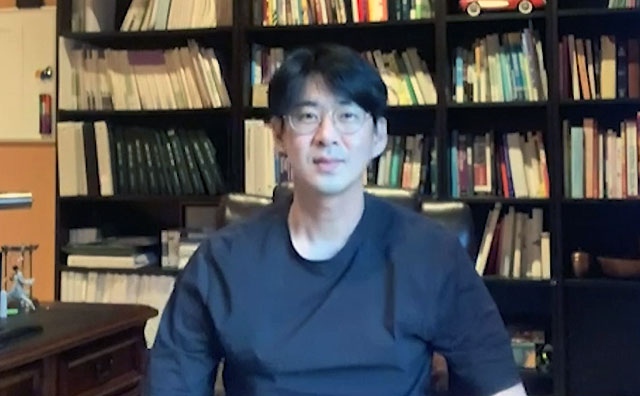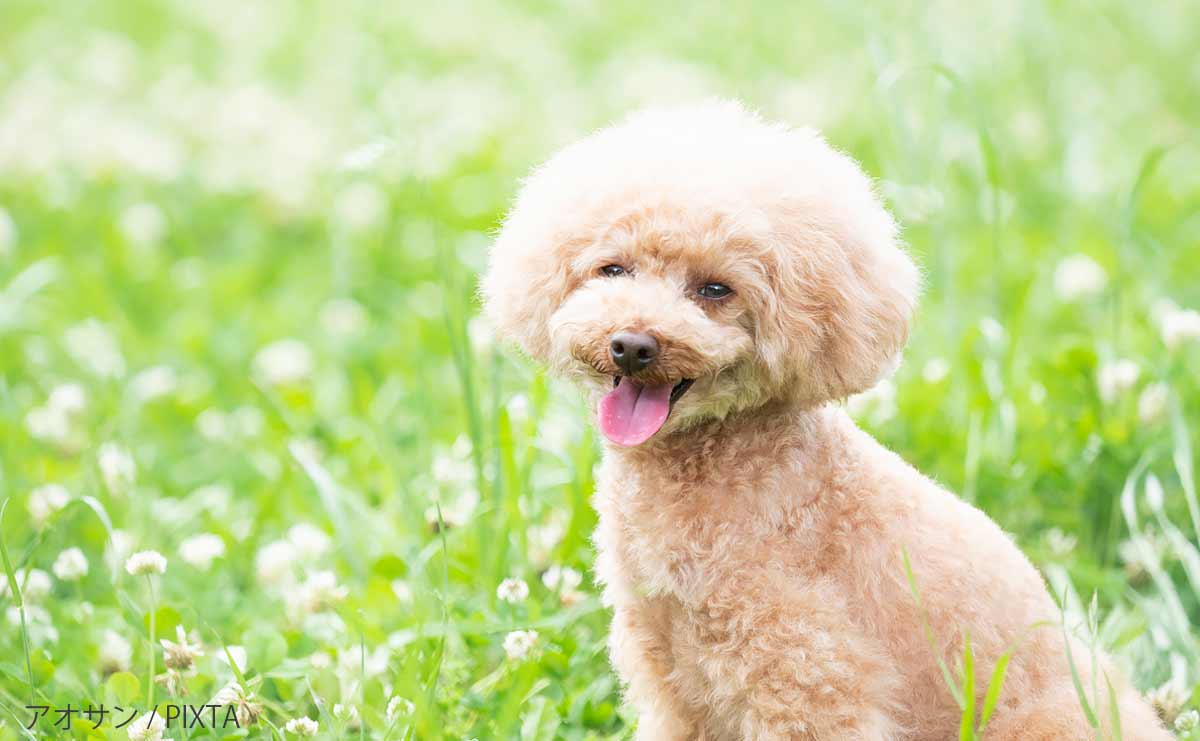人口ベースの経済に回帰する時代
2010年11月24日 公開 2022年12月20日 更新

"産業革命以前に戻る経済情勢
2008年のリーマン・ショックから2年がたった。底値からみればアメリカなど先進国の株価は大きく戻したが、ここにきてデフレ懸念の増大など、先行きに不透明感が生まれている。10月6日、IMF(国際通貨基金)はアメリカの2010年度の予想成長率を3カ月前に比べて0.7ポイントも引き下げ、2.6%とした。
対照的なのは中国をはじめとする新興国である。同じくIMFは10年度の新興国の成長率見通しを、7.1%と予想している。
危機を乗り越え、大きな経済成長を続ける新興国経済について、先進国の相次ぐ金融緩和で市場に溢れたマネーが資産インフレを引き起こしているだけ、などという指摘もあるようだ。しかしその議論は、なぜいま新興国が発展しているのか、という問いに対する本質的な答えになっていない。
先に答えをいってしまうなら、現在の新興国の経済成長は、今般の経済危機とは直接因果関係のない、いわば歴史の必然である。18世紀後半から始まった産業革命以前には、世界のGDPランキングは各国の人口規模とほぼ等しかった。当時は、現代以上に個人消費(内需)が経済に占める割合が大きかったからだ。たとえば17世紀は中国とインドの2カ国だけで、世界のGDPのおよそ3分の2以上が占められていたという。ところが産業革命以降、そのような人口規模と経済規模の相関関係が崩れていった。そして、一部の欧米諸国が世界のGDPの大部分を占めるようになったのである。
理由は二つある。まず一部の欧米諸国が先進的な技術を独占したこと。もう一つは、そのような技術伝播を拒むイデオロギーが国家間に存在したことである。市場主義を嫌った「改革開放」以前の中国、あるいは現在の北朝鮮などがそのようなイデオロギーに影響された国といえるだろう。
しかし、インターネットの出現によって、そのような状況は大きく変化を遂げた。たとえばいまでは最新の技術論文すら、インターネットを使えば簡単に読むことができる。そのように情報が世界に還流することで、一部の国を除き、イデオロギーは崩壊していった。もちろんいまでも中国政府は共産主義を採っているが、いくら政府が阻止しようとも、技術の伝播が進んでいくことを止めることはできない。もちろん、インターネットがあまり普及していないアフリカ諸国や、引き続き強いイデオロギーで管理されている北朝鮮など一部例外はあるにせよ、私は最終的に、世界はフラット化していくように思う。
そして、インターネットの普及によって、先進国がGDPの大部分を占める条件が失われつつある。世界各国の経済情勢は、再び産業革命以前に戻りつつあるのだ。換言すれば、人口規模が経済規模を決定する時代に世界は回帰しはじめたのである。
GDPの大きさで描いた世界地図というものがあるが、それをみると、その地図でいちばん大きいのはアメリカ、日本も芋虫のような巨大なかたちをしている。現状はそれが本来の地理的な世界地図のかたちに向かう過程にある、といってよいのではないか。
そのような新興国のなかで私が注目しているのは、やはり世界一位の人口大国である中国である(約13億5,000万人/2009年推計)。中国のインターネット普及率は日米に比べればまだ低いが、じつは利用人口では約3億8,400万人と、世界一だ(アメリカは約2億4,000万人、日本は1億人弱、2008年度)。
一方、中国に次ぎ、約12億人と世界で2番目に人口の多いインドであるが、インターネット利用人口は約6,000万人にすぎない。また、世界4位の人口(約2億3,000万人)を誇り、株価上昇率の高さで注目されているインドネシアに至っては、いまだ2,000万人である。東西に長く、島嶼の多いインドネシアという国は、情報効率という点でみれば分が悪いのかもしれない。
とはいえ、いずれそれらの新興国でもインターネット人口が増えていくのは時間の問題だろう。そうなれば人口規模の威力を発揮して、経済成長にもさらなるドライブがかかるのではないだろうか。
そのような高成長を続ける新興国経済だが、もちろん、そこにリスクが伴っていないわけではない。実際の経済成長を上回る速度で世界から資金が集まり、バブルに見舞われる国も今後出てくるだろう。しかし、そのような点にとらわれすぎて、先に述べた歴史の必然ともいえるべき、大局的な流れを見逃してはならない。いわばそのようなバブルの崩壊は、人口ベースの経済に世界が回帰していくという、大波のなかにおける小波にすぎないのだ。
恵まれた日本のポジション
そのような状況下、先進国としてみれば、新興国が発展することで世界経済全体のパイが大きくなれば、必然的に自らの成長率も上がるわけである。たとえば、先進国の成長率をX、新興国を3Xとすると、世界経済の成長率は4Xとなる(X+3X=4X)。ここでX=1であれば、新興国は3、世界経済の成長率は4だ。しかし、Xが0.25であれば、新興国は0.75、世界経済の成長率も4となる。世界経済の全体のパイを大きくしなければ成長は実現できない意味では、リーマン・ショックと同時に先進国が持ち出した「地球温暖化」は、あまり筋のいい議論とはいえないものだった。
そもそも「温暖化」に関しては、じつは地球はいま大きなサイクルでみると、氷河期に向かっているという説もあり、「温暖化」が進んでいるという主張自体も検証されてよいだろうし、先進国にとっては、「温暖化」を持ち出すことで、自らの国力の差を維持したいという思惑もあったのかもしれない。
もちろん、環境関連のビジネスは新しい需要を生むこともあるので、すべてを否定するべきではないし、先進国での「温暖化」問題が政治イシューにとどまらず、草の根レベルまで広がり、支持されていることも肯定されてよい。しかし、「温暖化」を理由に世界経済の成長にキャップをかけることは、先進国の成長をますます鈍化させる要因となるだろう。その意味で、2005年2月に発効した京都議定書にアメリカが参加しなかったのは、大国のエゴとも批判されるが、したたかであるともいえよう。
一方で、温暖化ガス排出量を2020年までに1990年度比で25%削減するという鳩山前首相の国際公約を受け、「地球温暖化対策基本法案」を閣議決定した日本の民主党は、私にいわせれば「ナイーブ」、つまり真正直すぎる。結局、先進国にいま問われているのは、人口ベースの発展を続ける新興国の成長をどう自らの成長に変えるのか、ということである。
日本においても今後、ますます少子高齢化が進んでいく。そうなれば当然、国内マーケットだけを相手にしている企業は成り立ちにくくなっていくわけで、株主に対するリターンを考えても、国外における新たな拠点づくりを急ぐ必要があるだろう。日本経済の未来に関しては悲観論も根強いが、この国は成長を続ける東アジア経済圏にいるわけで、戦略的にきわめて恵まれたポジションに位置しているという捉え方もできる。その際、まず進出を考えるべきは、今後も高い成長率が望める新興国ということになる。
当社もまた、海外での事業展開を重要な経営課題と位置づけ、今夏、香港のBOOM証券グループの経営権の取得を発表し、現在、当局の許認可を待っている状態である。同グループはアジア・太平洋地域における最初のオンライン証券であり、個人投資家向けにサービスを展開している。
香港は中国のオフショア市場(金融税制上の制約を少なくし、主に非居住者取引のために設けられた国際金融市場)という性格をもち、世界の資金・情報・人材が集まる国際センターだ。今後、当社は香港の同グループを拠点にして個人投資家向けオンライン証券ビジネスを拡大し、将来的には中国全土にそれを展開していきたいと企図している。
先にも述べたように、数ある新興国のなかでも中国はいっそう大きな経済発展が見込まれ、距離的にも日本に近い。中国や香港、その周辺を含めた「グレーター・チャイナ」をどう捉え、自らの成長につなげていくのか。日本企業にも、そして日本という国にもそのような問いがいま、向けられているのである。
"