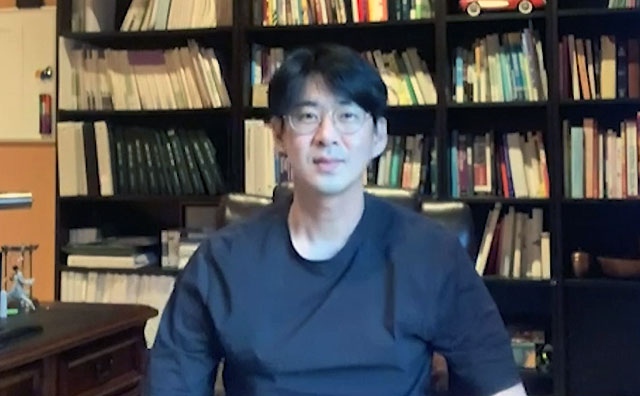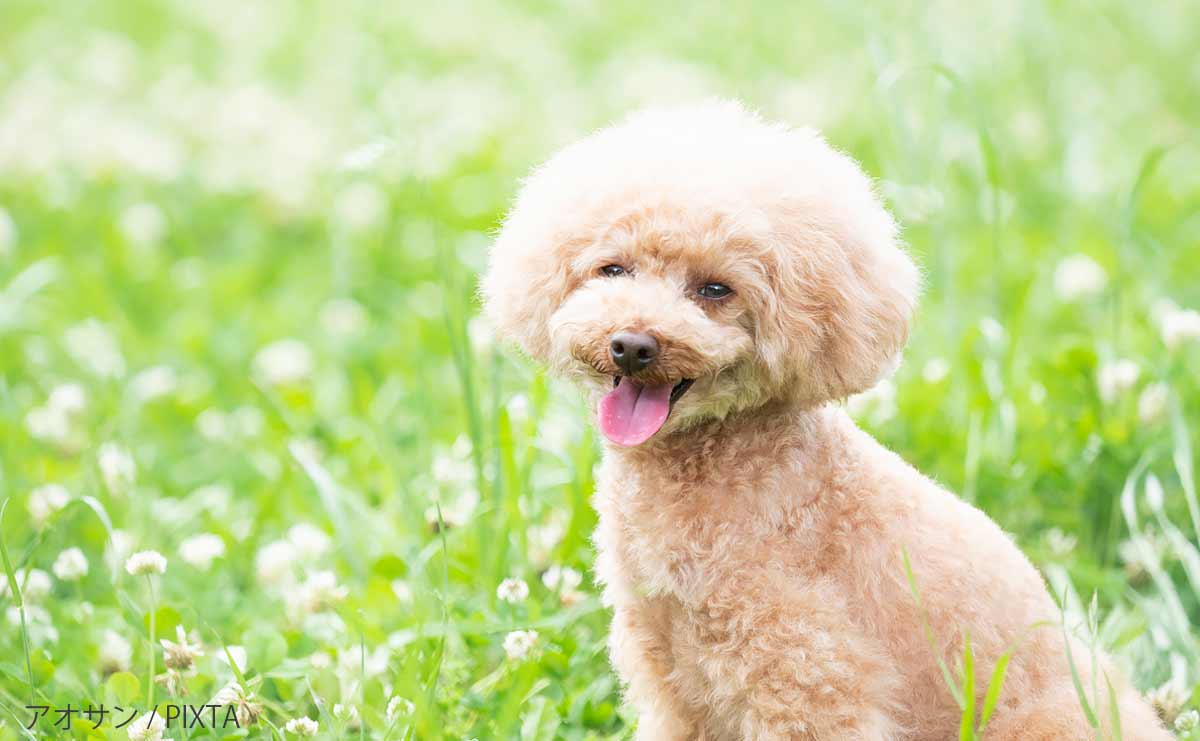だれもできなかった鎌倉時代の名刀を再現した刀匠が語る!
やり抜ける人、やり抜けない人
 実は、ものをつくる人間が潰れて、生活をダメにしていくパターンがあります。それは自分自身が美術品などの世界に興味を持ち出すことです。美に対して異常なぐらいの神経を持っている人が、下手に趣味に凝ると、中途半端で済まなくなってしまいます。よいものはどうしても欲しくなる。そうすると見境がなくなって、どんなに高額でも手に入れないと収まらなくなってしまう。それを買うために、自分自身の作品を駄作でも構わずに多作することになり、ほとんど皆、生活が崩れていくのです。
実は、ものをつくる人間が潰れて、生活をダメにしていくパターンがあります。それは自分自身が美術品などの世界に興味を持ち出すことです。美に対して異常なぐらいの神経を持っている人が、下手に趣味に凝ると、中途半端で済まなくなってしまいます。よいものはどうしても欲しくなる。そうすると見境がなくなって、どんなに高額でも手に入れないと収まらなくなってしまう。それを買うために、自分自身の作品を駄作でも構わずに多作することになり、ほとんど皆、生活が崩れていくのです。
一方、自分自身で制限を掛けてしまう人もいます。最近ではインターネットでオークションなどもできますが、ある一定の値段になるとピタッとやめてしまえるような人です。こういう人は、ある意味では自分の限度を知っている人ともいえるでしょう。自分には無理だからといって抑えてしまうわけです。もちろん、そうでないと生活破綻してしまうのですが。
人間としてどちらのタイプがよいのかは、わかりません。しかし、作家として生きようという人で、自分の気持ちにそういうブレーキをかけられる人というのは、意外と伸びない。
自分で限界を知っているということは、ついつい自分の技術にもそういう限界を設けてしまいかねないのです。
逆に、たとえ身を持ち崩しても、止まることを知らない人のほうが、成功することがある。後世に作品を残せる人というのは、作家全体の0.1パーセントに満たないかもしれません。その0.1パーセントに残る人になれるのは、それだけの気魄で自分の仕事に賭けていく人でしょう。
もちろん、骨董美術品や賭博などに全身全霊をかけられなくてはダメだという話ではなく、それくらい、一度はまったらトコトンまで行ってしまうような人でなければ、本当の意味での成功はできないということです。
「ニーズに応える」という発想では日本の製造業は滅ぶ
私がものをつくるうえで一番嫌いなのは、「ニーズに応える」という考え方です。
「ニーズ」とは何でしょうか。たとえば刀でいえば、「ニーズ」を語る人よりも、自分自身のほうがよほど刀を知っているという自負がなければ、刀工などと名乗れないはずですし、刀をつくるために日々、死ぬ思いをして苦労してやっているのです。それなのに、どうして「ニーズ」なるものに合わせる必要があるのでしょうか。
私は、日本の工業力が究極のところでダメになってしまうのは、そういうところからではないかと思います。
たとえば製鉄所でも、自動車メーカーの人がやってきて「こういう鉄をつくれ」などとやる。製鉄会社も、それをやれば売れることがわかっているから、全部意見を取り入れる。しかし、そこに製鉄屋としての誇りはないのでしょうか。「あなた方がそういうスペックを要求するのなら、われわれはこういう鉄を生み出してみせる」と言い切って、実現してみせる気概はないのでしょうか。
「ニーズにあわせる」「市場調査をする」「マーケット・イン」「お客様は神様で、お客様の声は天の声」――言葉は何でもいいですが、しかし、そういう発想からは、本当に突き抜けたもの、本当に美しいものは生み出せないはずです。
本田宗一郎さんやソニーの井深大さん、松下幸之助さんなどを挙げるまでもなく、かつての日本企業では、そんなせせこましい発想ではなく、もっと作り手の誇りを大切にして、尖った製品を生み出してきたケースがたくさんあったように思います。そして、それだけ突き抜けたものがあったからこそ、日本の製造業は世界一と称されるまでになっていったのではないでしょうか。
「二番だったら死んでいる」という責任感
もう一つ、ひどい例を挙げると、ある経営コンサルタントがあたかも「芸術家も材料費から値段を決めたらどうか」とでもいうような話をしているのを聞いたことがあります。なんと「ものの価値」がわかっていない話かと、大いに驚いたものです。
話としては、値段を決めるのに材料費から積み上げるということはわかります。しかし芸術家は、その道をめざす99.9パーセント以上の人が歴史に名を残すことができないことを承知したうえで、どうやって0.1パーセントに残るかに全身全霊を賭け、死ぬ思いでイノベーションを生み出しているのです。
東山魁夷さんの絵の値段は、絵の具などのコストから決められるのでしょうか。そうではなくて、東山魁夷さんほど突き抜けた存在になれるのは、いったい何パーセントの確率なのかという、そういう部分から価値が生まれてくるのではないでしょうか。
今挙げたコンサルタントの発言はずいぶん極端な例ですから、誰もが「おかしい」と思うかもしれません。しかし考えてみると、ついつい「材料費から積み上げて」という発想になってしまっているケースが、実は今の日本では多くないでしょうか。
日本人はソフト産業で勝ちきれないというのも、そういう発想からきているように思えてなりません。「世界で一番の『よいもの』をつくるのに、どうやって突き抜けるか」という発想ができなければ、所詮勝ち抜くことなどできないのです。
そのことを痛感したのは、零戦のエースパイロットだった坂井三郎さんの刀をつくったときのことでした。坂井三郎さんが80歳の時に刀の注文を受けたのです。戦時中はいい刀を持てなかったので、あらためて日本刀をつくりたいということでした。結果的にはご存命中に間に合わなかったのですが、二度、お目にかかり、色々なお話をうかがいました。
そのお話の中で強く印象に残ったのは、「二番だったら死んでいる」ということでした。
「空戦のときに少しでも自分の体調が悪かったら死んでいました。体調管理できない人から戦死してしまいます。自分を律せなかったら、私は今、ここにいません」というような言葉が、坂井さんからどんどん出てくるのです。
この言葉を聞いて、私自身、身が引き締まる思いがしました。
もし自分のつくった刀が「二番」の性能だったら、それを使った人は戦場で命を落としてしまうかもしれない――そういう緊張感を伴ったものであることは、私ももちろん頭ではわかっていたかもしれませんが、坂井さんのお話をうかがって、まさに実感として胸に迫ってきたのです。
刀は本来、「武器」ですから、そういうことがわかりやすいのかもしれません。しかし本来、ものづくりに携わる人ならばすべて、あらゆるものに「自分がつくったものが一番でなかったら、使ってくれた人に大きな迷惑をかける」という緊張感が必要なのではないでしょうか。
本当の意味で突き抜けたものをつくる。「一番」のものをつくる。そうでなければ、作り手として、それを求めてくれた人に申し訳が立たないはずなのです。