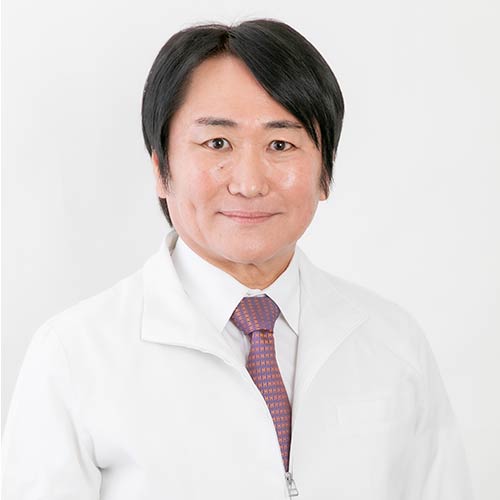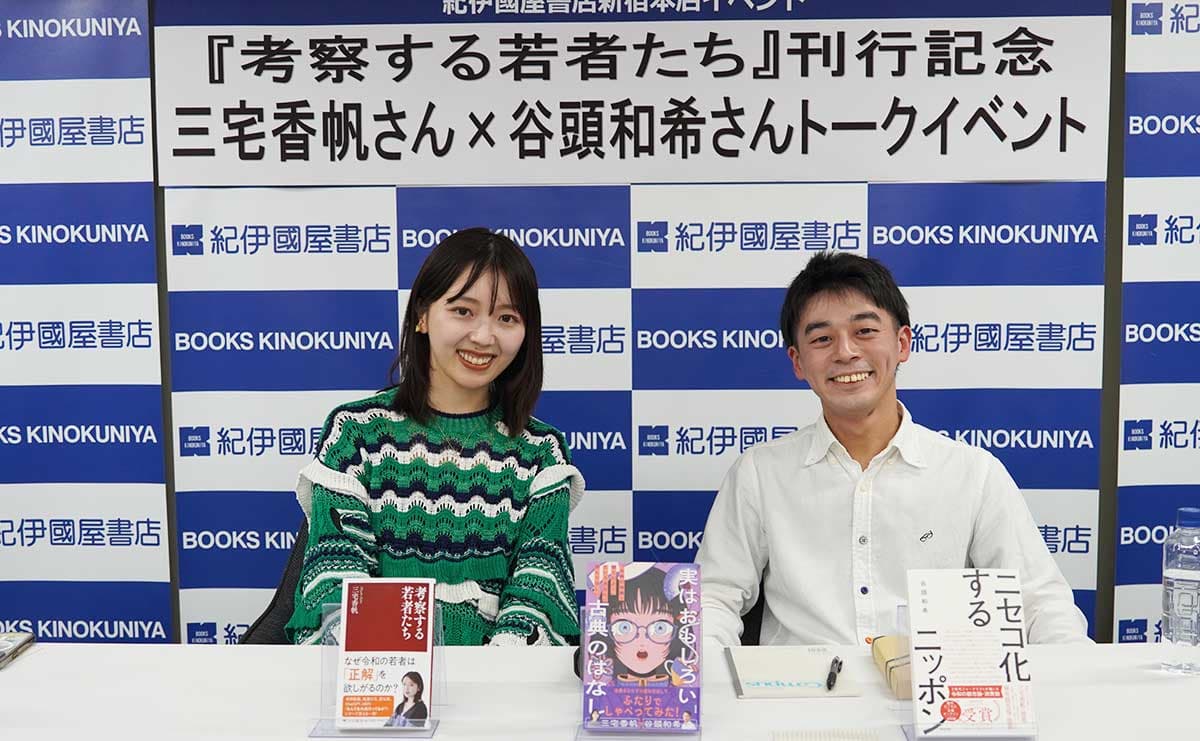歯の黄ばみ、着色を防ぐ「食べ方」 歯科医師が指摘する間違ったセルフケアとは?
2025年05月28日 公開

歯の白さは清潔感や若々しさの印象につながるために、黄ばみや着色を改善したいと考える人も多いでしょう。黄ばみや着色は「不健康」「だらしない」などの印象にもつながりやすく、せっかくの笑顔の魅力を下げる可能性も。今回は歯の黄ばみ、着色を防ぐ方法や食べものに関することをご紹介します。
歯の黄ばみの原因は「脱灰」 カギを握るのは「間食」
歯の表面はエナメル質という硬く半透明な白色の層で覆われて、ハイドロキシアパタイトというリン酸カルシウムの一種で構成されています。
通常、お口の中は歯が安定する中性〜弱酸性なのですが、歯が苦手な酸性の状態になると、エナメル質からカルシウムイオンとリン酸イオンが溶け出します。この状態を「脱灰」と言います。
歯が脱灰すると表面に凸凹が生じて、光が乱反射するために歯の輝きが減少。歯が黄ばんで見えるようになります。通常は唾液が持つ中和作用で酸性から中性〜弱酸性に戻し、「再石灰化」作用によりカルシウムやリン酸を再び歯に取り込みます。
お口の中を酸性の状態にするのが飲食です。そのため「脱灰」しても食事と食事の時間が空いていれば「再石灰化」しますが、度々間食すると「脱灰」と「再石灰化」のバランスが崩れてしまいます。そうなると脱灰状態が進行し、歯の黄ばみリスクが上がります。つまり「ダラダラ喰い」が歯に黄ばみをもたらす犯人です。
「脱灰」は歯の黄ばみだけでなく、むし歯のリスクも上げます。「脱灰」により歯の表面が弱くなり、むし歯菌の抵抗力が下がってしまうからです。歯の健康を考えると「ダラダラ喰い」はNG行為ですから、間食するなら短時間で切り上げた方が良いです。
こういう指導を患者さんに行うと、時々「間食は短時間で食べれば良いのですね?お菓子を鷲掴みにして、一気に口に入れて食べます!」と言う方がいらっしゃいます。言うまでもなく、危険ですから辞めてくださいね。「ダラダラ喰い」をしなければ良いのですから。
歯の黄ばみ、着色につながる食べ物、飲み物
歯の黄ばみにつながる飲食物は「酸性」が強いものです。食べ物ではレモンやオレンジなど柑橘系の果物全般がそれにあたります。その他に野菜類も酸性のものが多いです。
反対にチーズなど乳製品は中性に近く、肉・魚類も歯の黄ばみリスクが低い食べ物になります。
飲み物では酢を使ったものは酸性が強いので、黄ばみリスクは高いです。コーラは酸性が強いだけでなく、糖分も多く含むのでむし歯リスクも高くなります。その他、栄養ドリンクやスポーツドリンク、果汁ジュースや野菜ジュース、お酒類も黄ばみリスクを上げます。
他方、豆乳は最もリスクがなく安全な飲み物で、その他に牛乳、水、お茶類もリスクが低いです。
「今晩はゆっくり晩酌でもしようかな?」と考える日は、歯の健康を考慮して「チーズ」をおつまみに「豆乳」を楽しむのがおすすめです(笑)。
黄ばみ対策として酸性が強い飲食をした後に、酸性の状態を早く中和する作用のマウスウォッシュでうがいをするとリスクは下げられます。(参考:アース製薬「リセットコートプロ」)
歯の着色の原因になる飲食物には、お茶やコーヒー、紅茶、赤ワイン、カレーなど色が濃いものが挙げられます。飲食物に含まれる色素が歯に付着して着色しますが、タバコのヤニは歯につきやすく落ちにくいので喫煙も原因になります。
まちがったセルフケアが悪化の原因に
黄ばみ、着色を促進させるものに歯の磨き残しがあります。原因は不十分な歯磨きです。また、口の中の乾燥も黄ばみ・着色リスクを上げます。通常、呼吸は鼻でするのですが、口の機能が弱い人や季節柄、アレルギー体質で花粉症の人は口呼吸になることが原因です。また、年齢が上がって唾液の分泌量が減ることや、歯にダメージを与える歯ぎしりや歯の食いしばりによっても黄ばみ・着色リスクが上がります。
絶対に行ってはいけないセルフケアは、着色除去効果のある研磨剤が入った歯磨き粉で歯磨きすることです。成分で言うとリン酸カリシウや酸化アルミニウム、無水ケイ酸がそれにあたります。確かに表面についた汚れは良く落ちるのですが、長年の使用により研磨剤でエナメル質の表面が傷つけられるため、その隙間にかえって汚れが付きやすくなります。
最近は研磨剤配合の歯磨き粉は減ってきていますが、購入の際に成分を確認した方が良いです。逆にピロリン酸ナトリウム・ポリリン酸ナトリウムは科学的に歯の着色を落とすので、歯を傷つける心配がありません。
また、硬い歯ブラシを使って力を込めて歯を磨くことも歯の表面を痛めるため、歯の黄ばみに繋がります。
歯の黄ばみ対策としては、食生活の改善が効果的です。酸性の強い飲食物や色の濃い飲食物は避けられるなら避けましょう。酸性の飲食物を摂る時は、なるべくお口に留まる時間を短くしたほうが良いです。
例えば酸性が強く、色も濃い赤ワインは、口の中でワインを転がす時間を程々にしたいもの。食後はフロスや歯間ブラシを使って歯と歯の間をしっかり丁寧に磨くと効果的です。
この時、歯磨き粉はフッ化物配合の物を選んでください。フッ化物はエナメル質のハイドロキシアパタイトを更に強いフルオロアパタイトにバージョンアップする作用があり、歯の黄ばみ対策では必須と言えます。
セルフケアでは改善できない「加齢による黄ばみ」
黄ばみは加齢によっても起こるのですが、自分で対応するのは難しいです。歯の表面のエナメル質は半透明な白色ですが、その下の層にある象牙質は黄色味を浴びた組織。加齢とともに摩耗して薄くなったエナメル質から象牙質の色が透けて見えるようになり、歯が黄ばんだようになります。
また象牙質自体も加齢で色が濃くなる性質なので、さらに歯の黄ばみが目立つようになります。この黄ばみは歯の構造的な原因ですので、セルフケアは難しいのです。
加齢での黄ばみ対策には「ホワイトニング」が効果的です。ホワイトニングには「歯を白くする」意味があるのですが、方法は「歯の表面の汚れを落とすホワイトニング」と「歯の元の色を白くするホワイトニング」の2つに分かれ、加齢対策のホワイトニングは後者にあたります。歯の元の色を白くするためには象牙質の水分を抜いて漂白するので「漂白ホワイトニング」とも言われます。
漂白ホワイトニングは元の色より白くできるので、画期的に黄ばみは消え、歯が輝く白さになります。2013年にイギリスの新聞サイトが男女2000人を対象に行った調査で、歯を白くすると5歳若く見えるとされていることからも、漂白ホワイトニングによる見た目のアンチエンジング効果は非常に高いと言えます。
歯科医院専用の薬剤と反応を高めるライトを使用する「オフィスホワイトニング」は短時間で歯を白くできます。薬剤を歯科医院で購入し、専用のマウスピースを使って自宅で行う「ホームホワイトニング」は、効果が出るまでに期間はかかりますが、歯科医院に通う手間は省けます。
歯科医院によって採用しているホワイトニングの方法が異なりますので、ホームページなどで確認してから受診することをおすすめします。