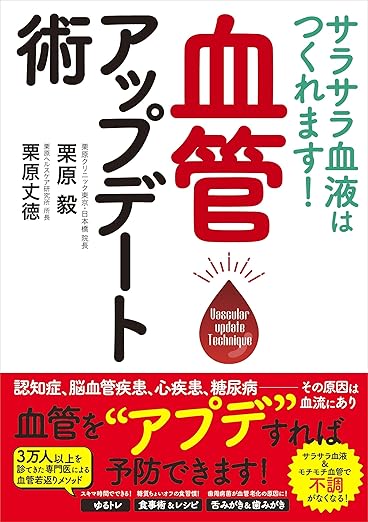「血糖値スパイク」という言葉をご存じですか? 血糖値の急激な乱高下は、気づかないうちに血管を傷つけ、将来の病気リスクを高めてしまいます。栗原クリニック・日本橋院長の栗原毅先生が、この血糖値スパイクを防ぎ、血管を健康に保つための具体的な食事のコツを解説します。
※本稿は、栗原毅・栗原丈徳著『サラサラ血液はつくれます!血管アップデート術』(日東書院本社)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
食べる順番を意識! 野菜と肉・魚はご飯より先に
糖質の摂り過ぎが体に良くない理由のひとつが、血液を汚してドロドロにすることですが、血管にもダメージを与えることがあります。その原因になるのが「血糖値スパイク」です。
血糖値スパイクとは、「血糖値の乱高下」のこと。空腹状態でごはんや麺類を食べると血糖値が急上昇し、そのあと急降下します。これを繰り返すことで血管がダメージを受けてしまうのです。
血糖値スパイクを繰り返す人は、血糖値が安定している人に比べて、心筋梗塞や脳梗塞などの"血管が原因の病気"の発症リスクが倍になるといった研究結果があります。それだけ、血糖値の乱高下は血管に大きなダメージを与えてしまうのです。
これを避けるには、日頃の食事において「食べる順番」を意識することが大切です。最初に野菜などの食物繊維、次に肉や魚、卵などのたんぱく質を摂ることをおすすめします。糖質、つまり炭水化物を多く含むご飯やパン、麺類はそのあとに食べるようにしましょう。
最初に食物繊維を摂ったほうがよい理由は、腸の中で糖質の吸収を抑えてくれるはたらきがあるからです。先に腸にたどりついた食物繊維が、糖質が体に吸収されるのを緩やかにするわけです。
また血糖値を上げないために、私は「お酢」を先に摂ることもおすすめしています。お酢を食事前に大さじ1杯摂ることで中性脂肪の数値を下げ、血糖値の急激な上昇を抑えてくれます。
「プラス10回余計に噛む」食事術
糖質の急激な上昇を抑えるには、ゆっくりと時間をかけて食べる食事法をおすすめします。「早食い」は血糖値スパイクの天敵で、とくに日本人は食事に時間をかけないことで知られていますから、意識してゆっくり食べることを心がけたいものです。
毎日の食事では、同じ量を食べても「噛む回数」を増やし、時間をかけて食べれば血糖値の上昇が緩やかになります。私は食事の際、ひと口につき「30回の咀嚼」が良いとして、ゆっくりと味わいを楽しむことをおすすめしています。
ただ、ひと口ごとに30回の咀嚼は、慣れないうちは時間がかかって大変だと感じるかもしれません。そのため、まずはいつもよりも10回多く噛むことから始めれば良いとお伝えしています。
よく噛んで食べることで消化を促すとともに、あごを開けたり閉じたりする咀嚼によって顔などの骨や筋肉が動き、血流が増加することも知られています。ぜひ噛むことの大切さを今いちど認識してほしいと思います。
お酒は適量であれば、「飲まないよりも飲んだほうがいい」
アルコールには血管を拡張するはたらきがあり、精神的なリラックス効果も期待できることから「酒は百薬の長」ともいわれてきました。
お酒は適量であれば、「飲まないよりも飲んだほうがいい」といえます。けれども適量を超えての飲酒、またお酒の種類によっては血流に悪影響を与えますから注意が必要です。
厚生労働省がまとめた飲酒ガイドラインでは、生活習慣病のリスクを高める1日あたりの平均純アルコール摂取量を「男性40g以下、女性20g以下」としています。1日の男性40g以下を適量とするのかはまだ議論の余地があり、重要なのは「適量には個人差がある」ということです。
つまり自分の適量を守れるのであれば、お酒は毎日飲んでも問題ないといえます。ちなみに、アルコール20gの目安となる「量」を紹介するので参考にしてみてください。
●ビール・缶チューハイ(5度):500ml(ロング缶1本)
●日本酒(15℃):180ml(1合)
●焼酎(25度):110ml(0.6合)
●ワイン(14度):180ml(1/4本)
※アルコール度数によって目安は変わります
肝臓に負担をかけない量に留めることが大事で、それを守っての飲酒なら、"休肝日"も必要ないといえるでしょう。
【栗原毅(くりはら・たけし)】
1951年、新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。元東京女子医科大学教授、元慶應義塾大学大学院教授。現在は栗原クリニック東京・日本橋の院長を務める。日本肝臓学会肝臓専門医。治療だけでなく予防にも力を入れている。血液サラサラの提唱者のひとり。監修書・著書多数。
【栗原丈徳(くりはら・たけのり) 】
1982年、東京都生まれ。歯科医師。鶴見大学歯学部卒業。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科中退。日本抗加齢医学会、日本咀嚼学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会、日本サルコペニア・フレイル学会などの会員。