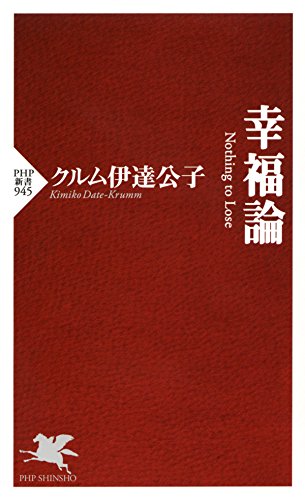※写真はイメージです
子どもか、テニスか――。当時37歳、プロテニス選手のクルム伊達公子氏がたどり着いた、自身の人生の「幸せのかたち」とは。
※本稿は、クルム伊達公子著『幸福論Nothing to Lose』(PHP新書)より一部抜粋・編集したものです。
憧れた彼女の幸せのかたち
2008年3月15日。待ちに待ったエキシビション・マッチ「ドリームマッチ2008」の舞台に私は立っていた。6カ月前から本格的な練習を重ねてきたのは、すべてこの日のためだ。試合は、ナブラチロワとの8ゲームに始まり、グラフとの3セットマッチ。
コートに足を踏み入れた時、観客席がいっぱいのコロシアムを見渡して感激した。本当に有明コロシアムがいっぱいになるほどの人たちが楽しみにしてくれていたのかと思うと、嬉しくなった。
この時、私はグラフを、6-2、6-3のストレートで破っている。現役時代、完璧な強さを誇ったグラフに私は憧れ、また尊敬の念を抱いていた。グラフは神様に選ばれた特別な才能をもった選手だと本当に信じていた。
だから、引退から9年のブランクがあったところで、以前と変わらないプレイをするのだろうと、いつも心のどこかで思っていた。この日、有明のコートで実際に打ち合うまでは。
観衆の見守る中、半年間の徹底したトレーニングを経てコートに立った私は、グラフと打ち合いながらも「まさか?」の気持ちを終始ぬぐえなかった。
いくらエキシビションとはいえ、これが本当に、女子シングルス1位の座を通算377週もの間守り、サイボーグのような強さで世界に君臨し続けたグラフのプレイなのだろうか?
しかし、ゲームを重ねるうちに気づかされた。グラフもまた、並々ならぬ努力の上に世界のトップに君臨し得た人だったのだ。孤独な頂点にあって私の何倍ものプレッシャーを受けながら、何年間も想像も及ばないような険しい道を、彼女はひとり走り抜けてきた。
そしてテニスにおいて、もうすでにやるべきことはやり終えたのだ。今の彼女は子育てと家庭が最優先。テニスへの情熱も闘争心も、現役の頃とはまったく違ったものになっている。それを表すかのように試合を前にしてグラフは言った。
「今、私は片時も子どもと離れたくないの。エキシビションが終わればすぐに帰る。一刻でも早く子どもに会いたいから」
試合後、本当に彼女はシャワーを浴びる時間も惜しんで空港へと向かったという。もはや、彼女のアイデンティティはテニスにはなくなっていたのだ。
このドリームマッチではもうひとりの主役、その時点で51歳のナブラチロワとも対戦することかできた。WTA最多優勝記録(シングルス167勝、ダブルス177勝)を誇るナブラチロワもまた、私の尊敬するプレイヤーであり、言わずと知れたスーパーな存在だ。
かつて、私はいつも「グラフとナブラチロワを足して2で割ったようなプレイをしたい」と思っていた。現役時代、ナブラチロワとは練習する機会が一度あったのみで、試合は一戦もしたことかなかった。そのため、彼女との対戦にも感無量のものを感じていた。
そのナブラチロワは、グラフとはまた対照的な人だった。テニスをきっぱりとやめて結婚し、妻として、毋として女性の幸せに生きるグラフ。引退とカムバックを繰り返し、シングルのまま49歳まで現役を続け、テニス一筋に生きるナブラチロワ。
私は自分がグラフ的な考えをもち、生き方をするものだとずっと思っていた。しかし、自分でも想定外のことに、結婚してからその考えが変わった。 今の私にはナブラチロワのすごさ、素晴らしさがよくわかる。
年齢を感じさせないパワーをもち続け、周囲の人たちに多大な影響を与え続ける彼女。そのためにどれほど多くの努力を今も続けているか。私は自分もトレーニングを始めることで、改めてナブラチロワの食事やトレーニングの徹底した自己管理ぶりに頭の下がる思いがした。
加えてライフスタイルや信条における明確な姿勢。何よりテニスに対する変わらぬ想い……。グラフとナブラチロワという対照的な、しかし自分の希求するものに対して妥協することを知らない、尊敬するふたりの生き方を垣間見ることともなった至福の時。それは終わってしまえばあっという間の出来事でもあった。
ちなみにこの日、私はナブラチロワにも8-6で勝つことかできた。そしてこの夢のような体験は、私にとってさらに新たな挑戦へのスタートとなったのだ。
ドリームマッチで得たもの
初めはこのイベント、夢のような対戦を楽しむつもりだった。ところが、知らず知らず、私の胸にまったく違う想いか芽生えていた。勝ちたい。この試合に勝ちたい。勝負にこだわっている自分に気づきながら、そのこと自体さえ、楽しいと感じていた。そうだ、私はテニスで真剣勝負がしたいのだ。
コートを走り回りながら、そしてボールを打ち返すたびに、その想いは確実に膨らんでいった。しかし勝負の世界に身を置くことは、同時にもう一方の幸せの実現可能性を、また確実に小さくするものでもあった。
37歳という年齢からしても、子どもを授かるのは、さらに厳しいものになるだろう。残されている時間が、少ない。ただでさえ、35歳と40歳ではずいぶん違うと言われる。1年の重みは大きい。それを今この年齢で、ましてや当然身体に負担がかかるような、また逆戻りするような方向へと自ら進んでしまうのだ。
長い時間をかけて悩み、考えた。子どもか欲しい。その思いに変わりはなかった。しかし日を追うにつれてテニスへの情熱が次第に大きくなっていった。子どもか、テニスか――。1カ月もの間、答えを出せずにいた。
そんな私を見て、マイクは言った。
「ぼくは公子と結婚した。子どもと結婚したわけじゃない。公子か一番大事だ。子どものために、自分のしたいことをあきらめようというのは間違っていると思う」
その言葉で、私は呪縛から解き放たれた。「とりあえず今は中断」というかたちをとってもいいのではないか。まずは私がやりたいと思うことを優先して、やっていけばいいのではないかという結論に落ち着いた。
今でも自分の子どもは欲しい。でも、テニスは私に必要不可欠なものだ。こんな人生を味わえる人は世界中見渡してもそうはいないだろう。だから戦い続けられるかぎりは、やってもいいのかもしれない、そう思えるようになった。
ナッシング・トゥー・ルーズ(Nothing to Lose)
ただし、私が恐れていたのは、子どものことだけではなかった。
あの時の決断が間違っていたということになるのが嫌だった。私としてはまったく違う気持ちでコートに立つつもりではいたが、復帰すれば、26歳の決断はやっぱり早すぎたのだと思われてしまっても仕方ない。加えて、世間に記憶されている1996年の時の私のイメージ。あまりにもかけ離れたプレイになったとしたら……とも考えた。
11年半のブランクかどれだけ大きなことか、自分自身でよく認識しているつもりだった。テニスは1日練習を休むとそれを取り戻すのに3日かかると言われる。ブランクもあり、さらに37歳という年齢。もうあの時には戻れない。「やっぱりテニスをしたい」という気持ちがあるとはいえ、それだけで踏み切ってしまっていいものだろうか。とうてい歯が立つとは思えないし、想いだけでそこに立ってしまっていいのだろうか――。
その時、マイクか言った。
「ナッシング・トゥー・ルーズ(Nothing to Lose)。失うものは何もないじゃない」
とてもシンプルな言葉だった。
「いいじゃない、今の年齢で負けても問題ないよ。以前のようにできるわけない。それがどうしたの? 同じことはできるわけない。でも今だからできることだってあるよ」
彼は続けて言った。私がやりたいと思い、やろうとしていることは、何も恥ずかしいことではない。たとえそれが失敗――全然歯が立たない、何もできないという結果に終わったとしても、これまでにやってきたことが消えるわけではないし、減るものでもない。反対にみなはすごいことをやったと思ってくれるはず。何も過去を引きずることはないと。今自分がやろうとしていることを、一からやればいいと言ってくれた。
何をそんなに周りのことを考えているんだ。とにかくシンプルに、公子はやりたいんでしょ。だったら、やればいいじゃないか。プレッシャーは、自分自身でかけているだけなんだよと、彼は言った。
思えばこの間、私はいろいろなものに取り組んできた。それでも本気で挑戦できるものをつかみ取ることかできなかった。それは、私にとってはやはり、テニス以外にあり得なかったのかもしれない。
幸福は誰に舞い降りる?
チャレンジ第1戦のカンガルーカップ国際女子オープン。岐阜のスタンドは2000人の観衆で埋め尽くされていた。
対戦相手は、私より20歳も若い現役高校生だった。11年半ぶりにプロとしてコートに立った最初の試合。今思い出しても、どちらに転んでもおかしくないような状態だった。何が起きるのかまったく見えない中でのスタート。
ただし、たとえまったく歯が立たなくても私の目的はそこじゃない。どんな結果も受け入れるだけの心の準備はあった。
ファーストセットを落とした。そこで何か吹っ切れた感じがあった。硬くなっていた試合用の筋肉がほぐれたとでも言えばいいだろうか。その後、セカンドセッ卜を取ってサードセットでは、身体が勝負を思い出していた。
マイクが私の試合、それも真剣勝負を見るのは初めてだった。スタジアムに座る彼も緊張していたらしい。ちなみに1回戦を勝った後に彼は、もう心臓か止まりそうだったと言っていた。
結果的には、この大会でシングルス準優勝、ダブルス優勝。この成績には我ながら本当に驚いた。ただあの試合を1回戦で負けていたら、その後のことは想像できなかったと思う。
テニスから離れた11年半を過ごす中で私は、それまでにもち得なかった広い視野を身につけてきた。コートの中にいては見られなかったもの、観客の目や試合をはじめとした大会運営にかかわる人、メディアを含めていろいろな角度からテニスというものを見ることかできた。その経験を得たことによって、改めてテニスがとても好きなのだと自覚することができた。
そうした年月を経たからこそ、かつての現役時代でしてきたこととはまた違うかたちでコートに向かうことかできるようになったのだと思う。
ツアー中にあって、自分自身が勝負師になっていることを自覚することがある。再びこの世界に挑戦できているというそれだけで、もうこれ以上のものなどいらないと思う一方で、この世界にどっぷり浸かっていると、やはりグランドスラムで勝ちたいという欲も出てくる。
さすがにグランドスラムで勝ち上がっていくなどというのは、それこそインポッシブル(Impossible)。あり得ないことだろうけれど、1回戦であれ2回戦であれ、その場所にやっぱり立っていたい。それほどグランドスラムという舞台は、テニスプレイヤーにとって特別な存在なのだ。
ただし今は、できるかぎりの努力をして最善を尽くし、出た結果が負けになるのだとしても、私はそれを受け入れることができる。その中で観客や私の挑戦を見ていてくれるみなに伝えられることがあるとたしかに思えるのだ。
ブランクを経て、40歳を超えても、まだ戦うことを楽しめる力。どのような状況にあってもあきらめない気持ち、ベストを尽くそうとする姿勢。それは、多少の背景は異なったとしても私だけに与えられた特別なものではない。当然同じプレイヤーである若手選手たちにも伝えられることであるし、テニスという競技の外にも通じるはずだ。
常にチャレンジし続けるのは、やっぱり楽しいことだと思う。何かに向かっている時は誰でも、子どもと同じようにがむしゃらでひたむきになっている。その子どもの頃の気持ちをもち続けるのは恥ずかしいことでもなんでもない。むしろ大切なことのはずだ。
そこには、ナッシング・トゥー・ルーズ(Nothing to Lose)という言葉がある。幸福とは、がむしゃらにつかみ取ろうとするものではなく、夢中になって楽しんでいる時にこそ、舞い降りてくれるものかもしれない。
だから今。たとえ自分がどんな環境にいるとしても、一歩を踏み出す勇気をもつ。それも義務ではなく、楽しみながら。一歩を踏み出す少しの勇気を誰もが手にするようになれば、世界はきっと変わる気がする。
<著者紹介>
クルム伊達公子(くるむ・だて・きみこ)
1970年生まれ。6歳からテニスを始める。1989年プロテニスプレーヤーに転向。1990年全豪オープンでグランドスラム初のベスト16入り。1993年全米オープンベスト8入り。1994年日本人選手初のWTA世界ランキングトップ10入り(ランキング9位)を果たす。1995年WTAランキング4位。1996年ウィンブルドンではシュテフィ-・グラフと決勝進出をかけて2日間の激闘の末、惜敗。同年マルチナ・ヒンギス戦を最後に26歳で引退。2001年レーサーのミハエル・クルム氏と結婚。2008年4月プロテニスプレーヤーとして「新たなる挑戦」を宣言。「クルム伊達公子」名で選手登録。復帰初年、全日本選手権シングルス・ダブルス制覇。その後、世界ツアーへ挑戦の場を移し、活躍している。エステティックTBC所属。