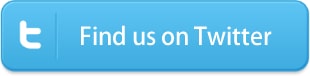なぜ、不動産投資は「サラリーマン向けの投資」なのか?
不動産投資は、ビジネススキルが活かせる投資法

株式や投資信託などに比べ、金額が大きく、長期的計画が必要な不動産投資。これまであまり投資をやってこなかった人が始めるにはハードルが高いと感じるかもしれない。しかし、実はとても堅実な稼ぎ方で、サラリーマンにこそお勧めできるという。不動産投資のコンサルティングを行なっている税理士の稲垣浩之氏に詳しくうかがった。《取材・構成=塚田有香、写真撮影=まるやゆういち》
「投資」と言いながら実は「事業」に近い
不動産投資とは、簡単に言えば「物件の表面利回り」と「金融機関からの借入利率」との差額で稼ぐ投資法です。お金の流れで説明すると、次のようになります。
(1) 金融機関でローンを組み、物件を購入する。
(2) 購入した投資物件から、月々の家賃が入る。
(3) 家賃収入から、借入金利と元本額を毎月金融機関に返済をする。
(4) そこから固定資産税や管理費などの経費を支払う。
(5) 手元に残った現金が、その月の収入となる。
(2)以降を毎月繰り返していくことで、継続的に収入が得られるのが不動産投資です。
「投資」という名前がついていますが、株やFXのように「一攫千金を狙う」というものではなく、たとえるなら百円玉をコツコツ貯金していくのに近い、堅実な稼ぎ方です。「売上から経費を差し引き、残った利益を管理する」という意味では、実際は投資というより「事業」と言ったほうが正しいでしょう。
日本では、ここ10年ほどで、不動産投資を始める人が急増しています。大きな理由は、金利の低下です。
先ほど説明した通り、不動産投資は表面利回りと借入金利の差額で稼ぐ仕組みですから、「できるだけ高い利回りの物件を買い、できるだけ低い金利でお金を借りる」というのが、利益を最大化するポイントです。
たとえば、価格が1億円、表面利回りが年8%の物件を、金利1.5%のローンを組んで購入するとします。すると年間の家賃収入は「1億円×8%=800万円」、金融機関に支払う利息は「1億円×1.5%=150万円」です。よって差額は650万円となります。
ところが、同じ物件を金利4.5%で借りると、支払う利息は450万円となり、差額は350万円にしかなりません。金利が低い今は、不動産投資で得られる利益をより大きくできるチャンスと言えます。
良い業者を見つければ大家は何もしなくていい
とはいえ、いくら金利が低くても、物件の利回りが低ければ、やはり手元に残るお金は少なくなります。では、どうすれば条件の良い物件に出会えるかと言えば、良い不動産業者を見つけることに尽きます。
不動産市場は、実は非常に「不平等」です。株式市場なら、すべての銘柄に関する情報が開示されているので、誰でも平等にチャンスがあります。しかし不動産の場合、大半の物件情報は表に出ず、不動産業者が持っています。よって、できるだけ多くの業者を回り、情報収集して優良物件を探すことが、不動産投資で成功する秘訣です。
そう聞くと面倒に思うかもしれませんが、不動産投資で手間がかかるのは、物件を購入するまでです。信頼できる業者にさえ出会えれば、金融機関も紹介してくれるし、物件購入後も入居者の募集や施設のメンテナンスなどはすべて管理会社がやってくれるので、オーナーがやることはほとんどありません。いったん仕組みを作ってしまえば時間を拘束されないので、本業が忙しいサラリーマンでも続けやすいのがメリットです。
THE21 購入
アクセスランキング(週間)
更新:05月11日 00:05
- 現代のリーダーに必須の「人間力」 どうすれば高められるのか?
- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック
- 50代で「腐っていく人」「花開く人」の決定的な違い
- 年間配当200万円超を達成した投資家が保有する「高配当株トップ10」
- 会議は準備が9割 「結論がまとまらない」事態を防ぐために上司がすべきこと
- 「部下のやる気が上がる」ほめ方とは? 性格タイプ別の伝え方
- リーダーが「意思決定の力を養う」には? 難しい判断を下すために必須の力
- いい年して幼稚な「ベビー社員」に振り回されないためには?
- 老後いくらあれば満足? 60歳でリタイアできる人の“枯渇しない資産”の築き方
- 個別株には手を出さない...投資歴25年「パックン流・超堅実な投資術」