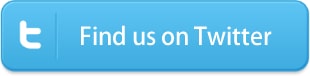Peatix「オンラインからオフラインへ、人を引き出したい」
2018年06月29日 公開
2024年12月16日 更新
【連載 経営トップに聞く】第3回 Peatix Japan〔株〕代表取締役 岩井直文

趣味の仲間がいる人、また、好奇心や向学心が旺盛な人は、イベントに参加する機会が多いだろう。そんな人にとっては、もうPeatixはお馴染みの存在かもしれない。イベントの主催者と参加者を、インターネット上でマッチングするサービスPeatixがユーザーを増やし続けているのは、いったいなぜなのか? Peatix Japan〔株〕代表取締役の岩井直文氏に取材した。
ユーザーの声を徹底して聞く。
ただし、そのまま反映はしない
――Peatixを利用したイベントが多くなったように感じます。
岩井 そう言っていただけると嬉しいですね。イベント数が増えているのはわかっていても、実際のユーザー様にそう感じてもらえるのが一番嬉しいです。
――オフィスに来て驚きましたが、社員数が少ないんですね。
岩井 少人数で頑張っています。ニューヨークとシンガポール、クアラルンプールにも拠点を置いていて、グローバル全体で40人もいません。日本からサービスを始めたので、日本の社員数が一番多いのですが、それでも26人です。
人が少ない代わり、パートナー企業との協力体制やテクノロジーを活用して、サービスを運営しています。
――サービスの開始が2011年5月。現在、どれだけの人が利用しているのでしょうか?
岩井 ユーザー数が280万人強、イベント主催者数が8万人強になっています。
――なぜ、そんなに伸びたのですか?
岩井 スタートアップでも大きく広告を打つ企業が少なくありませんが、当社は、広告も含めて、営業活動はごく一部しかしていません。
イベント主催者がPeatixを使うきっかけは、8割が口コミです。そのうち半数は、Peatixを利用したイベントに参加したことで、Peatixを知った方です。そういった実体験や口コミでユーザー数が伸びていきました。
――口コミで広がるということは、ユーザーやイベント主催者の満足度が高いということだと思います。どのようにして、満足度を高めているのですか?
岩井 月並みな言い方になりますが、ユーザーの声を聞くことに尽きます。
もちろんアンケートも取っていますし、カスタマーサポートにいただいた声も聞いていますし、ユーザーがどの画面をよく見ていて、どの画面から先に進まなくなっているのかなどのデータも分析しています。
ただし、ユーザーの声を、そのまますぐに反映することはせず、慎重に検討しています。特に気をつけているのは、複雑化しないこと。できるだけシンプルなインターフェイスにこだわっています。
というのは、日本だけでなく、世界での展開を前提にしたサービスだからです。様々な文化の人たちに使っていただくためには、シンプルでなければなりません。
サービスを始めて2年目に海外に進出したのですが、すると海外の方から「わかりづらい」という声を多くいただきました。そこで、抜本的にデザインを変えることにしました。ニューヨークに拠点を置いているのは、優秀なデザイナーが多いのも理由です。
今は特にアジアでのユーザー数の伸びが大きいのですが、それもインターフェイスがシンプルだからだと思います。
次のページ
企業イベントへの集客支援のニーズが高まっている >
THE21 購入
アクセスランキング(週間)
更新:05月17日 00:05
- 管理職に求められる役割とは? 部長と課長で異なる「取り組むべき課題」
- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック
- 現代のリーダーに必須の「人間力」 どうすれば高められるのか?
- 50代で「腐っていく人」「花開く人」の決定的な違い
- 年間配当200万円超を達成した投資家が保有する「高配当株トップ10」
- いい年して幼稚な「ベビー社員」に振り回されないためには?
- 会議は準備が9割 「結論がまとまらない」事態を防ぐために上司がすべきこと
- 老後いくらあれば満足? 60歳でリタイアできる人の“枯渇しない資産”の築き方
- 個別株には手を出さない...投資歴25年「パックン流・超堅実な投資術」
- 議論の末に「誤った判断」をしてしまったときに、リーダーがとるべき態度