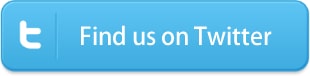Voice » 健康経営の本質を見誤るな――たばこ休憩をめぐって
健康経営の本質を見誤るな――たばこ休憩をめぐって
2023年05月31日 公開
2024年12月16日 更新

2020年の新型コロナウイルス禍以降、日本の職場でも、リモートワークが「当たり前」となった。ビジネスパーソンは、いまやリモートとオフィスそれぞれのメリットをふまえて自分の働き方を決めるべき時代だが、なかには在宅リモートワーク中も全面禁煙とする会社もあるという。企業側が抱えている矛盾とは。
「リモートか、オフィスか」ではない
――新型コロナウイルスの蔓延をきっかけにしてリモートワークが定着するかに思えましたが、オフィス回帰が鮮明になりました。リモートワークをどのように捉えればいいのですか。
【松下】リモートワークとオフィスは、二項対立で考えることではありません。それぞれの働き方にメリット・デメリットがあるので、どちらか一方を選ぶものではなく、状況に応じて使い分ける。もう一歩踏み込んだ言い方をすると、リモートで十分機能することをわざわざ対面でやる必要はないし、逆に対面でしかできないこと、たとえばお店に集まれないからといって、オンライン飲み会で代替しようとしてもうまくいかない。
リモートという手段があるからこその対面の意味、コロナが落ち着いてきて対面でできることが増えてきたからこそのリモートワークと対面それぞれの価値を、再定義していく必要があるでしょう。欧米でいうところのハイブリッドワークのデザインですね。
さらにいえば、リモート適性のある仕事はリモートだけ、対面が有利な仕事は対面だけに限定するのも避けたい。たとえば先日、関西は降雪の影響で一部の鉄道がストップしました。こうした事態に備えて、出社して対面に適した仕事でも非常時にはリモートで代替できる態勢や環境を整えておく。冗長性をもたせるという意味での仕事のリモート化は、通常の業務体制と切り分けて議論していかないといけない。
「リモートか、オフィスか」という議論は、新型コロナ以前のIT環境や業務上どちらかしかできなかった時代の産物で、リモートワークを実際に経験したいまとなっては成立しない。企業も人も時代の変化に即したアップデートが必要です。
――リモートで代替できない対面ならではのメリットはどこにあるのですか。
【松下】いろいろありますが、直感的にわかるというスピード感と併せた「曖昧さ」はその一つです。相手の表情を見ただけで「たぶんこうだろう」と察知できるとか、その場の空気や顔色みたいな曖昧なものを読み取る直観性が、対面の価値だと思います。
たとえば「香り」はなかなかオンラインでは再現できないものですが、人は嗅ぐと一瞬で多くのことが伝わります。なぜ感覚的にわかるのかを論理的に説明しようとすると、難しいわけですが。香りなんかは対面の意味や価値を説明するのにわかりやすい喩えだと思います。
企業のダブルバインド
――香りは「臭い」とネガティブに使う場合があって、たとえばたばこが敬遠される理由の一つが臭いであり、煙が臭くて迷惑だという人がいます。健康への影響も懸念されるので、オフィスが禁煙になるのは納得できます。しかし、リモートワークの場合は仕事中に喫煙しても問題ないはずです。にもかかわらず、在宅リモートワーク中も全面禁煙とする会社があるのですが、いかがですか。
【松下】個人的には、そこまでしなくていいと思います。まず、リモートワークでは社員の自律性をいかに確保するかが重要になります。日本企業の場合、どちらかというと細かくコントロールしたり規制したりして、それによって社員全体のリモートワークを制御しようと考えているようです。
でも、このやり方はほぼうまくいかない。リモート先のPCが動いているかどうかを記録したり、離席をすぐに把握できるようにして自律性を損なう管理体制を取りながら、社員に対しては表向き「自律的に動くことが大事だ」などという。会社側が矛盾したダブルバインドをかけている状態ですから。
――必要な人材は明らかに自律的に動ける人ですよね。
【松下】そうなのですが、現実的な問題として、たとえばマスクの問題があります。この3月13日から、政府は職場や学校では個人の自主判断に委ねる方針に転換しました。それでも自分で判断するのは嫌だから、「会社が指針を示せ」「するケース、しないケースを上司に決めてほしい」という人もやはりいます。
そういった人たちへの対応だったり、そもそも自律性の乏しい人を社員として採用するかしないか、自律性がある/ないのどちらを良しとして人材育成するのか、企業それぞれの人材育成・採用ポリシーと関連してくるでしょう。
――日本企業の多くがダブルバインドをかけている状態という現状には、何か要因があるのでしょうか。
【松下】そこが今回、テーマの一つである「生産性」の問題だと考えています。私たちはいいかげん、生産性の向上がいったい何に起因するのかに向き合わないといけない。生産性にはいくつかの計算式があるのですが、労働生産性でいうと、モノ・サービスを作り出すために、どれだけの労働力(時間×人)を投下したかで計算できます。
同じようなモノ・サービスを作り出しながら生産性を高めるには、投下する労働力を減らす、つまり労働時間を短くし、労働コストを低減していく方法を取ってきました。このロジックでいくと、リモートワーク中の離席時間を管理して極力減らしたり、喫煙を禁止したりするというのも、労働時間の削減=投下労働力の低減にはいくらか寄与するわけですね。
でも半面、失われた30年じゃないですけれども、日本経済の負けが込んでいる理由は、生産性の向上に関して作り出すモノ・サービスの付加価値の付け方が弱かったことにある点は否定できない。
仮に同じようなものを売るにしても、売り方を変えたりして付加価値を付けて高く売る。この付加価値は、まさに社員の「クリエイティブ」な部分に依拠します。付加価値重視で考えると、投下する労働時間と労働コストを倍にしても、製品が十倍の価格で取り引きされるのであれば、生産性は大きく向上することになるわけです。
20世紀後半以降に成長したIT、デジタル産業は、労働力をどんどん投下しながら作り出す製品の付加価値を大きく向上させていくやり方でした。そこに順応した欧米企業の生産性が高い。新しい産業だけでなく、古くからあるファッション・ブランド企業も付加価値を付けるロジックでグローバル企業に生まれ変わりました。日本企業はその転換がうまくいきませんでした。
攻めの健康経営とウェルビーイング
――リモートワーク中の禁煙や職場のたばこ休憩を制限する動きは、「健康経営」というキーワードでも語られます。この健康経営も生産性の議論と関連しているのでしょうか。
【松下】じつはそうです。過労死や休職者数の増加が、働き方改革とも関連して社会問題化しています。たとえば、「アブセンティーズム」と「プレゼンティーズム」といわれる問題です。アブセンティーズムは社員が休職・欠勤していると生産性が落ちるので、そうならないよう社員の健康を維持するというロジックです。
一方で、とにかく出社するという圧力が高まると、見かけ上出社してるだけで、生産性に寄与する働きができない。これがプレゼンティーズムです。生産性の視点で見ると、出社する/しないの問題ではなく、社員が毎日モチベーションの高い状態で働ける健康状態を保つことを重視し、そこに投資するほうがよほど重要になります。
――健康経営はヘルスだけではなく、モチベーションに関わることと考えたほうがいいのですね。
【松下】そうです。従来型の福利厚生を中心とした守りの健康経営でいくと、怪我をさせない・病気をさせない・過労死を出さないためにどうするかということになりますが、いまいわれているのはもう一つ、社員の幸福度やモチベーションを高めるための「攻めの健康経営」で、「ウェルビーイング」とも呼ばれます。
――モチベーションを高めるウェルビーイングは、法律で定められているのですか。
【松下】社員の健康を守るための法律・規制はいくつもありますが、ウェルビーイングに関しては「こうしなければならない」という法律も「こうすればうまくいく」という決まりきった正解もありません。しかし最近は、社員がウェルビーイングであることがクリエイティビティを発揮しやすくし、生産性を高める必要条件となっている。だからこそそこに投資していくべきだ、ということで注目され始めているのです。
――モチベーションアップの源泉は個人個人によって違うので、むやみに社員の行動や習慣を規制するのは好ましくないですね。
【松下】そうなります。とはいえ健康はモチベーションの前提で、一日のかなりの時間をオフィスや工場で過ごしていますし、リモートワークになったときに体を動かさないと健康リスクが高まるので、どうコンディションを維持してもらうかも大事な課題です。
嗜好品を軸にしたコミュニティ
――心身の健康とモチベーションを保つ意味で重要なのが嗜好品の存在だと思うのですが、いかがですか。
【松下】二つの意味で、嗜好品文化はとても大事だと思っています。一つはやはり、個人のストレス軽減やモチベーションのキープ、リフレッシュなどに効果がある。仕事前の香り、目覚めの一服といった個人のタイムラインもあって、私は朝、コーヒーを飲まないと仕事が始まらない。
もう一つは、嗜好品を軸にしたコミュニティ効果です。たばこ休憩で行く喫煙スペースでのつながりがまさにそうですし、チョコレートやコーヒーもありますね。シェアオフィスのコワーキングスペースでもよくコーヒーサーバーが置いてあり、コーヒーを飲みながらちょっと喋ることは普通にありますね。嗜好品を軸にすると、部署や職種とはまったく別のネットワークコミュニティが構築されていく。
――まさにインフォーマル・コミュニケーションの場ですよね。
【松下】日本企業のインフォーマルなコミュニケーションって、たばこ、麻雀、ゴルフくらいしかなかった。もう就業時間外にゴルフコンペをするのが難しい時代になり、これからの働き方がリモートとオフィスのハイブリッド化していくとすると、出社することの価値を「拡張したたばこ休憩」だと捉える考え方もあるかもしれない。誰かとちょっと喋りたくなった、気分転換したくなって出社する、みたいな感覚です。
仕事関係の報連相はすべてリモートでできるわけで、リモートワークの一番のデメリットはインフォーマルなコミュニケーションが取りにくいことなんです。だから企業としてもたばこ休憩に限らず、お茶でもコーヒー休憩でも社内で偶然出会った人同士が日常的な会話、雑談、何気ないやりとりを通じてセレンディピティ(幸運な偶然を手に入れる力)を高めていく。そのための出社になるよう、オフィス空間をデザインしたり演出したりする工夫をしていくべきだなと思いますね。
――やはりオフィスや仕事のあり方を昭和時代のものから、クリエイティビティを発揮できる付加価値の高いものにシフトしていく必要がありつつ後手に回っていたわけですが、コロナ禍でそれが露呈しました。
【松下】もちろん一つひとつのサービスや製品を見ると、面白いものを作っている日本企業はたくさんあります。ただし、打ち出し方が惜しい。逆にいうと、欧米で画期的とされるサービス・製品でも技術的に必ずしも先端というわけではない。それでもストーリーが共感されて付加価値が付く。
たとえば米「オールバーズ」のスニーカー。天然素材で足にも環境にも優しい洗濯機で洗えるサステナブルな商品ですが、日本メーカーが作れないことはないと思うんです。けれども彼らは、スニーカーに加えてライフスタイルやストーリーを売ることで消費者に受けている。
――既存技術を統合して新しい付加価値を生み出すイノベーションですね。
【松下】日本だと新製品=新しい技術・機能というイメージが強いですけど、消費者が欲する付加価値は必ずしもそうではない。既存の技術でも新しい発想で組み合わせて、こういうかたちで提案したら生活がもっと豊かで面白くなるんじゃないか? その物語性とかライフスタイルをイノベートしたんですね。日本企業の苦手な部分です。
「余白」の重要性
――イノベーションのアイデアは、厳しい管理体制からは生まれないと思うのですが。
【松下】慣例や規則を厳しくすると、組織が内向きで閉鎖的になり、「いわなくても伝わるだろう」というカルチャーが形成されていきます。先日、ポルトガルのマデイラ島にある通称「デジタルノマド村」を訪れたときも感じたのですが、ランチ会やパーティーなどを定期的に開催し、みんなでよく会話をしています。
多様な人たちと喋ったり話を開いたりしていると、自分では当たり前だと思っていることに相手が驚いたり、予期せぬ反応が返ってきたりして「そういう見方ができるんだ」と発見があるのです。その積み重ねでセレンディピティが高まっていくわけです。
――昭和の会社にもよい点はあって、仕事を半分サボって同僚と喫茶店に入って喫煙しながらムダ話をし、会社の経費で精算していた、なんていう話をよく聞きます。
【松下】マンガ『美味しんぼ』の主人公の山岡士郎みたいな働き方の人がいなくなりました。新聞記者なのに記者らしい描写はあまりない。仕事をしなくても何となく職場は回っていて、許される雰囲気や余裕が職場にありました。それで彼らがごく稀に、偶然の産物でホームラン級の成果を出す。英語ならセレンディピティですが、日本語でいうと偶然性より「余白」が合いそうです。一見よくわからないものも、経費で何となく落ちていることも多かったのではないでしょうか。それは無駄といえば無駄なのですが、何かの拍子に成果につながる。
そうした余白が職場にはけっこうあったのに、余白をなくすことが経営効率を高めることだ、と合理化・効率化の名のもとに余白を削っていった結果、縮小再生産に入っていった。たばこ休憩してる時間があったら営業電話の一本もかけられる、ということになってしまいました。
――余白を自ら埋めてしまったんですね。
【松下】それがおそらく、いまになって裏目に出ています。大学の科学技術などの研究でよくいわれるんですけど、「イノベーションが起きそうな研究だけにお金を出す」のは無理です。企業でも同じだと思います。たとえば付加価値十倍とかいうホームラン級の仕事は、コンスタントなヒット狙いの人からは生まれないんですね。
協調性のアップデートが必要
――一律に昭和的な企業を否定してはいけない。
【松下】いまでも定年まで勤め上げるとか、家族的に社員を抱える企業があってもいいと思いますし、その社風に合う人たち、そうした環境下で付加価値の高い成果を出せる人もいると思います。ただ家族的な会社であるにしても、上司と部下との関係性はいまの時代に合わせてアップデートしていかないといけない。仕事の面でのフィードバックはよいけれども、プライバシーに露骨に干渉する関係性は敬遠されます。
さらにいうと日本企業の多くは、職場における協調性のアップデートが必要です。協調性には、同質性の高い男子校のノリに近い協調性と、多様な人たちをインクルーシブ(包摂)していくための協調性の二種類があり、必要なのは後者です。
――日本企業でも、多様な人材を採用する組織になりますか。
【松下】企業ごとに進み具合の差はあれ、全体のトレンドとしては多様にならざるをえない。なぜかというと、日本企業が採用の主な対象としてきた男子学生の数が不足しているからです。
女子学生は当然として、海外人材や介護や育児で一度会社を離れた人、マイノリティの人たちも採用していくことになるでしょう。そうした多様な人たちに対して、日本人男性にさせてきた働き方をしろといってもうまくいかない。それも人事システムを変更するだけでは足りなくて、組織風土をまずはルールの部分で変える。育児・介護休暇、宗教や食生活の配慮なんかがルールとして整備されていること。さらに次の段階としては、ルールはあっても事実上使えない、みたいな風土自体を変えないといけない。
――どうすれば多様な人材のモチベーションを維持できますか。
【松下】一つは、やはり余白に投資することではないでしょうか。「働かないおじさん」問題が報道されていますが、善意の働かないおじさんもいます。そういう人たちは組織がもつ余力の部分で、必要な人材でもあるのです。
たとえば子育てをしている社員が、降雪で保育園が休園したから今日は出社できません、と。すると、たまたまオフィスの近くに住んでいる働かないおじさんが出社して仕事の穴を埋めることもあるでしょう。職場の足を引っ張る悪意の働かないおじさんではなく、善意の働かないおじさんは職場のモチベーションを維持する戦力になりうるんです。たばこ休憩やコーヒーブレイクと同じように、余白の存在が本体を支えていると思います。
Voice 購入
アクセスランキング(週間)
更新:05月12日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 中国史上唯一の女帝にして暴君 則天武后の「残忍政治とその原点」
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- アメリカ軍は弱体化している...世界トップに躍り出た「中国海軍の軍事力」
- 「リバタリアン」はなぜ民主主義を否定するのか? 激変するアメリカ現代思想
- なぜモテない? 「パートナー探しが無理ゲー」になった進化論的背景
- 「プーチンの判断ミス」で国家の危機に...NATOに裏切られた屈辱的な記憶
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史
- 「中国は嫌われている」一方で、三国志を好む日本人...この矛盾はなぜ生まれたのか?







.jpg)