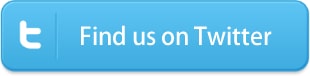『SPY×FAMILY』ヒットは心理戦がないから? 若者が“表層的な物語”にハマる理由
2022年06月18日 公開
2024年12月16日 更新
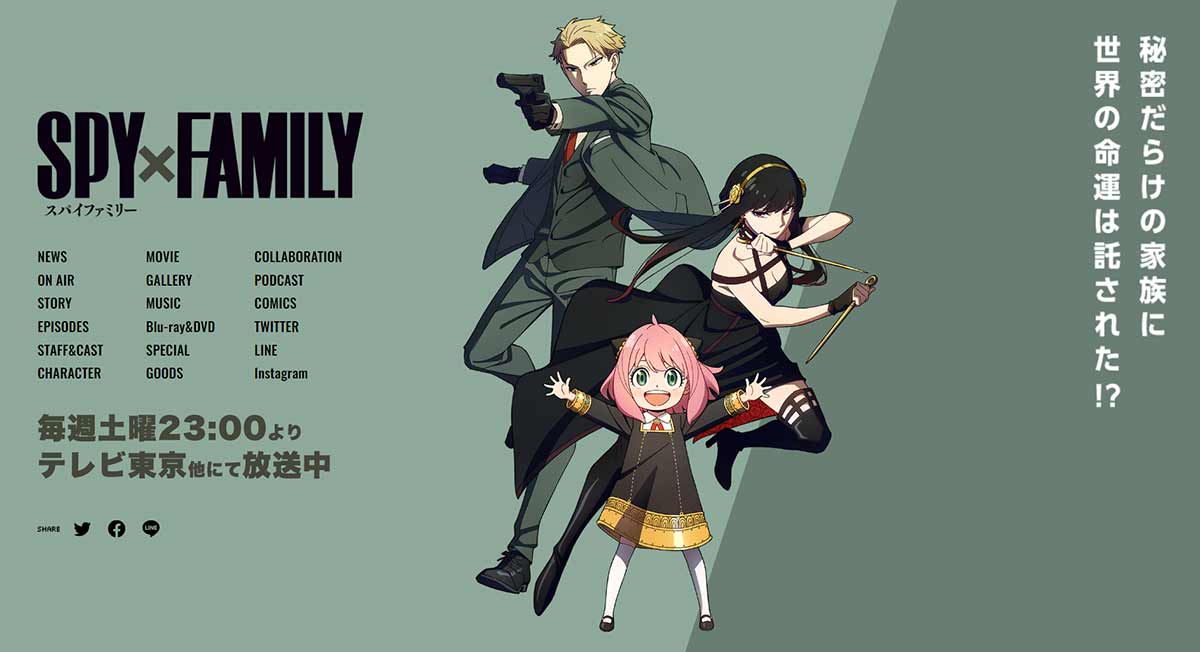
TVアニメ『SPY×FAMILY』公式サイトより。Ⓒ遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY 製作委員会
マンガ原作のテレビアニメ『SPY×FAMILY』。連日インターネットで話題の作品だが、なぜここまでの人気を獲得することが出来たのか。批評家の渡邉大輔氏は、この作品と若者世代の慣習に親和性があることが人気の一因となっていると指摘する。スパイものの歴史を辿りながら、作品を解説する。
※本稿は『Voice』2022年7⽉号より抜粋・編集したものです。
実利だけで結びつく擬似家族
この4月からテレビ東京系列で放送中のテレビアニメ『SPY×FAMILY』が話題を呼んでいる。いかにも令和らしいこのホームドラマの面白さについて考えてみたい。
本作は、遠藤達哉が2019年から『少年ジャンプ+』(集英社)で連載中の大ヒットマンガを原作にしたスパイもののホームコメディである。物語の舞台となるのは、東西冷戦を髣髴とさせる架空の西欧世界。
西国(ウエスタリス)の辣腕スパイである。黄昏(たそがれ・声:江口拓也)は、所属する情報局〈WISE(ワイズ)〉からオペレーション〈梟(ストリクス)〉という重大ミッションを託される。
それは、緊張関係にある隣接する東人民共和国(オスタニア)の政治家ドノバン・デズモンドと接触するため、1週間で偽の家族をつくり子女を彼の息子が通う名門イーデン校に入学させるという諜報活動だった。その後、黄昏は、精神科医「ロイド・フォージャー」と名乗り、孤児院で見つけた少女アーニャ(声:種﨑敦美)を養子に迎える。
さらにイーデン校の面接試験に合わせるため、市役所の事務職員ヨル・ブライア(声:早見沙織)という女性と偽装結婚も果たす。しかし、じつは「娘」のアーニャは他人の心の声が見聞きできるテレパシー能力のもち主であり、「妻」となったヨルは「いばら姫」のコードネームで恐れられる凄腕の殺し屋だった。
スパイ(父)、殺し屋(母)、超能力者(娘)というそれぞれに秘密を抱えながらも、絶妙なバランスで利害の一致したキャラクターたちが、「家族」を装って暮らす様子をシュールでコミカルに描いたコメディである。
まず、本作の物語の妙味は何といっても、タイトルどおり、「スパイ」と「家族」という要素を巧みに掛け併せた点にあるだろう。もとより、この両者はどちらも何らかの意味で近代社会的な公共空間から弾き出された存在である点において共通している。
スパイであれば、黄昏のように自らの真実の素性を公共空間から隠匿し政府や組織から与えられた任務を極秘裏に遂行する者だし、家族はもちろん、近代以降の社会においては公共空間とは対立する親密圏を構成するとみなされてきた。
とはいえ、『SPY×FAMILY』のポイントは、その家族をつくる黄昏=ロイドたちがあくまで個々の実利的な目的だけで結びついているという奇抜な設定にある。
したがって、彼ら3人は、本来ならば、公共空間には見せられずとも、そこでならプライベートな真実の姿(素性)を安心して曝け出すことができるはずの親密圏=家族の内部においても、実際には公共空間とほぼ同様の振る舞いを強いられることになる。
その点で『SPY×FAMILY』の擬似家族は、「裏返った社会空間としての家族」という逆説を生きなければならない人物たちだ。
そして、ここで半ば必然的に焦点化されて描かれるのは、そんな彼ら一人ひとりの――たとえ家族間でも互いに隠蔽された――個人の喜怒哀楽を含む「内面」(思惑)である。事実、『SPY×FAMILY』では、ある意味で会話よりも、登場人物たちの内面の独白(モノローグ)が多くの部分を占めている。
「内面」の葛藤を描かない現代性
こうした『SPY×FAMILY』の主題や趣向は、いかにも現代らしい感性を物語に呼び込むことに成功しているように思う。たとえば、さしあたりここで本作と比較してみたいのが(いささか唐突に感じるだろうが)、戦間期に相次いでつくられたドイツ時代のフリッツ・ラングの犯罪映画群だ。
『SPY×FAMILY』の世界観は、東西冷戦や情報戦がモティーフになっているものの――なおかつ、舞台は1960~70年代を想定しているという原作者自身の証言もあるようだが――、具体的な街並みや小道具などを見ていると、実際にはもう少し古い時代を思わせる。
戦後世界というよりは、さしずめヨーロッパ諸国に近代都市空間が成立する19世紀末から20世紀初頭の雰囲気というほうが妥当だろう。
また、モデルとする国は(これも原作者のいうとおり)明らかにドイツであり、実際、「精神科医」に扮した「スパイ」という主人公・黄昏=ロイドや、「他人の心を読める」というアーニャの設定などは、この巨匠監督の映画を連想させる要素がある。
ラングの造形した『ドクトル・マブゼ』(1922年)の犯罪者マブゼ博士は変装の達人であり、催眠術で人の意識を自在に操ることができる(しかも、その作中の変装の1つには、「精神分析医」も含まれていた! )。
そして、同作の数年後には、マブゼ博士を受け継ぐハギが登場する、まさに国際スパイ映画の傑作として名高い『スピオーネ』(1928年)も撮られている。こうしたほぼ100年前のラング映画の数々は、他人の心が読めるアーニャと精神科医になりすますスパイの黄昏という『SPY×FAMILY』の基本設定とも符合するのだ。
だがもちろん、ワイマール共和国が存在する1920年代ドイツのラングのスパイ映画と、2020年代の令和日本のスパイアニメでは、やはり決定的な差異も存在する。
かつて映画批評家の三浦哲哉は、近代都市空間やフロイトの精神分析とともに登場した以上のようなラング的サスペンスの本質を、ポール・ヴァレリーを参照しながら「精神が精神自身に抱く」「深い疑い」の表現だと要約した(『サスペンス映画史』みすず書房、95頁)。
他人の心を自在に操ったり、はたまた自らの「無意識」の蠢きに怯える人物たちを描くラングの映画では、他者や自分自身の「内面」に対する葛藤や抗争がつねに重厚かつ執拗に描かれる。
ところが、『SPY×FAMILY』が描くのは、同じようにキャラクターの「内面」(精神)を焦点化しながらも、逆に、むしろ登場人物たち同士や彼ら自身の「内面」の葛藤の徹底した欠如や希薄化である。
なんとなれば、すでに触れたように、彼らはつねに自らの「内面」を「実利」のために「家族」にすら隠蔽しないといけないからだ。したがって、さしあたり彼ら個々の「内面」=思惑が作中で必要以上に内省されることもなければ、彼らのあいだで心情的な軋轢が起こることもない。
Voice 購入
アクセスランキング(週間)
更新:04月13日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 中国史上唯一の女帝にして暴君 則天武后の「残忍政治とその原点」
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- アメリカ軍は弱体化している...世界トップに躍り出た「中国海軍の軍事力」
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- なぜモテない? 「パートナー探しが無理ゲー」になった進化論的背景
- 「リバタリアン」はなぜ民主主義を否定するのか? 激変するアメリカ現代思想
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 「中国は嫌われている」一方で、三国志を好む日本人...この矛盾はなぜ生まれたのか?
- 吉柳咲良さんが目指す「他者に寄り添える存在」 多様な役柄に向き合う意味








.jpg)