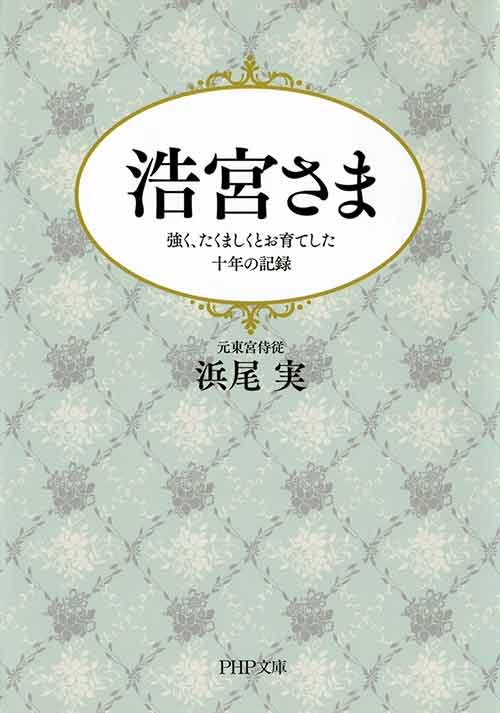東宮侍従として、浩宮さま(現在の天皇陛下)のご養育掛りを約10年間もつとめられた浜尾実さん(平成18年逝去)。「オーちゃん」と呼ばれていた浜尾さんは、天皇陛下の日々のご成長を間近で見守り続け、その後、教育評論家として書かれた多くの著作で、その日常のお姿を紹介された方です。天皇陛下は本年2月23日、65歳の誕生日を迎えられますが、その幼少期の逸話に心が揺さぶられます。
※本稿は、浜尾実著『浩宮さま』(PHP文庫)の一部を抜粋ごしたものです。見出しや〔 〕内注記は編集部によるものです。
「テレビがある」時代に、ご幼年期を過ごされた浩宮さま
浩宮さまは、昭和38年2月23日、満3歳のお誕生日を迎えられた。両陛下〔現在の上皇上皇后両陛下〕は、この日は、恒例にしたがって、宮さまがお生まれになったとき、お世話をいただいた各方面の先生たち(主としてご出産関係の医師の方々)を、東宮御所にお招きになって、お祝いのティー・パーティを催された。
私は、3回目のお誕生日を迎えられた宮さまを、しみじみとした思いで見守った。どちらかというと、お小さいお身体つきであるが、それでも、なかなかしっかりとした印象を与えるご成長ぶりであった。
たしか、このころのある日のことだと思うが、皇后さま〔現在の上皇后陛下〕が、「ナルちゃんは、オーちゃんの子どものようですね」と言って笑われたことがあった。
浩宮さまは、ご両親といっしょの時間よりも、私のそばにいらっしゃる時間の方が多かった。ご両親は御所においでになっても、ご進講、内外のお客さまの謁見などのご公務があり、私はおつとめとして宮さまのお世話をしているのだから、これは仕方のないことであったが、皇后さまがそのように言われたのは、半分は私に対して「よくやってくださって......」という、いたわりのお気持ちがあったように私には感じられた。
それが、私は、うれしかった。と同時に、身震いするようなおそろしさに襲われた。いうまでもなく、責任の重さをあらためて考えたからであった。
たとえば、ちょっとした仕草や物の言い方に、私がお教えしたことの影響があるのを発見することがあった。
私の話し方は、一語一語を明確に発音することを心がけて話す。そのために比較的ゆっくりした口調になる。そうした私の説得調で、ややゆっくりした口調が、宮さまの話し方に少なからず影響してしまったのだろう。
皇后さまはさもおかしそうにお笑いになったが、私は、そのたびに、ありがたいような嬉しいような感動を覚えた一面で、おそろしいという気持ちになったものであった。
三歳を過ぎてからは、そろそろ、幼稚園へお入りになるということを予想した教育が必要だった。あらたまった形ではなかったにしても、それとなく準備しておかなければならないことは、いくつかあった。たとえば、幼児語からの卒業ということを、心がけるようになったのも、そのころであった。
陛下〔現在の上皇陛下〕のご幼年時代と、浩宮さまの時代との大きなちがいのひとつは、テレビがあるということであろう。
はじめのころは、皇后さまが、こども向けの音楽番組「おかあさんといっしょ」とか、「鉄腕アトム」「鉄人28号」などのような、マンガを選んでお見せになっていたようであるが、間もなく、チャンネルの選択を宮さまの自由に任された。一般のこどもたちが、テレビによって言葉の影響を受けるように、浩宮さまも、言葉については、まったく自由であった。
ただ、皇室だけに残っている特殊な言葉というものが宮さまにとってはひとつだけある。それは、お父さまを「おもうさま」、お母さまを「おたたさま」とお呼びするということである。
しかし、浩宮さまも、はじめは、「パパ」「ママ」であった。幼児には発音しやすい呼び方だから、そのほうが自然だったのである。幼児語からの卒業を心がけるようになってからは、皇室の習慣にしたがって「おもうちゃま」「おたたちゃま」と改めて行った。いずれは、「ちゃま」でなく「さま」になるための段階として――。
3歳を過ぎてから、「幼児語にさようならする」ための努力
幼児語にさようならするには、まず周囲がそれを使って語りかけないようにすると同時に、ひとつひとつの言葉について、根気よく言いなおしをくり返して行かなければならない。私は、意識して、そのことに努めた。
その他の宮さまの幼児語は、ほとんど、こどものすべてが使う言葉と、同じであった。
ブーブー(自動車)、ワンワン(犬)、トット(にわとり)、デチュ(です)、アチュイ(熱い)。宮さまが「ワンワン」と言われると、そのたびに私は、じっとお顔を見て「いぬ(、、)ですね」と言いなおすようにした。両陛下も、しばらくの間は、かなり意識して、その言いなおしに努力された。
宮さま特有の言葉も、いくつかはあったようである。ある日、「ペタンペタン」と言われるのを、侍医長の佐藤博士が、どうしてもわからないと苦笑しながら皇后さまにおたずねになったことがあるそうである。
それは「うがい」のことだったのだが、語源(?)は、とうとうわからずじまいであった。「ボク」のことを「ボボ」あるいは「ボボちゃん」と言われたこともあったが、そう長い期間ではなかったように思う。
幼稚園へすすまれるための準備として、もうひとつ、「自分のことは自分でする」ということがあった。
もちろん、そのご年齢にふさわしいこと――たとえば、ボタンをかける、靴の紐を結ぶ、遊んだあとの片づけをキチンとする、などということであったが、困難なことを要求するのではなく、日常のきまりとして当然のことは、ご自分でなさるように仕向けるという点で、皇后さまは、かなりきびしかった。私も、すぐ手出しすることのないように気をつけた。
お世話をするということは、なんでも手をさし出すということではないのだと、私はたえず自分に言い聞かせ、わざと、知らん顔をして宮さまのなさることを見守るようにした。
話は飛ぶが、浩宮さまは、昭和46年の夏、学習院初等科の臨海学校(沼津)に参加された。そこで、生徒たちのほとんどが、軽い食あたりに見舞われるという出来事があった。
食品をおさめている業者の手落ちだったらしいが、浩宮さまも他の生徒たちと同じように、腹痛をおこし、吐き気を催されたという。私は、すでに東宮職を離れていたので、そのことをニュースで聞いたときはびっくりした。
幸い、大事にはいたらなかったという詳報でホッとしたが、後日そのときの模様を聞く機会があった。それによると、浩宮さまはすこし吐かれたけれども、その後始末をきちんとご自分でなさったということである。それで、はからずも、私は、幼稚園にお入りになる前のころ、「自分のことは自分で」ということをやかましく申し上げていたことを思い出したのであった。
臨海学校で、ご自分が汚したあとを一生懸命に始末していらっしゃる宮さまのお姿を想像して、私は、小さな種子が実を結んだという実感を持ち、嬉しさとともに、宮さまに対するいとおしさが募ってくるのを抑えることができなかった。これは一例にすぎない。そういう小さな種子が多く集まって人間をつくりあげて行く。それが教育というものであろう。
民間の幼稚園へ――皇族では、はじめてのケース
陛下と皇后さまは、浩宮さまを民間の幼稚園にお入れになる方針を、早くから決めておられたようである。民間の幼稚園ということになると、学習院を考えるのが妥当なところであった。そのことは、すんなりと決定した。当時、安倍能成先生が園長であった。
そもそも、皇族が幼稚園へお入りになるというのは、浩宮さまがはじめてのケースであった。しかも、宮さまだからといって、特別な扱いをしない保育を、両陛下は希望された。
そうなると、近所のお友だちと自由に遊び歩くという経験をまったくお持ちにならない宮さまが、幼稚園というはじめての集団生活に、うまく適応されるかどうか、私は、正直なところ不安であった。そのために、私は、なにかというと、幼稚園のことを口にしてお叱りしたりすることが多かった。
ある日宮さまが「ボク、幼稚園に行くのやめようかな」と言われたことがあった。私が「そういうことをされると、幼稚園に行けませんよ」と言っていたので、すこしばかり心のお荷物だという感じを抱かれたのだろう。そういうこともあるにはあったが、それでも、幼稚園という未知の世界への楽しみのほうが強かったことはたしかである。
38年11月2日は、皇后さまと浩宮さまで、上野動物園へお出かけになった。子どもの世界では、動物園の話題がかならず出るものである。このご体験も、後に役に立ったにちがいないと私は思った。
翌39年の1月21日、浩宮さまは、学習院幼稚園の入園試験をお受けになった。皇后さまが付き添って行かれた。
幼稚園の試験だから簡単なものではあったろうけれど、宮さまにとっては、記念すべき日であったといっていいだろう。しかも、他の子どもたちとまったく同じ条件で、順番を待ってテストを受けられたのである。皇后さまも、そこではひとりのお母さまとして付き添っておられた。
入園が決定し、入園式が行なわれるまでに、浩宮さまは、一度、幼稚園のひなまつりに招待された(3月3日)。もちろん、皇后さまもごいっしょである。"先輩"にあたる園児たちの歌や遊戯をごらんになりながら、宮さまは眼を輝かせておいでになった。ご自分がそこに参加される日のことを思っておられたのだろう。
3月9日の父母会へは、皇后さまが、お母さまのひとりとしてお出になった。そして、4月13日に入園式。いよいよ、浩宮さまの幼稚園生活がはじまった。