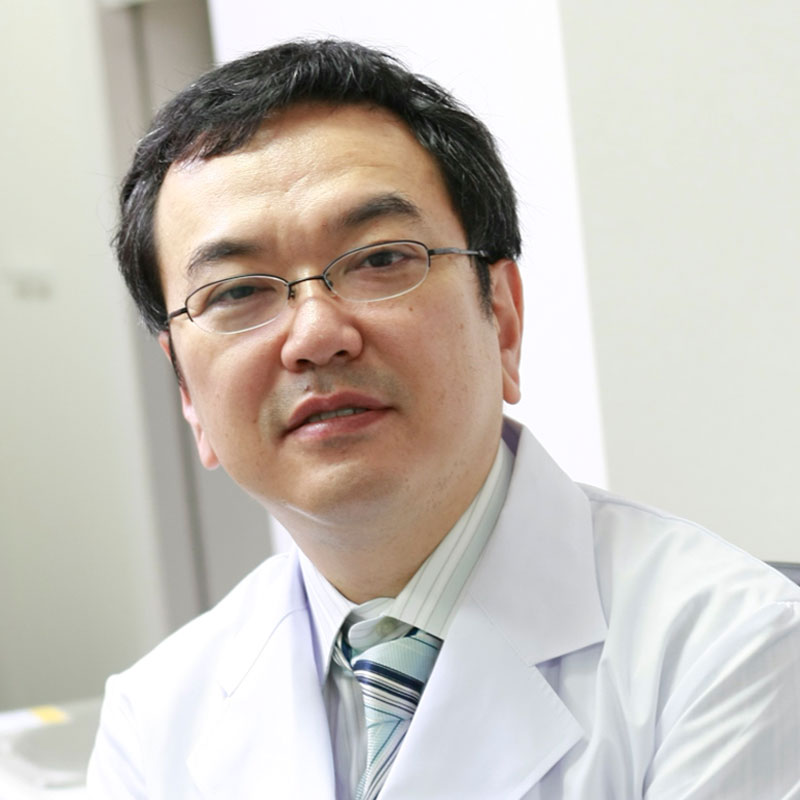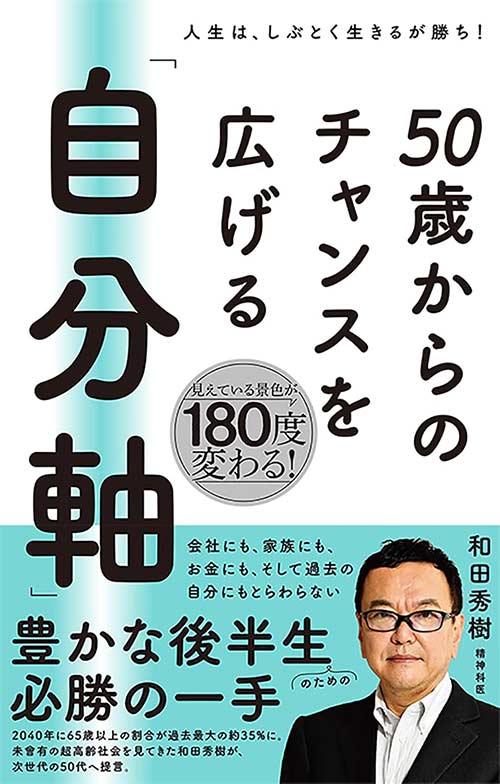みんなと同じでないと不安というのは、日本人特有の心理です。右や左を見てみんなと同じならば安心するのではないでしょうか。
でも本当は、全員が同じ意見を持つことなど、ありえません。ですから、みなさんは50代のいまのうちから「こうあるべき」を疑うトレーニングをしましょう。
テレビやインターネットで有識者がニュースについて解説していても本当なのかと自分の頭で考えてみましょう。「こうあるべき」は時代とともに移り変わるものです。だからひとつの「べき」に縛られる必要はありません。自由に発想し、自由に生きる。それが豊かな人生につながります。
※本稿は、和田秀樹著『50歳からのチャンスを広げる「自分軸」』(日東書院本社)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
過去にとらわれず今を充実させれば、長生きは楽しい!
50代になると「昔はもっと体が動いた」「若い頃はこんなことできた」と過去と比べて嘆く人が少なくありません。
今はそのように感じていなくても遅かれ早かれ誰もみな自身の老いに気づき始めるときがやってきます。確かに、歳を重ねれば身体能力は衰えます。悲観的になるのは自然な感情と言えるでしょう。
人生の折り返し地点を越えれば、少しずつ体の自由が利かなくなる可能性があります。その時に、「昔はできたけど、今はできない」とマイナス思考に陥らないでください。「今の自分に何ができるか」にフォーカスを当て、今を楽しむ姿勢が大切です。
私は仕事の関係で100歳まで生きてきた人とお会いすることも珍しくありません。50代の人の中には「100歳まで生きるのは大変そう」と思っている人もいるでしょう。実際、100歳まで生きた人たちも「長く生き過ぎました」と冗談交じりにおっしゃるのですが、みなさんとにかく楽しそうなんですね。まったく辛そうではない。
「長生きはしてみるものですね」とむしろ肯定的にとらえています。肉体的に辛いことは当然あるでしょうが、マイナスの面ばかり見ずにプラスの面を大切にしているのです。そんなロールモデルに出会うたび、「歳を取るのも悪くない」と勇気づけられる思いがします。
みなさんの先輩のシニアの中には、そんなふうに、体力の衰えを感じながらも生き生きと暮らしている人が大勢います。不自由ながらも自分の体の機能を最大限に活かしながら、趣味や社会活動に熱心に取り組む。人生の先輩として、若い世代に経験を伝え、時に学び合う。
「すべてを自分でこなさなくては」と身構えるのではなく、「困ったときは助けを求めていい」と肩の力を抜く。そんな柔軟な発想の転換から、新しい生き方が見えてくるはずです。
いずれにせよ、60歳を超えると、時間の流れは速く感じられるのは間違いありません。だからこそ、「あの時こうしておけば」と後悔するのではなく、今を大切に生きることが何より重要になります。その意識がこれからの長寿時代を生きる、50代のみなさんの心構えと言えるのかもしれません。
「べき」の束縛から自由になれば、豊かな人生が広がる
人生100年時代を生きるうえで、私たちを縛る「とらわれ」の正体は、「べき」の束縛といってもいいすぎではありません。「シニアはこうあるべき」「老後はこう過ごすべき」。そんな思い込みから自由になれたとき、人生は無限に広がります。
「自分軸の生き方」とは、決して「孤独な生き方」ではありません。むしろ逆です。周囲の支えに感謝しながらも、自分の人生の舵を自分で取る。医療やテクノロジーの助けを借りながらも、主体性は失わない。そうやって、自分軸を持って生きることこそが、「自立」の本質だと私は考えます。
これから先の人生は当然ながら歩いたことのない道のりです。先人の知恵を参考にしながらも、結局はひとりひとりが自分なりの答えを見つけていくしかありません。答えのない人生だからこそ、面白いともいえるのです。
そして、これまでは老後のモデルが少なかったですが、今の60代、70代、80代は長寿命化していますから、みなさんがモデルに困ることはありません。
「自分はこう生きたい」「こんなふうに歳を重ねていきたい」。そんな思いを胸に、自分なりの答えを探していきましょう。
時にはつまずくこともあるでしょう。思うようにいかないこともあるはずです。でも、その試行錯誤こそが、かけがえのない財産になります。ここまでの道のりを振り返れば、失敗も成功も、すべては自分を作ってきた。そう思えたら、この先の人生も何も怖くはないはずです。
「とらわれ」の呪縛から逃れるのは、たやすいことではありません。長年染みついた生き方を変えるには、相当の覚悟が必要です。でも、その一歩を踏み出せたとき、新しい世界が開けます。「こうあるべき」からの卒業が、自分軸への第一歩になります。