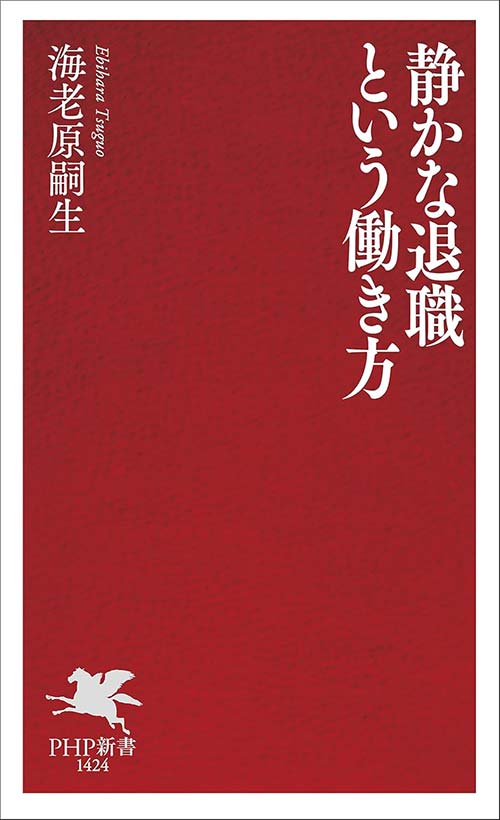働いてはいるけれど、積極的に仕事に意義を見出していない「静かな退職」状態のビジネスパーソンが、日本にも浸透し始めているという。
一方従来の日本に蔓延していたのは私生活を犠牲にした「忙しい毎日」。「やっている感」を醸し出すブルシット・ジョブを繰り返し、労働時間がいたずらに延び、結果として生産性が下がっていた。
今なぜ「忙しい毎日」を生み出した日本型労働は崩壊しつつあるのか?雇用ジャーナリストの海老原嗣生氏に解説して頂く。
※本稿は『静かな退職という働き方』(PHP研究所)より一部を抜粋編集したものです。
女性の社会進出が「忙しい毎日」を揺るがし始めた
なぜ、近年、会社の縛りは弱まったのか?
そこに実は、女性の社会進出があるのです。
元来、日本の会社の主要な職務は男性が占め、女性は独身時代にアシスタント職として勤務するのが関の山でした。代わりに女性は、性別役割分担という名のもと、家事・育児全般をワンオペで引き受けることとなります。
バブル期までは、「女性は一般職として企業に腰掛け勤務し、結婚したら退職」という常識が世にはびこりました。
ところが、バブル崩壊で経営が苦しくなると、企業は真っ先に一般職の新規採用を止めることになります。
女性の一般職は早期に結婚退職するから、採用を止めると即減員できるからですね。その結果、今度は「短大行ったら就職ないよ」という状態となり、代わって1990年代前半から女性の4年制大学進学率が高まっていきます。
そして、1996年に短大と4大の進学率が逆転。彼女らが卒業する2000年頃から、大卒女性がグンと増え始めました。
こんな感じで、2000年頃より、「大卒総合職の女性」という変数が、企業内の日本型男社会に入り込み始めます。
ただし、企業は何の準備もなくいきなりこの変数を取り込んだために、当初は社内の各所で軋轢が生じました。そして、圧倒的多数の男性に囲まれて、女性の声はもみ消され、「忙しい毎日」はまだまだ保たれることになります。
女子のキャリアは4R→肉食系女子→一般化
当初、企業が女性を迎えるために取ったフォーメーションは、俗に4Rなどと呼ばれる「内勤への集中配属」でした。人事(HR)、財務(IR)、広報(PR )、顧客対応(CR)といった4部署が女性の受け皿となり、そこだけが別世界となっていくのです。
この4Rではじきに、総合職の男女数が逆転する会社まで出現しました。そして、2010年頃には「もう内勤管理部門では女性を受け入れられない」という企業が多数現れます。
そこで次に企業が力を入れたのが「肉食系女子採用」でした。運動部などの上意下達型の組織に長く籍を置き、パワハラにも耐えられ、体力も万全な女性を積極採用したのです。
それは、男社会への親和性が高い女性を現場職(営業や生産管理など)に取り込むという、「忙しい毎日」の一種の延命策ともいえたでしょう。
ただ、肉食系女子は人数が限られるため、この手法を各社が取るようになると、途端に候補者が足りなくなります。
世界に冠たる某メーカーでは、この頃に「30代女性の積極採用」を掲げ、3桁に迫るほどの大量中途採用を複数年にわたり行ったりもしています。
「バリバリ」なキャリアウーマンが、落下傘方式で各所に配置されると、彼女たちはそれまで気づかなかった「男社会型の無理・無駄」を指摘し始めます。
それをテコに社内を変えようという魂胆でした。このような流れで形を変えながら企業への女性進出が、ジワジワと速度を増していったのです。
女性が増えて10年経った頃、企業は葛藤し始める
さて、多くの女性が男社会に放り込まれれば、多勢に無勢で彼女らの声はかき消されてしまう、と書きました。確かに当初はその通りだったでしょう。
当時の男性社員は、部内の「女性」に対して腫れ物に触るような対応をしていたり、もしくは真逆で、威圧的に命令したりといった状態であり、女性たちも独身のうちは(ある程度、配慮を受けながらも)男性同様、「忙しい毎日」を送ることができました。
結婚しても子どもがいない間は、独身時代の延長で、このワークスタイルは続けられるので、この頃から「寿退社」も減っていきます。
ところが、出産は大きな壁となりました。
当時すでに育休制度は整っていましたが、まだ出産適齢女性が少なかったから、それを取った先輩たちは少数派です。逆に言えば、その程度の少数だから、職場への影響も少なかったと言えるでしょう。
ところが、2010年代には、増えてきた総合職女性の出産ラッシュが始まります。企業はここで、今までとは全く次元の異なるショックを受けるわけです。
当初は「出産退職」を止めなかった会社も、多数が同時に辞めるとなると、事業が成り立たなくなるという危惧を抱き、本腰を入れて対策に取り組み始めます。ただ、不慣れなために、ここで大きな瑕疵を生じさせてしまいました。
2010年代前半に反動が起きた理由
当時、企業は育児女性向けに短時間勤務制度を導入するのですが、これが、ずいぶんと粗い内容だったのです。
営業や企画、人事、経理などでバリバリ働いていた女性でも、その復職先は、コールセンターや事務処理などのバックヤード業務が主。
会社としては「短時間で帰れるように」と慮ったつもりなのですが、復職した女性からすると、「慣れていない仕事」であり、しかも「自分が求めるやりがいとは異なる」と納得がいきません。
一方、周囲もそうした短時間勤務者には慣れていません。復職した女性は、16時になると帰ってしまいます。周囲ではその「特別待遇」が鼻につくでしょう。聞けば、基本給も一般職の自分たちよりも高いという。
さらに、「子どもが発熱」すれば早退し、「保育園の行事」といえば休む...。はた迷惑だ、という声が漏れ始めます。そうした冷たい視線を浴びることに限界を感じ、退職を選ぶママさん社員が後を絶ちませんでした。
そうすると今度は夫が、妻から「私は家庭のためにキャリアを犠牲にしたのだから、あなたは、きちんと階段を上りなさい」というプレッシャーを受けることになる。
2010年代の前半は、こんな八方破れな状態が続き、「女性の社会進出」が危ぶまれもしました。そして、性別役割分担への反動が起きています。
本気で女性活躍を考えねば経営が成り立たなくなった2010年代後半
さて、こうした女性の社会進出が「苦悶する時期」を経て、2010年代半ばからは、いよいよ本格的に風向きが変わり始めます。
企業は、手塩にかけた総合職女性を出産で手放す現状に我慢がならなくなったのでしょう。
とりわけ大手優良企業は、人材流出が基本的に定年退職だけで、長い期間をかけて育成投資を回収できる体制が整っていたのですから、バリバリ女性が予期せぬ退職をすることには危機感が募ったはずです。
折しも、出生数の急減が騒がれ、一方で当時の安倍政権が女性活躍を積極的に推進し、大企業に「女性役員」を努力義務化するといった、周囲からの圧力が強まった時期でもありました。
こうした流れの中で、出産した女性が長く働けるよう、元の職場・元の仕事に戻し、業務量だけ減らす、という制度が広まり始めます。
さらには、その減らした業務量の中で、しっかりパフォーマンスを上げれば、査定さえも通常通りに行い、昇進昇格評価の蓄積点に加えるという企業さえ出てきました。
こうして、2010年代半ばから、「女性がキャリアを途切らせずに長く働ける」会社が増えていきます。
結果、少なくとも育児女性に関しては、「忙しい毎日」型の労働からは脱し、短時間で会社から帰る権利が確保されました。
彼女らはもちろん、社内行事への不参加も許され、上司や顧客からの飲み会の誘いもスルーできることになります。不意の早退や有休も当然、許されてしかるべきでしょう。
明らかに過去の日本企業とは相容れない類の社員が、会社に一定数存在することが、当たり前になりました。
加えて直近になれば、イクメン・カジメンの奨励まで起き、ここにコロナ禍が重なったことで、リモートワークさえも浸透していきます。
中からも外からも、「働き方が変わらざるを得ない」ような圧力・エポック・事情が集中砲火的に重なったことにより、日本人の常識が大きく揺らいだ――だから、「静かな退職」が市民権を獲得し始めたと言えるでしょう。