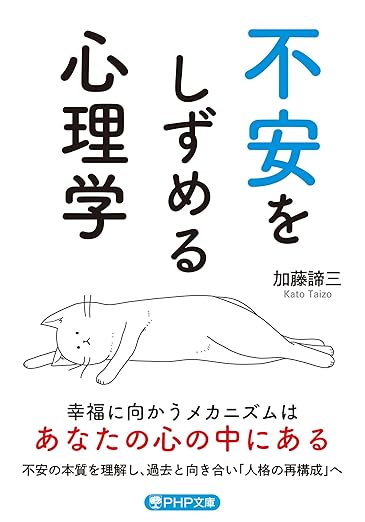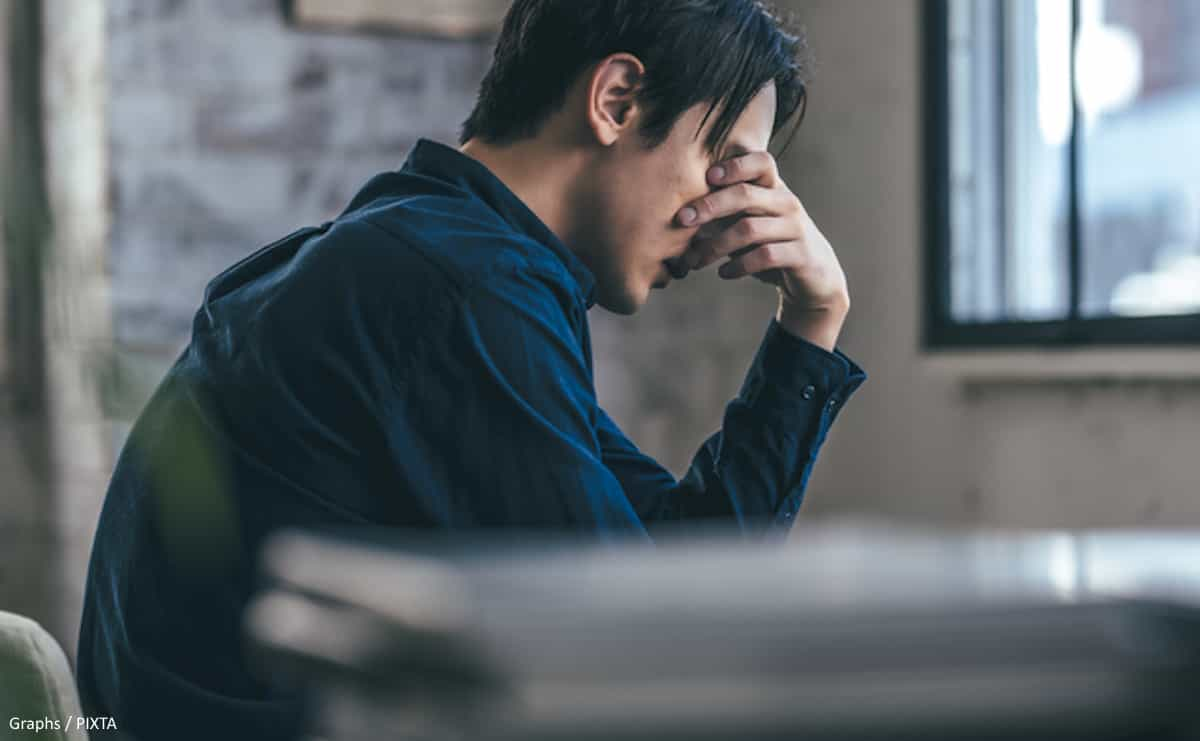
病気やケガ、自然災害、介護や人間関係、お金のこと、常に私たちの中にある不安や悩み。それらをどう考えて、対処していったらよいのか、早稲田大学名誉教授の加藤諦三氏に解説して頂く。
※本稿は、加藤諦三著『不安をしずめる心理学』(PHP文庫)を一部抜粋・編集したものです。
実年齢と精神年齢はまったく別
人間は非常に不公平です。
両親の仲が良い家庭に生まれれば、お母さんに母親固着を満たしてもらい、お父さんに励ましてもらえます。そうした環境で、人生の課題をそれぞれ乗り越えながら、自立して生きていくことができます。
しかし、生まれた家庭が、両親の仲が悪い場合もあります。いつもお父さんがお母さんに暴力を振るっていて、お母さんの泣き声を聞くのが嫌で、耳をふさいで押し入れに入っていた。そればかりか現在では、幼児虐待が増えています。
このように、とことん虐待される家庭に生まれる人もいれば、家族仲の良い家庭に生まれる人もいる。肉体的にも心理的にも不安を抱えた、孤独で虐待される環境に生まれる人もいれば、イギリスの精神科医ボールビーが言うような「無意識の安心感」を持って成長する人もいます。
ボールビーの言う「無意識の安心感」とは、意識しないで自分は安心感を持っている、ということです。つまり、保護と安心、安全を保障されていると無意識に感じている。ボールビーはこれを「Unconscious reassurance」という言葉で表現しています。
どんなことがあっても必ず助けてくれる人がいると信じている、自分は常に愛されて保護されている、という安心感のもとに生きていて、無意識の安心感を持てるというのは、本当に素晴らしいことです。
そんな、どんなことがあっても自分を助けてくれるという無意識の安心感を抱き、保護と安全という人間の根源的な欲求が満たされている人がいる一方で、そうではない人もいる。
ところが社会は、こうした前提の違いがあるのにもかかわらず、全員を同じように取り扱います。無意識の安心感のある、なしにかかわらず、20歳になったら、20歳の人間として同様に扱うのです。
しかし、その20歳の人の中には、心理的には2、3歳どころか、さらに未熟で、生まれたままのような精神年齢の人もいれば、人間として成熟しつつある人もいる。
さらに、心理的に幼い人のもとに生まれてくる子どももまた、肉体的にも心理的にも不安のまま生きていくことになるのです。
しかし、どのような環境のもとに生まれようとも、自分の運命を成就して、最後まで生きなければならない点は同じです。
自分の人生はどういう人生なのか
その意味でも我々にとって大切なことは、人格の再形成です。
つまり、これまでとは別の視点で、自分の価値観を見つめ直すということです。
周囲の人が自分に求めてきた価値ではなく、自分が信じる自分の価値に価値観を再構成するのです。
前述したように、世の中には「無意識の安心感」を持つ人もいます。何かあったら、必ず自分を助けてくれる人がいると無意識に信じられる人がいる。その一方で、他人が怖い、何をされるか分からない、生きるのが怖いという人もいます。
あるいは「記憶に凍結された恐怖感」という言葉があります。これは、幼児期に自分はいつ殴り殺されるか分からないような環境の中で育った結果、抱くようになった恐怖感です。
記憶に凍結されたこの恐怖感は10年、20年、そんな期間では変わらないと考えられています。何もしなければ、死ぬまでこの恐怖感を持って生きていくことになります。
どのような家庭に生まれるかは、もちろん当人の責任ではありません。
しかし、そうした運命を抱えて生まれ、いつまでも「記憶に凍結された恐怖感」のような恐怖を抱えて生きていると、40歳になっても50歳になっても、70歳になっても80歳になってもその人は幸せになれません。
大切なのは、我々は自分がめぐり合わせた人生としっかりと向き合い、自分の人生を受け入れながらも、人格を再構成することによって、新しい人生を切り拓くことです。
「おやじがアルコール依存症で暴力を振るってどうしようもない」。そういう環境の中で生まれた人にとって、これは「記憶に凍結された恐怖感」です。これは長い間、強く残ります。しかし、何もせずにそのまま生きて、「はい、あなたの人生つらかったですね」ではあまりにも悲劇的ではないでしょうか。
そういう人生を全部、再構成していかなくてはいけません。またそのためには、自分の人生はどういう人生なのかを考えることが、極めて大切なのです。
本当は助けを求めている
私たちはいま、不安の時代を生きています。もちろん、その不安は人によって違います。極めて深刻な不安を抱えている人もいれば、そうでない人もいます。
まず覚えておいてほしいのは、不安は助けを求める形で機能するという点です。
不安な人はさまざまな不安を口にします。しかし、悲観的な人が口にする不安というのは、楽観的な人から見ると、「なぜそんなに悲観的なことばかり口にするのだろう」と思うものもあります。
相手は不安を口にすることで助けを求めているのだ、ということが分かっていないと理解できません。それこそ「どうして、あんな不安ばかり言っているのだ」という話になってしまいます。
ですから、不安は、「助けを求めている」ことだと理解してください。
私はキリスト教の勉強はしていませんが、使徒のパウロは「前向きなこと、楽しいことを考えよう」と言っています。2000年以上前の紀元前の頃から、「前向きなことを考えよう」「楽しいことを考えよう」と言っています。しかし、人間は、1000年たっても2000年たっても、それを実現できていないのですが...。
人は助けを求めています。自分は不安だという人も、自分は助けを求めているのだということを意識することが大切です。
悩んでいる人の本音を整理すると
ここまでの話を整理すると、次のようになるでしょう。
・悩んでいる人は、悩んでいない人から見ると、「なんで、いつまでもそんなにくよくよ悩んでいるんだよ」「悩んでいたってどうしようもないじゃないか」と言いたくなるようなことで悩んでいる。
・悩んでいる人も、くよくよ悩んでいたって現実はどうしようもないということは分かっている。
・分かっているのならやめればいいが、そうはいかず、やはり悩み続ける。
・なぜなら、悩んでいるということは「助けて!」と言っていることなのに、それが他人に理解してもらえないから。
赤ん坊は「お腹が空いた」「水を飲みたい」「怖い」時に泣いて助けを求めます。赤ん坊が泣いている時というのは、「助けて」と言っている時です。
これと同じで、不安を口にする人が、意識の領域でいろいろな悩みを話しているのは、その人が無意識で「助けて」と叫んでいるということなのです。これは社会的に示されたサインです。
悩んでいない人がこの事実を理解し、一方で不安を口にする本人も自分が「助けて」と言っているのだということをしっかり認識しないと、悩みというのはなかなか解決しません。