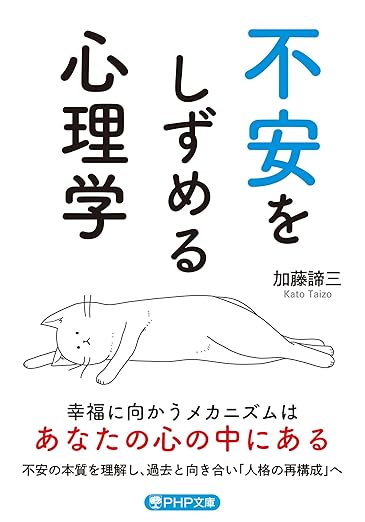病気やケガ、自然災害、介護や人間関係、お金のこと、常に私たちの中にある不安や悩み。早稲田大学名誉教授の加藤諦三氏は、それらによって敢えて不幸を選び取ってしまう人たちがいるという。
※本稿は、加藤諦三著『不安をしずめる心理学』(PHP文庫)を一部抜粋・編集したものです。
いじめがなくならない決定的理由
不安を簡単にしずめることができる方法はありません。
また一方で、不安をはじめとした人生で直面するさまざまな悩みに対して、「簡単な生き方がある」ことを競って教えているような、そういう社会に私たちは生きています。
少し話はそれますが、私たちの生きている社会には、容易に解決できない問題があります。例えば、いじめもそうした問題の一つで、なかなかなくなりません。
不登校の問題もなくなりませんし、幼児虐待も尽きません。ドメスティック・バイオレンスもパワーハラスメントも、みんな簡単にはなくなりません。
心の病は、ずっと存在しています。これらは何十年、何百年たってもなくならないでしょう。
では、なぜ同じことを繰り返しているのでしょうか。
それは、不安の心理がいかに恐ろしいものであるかが、私たちに理解できないからです。実はこれを理解しない限り、どんな教育をしてもみんな失敗します。
「いじめは良くない」ことは、ずっと教えられていました。しかし、それでいじめがなくなったかというと、いまもいじめは続いています。なぜなくならないのでしょうか。
「いじめは良くない」ことは、もちろんみんな知っています。
仮に、「いじめは良くない」ことを半数の人が知らないというのなら、「いじめは良くない」という教育にも効果があるでしょう。しかし、いじめている本人たちだって「いじめは良くない」ということくらい知っています。
だから、先生に隠れていじめているのです。そして、いじめた当事者たちに聞いてみると、「先生に見つかるようないじめ」はやっていない、というようなことを言います。
「いじめは悪い」ということを、みんなが知っているにもかかわらず、それでもいじめはなくならないのです。
少し回りくどい説明になりましたが、ここで何を述べたいかというと、「なぜなくならないのか?」という原因を考えずに、ただ「悪い、悪い」と言っているだけでは、何の解決にもならないということです。
そして私たちがすべきは、「なぜ困難を克服する能力がつかないのか?」を考えることなのです。
不幸になる選択を助けるのが消費・競争社会
いま私たちは消費社会の罠に陥っています。まずは、そのことをしっかり理解しておかないと、社会にあるどんな問題も解決しません。
消費社会は、あるはずのない安易な解決を教える。こうすればナルシシズムを満足させられると教える。その結果、人を神経症に追い込む。あるはずのない成長せずに生きていける社会を「ある」と教える。
人間が生きる上であるはずのない「魔法の杖」があると訴えて、競って物を売る消費社会、競争社会でいまの人は生きている。
その幻想の魔法の杖を求めて、人は必死で不幸を選ぶ。最後に人生が行き詰まる。
「不幸な人の中には、不幸であり続けようとする執念でもあるかのように、自分を不幸にする考えかた、生きかた、感じかたにしがみついている人が多い。」(『プライアント・アニマル』ジョージ・ウェインバーグ〈著〉、加藤諦三〈訳〉、三笠書房、238頁)
「幸せになりたいですか?」と聞くと、誰もが「幸せになりたい」と言います。しかし、なかなか幸せにはなれません。私たちは反対に死にものぐるいで不幸にしがみつきます。
なぜかというと、「幸せになりたい」よりも「不安を避けたい」気持ちのほうが強いからです。だから、結果として「不幸になる道」を選択します。
そして、それを助けるのが消費社会、競争社会なのです。
ここで、アルコール依存症の夫を持つ女性について考えてみます。幸いにしてアルコール依存症の夫と離婚できたとしましょう。本来は、そこで幸せになれますし、幸せになればいいわけです。
ところが、アルコール依存症の夫と離婚した女性を調べてみると、再婚した相手の多くが、またアルコール依存症の男性だったと述べました。
意識の上では、その女性はもうアルコール依存症の男性とだけは一切かかわりたくない、と思っています。暴力は振るうわ、他に女性はいるわで、自分が一生懸命パートで働いたお金を取り上げて、愛人に貢いでしまう。
もし本当に「もう嫌だ」と言うのなら、もうアルコール依存症の男性とは再婚などしなければいいのです。
それなのに、ほとんどの人はアルコール依存症の人と離婚もしないし、離婚した女性も、またアルコール依存症の男性と結婚するのです。
どういうことかというと、意識の上ではアルコール依存症の男性とは一生かかわりたくないと、確かに考えています。本当にそのように思っています。ところが無意識では、その女性が求めているのは、そういう男性なのです。
この意識と無意識との乖離が、不安な人たちが持つパーソナリティーの特徴です。
我々自身は意識してはいませんが、実際に我々を動かしているのは、意識ではなくて無意識のほうなのです。だから、アルコール依存症の男性と再び一緒に暮らすようになるのです。
不幸を選んで人を恨む
アルコール依存症の夫と暮らす不満と、別れて一人になる不安のどちらかを選ぶとしたら、多くの女性は不満のほうを選ぶという話をしました。
右に行くと幸福、左に行くと不安、あるいは劣等感が癒されるという分かれ道で、多くの人が左に向かってしまいます。こうして人は自ら幸福を捨てるのです。
なぜ人は毎日悩むのか?なぜ人は毎日「死にたい」と言うのか?それは、不満の感情よりも、不安の感情のほうが、はるかに強いからです。
だから「死んでも不幸を手放しません」という生き方にならざるを得ないのです。
それは不安よりも不幸のほうが心理的には楽だからです。不幸になるだけの努力がある。それをやめれば幸せになれる。頑張って不幸になるだけの努力をやめようとしてもやめられない。
それはアルコール依存症の人がアルコールをやめられないのと同じです。
人はみな幸せになりたいと願っています。その気持ちに噓偽りはありません。
しかし幸せになりたいという願望よりも、不幸になる魅力ははるかに強烈です。
人に意地悪をしていては幸せになれない、と誰もが分かっています。人の幸せのために働くことの気分の良さが、自分の幸せになると分かっています。
しかし、仲間はずれになるのが怖くて、人をいじめる輪に加わってしまう。
また不幸な人は、人の幸せを願う気持ちよりも嫉妬の気持ちのほうが強い。
そういう人は、だから意地悪していては幸せになれないと分かっていても、そうしてしまう。不幸になる道を自分で選んでしまうのです。
そして実際に不幸になりながら、さらにそこでまた人を恨む。そうやって、自分で不幸にしがみつき、その一方で「私は幸せになりたい」と嘆いています。
自分の無意識にある憎しみに気がつくことが幸せになる出発点です。
それを認めなければ、死ぬまで不幸です。死ぬまで不幸になるだけの努力を続けることになります。