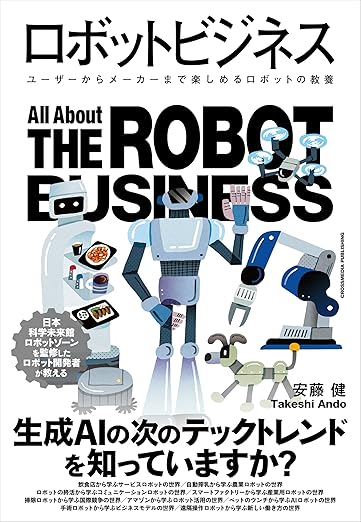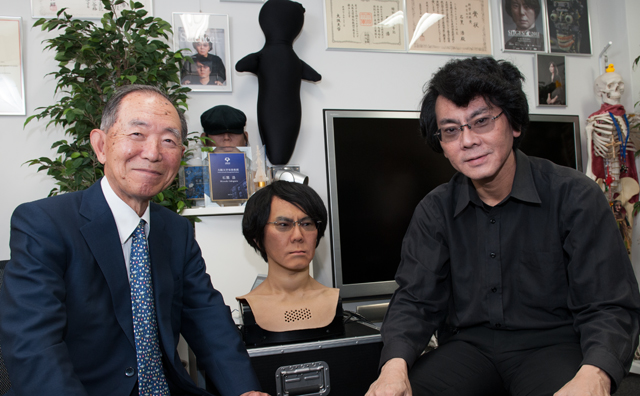約10秒に1回...全世界で使われている手術ロボット「ダヴィンチ」の圧倒的戦略とは?
2025年06月04日 公開

我々の生活の中で欠かせない存在になってきているロボット。手術ロボット「ダヴィンチ」は全世界で約10秒に1回使われているという。そんなロボットの今をロボット開発者の安藤健さんに解説して頂きます。
※本稿は『ロボットビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)より一部を抜粋編集したものです。
世界最大のロボットメーカーの驚くべき業績
世界最大のロボットユーザーは、全世界300カ所以上の拠点で移動型ロボットを稼働させるアマゾンといわれていますが、世界最大のロボットメーカーはどこでしょうか。ファナック、安川電機など産業用ロボットメーカーでしょうか。
ロボットの本体の売上規模、販売台数など、どのような指標で考えるかにもよりますが、ロボットビジネスの売上規模という意味では、意外にも、手術ロボット「ダヴィンチ」を製造するアメリカのIntuitive Surgicalが有力候補になります。
2023年に発表された業績によれば、Intuitive Surgicalは売上高約71億米ドルを記録し、営業利益は17.7億ドル(営業利益率は約25%)となっています。1ドル150円と換算すると、売上高は堂々の1兆円超えとなるので医療分野では、手術ロボットが新たなスタンダードとして定着しつつあります。
そのなかでもIntuitive Surgical社は圧倒的な存在感を誇ります。同社が開発した「ダヴィンチ」という手術システムは、その市場シェアが金額ベースで約80%という驚異的な数字を叩き出しています。
ダヴィンチシステムによって外科医は小さな切開から人間の手では難しい精密な操作を実現し、患者への負担を劇的に減らすことができます。
ダヴィンチを使うことで、傷口が小さくなり出血量が減るほか、入院期間の短縮というメリットや細かい作業が可能なことで合併症が低減できるなどの利点も報告されています。このような事例は、多くの医療機関や患者にとって大きな魅力となっています。
ダヴィンチの成功の背後には、非常に興味深いビジネスモデルがあります。なんと本体販売は売上の約3割にすぎず、残りの70%は消耗品やサービスからの収益なのです。
ロボットアーム先端のハンドにあたる鉗子などの手術器具は約10回使用すると交換が必要になっており、交換頻度の高い消耗品になっています。
一方、サービスはロボット本体の保守と関連する医師や看護師などへの教育訓練です。このような収益モデルを構築することで、高い収益性を実現しています。
手術ロボットという言葉からイメージする事業とはギャップがあるかもしれませんが、「プリンターのトナー」や「髭剃りの剃り刃」のような消耗品のビジネスモデルを展開しているのです。各手術で使用される道具やメンテナンス、サービスは、継続的に収益をもたらす重要な要素となっています。
年間販売台数の約1350台という数だけにとらわれると、このビジネスの本質を見誤ってしまうことになります。単価が高いので、本体だけでも約2500億円という販売金額の規模になるのも、もちろんすごいのですが、その本質は本体販売の裏にその約3倍の規模を稼ぎ出す消耗品やサービスのビジネスモデルが存在しているということなのです。
データの量がつくり上げる参入障壁
手術ロボット業界で圧倒的な存在感を持つ「ダヴィンチ」の事業をするIntuitive Surgical社にとって、最も大事な指標は何でしょうか。
Intuitive Surgical社のレポートなどを見ると、3つの指標を重要視していることがわかります。
1つは「販売台数」。もう1つは「ダヴィンチを使った学術論文の数」。そして、その2つを抑えてプレゼンなどの最初でアピールしている数字は、なんと「手術回数」です。
その数は、2023年は225万回を超え、24年は250万回を超えると予想されています。世界中で年間250万回の手術がおこなわれているということは、約10秒に1回、世界のどこかでダヴィンチにより手術されている人がいることを意味しています。
私が知る限り、手術回数、つまり、どれくらいロボットが使われているかを最重要視しているロボットメーカーは見たことがありません。多くのメーカーが販売台数、全額規模を重要視するなかで、この事実は一体何を意味するのでしょうか。
これは会社のビジネスモデルと大きく関連しています。前述したように、Intuitive Surgical社は本体の売上が3割、消耗品・サービスが売上の7割を占めるという構成になっています。すなわち、販売後も継続的に収益が期待できるリカーリングビジネスということになります。
最新の資料では、23年のリカーリング比率は83%まで高まるとも言われています。まるでソフトウェア企業が「SaaS(Software as a Service)」として月ごとに利用料を稼ぎ、事業を成長させているかのように、手術のたびに消耗品で稼いでいるのです。
そして、手術回数がつくり上げるのは、単なる収益面での特徴だけではありません。この頻繁な使用が生み出すのは、膨大なデータであり、そのデータが他の企業の参入を困難にしています。
Intuitive Surgical社の主要な特許が2020年頃に切れたことで、多くの企業がこの市場に参入しました。たとえば、川崎重工業やJohnson&Johnson、さらにはGoogle関連企業などさまざまな業種が興味を持ったのです。
そして、メディアなどでは、ダヴィンチ一強の時代も遂に終焉するという報道が目立ちました。しかし、これらの企業が市場のシェアを奪うのは容易ではありません。その理由は、Intuitive Surgicalが持つ蓄積されたデータの量と質が大きな壁となっているからです。
手術がおこなわれるたびにデータが収集され、システムの改良に役立てられます。この循環が新規参入企業には大きな障壁となります。
どの症例にどのように対応するかという詳細なデータが蓄積されています。これにより、ダヴィンチは他の企業にはない信頼性と実績を持つことになり、冒頭に紹介したもうひとつのKPIである学術論文として発表され、エビデンスを重んじる医療機関からの支持を得やすい状況になっていくのです。
さらに最新のモデル「ダヴィンチ5」では、センサーが追加され、手術者が力を感じながら手術できるようにする機能の追加がありました。もちろん、より安全に、より精密な作業ができるというメリットもあるかもしれませんが、この機能の裏にはもっと大きな戦略があるのではないかと思います。
このセンサーにより、手術中のどのタイミングで臓器などにどの程度の力をかけているかというデータを収集できます。
これにより手術の一部、またはすべてを自動化する際の基盤となる情報が得られるのです。現状は医師が遠隔操作でおこなう手術がメインですが、蓄積されたデータを活用すれば、簡単な処置から始めて最終的には完全自動化まで進む可能性があります。
今後、データを収集するだけでなく、それをどのように最適化し、実際の手術や治療に応用するかが重要な課題となります。
要するに、ダヴィンチという手術システムがつくり上げた参入障壁は、技術レベルが高いというだけではなく、データの蓄積とその活用によるものなのです。
新たな参入企業が同じ量と質のデータを収集し、活用するのは容易ではありません。このデータの蓄積が、自社のビジネスはもちろんのこと、未来の医療に大きな影響を与えることでしょう。
手術ロボットの王者の事業は、ロボットビジネスが機械の性能の競争だけでなく、データの知識と運用が鍵となる時代へと進化していることを示唆しているのです。
もちろん、Intuitive Surgical社にも解決すべき課題があります。本体価格が数百万ドルという1億円を超える金額になっており、この高額な初期投資が導入の障壁となる場合も多いのです。多くの病院では予算制約から新しい技術導入に踏み切れないことがあります。
このような状況下で、競合他社も黙って指をくわえているだけではありません。低コスト化やビジネスモデルなど導入しやすさで勝負する企業、東南アジアなどまだ手術ロボットが普及していない地域で勝負する企業。それぞれの企業が戦略を持って取り組み始めており、今後この市場はより洗練されていくでしょう。