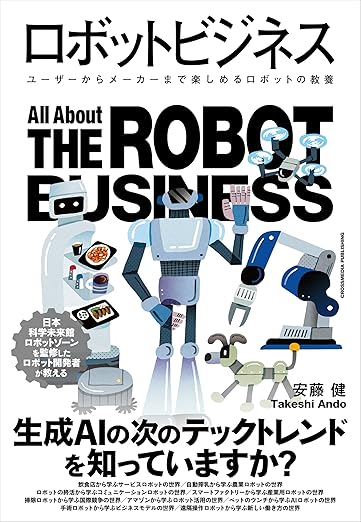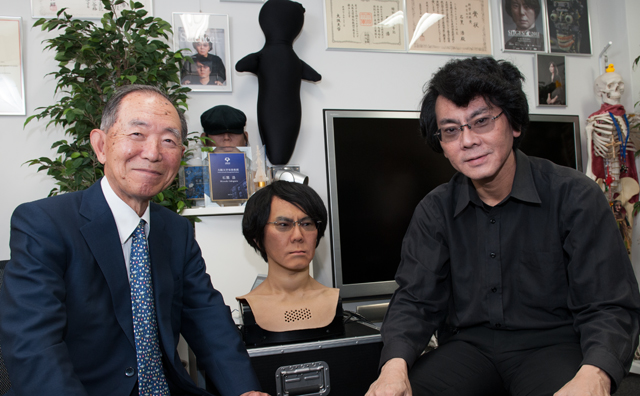AIでイチゴの色を判別...日本の農業を救う「自動収穫ロボット」の目覚ましい進化
2025年06月10日 公開

我々の生活の中で欠かせない存在になってきているロボット。日本の農業が直面する深刻な課題を解決する鍵ともいわれているロボットの今をロボット開発者の安藤健さんに解説して頂きます。
※本稿は『ロボットビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)より一部を抜粋編集したものです。
コメは自動化の最先端へ
大雨のなか、無人のコンバインが田んぼを縦横無尽に走り回り、正確に稲を刈り取っていく。こんなシーンが2018年に放映された人気ドラマ『下町ロケット』の一幕であったことをご存じでしょうか。
大雨のなかかは置いておき、このような光景はドラマの世界だけではなく、すでに実際の日本の農村で現実のものとなっているのです。
稲作は耕し、植え、収穫するという業務が比較的シンプルなため、他の農業分野に比べて機械化が早く進みました。そしていま、その稲作が自動化の最前線に立っています。
GPSを利用した自動運転トラクターが人間以上の精度で田んぼを耕します。さらに、熟練農家の技術を再現する自動運転田植機も実用化されています。そして、冒頭紹介したような収穫作業をおこなう自動コンバインまで登場しているのです。
このような自動走行する農機は、たとえば、AIカメラとミリ波レーダーといった周囲環境を測るセンサーを搭載し、収穫対象の稲と周囲の人や障害物を識別でき、人が乗らなくても自動で収穫作業をおこなえるようになっています。
車の自動運転と比べると、農機の自動運転はスピードが遅く、比較的人も少ないエリアを走行することが多いため、複数台の同時走行、圃場間の公道走行など先進的な取り組みも増えていますし、これからも進化が見込まれます。
これらの最新のロボット技術が、日本の農業が直面する深刻な問題を解決する鍵となっています。その問題とは、農業従事者の高齢化です。
農林水産省の調査によると、2020年の日本の農業従事者の平均年齢は何と67.8歳。これは、日本全体の平均である46.9歳はもちろんのこと、同じく高齢化が進む漁業の56.9歳(2018年時点)をはるかに上回っています。
この危機的状況にロボットが光明をもたらすかもしれません。
自動化と省力化により高齢者でも農業を続けられるようになり、また早朝からの長時間労働による負荷を軽減することは若い世代にとっても農業の魅力アップにつながります。
すでに多くの水田や畑での実績が日本全国で蓄積されており、ロボットトラクターを使用することで従来よりも平均で約3分の1と大幅に作業時間を短縮できたことも報告されています。
さらに、ロボット技術には意外な効果もあります。それは、熟練農家の技術やノウハウをデジタル化し、次世代に継承できるとことです。これにより、後継者不足という農業界のもうひとつの大きな課題にも対応できるようになるのです。
農業分野におけるロボット活用は、単に農業界だけの問題ではありません。食料安全保障、地方創生、そして日本の産業競争力に直結する重要な課題なのです。
ロボットだけではなく、IoTやAIと組み合わせることで、より効率的で持続可能な食料生産システムを構築できるかもしれません。そして、都市部の若者が農業に参入しやすくなることで、地方の活性化につながる可能性もあるのです。
野菜も果実も自動収穫が進む
トマト、ピーマン、キュウリ。いずれも多くの家庭の食卓に並ぶ野菜たちですね。実は、これらの野菜はすでにロボットによる収穫が始まり、実際にロボットで収穫されたものがスーパーに並んでいます。
自動収穫の波は、稲だけでなく、野菜や果実にも広がっているのです。
たとえば、アスパラガスの自動収穫ロボットが開発されています。アスパラガスは稲のように下から上にまっすぐ伸びるため、自動化しやすい作物だったのです。このロボットは、カメラでアスパラガスの位置を認識し、適切な高さで切断します。
さらに驚くべきことに、最近ではアスパラガスのように似た形状のものだけではなく、かたちや色が同じにならない野菜の収穫でも自動化が進んでいます。
冒頭に紹介したトマト、ピーマン、キュウリなどがまさにそれです。色が緑から赤に変化したタイミングを見逃さずにトマトを収穫したり、いろいろなサイズやかたちがあるキュウリを収穫したりできるようになっているのです。
野菜だけではありません。AIを使って、イチゴの色を判定し、収穫に適したものを自動で摘み取るイチゴ収穫ロボットも開発が進んでいます。
現段階では、単価が高い、収穫時期が長い、収穫量が多い、生育環境がハウスなど工場化している、などビジネス的に成立しやすい作物が優先的に収穫ロボットの対象になっていますが、今後は、より植物を傷つけない収穫、高速での収穫、不整地での走行などの技術の進展とともに、その範囲がより多くの作物に拡大していくと考えられます。
ただし、技術の進化だけでは市場の拡大は困難です。特に自営業者や小規模の法人の多い農業では、投資のしやすさが必須です。
現在は、まだまだ先行投資ができる企業での活用に限定されていますが、コストダウンはもちろんのこと、現在も一部で導入され始めている収穫量に応じたサブスクリプション方式のように利用の障壁を低下させる取り組みにより、ユーザーの幅はより広がっていくことになります。
対象となる果実や野菜、そして農園の規模などによっても異なりますが、収穫作業は全労働時間の20~50%ほどを占めているとも言われており、これらの自動収穫技術の導入効果は絶大です。
ロボットは昼間だけではなく、夜間も作業をおこなうことができ、労働力不足の解消、作業効率の向上、品質の安定化などのさまざまな効果が期待できます。
また、AIによる収穫予測技術も進化しています。過去のデータや気象情報、栽培状況などを総合的に分析することで、将来の収穫量を正確に予測できるようになりました。これにより、農家は生産計画を最適化し、過剰生産や在庫の廃棄を減らすことができます。
さらに、収穫時期や品質のピークを正確に把握することで、品質向上にもつながるのです。
今後は、ロボットやAIの技術進歩により、収穫だけでなく、栽培管理全般の自動化も進むと予想されます。
つまり、農業の自動化は、単に労働力不足を解消するだけでなく、農業のあり方そのものを変える可能性を秘めているのです。
たとえば、24時間稼働の植物工場と自動収穫ロボットを組み合わせることで、天候に左右されない安定した生産が可能になるかもしれません。すでに屋内で照明や栄養がコントロールされた植物工場は世界中で活用されていますし、一部の植物工場ではロボットの活用のトライも始まっています。
まさに製造業の工場で商品を自動的に生産するように、食べ物も自動生産される時代が来るかもしれません。
結果として、自動収穫技術の進化は、私たちの食卓にも影響を与えるでしょう。品質の安定した農産物が年間を通じて供給されるようになり、季節を問わず新鮮な野菜や果物を楽しめるようになるかもしれません。
農業の自動化は、まだ始まったばかりです。しかし作物の種類、対象とする作業など、その進化のスピードは私たちの想像を超え、中国なども含めて世界中で取り組みが加速しています。近い将来、畑や果樹園でロボットが働く光景が当たり前になるかもしれません。