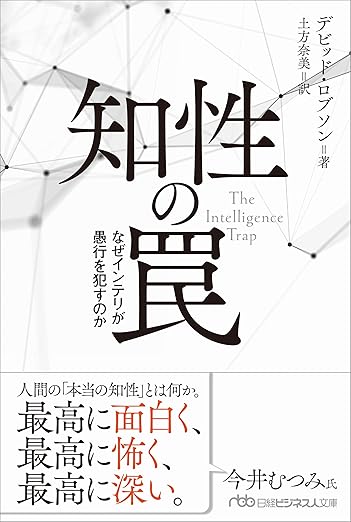エジソンも間違えた? 「電流戦争」に敗れた発明王の知性の罠
2025年05月16日 公開
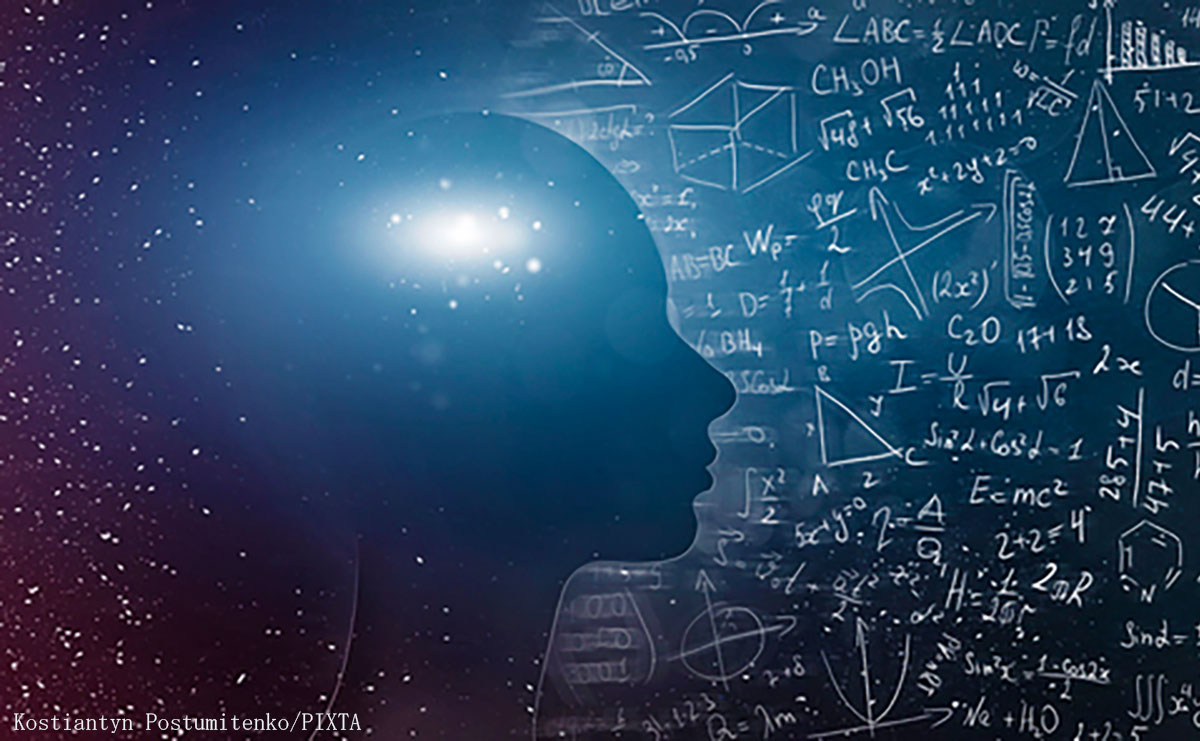
科学的に広く受け入れられている事実を否定する極めて知的で優秀な方々がいる。「優れた知性」は「優れた思考力」と同義とは言えず、賢い人はある種の愚かな思考に人並み以上に陥りやすい。彼らは、何故"知性の罠"に陥ってしまうのか?
天才と呼ばれる3人の実話をもとに、「動機づけられた推論」(感情的思い入れのある自己弁護的な思考)や「認知の死角」(他人の欠点には目ざとい一方で、自身の偏見や思考の誤りに気づかないこと)といった思考の罠について、科学ジャーナリストのデビッド・ロブソン氏の書籍『知性の罠』より解説します。
※本稿は、デビッド・ロブソン著, 土方奈美(翻訳)『知性の罠』(日経BP)を一部抜粋・編集したものです。
神の思考に挑んだアインシュタイン
すばらしい知能を持ちながら、狭量な思考によって正気を失ったと見られる人は少なくない。
心霊や妖精に心を奪われることはなくても、およそ正当化できない主張を正当化することに多くの時間を浪費し、残念な結果を招いた。
たとえば天才の代名詞とも言えるアルバート・アインシュタインだ。
まだ若き特許局員として働いていた1905年には、量子力学、特殊相対性理論、そして彼の業績のなかでも最も有名な質量・エネルギー等価の原理(E=mc²)をまとめた。その10年後には一般相対性理論を発表し、アイザック・ニュートンの万有引力の法則を否定した。
しかしアインシュタインの野心はそこで終わらなかった。その後の人生を通じて、電磁気力や重力を統一理論にまとめ、さらに壮大で包括的な宇宙論を構築しようとした。
「神がどのようにこの世界を創られたのかを知りたい。個別の現象、特定の元素のスペクトルに興味があるわけではなく、神の考えそのものを知りたいのだ」と書いたこともあり、この統一理論は神の思考の全体像を理解するための試みだった。
しばらく闘病生活を送ったのち、1928年にはそれが完成したと考えた。「私はすばらしい卵を産んだ。(中略)そこから生まれる小鳥が元気で長生きするかは、神の御心に委ねられている」と書いている。
しかし神はすぐにその小鳥を殺してしまい、それから25年にわたってアインシュタインは次々と新たな統一理論という小鳥を生み出していったが、いずれもあっという間に死んでしまった。
死の直前、アインシュタインは「私の生み出した子孫の多くは、幼くして失望という名の墓場に埋もれてしまった」と漏らしている。
しかしアインシュタインの失敗は、周囲には決して意外なことではなかった。伝記作家で物理学者のハンス・オハニアンは著書『Einstein’s Mistakes(アインシュタインの失敗)』(未邦訳)に、こう書いている。
「アインシュタインの計画そのものが、不毛な試みだった。(中略)はじめから命運は尽きていた」。しかし理論にのめり込むほど、諦められなくなっていった。
プリンストン大学の同僚だったフリーマン・ダイソンは、アインシュタインの雲をつかむような話を聞くのに耐えられず、8年にわたって意識的にキャンパスで顔を合わせないようにしていた。
問題は1905年には大いに役立った有名なひらめきが、今回はとんでもなく方向を見誤る原因となったこと、そしてアインシュタインが自らの理論を否定するような見解に徹底して目をつむったことだ。
たとえば自らの壮大なアイデアに矛盾する核力の存在にかかわる証拠を無視したり、かつて確立に寄与した量子論の研究成果をバカにしたりした 。科学界の会合では、ライバルの誤りを証明すべく凝りに凝った反例を1日中考えた挙句、あっさり否定されるということを繰り返した。
プリンストン大学の同僚であったロバート・オッペンハイマーは「アインシュタインは実験に完全に背を向け、事実から目を背けようとした」と語っている。
アインシュタインも晩年にはそれを自覚していた。「おそらく私は、邪悪な量子を見るまいと、相対性理論の砂に頭を突っ込んだままのダチョウのように見えるのだろう」と友人で量子物理学者のルイ・ド・ブロイに書き送っている。
それでも不毛な努力をやめることはなく、その才能が朽ち果てようとする死の床にあっても、誤った理論を証明するための数式を何ページも書き綴っていた。サンクコストの誤謬が、「動機づけられた推論」によって重症化したようだ。
「電流の戦い」に敗れたエジソン
次に、史上最も偉大な2人のイノベーターのエピソードに目を向けよう。トーマス・エジソンとスティーブ・ジョブズだ。
1000件を超える特許を持つトーマス・エジソンが、ずば抜けて優れた知能を持っていたのは明らかだ。しかしひとたびアイデアを思いつくと、それを変えるのは非常に困難だったようだ。その最たる例が「電流の戦い」と呼ばれる一件である。
1880年代末に電球の実用化に成功したエジソンは、アメリカ中の家庭に電力を送る方法を考えはじめた。
そして考えたのが、安定的な直流(DC)を使った送電網を構築する、という案だったが、ライバルのジョージ・ウエスチングハウスは交流(AC)を使って送電するという安価な方法を考案した。
今日、私たちが使っているのは後者である。DCでは電気が流れる際の電圧が一定だが、ACは2つの電圧のあいだで周期的に切り替わり、長距離送電の際の電力損失を抑えられる。
エジソンは、ACは感電死のリスクが高く、危険すぎると主張した。根拠のない主張ではなかったが、感電のリスクは適切な絶縁や規制によって抑えることができ、また経済性のメリットは無視できないものだった。大衆市場に電気を供給する手段として、現実味があったのはACだけだ。
DCという選択肢に固執するより、新たなAC技術を活用し、その安全性を高めるのが合理的対応だったはずだ。エジソンの部下であった技術者のニコラ・テスラも、そう説得している。
しかしエジソンはテスラのアドバイスを聞き入れず、ACを研究しようとするテスラに資金を出すことも拒否した。この結果、テスラは自らのアイデアをウエスチングハウスに売り込むことになった。
しかしエジソンは断固として敗北を認めず、ACに対する世論の批判を煽るため、激しいPRキャンペーンに打って出た。最初に行ったのは、野良犬や馬を感電死させるという、おぞましい公開実験だ。
またニューヨーク裁判所が、死刑執行手段として電気を使えないか検討していることを小耳に挟むと、裁判所に電気椅子の開発をアドバイスした。ACが死を連想させるように、と考えたのだ。
かつて「死刑の完全廃止のための取り組みに心から賛同する」と宣言した人物とは思えないほど、衝撃的な変わり身である。
冷酷なビジネスマンらしい行動だと思うかもしれないが、この戦いはどこまでも不毛だった。1889年には、ある学術誌がこう指摘している。
「交流電流の開発という流れは、もはや誰にも、どの団体にも止めることはできない。(中略)旧約聖書のヨシュアなら太陽に止まれと命じることもできるかもしれないが、エジソン氏はヨシュアではない」。
1890年代にはエジソンも敗北を認めざるを得なくなり、別のプロジェクトに関心を向けるようになった。
科学史家のマーク・エシグは「問題はなぜエジソンの試みが失敗に終わったかではなく、なぜそんな試みが成功すると思ったか、である」と述べている。
ただサンクコスト・バイアス、「認知の死角」、「動機づけられた推論」といった認知的過ちを理解すると、これほど優秀な知能がこれほど破滅的な行動を続ける理由が説明できるようになる。
自らの死期を早めたジョブズ
アップルの共同創業者、スティーブ・ジョブズもエジソンと同じようにすばらしい知性と独創性に恵まれながら、現実世界に対して驚くほど歪んだ認識を抱くことがあった。
ウォルター・アイザックソンの手による公式伝記では、ジョブズの知人たちが「現実歪曲フィールド」について語っている。
元同僚のアンディ・ハーツフェルドはそれを「カリスマ的な語り口、強靭な意志、目的達成のためなら事実を曲げることも厭わない情熱が入り混じって生まれる、周囲を困惑させるような状況」と描写している。
この断固たる意志の力は、テクノロジーに革命をもたらす原動力となったが、私生活において裏目に出ることも多かった。2003年に膵臓癌と診断されたときが、その最たる例だ。
ジョブズは主治医のアドバイスを無視して、ハーブ療法、スピリチュアル治療、果汁中心の厳格な食事療法など、いんちきな治療法に走った。周囲の人々によると、ジョブズは自分の力で癌を治せると確信しており、その驚くべき知性をあらゆる反対意見を退けるために使ったようだ。
ようやく手術を受けようと決めたときには、癌は手の施しようのないほど進行していた。医師のなかには、主治医の助言を素直に受け入れていれば、ジョブズは今も生きていたかもしれない、という見方もある。
いずれのケースでも、すばらしい知能が論理的で合理的な思考ではなく、理屈づけや自己正当化に使われたことがわかるだろう。