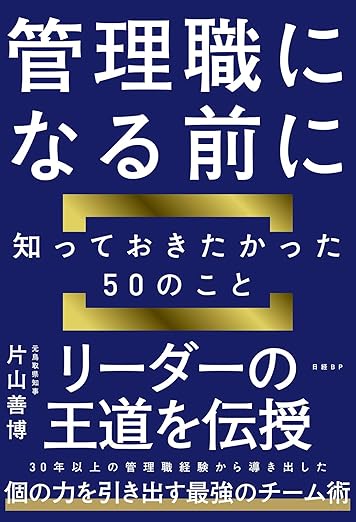厚生労働省の報告によると「管理職に昇進したいと思わない」人は61%にのぼるといわれています。一方で、実際に社会や会社を動かしていくためには、管理職の仕事は必要です。
本稿では、鳥取県西部地震被災者のために住宅再建支援に尽力された元鳥取県知事で大正大学特任教授の片山善博さんに、当時の状況とともに管理職としての考え方、行動規範について解説して頂きます。
※本稿は、片山善博著『管理職になる前に知っておきたかった50のこと』(日経BP)を一部抜粋・編集したものです。
M7.3地震発生、その時
2000年10月6日、鳥取県で阪神・淡路大震災とほぼ同じ規模の地震があったことをご存じでしょうか。
当時、鳥取県知事を務めていた私は、地震直後に災害対策本部を立ち上げ、ヘリコプターで被災地の上空から撮った映像を送ってもらい、県庁内の災害対策本部で遠隔で状況を確認しました。がけ崩れなどの大きな被害を目の当たりにし、翌日から毎日ヘリコプターで被災地へ行って避難所を回り、被災者の皆さんの声を聞きました。
被災地は中山間地で、多くの高齢者が家を失っていましたから、私は「どうすればいいだろうか」と考えました。私だけではなく、ほかの幹部たちとも手分けして、毎日被災地と県庁を往復しながら、どんな対策を打つべきか、議論を重ねたんです。
避難所では被災者の方に「大変でしょうが、頑張ってください」と声を掛けました。これから復旧、復興していくために、目の前の被災者の皆さんを支えたいと真剣に考えていました。でも、相手の方にしてみれば、75歳にもなって家を失い、知事から「頑張ってください」と言われても、果たして頑張る気になるだろうか、と感じたのです。
被災者の方に「私はもう帰る場所がなくなりました。知事さんは知事公舎があって、家族も無事でいいですよね」と思われてしまう可能性もあるのです。そこでやはりその人の立場に立って考え、「どうしたら、この目の前の被災者を不安や絶望から解き放つことができるのか」と悩みました。
「やはり住む家がないと安心して暮らせないよね」――、これが私が思ったことの1つでした。
避難所ではたくさんの被災者が県外に出ていく相談をしていました。「家が壊れて住めなくなった。東京にいる子どもが『お母さん、こっちに来ればいいよ』と言ってくれているから、行こうかと思っている」と言って泣いている方もいました。
「おばあちゃん、本当に東京に行きたいの?」と聞くと、「行きたくないですよ」「ここに住み続けたい?」「そうですよ、一生ここで暮らしたいと思っているし、本当は東京には行きたくない。でも行かざるを得ないですよ。こんなありさまですから」と言うのです。
その方の本心は、「住み慣れた場所に住み続けたい。暮らせる家が欲しいけれど、建て直すお金も気力もない」でした。こういう状態のとき、知事である私ができることは何だろうかと考えたわけです。
数日間、避難所に通ううちに「やはり住む家が一番重要だ」という思いに至り、これが私だけでなく、県庁幹部の間でも共通認識になっていきました。
そして私たちが検討し始めたのが住宅再建支援制度をつくることでした。今では全国規模の制度になりましたが、当時は全国どこにもこの制度はありませんでした。この制度の整備に向けて動き出した私たちは、国から「そんな制度をつくってはいけない」と言われることになります。
「付き合い方を考え直す」霞が関の抵抗
「住宅再建支援の制度が必要だ」と考えた私たちは、まず国の制度を調べて、既存の法律が活用できないかを探りました。その結果、住宅再建支援に関する制度が存在しないことが明らかになりました。
被災者が住宅金融公庫からお金を借りて、住宅を自費で再建した場合に、金利負担を軽減する制度はありました。しかし、その制度を使えるのはお金を借りられる人だけです。自力で建て替える気力も資力も持たない人は借金をしませんから、活用できません。
そこで今度は鳥取県の職員がいろいろな省に電話を掛け、「既存の支援制度の中に、何か使えるものはないか」と問い合わせました。被災体験のある兵庫県や神戸市にも「住宅支援はどうやったのですか?」と聞いたところ、「政府に支援制度を断られた」と言うのです。
そんなやり取りを2~3日間続けていたので、国のほうも、こちらの動きを何となく察します。それに、地方自治体には国の人間が出向して働いていますから、そこからも現場の情報が上がっていくんです。
すると、鳥取県庁にファクスが何通も届くようになりました。「(住宅再建支援制度は)絶対やってはいけない。やめろ」「やるべきでない理由は...」「税金をプライベートな財産形成に使ってはいけない」といった内容でした。加えて、政府のいくつかの省庁の幹部から強い口調で「だめだ」とも言われました。
「そんなことをしたら鳥取県との今後の付き合い方を考え直さなくてはいかん」というけんまくの人もいたのです。
使うのは国ではなく、県のお金ですから、私たちが国に黙って新制度をつくることは可能でした。でも、国との関係をあまり険悪にしても、後になって困るかもしれませんから、ある程度、理解と納得をしてもらっておいたほうがいいと考えました。
そこで、鳥取県東京事務所から東京の省庁に電話を掛け、「地震の被害状況や国への要請を知事が話しに行きます」と説明してアポイントを取ってもらい、急いで飛行機で上京しました。
霞が関でいくつかの省を回り、「かくかくしかじかで」と現場の事情を説明しました。しかし、けんもほろろで「憲法違反だ!」と突き返されました。こちらが「憲法第何条に違反しているのでしょうか。学生時代に憲法を勉強しましたが、住宅再建支援をしてはいけないなんて、どこにも書いていないと思いますよ」と言ったら黙ってしまいましたけれどね。
なぜこんなに反対されたのか。そこには理由があったのです。当時から5年前、阪神・淡路大震災が起きたとき、やはり「住宅再建手当てをしてほしい」という声が被災地から上がったんです。でも政府は「支援したいのは山々だが、私有財産に税金を使うのは、憲法で認められていない」という理由で断ったのだそうです。
被災者の要望を政府に伝えたのは弁護士の人だったのですが、「それなら仕方がない」と言って引き下がってしまった。しかしその後に鳥取県が新制度を実現したとなれば、「あのとき政府が言ったことは間違いだった」と認めることになってしまう。
それが嫌だったのではないでしょうか。このいきさつは後から知ったことですが、あのとき執拗に「だめだ」と言ってきた人たちは自分たちの立場やプライドを守るために必死だったんでしょう。
とにかくこちらも必死ですから、諦めずに説明して回りました。そして、ある大臣に「住宅再建を支援する新制度をつくろうと思うのですが、官僚の人たちに猛反対されています。大臣のお立場もあると思いますが、どうかここは目をつぶってください」と伝えたところ、「片山さん、あなたの言うことはよく分かります。私は聞かなかったことにするから、あなたがやりたいと思ったようにおやりなさい」と言ってもらえたのです。
役所を4つほど回って、20~30人に会いましたが、そう言ってくれた人はたった1人でしたね。そして、夕方、鳥取に戻り、記者会見を開きました。
忘れもしない10月17日のことです。記者会見で「県独自に住宅再建支援をします」と発表したら、被災者の皆さんが一気に元気になりましてね。それまで避難所で元気なく横たわっていた方々の多くが、翌日には避難所からいなくなってしまった。「皆さん、どこへ行ったの?」と聞いたら「工務店探しです」と。
当時、メンタルケアのために何人もの精神科医や保健師に避難所に入ってもらっていたんですが、その人たちが後で言いました。「私たちは無力でした。私たちも一生懸命メンタルケアをやりましたが、知事さんの記者発表が一番のメンタルケアになりました」と。