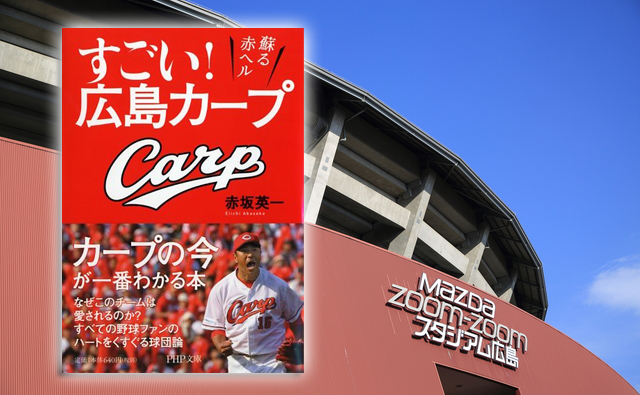樽募金~広島東洋カープを支えた市民の力
2014年06月03日 公開 2024年12月16日 更新
「二度とこのような郷土チームは現われない」
昭和26年(1952)のペナントレース開幕前、カープに「解散」、または「他球団との合併」の話が持ち上がる。
勝率が3割にも満たず、選手にろくに給料すら払えないチームにリーグに参加する資格はない。連盟はそう考えたのだ。そして、実のところ、同年3月14日に球団重役会が開かれ、当時下関にホームグラウンドを置いていた大洋ホエールズ(現横浜DeNAベイスターズ)との合併を一度は決定している。重役たちも、給料もきちんと支払えない現状ではやむ無し、との苦渋の決断だったのだろう。
ところが、予期せぬ事態が起きる。報せを聞きつけたファンが、その日の夜に重役会が開かれていた旅館に押し寄せたのだ。カープがなくなるなんて考えられない、今すぐ存続の懇願に向かわなくては…。大勢のファンが、いても立ってもいられないと駆け付けた。
カープをなくすな、頼むからなくさないでくれ――。そんな叫び声に真摯に耳を傾けたのが、監督の石本秀一だった。
「うちには、こんなにも熱いファンがいます。いまカープを潰せば、日本に二度とこのような郷土チームは現われない」
こうして、合併の話は一旦は保留とされたものの、資金不足の問題が解決されたわけではない。球団が存続するには、まずは約400万円が必要だった。そんなカープの窮境を支えたのも、またファンだった。
広島市民は、こぞって石本が組織した後援会に募金を始めた。老若男女問わず、カープになけなしの金を差し出した。ある小学生は1年がかりの貯金をカープのために崩す決意をした。父親の仕事を手伝う度にもらった数円の小遣いを貯めたもので、その額は200円に達していた。また、こんな逸話もある。シーズン開幕を控えた選手たちが練習しているところに、パトカーがやってきた。「何か事件があったのか」。球場は騒然となるが、どうも様子が違う。実は、市警本部の有志が各署から募った激励金を届けに来たのだ。パトカーを使ったのは一刻も早く手渡すため。約400人から集まった金額は、1万5620円にのぼっていたという(当時の大卒公務員の初任給が5500円)。
そして、こうしたファンの動きの象徴となったのが「樽募金」だ。
ある日、広島総合球場の正面入り口に2つの四斗樽が置かれた。地元紙・中国新聞の野球部員が発案したもので、練習や試合を見に来た人に、樽の中に浄財を投げ入れてもらおうというのだ。日用品の「樽」が用いられたところが、なんとも「市民球団」らしい。この頃の新聞記事によれば、一日で集まった額はおおよそ3万~6万円。多いときには10万円を超すこともあったという。確かに、全体の必要額からすれば一部に過ぎない。しかし当時を知る広島市民は「集まった額も、いつまで設置されていたかも覚えていない。集まった金よりも、カープと市民の絆を表わす象徴だった」と語る。
シーズン開幕後も、ファンはチームの成績が振るわずとも球場へ向かい、試合の行方に一喜一憂するとともに支援を続けた。そして同年末、支援金は目標額の400万円を突破して、球団存続が正式に決まったのである。監督、コーチ、選手、フロントなどの球団関係者、そして何よりもファンが抱いた感慨はいかばかりだったろうか。その後もカープは市民球団として戦い続け、潤沢な資金は持たないものの、昭和50年(1975)には悲願の初優勝を遂げることとなる。この時、優勝が決まると、選手とファンは一緒になってグラウンド上で喜び合った。
実は、「樽募金」は平成の世にも復活している。一度は5年前にオープンした新球場建設の際だ。筆者も平成17年(2005)春の宮崎キャンプを訪れた時、練習場の日南市天福球場の入り口に樽が置かれていたのを強く覚えている。「少しでも新球場建設の足しになれば」と、多くのファンが樽の中にお金を入れていた。また、先の東日本大震災が発生した際には、選手たちが率先して試合前に樽を持って義援金を呼び掛けている。
ファンの力に支えられたカープと、そのカープを生きがいとして戦後復興に励んだ広島の人々。樽募金の逸話からは、両者の間の強い「絆」を感じずにはいられない。