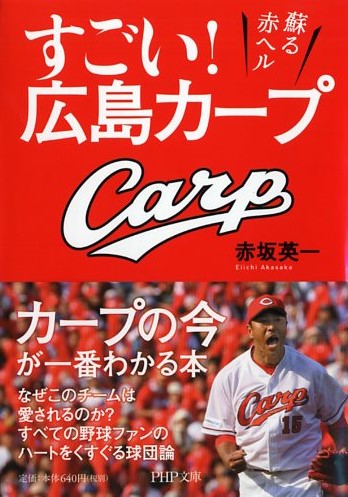勝って驕らず、負けて腐らず。黒田博樹がカープにもたらしたものとは
2016年09月10日 公開 2024年12月16日 更新
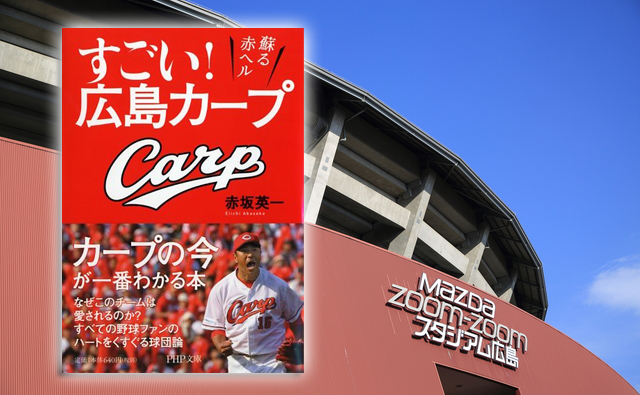
PHP文庫『すごい!広島カープ』より一部抜粋
黒田あってのカープ、カープあっての黒田
2016年の広島東洋カープは、黒田博樹を抜きにしては語れない。マウンド上で黙々と投げ込む黒田の姿はなぜわれわれファンの心を揺さぶるのか、そして彼はカープに何をもたらしたのか。
黒田が達成した200勝についてはすでにテレビ、新聞、ネット、雑誌、関連書籍などで繰り返し報じられている。これからも様々な人間、あらゆるメディアによって、何度も何度も語られることだろう。
「カープに入ったころは、まさかこういう日が来るとは思っていなかった。これだけたくさんのファンの方々に声援を送っていただいて、とてもうれしいし、ぼく自身、とても感動しています」
それは7月23日、本拠地マツダスタジアムでの阪神タイガース戦で達成された。相手が現役時代の僚友・金本知憲監督率いるチームであったことも大きな因縁を感じさせる。メモリアルゲームは7回、115球を投げて5安打無失点と堂々たる投球内容。その黒田を打線も序盤から援護して、スコア7−0の大勝だった。
日米通算(メジャーリーグではロサンゼルス・ドジャース4年間、ニューヨーク・ヤンキース3年間で計79勝)としては05年の野茂英雄(当時タンパベイ・デビルレイズ)以来、11年ぶり2人目。広島の投手としては1992年の北別府学以来、24年ぶり2人目。もっと言えば、大卒(専修大学)のプロ野球選手としては1970年の村山実(関西大学−阪神)以来、実に46年ぶり5人目の大台到達であり、歴史的快挙である。
ちなみに、カープ史上初の200勝投手・北別府がこの大記録を達成したのは、アウェーのナゴヤ球場(1997年以降は二軍専用)での中日ドラゴンズ戦だった。だから、黒田の本拠地での200勝目達成は、球団史上初めての偉業でもある。そういう意味では、広島の地における歴史的偉業でもあったのだ。
「アメリカに行ったころは、マツダスタジアムでこういう日を迎えるとは想像していなかった。(2試合の)足踏みをしている間はファンの方々、メディアの方々にもたくさんプレッシャーをかけていただいたので、早く決めたいという気持ちが強かった。そういう意味ではホッとしてます」
そういうセリフを聞いたとき、私の脳裏をよぎったのは阪神戦の前の登板、200勝まであと1勝と迫っていながらノックアウトされてしまった試合である。プロ野球の世界では、200勝という節目の試合は何度となく語り継がれても、199勝どまりで終わった試合は忘れ去られてしまうものだ。しかし、その足踏みした試合で見せた黒田の態度にこそ、これだけファンに愛された投手の人間性、流行語にもなった「男気」がよく現れていた、と私は思う。
その「あと1勝」が挙げられなかった7月13日、セ・リーグ前半戦最後の試合は、本拠地での読売ジャイアンツ戦だった。記念の200勝が地元で達成されるゲームとあって、もちろん切符は完売、朝から強い雨の降る中をファンが席取りのための列をつくり、いつもより早い時間から報道陣が詰めかけ、期待と緊張感の入り交じった異様な雰囲気がスタンドにもグラウンドにも充満していた。
ところが、結果は0−6と黒田が一方的に打ち込まれ、打線が巨人の田口麗斗から1点も取れずに完敗である。黒田は2回に阿部慎之助にソロ本塁打を打たれたあと、5回までは0 −1のまま辛抱強く投げていたが、6回に村田修一の2ラン本塁打などで3点を奪われた。さらに、2点を追加された7回途中でついに降板だ。ちなみに、6失点はこの時点でシーズンのワーストタイ記録だった。
黒田はたとえ負けても、よほどのことがない限り、必ず報道陣の取材に応じる。この日もTシャツ姿でわれわれの前に現れ、腕組みをして立ったまま、冷静な表情で淡々と質問に答え始めた。
「(村田に打たれたのは)ツーシームです。抑えるつもりで(カウント2 −2からの勝負球を)あそこ(内角低め)へ投げたら、甘く入った。(試合)展開的にはあのホームランが一番痛かったですね。勝負にいったんですけど、完璧に打たれました。これだけ地元で応援してもらって、期待に応えたいというのはあった。5回まではしのいだんですが」
制球が甘くなったのは、コンディションに問題があったからか。私の問いに、いつもと変わらないと、黒田はこう答えた。
「どこも悪いところはありませんけど、打たれてしまったという結果がすべてですから。自分の力の無さですね。こういう試合のたびに、次の試合、次の試合、と思ってここまでやってきた。今回も次のマウンドに向けて、しっかり準備できることをやっていきたい」
徹頭徹尾、真摯で律儀な受け答えだった。黒田の場合、お立ち台での晴れがましいインタビューで発するセリフもさりながら、こういう負け試合のあとの朴訥な言葉に独特の味を感じる。これもまた「男気」という古臭い言葉で表現される魅力の一部ではないか。
この試合では、黒田自身、200勝を目前にして硬くなっていたことは否めない。黒田が緊張していることが野手たちにも伝わったのか、打撃でも守備でも、ぎごちないプレーが目についた。16年から打撃コーチとなった石井琢朗も試合前、こうもらしている。
「黒田の200勝には野手もプレッシャーを感じてます。ましてや本拠地でしょう。チャンスで打てんかったりしたら、お客さんに何をやっとんじゃと言われて、スタンド全体がそういう雰囲気になってくるだろうから」
試合を決定づけた村田の2ランが飛び出す前には、阿部の打球を2点目のタイムリーにした一塁手・新井貴浩の拙守もあった。記録上でこそエラーでなくヒットになったが、誰よりも新井自身が責任を痛感していたに違いない。その新井も試合後、すぐにはロッカーへ入ろうとせず、周りに記者たちが集まるのを待っていた。囲まれたところで「いいよ」と質問を促し、きっぱりとこう言っている。
「援護できなくて悔しいです。以上!」
黒田の200勝と同じシーズンに2000安打を達成した主砲もまた、この黒星を必ず糧にすると、態度で示したのだ。負けを引きずることなく、気持ちを切り替え、次の試合にどう立ち向かっていくか、黒田と新井の両ベテランがそろって範を示した一幕だった。
勝って驕らず、負けて腐らず。15年に復帰して以来、黒田がカープにもたらしたものはいろいろあるだろうが、一番大きかったのはやはり、このプロとしての基本的な姿勢ではないか。「男気」より「黒田イズム」とでも言ったほうがふさわしいような気がする。
赤坂英一(あかさか・えいいち)
1963年、広島県生まれ。法政大学文学部卒。日刊現代のスポーツ編集部で長年プロ野球取材を担当し、2006年に独立。スポーツを中心に人物ノンフィクションを執筆する気鋭のライターとして活躍中。新聞、雑誌への執筆をはじめ、単行本も著し、スポーツに携わる「人間ドラマを描く」スタイルに定評がある。主な著作に『バントの神様』『キャッチャーという人生』『プロ野球二軍監督』(以上、講談社)などがある。