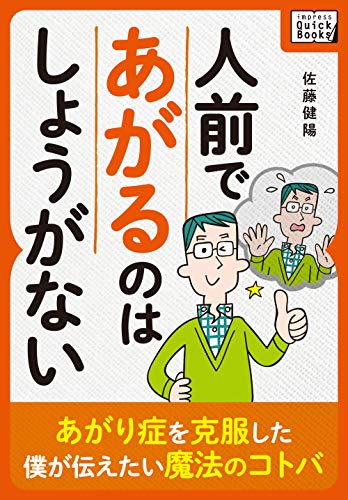「あがり症は治さなくていい」 あがり症を克服したカウンセラーが主張する理由
2020年05月06日 公開 2024年12月16日 更新

過去20年にわたって、あがり症に悩まされてきた佐藤健陽さんは、現在あがり症の専門家として、自身の過去の体験を基に「あがり症を克服する方法」を説いている。
スピーチや大人数での会議での発言は誰しも緊張するが、過度な緊張に悩まされているのであれば「あがり症」を疑うべきだろう。
本稿では佐藤健陽さんの著書『人前であがるのはしょうがない』より、あがり症とどう向き合えばラクになるのかを語った一節を紹介する。
※本稿は、佐藤健陽著『人前であがるのはしょうがない ~あがり症を克服した僕が伝えたい魔法のコトバ~ 』(impress QuickBooks)より一部抜粋・編集したものです。
「あがり症」は正式な診断名ではなく俗称
まずは、私が考えるあがり症の定義をお伝えします。それは、「あがり症は治るものではなく、忘れるもの、軽減するものだ」ということです。
そうです、あがり症は治りません。がっかりしましたか?
でも、それが真実です。しかし、だからといって悲観することはありません。あがり症は、自分があがり症であることを忘れてしまうほどに、軽減できるものだからです。
そもそも、あがり症は正式な診断名ではなく、俗称です。自分があがり症だと言えばあがり症だし、いや、自分はあがり症ではなく単なる恥ずかしがり屋なんだといえば、そうなのかもしれません。
あがり症とは、極めて曖昧なものなのです。人前で緊張してしどろもどろになる、発言がおぼつかなくなるということは、誰でも一度や二度は経験がありますよね。
むしろ、大勢を目の前にして緊張しないという人は珍しいのではないでしょうか。しかし、大抵の人は緊張する場面が終わってしまえば、気持ちが楽になるでしょう。
でも、あがり症は、人前などの緊張する場面はもちろん、その前後の長い時間も、あがることに意識がとらわれる症状を指します。
例えば、月に一度の定例会議があり、次の回では発表の順番が自分に回ってくるとします。大抵の人は、数日前あたりに資料を用意して話す内容をざっくりと決め、当日は資料を見ながら発表すると思います。
しかし、あがり症の人は、発表が決まった時点で苦悩が始まります。
「あがってスラスラ読めなかったらどうしよう」
「失敗したら皆はどう思うだろう」
と、不安と恐怖におののくのです。
そして、あがらないようにするためには万全の準備をしなければならないと考え、1ヶ月も前から台本を作り、毎日一生懸命練習して、一字一句間違えないように言えるまでに仕上げます。
台本通りに話すということは、逆に言えば台本通りに言えないと即失敗につながるので、本当は台本を作った時点で、自分でハードルを上げているのですが……。
さて、当日なんとか乗り切ったとしても、終わった後は「何かミスはなかっただろうか」と考えはじめます。あるいは微かなミスや緊張や震えを何度も思い返して、今度は発表のことが頭から離れません。
次のページ
1つでも当てはまるなら、あなたもあがり症かもしれない