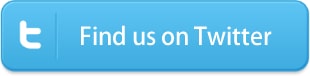「近くて遠い隣国・中国」日中両国はなぜ衝突を繰り返してきたのか
2022年02月23日 公開
2024年12月16日 更新

日清講和記念館・料亭 春帆楼(山口県下関市)
グローバル社会にますます影響力が高まる中国。古代より長い歴史をもつ日本とこの隣国との関係は、これからどうなっていくのでしょうか。本稿では、近代アジア史の研究者である筆者が、両国関係のこれまでの歴史を俯瞰することで、その軋轢と衝突の「構図」と、いまなお解消されぬ「問題の根源」について解説しています。
※本稿は、歴史街道編集部編『満洲国と日中戦争の真実』(PHP新書)の一部を再編集したものです。
【岡本隆司】京都府立大学文学部教授。昭和40 年(1965)生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。博士(文学)。専門は近代アジア史。『近代中国と海関』で第16回大平正芳記念賞、『属国と自主のあいだ』で 2005年度サントリー学芸賞、『中国の誕生』で第12 回樫山純三賞、第29 回アジア・太平洋賞特別賞を受賞。『世界史とつなげて学ぶ中国全史』『中国史とつなげて学ぶ日本全史』など著書多数。
「疎遠」が常態だった
日中関係の歴史を眺めると、ほとんどの期間、日本は大国の中国からプレッシャーを感じてきたといってよい。
古代の白村江の戦いや中世の蒙古襲来のように、軍事的なプレッシャーもあった。しかし日本人の感覚では「唐=外国」「中国=世界」であり、文化的なプレッシャーを感じることのほうが多かったと思われる。
日本人の精神生活で大きな要素となっている仏教にしても、中国を経由して受容した「中国化された仏教」だ。来日した鑑真も、唐の僧侶だったし、日本仏教の源流に位置づけられる空海も最澄も、唐に留学して、真言宗と天台宗をもたらしたことは周知の通りである。
その意味で、日本人にとって「世界」そのものである中国は、対抗すべきライバルでもあり、学ぶべき先生でもあった。とはいえ、やはり中国は遠い。
日中の関係は、「一衣帯水」という言葉を用いて、近接しているように表現されることがある。だが、双方を隔てる東シナ海は「荒い海」で、陸続きの隣国のように人の往来が容易なわけではない。
わずか三十数キロメートルの海峡に隔てられた、イギリスとヨーロッパと比べると、日中の距離感は「隔絶」と表現しても過言ではないだろう。
したがって、日本と中国の間で、直接的な交流のない時間のほうが長かったのは無理もない。また基本的には、中国と接触をもつ日本人は、政権のごく一部の要人に限られていた。時代が降ると、禅宗の僧侶や貿易従事者が往来することもあったが、ほとんどの日本人は無関係だった。
つまり、日中関係は「疎遠」が常態だったのである。そのため、相手のことを「こうではないか」と、勝手に独り合点で誤認しても、それほど差し障りはなかった。しかし、実際に接触する機会が生じると、当然ながら問題が起こってくる。
大昔のことはさておき、日中間で国際関係というレベルの交渉が始まったのは、室町幕府3代将軍の足利義満からだろう。義満が、国交と通商を求めようという日本側の事情で明に使いを出すと、明の永楽帝から日本国王に封ぜられた。義満が求めていないにもかかわらず「国王」としたのは、明が日本の状況に頓着しなかったからであろう。
時代が降って、豊臣秀吉が「明を征服する」として、文禄元年(1592)と慶長2年(1597)、朝鮮に出兵した際も、相手のことをよく理解していなかった。苦戦も当然である。文禄の役の講和交渉のおり、日本は下位の国だからと、「秀吉を日本国王に封じてやればすむだろう」と中国は考えた。これに秀吉が怒って、交渉は決裂。慶長の役へと至るが、結局は両者がともに、相手をよくわからぬまま戦争をはじめ、やめられなかったのである。
その点、交流を必要最小限にとどめた江戸幕府は賢明だった。当時の「必要最小限」の交流とは貿易であり、「理解を超えている相手」と政治的な接触を避けた対応は、理想的な通交の一類型と捉えられるのではないだろうか。
日清戦争と「パーセプション・ギャップ」
嘉永6年(1853)のペリー来航によって開国した日本は、明治維新以降、西洋文明をスタンダードとして、新国家の建設を進めた。それは国内政治だけでなく、国際関係も同じである。
日本は「主権国家として国境線を確定し、他の国々と条約を結んで国交を樹立する」という西洋流の国際関係に則り、明治4年(1871)に中国と日清修好条規を、明治9年(1876)には朝鮮と江華島条約を結んだ。
しかし、中国も朝鮮も、それまでの東アジアにおける国際秩序を前提としていて、それを改めるつもりはない。条約にしても法にしても、西洋のロジックとは異なる立場・観点で考えていた。
たとえば、江華島条約に「朝鮮は自主の国」とある。日本は「自主の国」を「インデペンデント ステイト」の翻訳語と理解し、「独立国」の意味として受け取った。ところが中国と朝鮮は、「朝鮮は国内政治も外交も自主」とする一方で、「朝鮮は中国の属国」という旧来の認識のままだった。
その齟齬が、「朝鮮の国際的地位」をめぐる問題で日本と中国を対立させ、明治27年(1894)、日清戦争へと至るのである。
これは陸奥宗光も論じたとおり、中国を中心とする東アジアの世界観や秩序関係と、日本が倣おうとした西洋流の国際関係が衝突したものともいってよい。
その意味では、中国と朝鮮に対する際、日本が相手をまったく忖度せず、西洋のロジックで考えたところに、争いの根があったと見ることもできる。日本人の言動の様式は中国大陸よりも西洋に近いようだ。逆にいえば、中国や朝鮮半島の人々は西洋と合わない、違うロジックで考えるのである。
たとえば、外国との約束に関して、西洋と日本は「条約を守ることは当然」とするが、東アジアでは「書いていないこと、必要としないこと、都合の悪いことは履行しない」というのが、スタンダードな考え方だった。
これほどロジックが違うのにもかかわらず、日本はそこをよく認識していなかった。一言でいえば、「パーセプション・ギャップ(認識のずれ)」が軋轢と衝突を不可避にしたのである。
歴史街道 購入
アクセスランキング(週間)
更新:04月10日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 天照大神は、本当は「男神」だった?…天皇家の最高神をすり替えた『日本書記』
- 世界史における「最強の武人」といえば誰? ランキング
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- 江戸を大都市にした天海が、街に仕込んだ「秘密の仕掛け」
- 三国志の英雄・曹操、劉備、孫権は史実でも本当にすごかったのか
- 本能寺の変で栄華から転落 「信長の弟・織田有楽斎」が心の拠り所にした茶道
- 豊臣秀吉、天下人の辞世~露と落ち露と消えにし我が身かな
- 日本と朝鮮半島の交流史~今だからこそ知っておきたい!
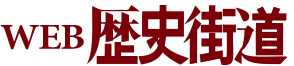






.jpg)