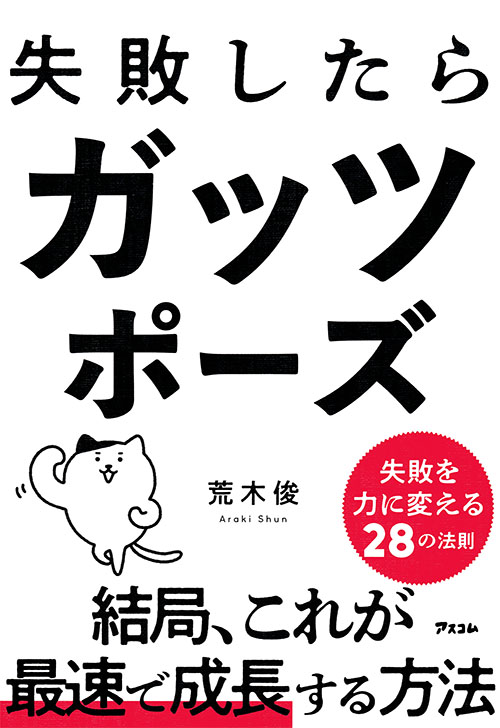YouTubeなどの動画サイトやTikTok、Instagramといった視覚的なコンテンツの台頭によって、近年「文字離れ」が顕著になっていますが、感謝の手紙を書いたり、日記をつけるなど、気持ちを文字化することはモチベーションを高く保つためにも非常に重要だとされています。
荒木電通株式会社代表取締役の荒木俊氏に話を聞きました。
※本稿は、荒木俊著『失敗したらガッツポーズ』(アスコム)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
感謝の手紙を書いてみる
あなたにも、これまでの人生の中で励ましてくれた人やチャンスをくれた人、ただそばにいてくれるだけで嬉しかった人がいると思います。
一人ひとり思い浮かべてみてください。
その人たちに直接感謝を伝えてもいいと思いますし、自分が成長・成功することで恩返しをするのもいいと思いますが、私がおススメするのは、その人たちに感謝の手紙を書くことです。
メールでもLINEでもいいのですが、自分が感じている感謝の気持ちを改めて伝えてみてください。いつもそばにいる家族であればなおさらです。口頭では気恥ずかしくて言えないことも、文章でなら伝えられるでしょう?
書く内容は、「いつもありがとう」でもいいし、もっと書くならば、
1.あのとき、こういう言葉をかけてくれた(こういうことをしてくれた)ことに感謝している。
2.そのおかげで頑張れたし、今の自分があると思う。
3.今、自分はこういうことをしている。あのときの感謝を、自分がもっと成長することと、自分が他の人に同じようにしていくことで、〇〇さんへの恩返しになればいいと思っている
といった感じでもいいでしょう。
こうした文章を書くことの利点は、自分の心が整うことです。
口に出す言葉は浅い内容でも違和感なくスラスラと流れてきますが、一方で、文章を書くときは深く内省する必要があります。そこで考えたことを文字として自分の外に出すことにより、謙虚になり、素直になり、軸が定まるのです。
また、その手紙(メールなど)を受け取った立場からすると、これはあなたが思っている以上に嬉しいものなのです。
あなたも恩を忘れていないでしょうが、受け取った側もずっと忘れません。この先も、力になってあげたいと思います。
だから、手紙(メール)を書いてみましょう。
ただし、一点だけ注意があります。家族は別として、お礼の手紙を出す際には、純粋にお礼の気持ちだけを伝えてください。
そこに応援してほしいという気持ちが出すぎると、「何か頼むときだけ連絡をしてくる人」という評価になりかねません。それでは、せっかくの感謝の想いが台無しになってしまいます。
困っているときは、機会を改めて「助けてほしい」と連絡しましょう。元々あなたを応援してくれている人たちならば、そのほうが気持ちよく助けてくれるはずです。
感謝日記をつけ続ける
感謝を文字にすることの効果に関して、興味深い研究があります。
国立研究開発法人 情報通信研究機構と立命館大学の共同研究によると、「日常生活で起こる様々な出来事や、その対象となる人々に感謝したことを振り返り記録することにより、学習モチベーションが向上すること」がわかったのです。
前述のような「感謝の手紙を書いて渡す」という行為は、それまでの実験では学習モチベーションの変化が見られなかったそうなのですが、これは1回だけの行為なので、「『感謝の感情』の変化による影響が小さかった」からではないか、と推測されていました。
そこで、「2週間にわたって、毎日、感謝したことや感謝した人のことを書く、『感謝日記』を利用する方法」を用いて実験したところ、学習モチベーションが向上し、その効果は3ヵ月後まで維持されたといいます。
この研究結果が面白いのは、「何かに感謝したところで人生はそんな簡単に変わらないよ」と思っている人への、良い答えになっていると思うからです。
大事なのは1回だけではなく、毎日、感謝することなのです。
これはあくまで学習に関するモチベーションの実験ですが、それが高い状態がずっと続くだけでも、毎日感謝する人としない人との差はとんでもなく大きなものになることは推測できます。
まさに、「継続は力なり」――。ことわざや、成功している人たちの間で当たり前に言われていることは、やはり根拠のある話なのだとわかります。
すべての判断軸を「この人の笑顔が見たい」に変える
ビジネスの世界で競争していくためには、しっかりとした目標(計画、戦略)と実行力が必要です。いくら夢を語っても、売上や利益が出なければ存続(生活)できなくなるのですから、経営ではそこが最重要事項になります。
だから、私も零細企業としては珍しいほど綿密に、創業当初から中期計画などをつくってきました。それをした上で、私は経営の判断軸を、「この人の笑顔が見たい!」というところに置いています。多くの経営者や起業を考えていらっしゃる方も、おそらくそう思われていることでしょう。
とはいえ、現実の仕事や生活の中では、そうは言ってもいられない場面もありますよね。誰だってお金がほしいし、成功したい。また、焦っているときや余裕のないときには、「自分のため」に行動しがちです。
そうならないために私がおススメするのは、「意識の矢印」をイメージすることです。今の自分の判断や行動は、「自分だけのため」という方向に向いているのか? それとも、「自分と人のため」という方向を向いているのか? と矢印の向きを考えてみるのです。
たとえば、人脈をつくりたいときや自分から仕事を獲りにいくときには前者ですし、相手の喜ぶ顔が見たいときや感謝しているときには後者です。
ちなみに、私は後者のほうに矢印の向きを変えてから、付き合う人も環境もガラリと変わりました。素敵な方が、向こうから近づいてきてくれるような感覚です。
あなたも、日々の仕事の中で自分の判断に何か違和感を覚えたら、そのたびに矢印の方向を確かめてみてください。
なお、この矢印は、「自分だけのため」のほうを向いてしまっても当たり前だということを覚えておきましょう。人間だから当然です。徐々に変えていけばいいし、気づいたときに直せばいいのです。完璧になどできませんから、そこは無理しないようにしてください。
「自分の強み」を他人からヒアリングする
この5年・10年ほど、自分の強みを自己診断するテスト、たとえば「クリフトンストレングス・テスト(ストレングスファインダー)」などが流行しています。
自分の強みを理解していることは失敗や挫折を乗り越えるためにも必要なことなのでしょう。
詳しく診断するためには各種テストを受けてみるとよいと思いますが、それと同時に私がおススメしたいのは、「私の強みは何だと思う?」と信頼できる人たちからヒアリングしてみることです。
私の経験から言うと、自分が弱みだと思っていたことを長所と指摘されたことや、その逆もあります。自分が自分を正しく評価するのは難しいものだと思いました。
1つ言えることは、自分で自分を過小評価している人が多いのではないかということです。他人の目には十分に強みだと映っているのに、本人が「たいしたことないよ」とヘンに謙遜して、その高い能力を活かしていないケースが多いと思うのです。
だから、多くの人にあなたの強みを聞いてみてください。 その声を集めるだけでも自信になります。