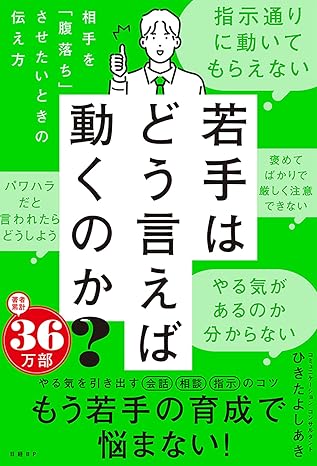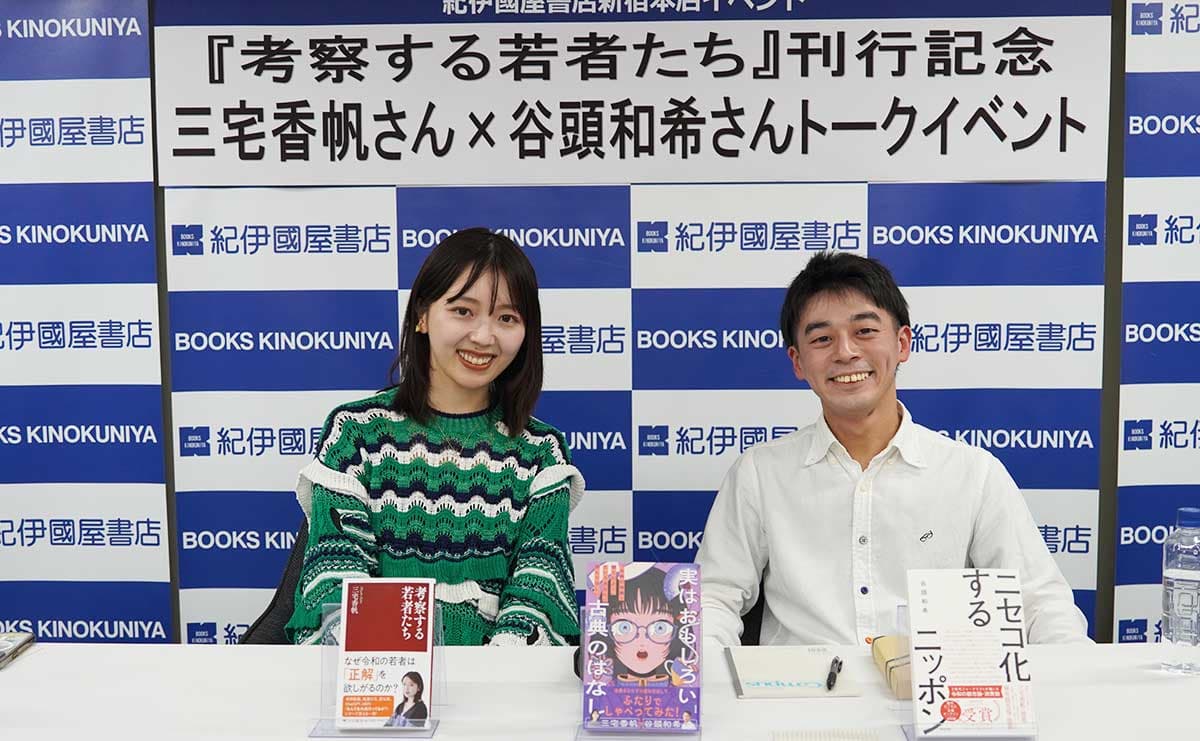明治大学や早稲田大学などで述べ1万人以上のZ世代の指導に関わり、300以上の企業や行政機関でコミュニケーションスキルを教える「伝え方のプロ」である、ひきたよしあきさん。ひきたさんによれば、若手を動かすカギとなるのは、リーダーの「伝え方」だといいます。
本稿では「無気力に見える若手」への伝え方を、書籍『若手はどう言えば動くのか? ~相手を「腹落ち」させたいときの伝え方~』よりご紹介します。
※本稿は、ひきたよしあき著『若手はどう言えば動くのか? ~相手を「腹落ち」させたいときの伝え方~』(日経BP)を一部抜粋・編集したものです。
有名大学の学生が「ラクな会社」に就職したい理由
●無気力に見える若手。どんな気持ちで仕事をしているのか分かりません
→「この仕事が君の人生にどう役立つか」を言葉で伝えよう
ある日、大学3年生が私の事務所にやってきました。有名大学の女子学生です。就職についての相談でした。
「先生、残業が少なくて、人間関係も面倒でなくて、できれば昔の年功序列のような感じで昇格が決まるような会社ってありますか」
私は一瞬、彼女の言葉の意味が分かりませんでした。真面目に就活はしているのだろうけれど、彼女の言葉からは「やりがいのある会社」ではなく「ラクな会社」を目指している印象しか受けない。なぜそんなことを言うのだろう? もう少し、詳しく聞いてみました。
「私、本名は出していませんが、ボカロP( ボーカロイドなどの音声合成ソフトで楽曲を制作し、インターネット上などに投稿する仕事)をやっていて収入はかなりあるんです。それにウェブライターもやっていますから、もう企業に就職する必要はないと思っています。
でも、どれも匿名で活動していて、親も知らない。それもあって、自分の名前でリアルな世界で働いてみるのもいいかなと思うのですが、時間が不規則で人間関係がきついところは『本業』に差し障るから絶対無理なんです」
これを聞いて、やっと全体像が見えてきました。高校時代にコロナ禍を経験した彼女は、「この状態がずっと続いても食べていける方法は何か」と真剣に考えたとか。その結果が、音声合成ソフトを使って音楽をプロデュースする仕事。これが当たりました。
企業で働くことに対する価値観は、ここまで変化している
「それならば、別にリアルに働かなくてもいいじゃない」
と私が言うと、それは「怖いし、不安だ」という。ボカロPもウェブライターも長くできるかどうか考えると不安になる。だからリアルな世界にも足場をつくっておきたいというのです。
こうした思いを持つのは、彼女だけではありません。リモートでできる仕事が増えた。副業を認めてくれる会社も多い。さらには少子化で、「食べるに困らない程度」の仕事ならいくらでもある。そんななかで、若手の「企業で働く」価値観が大幅に変わってきています。
「リモートで仕事をしていて、上司に叱られたとします。その同じモニター上に詳細な転職情報が次々流れてくる。勤めている会社との関係が希薄にもなりますよ」
とは保険会社の人事担当の言葉。リアルな仕事のほかに、バーチャル空間やSNSなどのコミュニティー。いくつもの顔を持って暮らしている彼らの働きぶりを見て、「なんの目的で仕事をしているのだろう」と考えてしまうのは当然のことでしょう。
彼らは無気力でも、不真面目なわけでもない
学生時代にバイトをしようと思ったら、若者は引く手あまた。「辞めちゃおうかなぁ」と言ったら、バイト先の店長や先輩から「なんとか続けてほしい」と懇願される。こうした環境下で選んだ会社は、「とりあえず籍を置いている」気持ちが強い。これは、どんなに苦労して入った一流企業でも同じです。
「とりあえず籍を置いてみたけれど、配属先が自分には合わないので、辞める」ということになる。教員採用試験を通った新任の先生のなかにも、赴任する学校や地域が自分に合わないと感じると、すぐに辞めてしまう人がいると聞きます。「一生かけてやる仕事」などという価値観は、すでに歴史上のものになっているのかもしれません。
しかし、彼らの話をよく聞くと、やる気がないわけでも、不真面目なわけでもありません。むしろ「大きな企業に入ったら一生安泰」なんて考えていた世代よりも、現実的に人生を見つめているようです。
企業内で出世することや、社会的地位を求めることをしない代わりに、「この仕事は、将来の自分にとってのメリットになるか」という一点は、非常によく考えている。成長意欲も高い。
会社を辞める理由も「労働と給料が釣り合わない」「人間関係がうまくいかない」ということよりも「将来の私にとってメリットを感じられない」ことを理由にする人が多い。
私はここに、「若手がどんな目的で仕事をしているのか」をひもとく鍵があると思っています。
「やらされ感」を与えないために
若い世代にとって、「会社の利益につながる」「チームワークを乱すな」なんて言葉は、正直どうでもいいものです。どんなに重要なことだと説明されても、「やらされ感」を覚えた時点で働く意欲がみるみる萎えてしまう。それよりも、大切なのは「自分軸」です。こう言葉をかけてみましょう。
「この仕事をすることは、あなたのキャリア、人生にとってこんなメリットがあるんだよ」
先ほどのボカロPの女子学生の場合「リアルで働く会社で得られる人脈は、ボカロPを続けるためのこんな力になってくれる」と解釈できれば、その会社でもきっとやりがいが見つかる。メリットがあると分かれば、すごい能力を発揮する可能性を秘めています。
大切なことは、「どんな目的で仕事をしているのか」を、自分の世代の価値観や、私たちの「自分軸」に合わせて考えないこと。若手に「ここで働くメリットはなんだと思うか」を聞き出すことも有効な方法です。
もちろん、こうした若手がすべてではありません。昔ながらの熱血漢もいるし、社長を目指して頑張ろうとする人もいるでしょう。
しかし、コロナ禍以降、リモートワークが増えてきた社会環境のなかでの「働く目的」は、随分と変化しているのです。自己研鑽のためと分かると、懸命に働きだす若手を私は何人も見ています。「自分軸」を見据えて、彼らの「働く目的」を考えてみる。こうした視点を持つことが必要なのではないでしょうか。