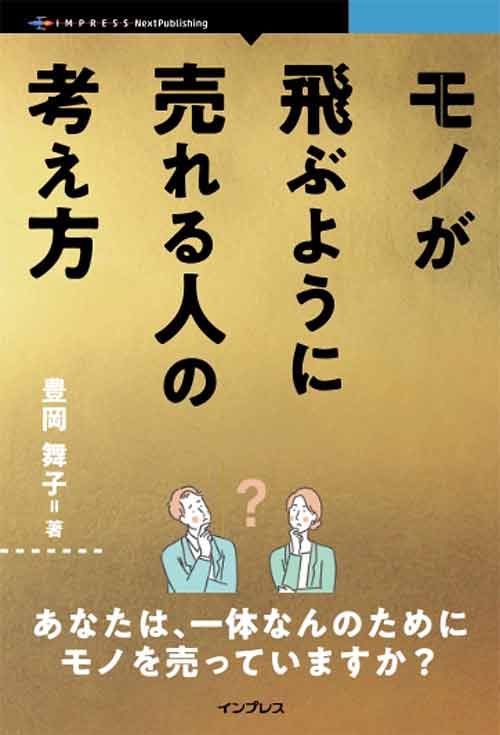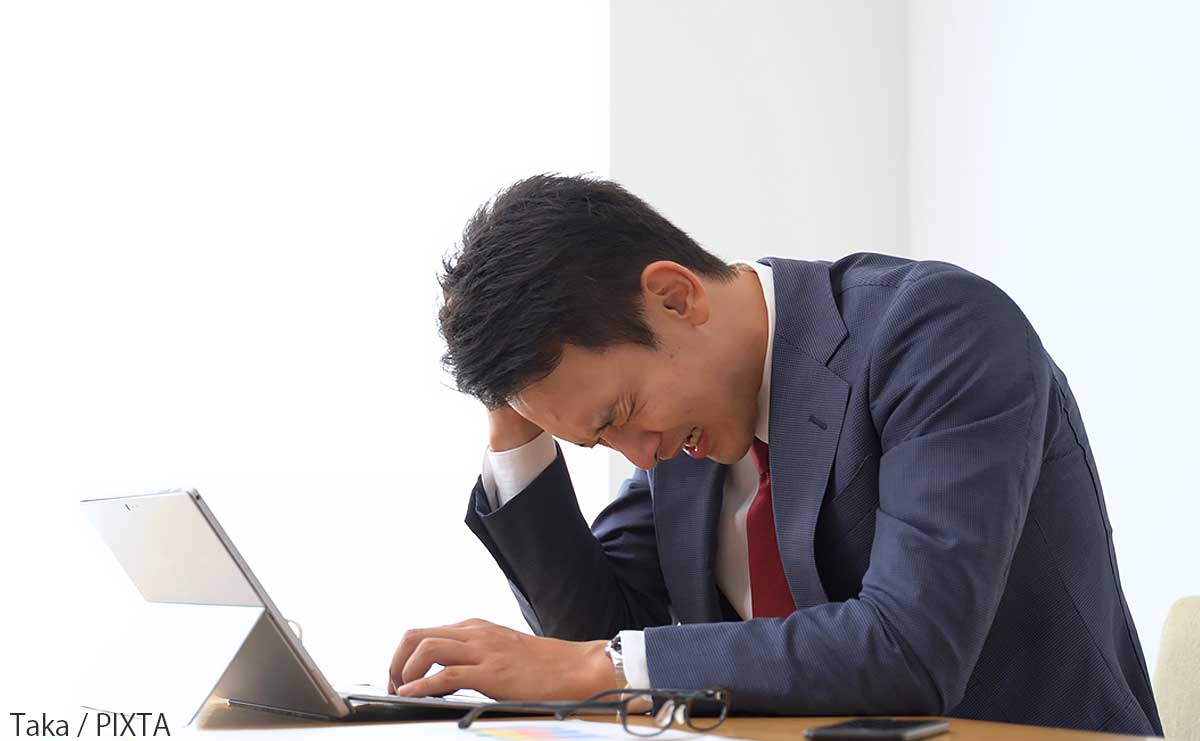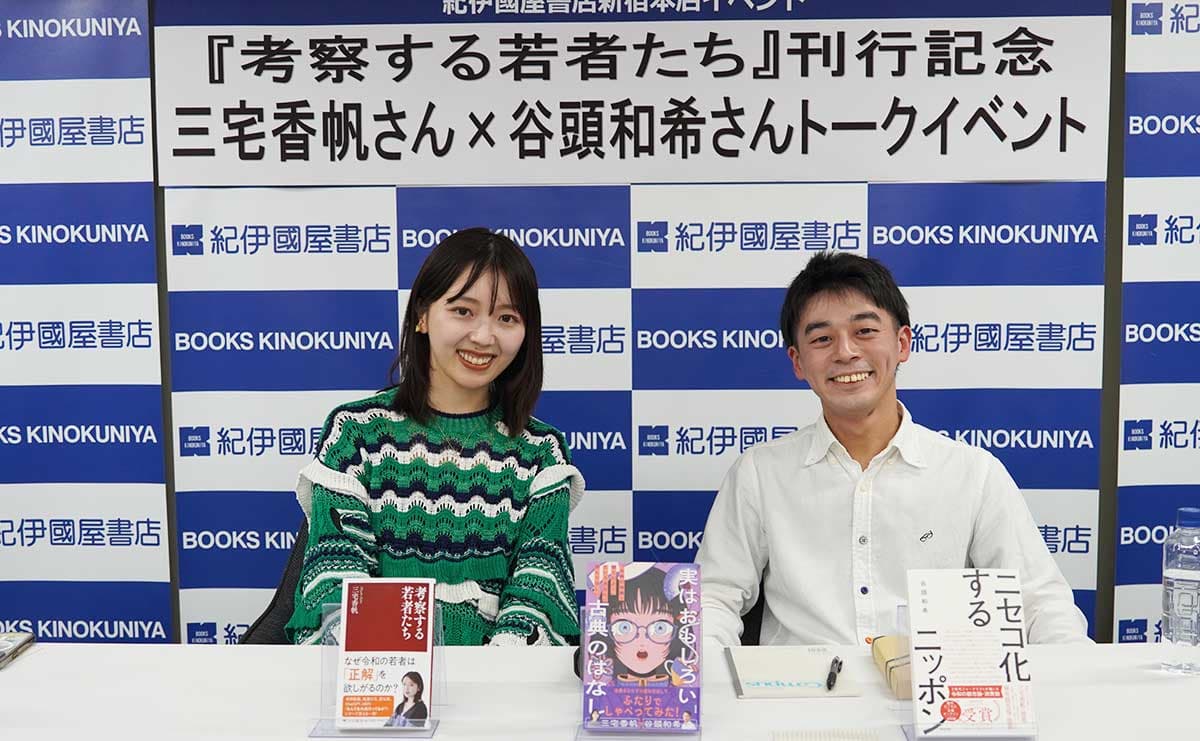顧客に商品の魅力を伝えようと、一方的に話し続けていませんか? もしかすると、それが成約を遠ざけている原因かもしれません。20年にわたり接客や販売員教育に携わってきた豊岡舞子さんは、本当に売れる営業は、顧客の声に真摯に耳を傾け、その心に寄り添う「聞き上手」であると説明します。本記事では、豊岡さんの著書『モノが飛ぶように売れる人の考え方』より、顧客心理を理解し、信頼関係を築きながら成果を上げるための具体的な方法を解説します。
※本稿は、豊岡舞子著『モノが飛ぶように売れる人の考え方』(インプレス)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
売れる人は「話上手」か「聞き上手」
話好きで、話が上手な人は売れると思っている人は多いかもしれません。それはある意味では正しいのですが、本質は違います。
売れる人とは、「対話」を大切にする人です。対話とは、単に互いに向かい合って直接話をすることではありません。言葉を交わすなかで、新しい価値や気づきが生まれ、互いに何らかの変化を来たすもの。それが本当の意味での「対話」です。
私たちが想像している以上に、対話には大きな力があります。人間関係の構築にも、信頼関係を作ることにも、ときには人生を変えることにも影響を与えます。なぜなら、対話とは自分以外の人を深く知るためのコミュニケーション手段だからです。
売れる人が対話に価値をおくのは、その本質を熟知しているためです。私も対話を重んじるやり方に変えてから、良い人間関係に恵まれて仕事もうまくいくようになりました。
売る本人が話さなくても構いません。売ることにおいて重要なのは、お客様から情報を引き出すこと。つまり、話好きな人と聞き上手な人が売れるのです。
対話に価値をおくからこそ、相手からまだ見ぬ情報が引き出せます。それをお客様に気づかせることができ、良い提案ができるのです。
お客様自身が「今日はこれを買いに来ました」と言ったはずなのに、話しているうちにそれが真の目的ではなく、本当に欲しいのは違うモノだったとその場で気づくことができます。
対話する相手は、お客様だけに限りません。
上司・部下間での対話、同僚との対話にも同じことが言えます。相手を理解しようとするために話すこと・聞くことに価値を置くからこそ、相手の事情がわかり、良好な信頼関係を築くことやビジネスの成長・強化にも結びつくのです。
本書の「はじめに」では、部下たちに夢を語ってもらい、仕事をしながら実現させていったことをエピソードとしてお伝えしました。これは私が部下との対話を行った例の1つです。
当時に実践していたことがありますので、詳しくご紹介します。
まずは一緒に仕事をする人に、その人自身の棚卸しをしてもらうことです。履歴書に書かれているだけではなく、生まれてからこれまでの出来事をすべて洗いざらい書き出してもらいました。できること・できないこと、好きなこと・嫌いなこと、その人の特性のすべてです。
これは私が部下のことを知るために取り組んでもらったことです。
この方法を取り入れた理由としては、私自身にも思い込みがあり、その人のスキルを伸ばすことや、本当に良いところを見つけ出すことが、自分だけの価値観になってしまうことがよくあるためでした。
人と会話するときに、話しているなかで「この人はこれが得意だ」「これが苦手だ」と勝手に決めつけてしまうことがあります。しかし、実情はそうではないことが非常に多いです。この人はこれが苦手だろうと思っていたことが、じつは誰よりも伸ばせる人だというケースもあります。それは自分自身も、周囲から同じような評価を受けがちなところがあると思います。
そうした決めつけがあると、チームは良くなりません。疑心暗鬼になったり、表面的な関係で終わったりしてしまいます。本当の意味での信頼関係を築くことは難しくなります。
子どもの頃に何が得意だったか。褒められた経験はあるか。できなかったこと、記憶に残っていること。そういうものを一度書き出してもらいます。賞を取った経験があればそれも教えてもらいます。立派な賞でなくても構いません。自分がとったという自覚があって、それが自信になったものであれば何でもいいのです。履歴書に書けないようなことを書いてもらいます。
本人の経歴というと、履歴書にはTOEICのスコアが何点か、英検何級か、普通自動車免許といったことしか書かれていません。それでは本人がどういう人なのかがわかりません。BtoCでもBtoBでも、モノを売る・営業することに関して、知りたいことはそれではありません。履歴書には書けないその人の特性や技能、能力、特殊技術、スキルなど、本当はそれらを最も知りたいのです。
例えば「スポーツで全国大会に行きました」「国体の選手でした」という情報です。それで仕事を獲ることができます。「ナンパがうまい」「合コンに行きまくっていました」でもいいのです。そういう情報を知っていると、得意不得意が明確になります。
このようなやり方は、なかなかまとまらないチームにも生かすことができました。私が会社を辞めるまでこのやり方を続けていたので、別の例もご紹介します。
例えば、年の差が離れていて他のチームではうまくやれなかった人が、自分のチームに入ってきたケースです。新しいチームでもやはりうまく信頼関係が築けずに「またあの人が......」と言われてしまったときがありました。
その場合でも、同じことをやりました。すると、ただの怒りでしかなかったものが、誰も怒らなくなります。なぜその人がそうなのかという理由が全部わかるためです。怒りが収まったり許せたりできるようになります。
基本的に、誰もが自分のことを優先してしまうものです。人を応援するというのはエネルギーが要るため、常にできることではありません。
それができるようになるには、その人のことを深く知り、その人が抱えるつらさや苦しみを知って「できない理由がわかること」が大事です。その人を表面上だけで判断せずに、本当の意味で理解することで許せるようになります。
職人気質な方のなかには「良いモノを作れば売れる」「売れないのは売る人の説明が下手だからだ」と言う方も少なからずいらっしゃいます。商品が良いモノであることは前提です。
その商品は、売り手と買い手の間にある存在に過ぎません。私たちはモノを介して、相手とコミュニケーションを取っているのです。そのことをどうか忘れないでください。
目の前の人に深く興味を持つ
前節を読んで、売れる人になるために、対話を大切にするには何をすればいいのか、ただ話す・聞くだけではいけないのかと疑問を持った方もいるかと思います。
私からのアドバイスとして伝えたいことは、目の前の人に深く興味を持ってほしいということ。それが対話への第1歩です。
興味を持つからこそ相手を本当の意味で知ろうとする意識が生まれますし、相手の事情がわかったうえで会話ができるようになります。興味を持たなければ、表面的な理解や決めつけのままで終わってしまいますから、信頼関係を築くことも難しいのです。
私が店長時代に経験したなかでも、その大事さを知ったエピソードがありますのでご紹介します。
以前に私が店長として働いていた店舗に、人との距離感を掴むことが苦手な女性スタッフが入ってきたことがありました。同じ店舗のスタッフたちが怒ってしまい、「店長、もうあの子無理です!」と泣きつかれたときに、スタッフ全員を揃えて話をしました。
その女性スタッフの生い立ちから現在に至るまでを聞いて、特殊な環境で育ってきたことや、過去にいじめに遭っていたことがわかりました。そのせいで人との距離が掴めない。家庭環境も特殊で、裕福で極端な育て方をされていたために、学校にも馴染めなかったそうです。そのスタッフ自身も、何が正しいのか判断がつかなくなっていたのです。それを「変わりたいと思って、この職場に入社しました」ということでした。
優秀だけれども、向いているのは技術職。接客業には向いていません。学校の成績は優秀で、大学院も出て首席で卒業していました。そんな彼女が自分の人生を変えるために、勇気を持って入ってきたのです。
本人が「変わりたいんです」と言い、それを聞いたスタッフたちも「それならしょうがないか」と溜飲を下げました。彼女と同い年で、タイプが真逆のギャルっぽい性格のスタッフもいたのですが、きちんと話を聞く以前は「嫌い」と言って喧嘩になっていたところが「協力するから」と仲良くなったのです。
その人についてわかっていることに関しては、人は許せるようになります。わからないから怖くて嫌いなのです。わかっていれば、自分と同じでなくても大丈夫になります。相手とは必ずしも共感しなくてもいいのです。
自分とタイプが同じだから好きということではなくて、全然違ったとしても認め合えるようになります。お互いにそれができるとチームが強くなります。
今までの話は、「モノが売れる人とは関係ないのでは?」と思う方も多かったことでしょう。ですが、じつはお客様を相手にしたときにも通じる部分があります。
例えば、売れない人はクレーム対応で「このお客様はなんで怒っているのだろう」ということがわからないときに失敗してしまいます。お客様の怒っているポイントがわからずに、「お客様はこう思っているのではないか」と決めつけてしまうと、どんどん違う対応をして空回りしてしまいます。お客様も「なんでそんなことをするんですか!」とますますお怒りになってしまうのです。
売れる人はクレーム対応からVIP顧客を作ることができます。それを実現させるために、目の前のお客様を理解しようとするマインドが、売れる人にはあるのです。
苦手なお客様というのは、売る側にとって誰にでもいます。自分にとって理解できない人やよくわからない人は苦手なのです。
それは同僚同士でも、上司部下の関係でも同じです。その人のことがわからないと恐怖でしかありません。何を考えているのか、怒っているのかどうか、怖くて嫌になってしまいます。それは誰にでもあるものです。
したがって、相手のバックグラウンドを決めつけないで知ること。目の前の人に興味を持ち、深く知ろうとすることが大切です。売れる人はそれを実践することで、お客様への理解が深くなり、ニーズを引き出すことができます。引き出した情報からお客様にとっての1番良い未来を考えることができて、お客様が「欲しい」と思えるモノを売れるのです。