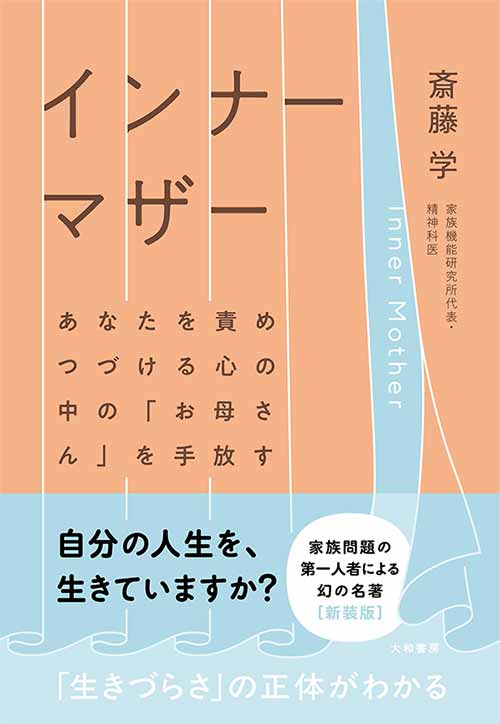いつもどこか罪悪感を抱えている、自分に対する批判的な感情が消えない...こうした心の状態は、子どもの頃に置かれていた環境が影響しているかもしれません。
精神科医の斎藤学さんは、子ども時代に「安全な場所」に居られたかが、その後のメンタルを安定させるカギになるといいます。斎藤さんの著書『インナーマザー』より詳しく紹介します。
※本稿は、斎藤学著『インナーマザー』(大和書房)より、内容を一部抜粋・編集したものです
「安全な場所」を持っていると感じられるか
家庭は子どもにとって「安全な場所」でなければなりません。
子どもは未成熟なヒトとしてこの世に生まれてきます。生まれてしばらくは、自分一人では何もできません。自分の生への欲求を、親(保護者)の愛情と庇護のもとで十二分に満たしてもらう必要のある王子さまであり、お姫さまなのです。
未成熟な赤ん坊は、こうした経験を経て、やがて一人で生きていける成熟した大人へと成長していきます。
赤ん坊は少し大きくなってくると、好奇心のおもむくまま、母親のひざもとから離れ、冒険に出かけるようになります。そこで不安や危険をわずかでも感じると、声を張り上げて泣き出したりあわてて戻ってきます。
そのとき、「よしよし、もう怖くありませんよ、もう大丈夫ですよ」と抱きしめ、受け止めてくれる母親がそこにいてくれることで、安心してまたもう少し遠くへと出かけられるようになります。部屋の中の探険から外への探険へと、じょじょに自分の世界を広げていきます。
時には母親に対して腹を立てることもあります。少し前までは、お腹がすくと泣けばおっぱいがもらえたし、おむつが汚れたら即座に取り替えてもらえました。ところが、だんだん大きくなってくるとともに、何もかもが自分の思いどおりにはならないということがわかってきます。そこで癇癪を起こすのです。
けれども、どんなに怒りをぶつけても、母親は自分を見捨ててしまわずにやっぱりそこにいて、また自分をかわいがってくれます。ちょっと怒ったくらいでは母親はビクともしないし、自分との関係も壊れてしまうことはないのです。
腹を立てたときには怒ったり、怖いときには泣いたり、不安なときにはその気持ちを言葉に出して訴えたり、見たり感じたりしたことを話し、受け止めてもらいながら、子どもの心は健康に成長していきます。
こうして育った子どもは、母親が常に目の前にいなくても、離れていても、「お母さん」に抱きとめてもらえる「家庭」という安全な場所があるという感覚を持てます。心の中に「お母さんと一緒にいる」感覚(基本的信頼感)を持つことで、安心して一人で外の世界に向かっていけるようになるのです。
ところが、こういう基本的な信頼感と安心感を子どもに与えてやれない親もいます。その場合、子どもは「自己」を発達させることができません。窒息しそうな息苦しさを感じながらも、家族から離れられません。なぜなら、どんなときでも抱きとめてもらえる基本的信頼感=安全な場所を心の中に持っていないからです。
正確にいえば与えられなかった。まだそれを求めている途中なのです。そのため外の世界になかなか踏み出していけない。健全に機能していない家庭は、子どもに「安全な場所」を与えてやれず、子どもの心の成長を阻はばみます。
その子どもたちが大人になり、自らの家庭を持ったときどうなるでしょうか。与えられなかった体験はなかなか伝えることができません。次世代でも同様のことが起こりうるわけです。
罪悪感を手放せない人が育った家庭
では「健全に機能していない家庭」がどのような様子なのか、少し具体的に見ていきます。
B子さんの叔父(母親の弟)は長いこと統合失調症で入院していたのですが、ときどき外泊の許可が出るとB子さんの家で受け入れ、生活をともにしていました。ところが、この叔父さんはすぐに刃物を出して暴れる人で、こういう発作が起こるとB子さんの父親が格闘して止めるということがたびたびありました。
「近づくとこの子を殺すぞ」
ある日、B子さんは叔父に抱きかかえられ、ナイフを突きつけられるという恐ろしい体験をします。騒ぎがようやく収まったあと、母親はB子さんにいいます。
「このことは、人にいってはいけないよ」
叔父のことは、家庭内でもなぜか口に出してはいけない雰囲気がありました。父親も母親も、普段はひと言も叔父の話をしません。あんなに恐ろしいことがあった次の日でも、まるで何事もなかったかのように素知らぬ顔です。
B子さんは、この体験を日記に書いていました。人間は、なんとかして心のバランスを保とうとするものです。家族にも友だちにも話せない恐ろしい体験を日記につづることによって、彼女は自分で自分を癒そうとしたのでしょう。ところが、その日記を母親に見られてしまう。
「このことは誰にもいっちゃいけないっていったでしょう!」
母親はB子さんを激しく叱りつけ、日記に紙を貼って「封印」してしまいました。B子さんが、日記にだけ聞いてもらっていた気持ちさえ、もうどこにも持っていき場がなくなってしまったのです。
大人になったB子さんは今でも、自分の体験したことや、そのとき感じた感情を、人に対して表現することに「罪悪感」を持っています。叔父のことを書いた日記が封印されると同時に、自分の生き生きした感情も封印されてしまったのです。
「しゃべってはいけない」という母親の検閲が、今でも心の中でB子さんにストップをかけるのです。
また、それ以上に苦しいのは、母親に対する怒りです。子どもだった自分の傷ついた心を守ることよりも、世間に叔父のことを知られないようにするのを優先した母親。B子さんには、何よりもそれが許せないのです。
家族の中に、他の人には絶対にしゃべってはいけない、という固い秘密があると、その家庭に育った子どもは、他人と親しい関係を持つことが難しくなります。彼らにとっての本当のことは、「しゃべってはいけないこと」なのです。誰かと友人になっても、いつもまがいもののコミュニケーションをしているような気分しか持てなくなる。
親自身が、子どもに対して率直に感情を表現するコミュニケーションをしていないために、子どもも同じような態度を身につけてしまうのです。