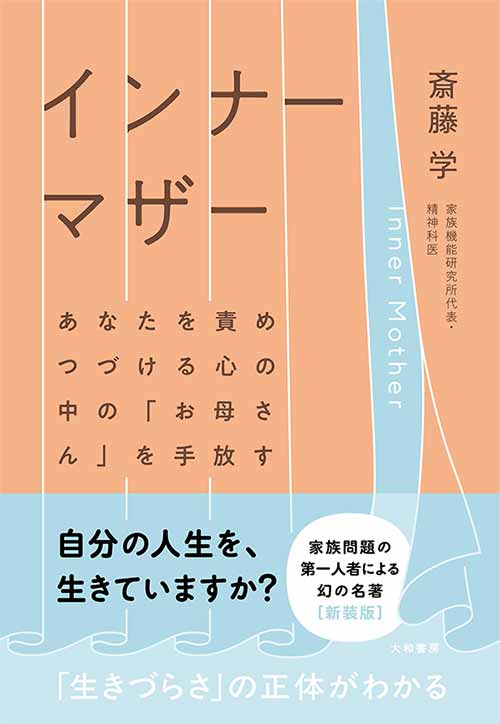精神科医の斎藤学さんは、自身を厳しく律し、罪悪感を抱えやすい生き方を「親教」にハマっている状態と捉えています。それは、心の中に形成された空想上の母親像「インナーマザー」からの「こうあるべき」「そうしてはいけない」という内なる声に縛られ、生きづらさを感じる状態です。
斎藤氏の著書『インナーマザー』では、自己を責め続ける根源となるインナーマザーの正体と、そこから抜け出すための方法が解説されています。本稿では、同書より「親教」に陥っている人の特徴を3つご紹介します。
※本稿は、斎藤学著『インナーマザー』(大和書房)より、内容を一部抜粋・編集したものです
行動が周囲の期待に縛られる
「親教」にハマり、「インナーマザー」に蝕まれた人がどのような感情を持っているか、その特徴を述べてみましょう。
まず、親教の信者たちは、自分自身が「こうしたい」と思う行動ではなく、周囲が自分に期待しているようにふるまおうとします。
「良い子にしていなければ、うちの子じゃありませんよ」
「人並みにしないと社会から落ちこぼれて、生きていけませんよ」
という親教の教義に従って、世間の期待する「良い子」の自分を演じます。良い子であろうとする以外の自分を出せないので、息苦しく、行動が制限される束縛感を常に抱いています。「世間」の期待といっても、本人が「こう期待されている」と心の中で思い込んでいる「インナー世間様の期待」です。現実の本当の周囲の期待とはズレている場合も多いのです。
親教にハマっていない人とつき合うときには、親教の教義が通用しません。相手に対する必死の努力は空回りしてしまいます。
相手が期待する自分を演じなければ見捨てられると思うので、相手がどんなサービスをすれば喜ぶかを読みとろうとするのですが、親教に支配されていない人は、相手に「ああしろ、こうしろ」という強い要求がない。そこでハタと困ってしまうのです。
「あなたはあなたで好きなようにしててくれればいい」などといわれると、もうどうしていいかわからず、「この人は自分を必要としていないのではないか」と不安になる。自分が他人にどう思われているか、他人の評価をとても気にしますし、評価されないと傷つきやすいのです。
彼らの行動は、自分自身の欲望や好き嫌いの感情、倫理観にもとづいたものではなく、世間が「いい」といえば「いい」し、周りの雰囲気を見て「おもしろくなさそう」なら「おもしろくないだろう」というものです。
その結果、何が正当かという確信が持てず、いつも「これでいいのだろうか」という漠然とした不安を抱えています。見逃されているうちは「これでもいいのだ」と思うのですが、「それではダメだ」といわれるのが怖くてビクビクしています。何がよくて何が悪いのか、自分はどうしたいのか、どうしたくないのか、自分で決められないのです。
また、親ならこういうだろう、周囲はこう思っているのではないかという恐れと不安を自分の中に取り込んでいるので、自分で自分を責めます。非常にまじめで、心の中では情け容赦ないほどの自己批判をしています。けれども、その情け容赦のない批判は他人にも向けられています。いってみれば、自分にも他人にも厳しいのです。
適正な自己評価ができない
親教に蝕まれている人は、「自尊心」を奪われています。自分の考えることや判断は、いつもインナーマザーに「ダメだ」といわれているので、「自己評価」がとても低い。どんなに美人でも、「こんな顔では愛されない」と心底信じている人もいます。
もともと他人の評価が基準になっているので、自分の評価はアテにならず、自分が信用できないのです。
けれども、他人の評価をすべて取り入れていたら、とてつもない完璧主義におちいることになります。すべての人に「すばらしい」とほめられることなどありえません。
どんなに完璧にやっても、「ちょっとあそこがまずい」「もう少しこうしたらよかったのに」ということになります。自分が現実にできることには限界があるのですから、達成したことを自分できちんとほめてあげればいいのですが、それができません。
何をやっても厳しい「世間様」の批判の声が聞こえてくるので、彼らは何もできなくなります。すべて完璧にできないなら、やらないほうがマシだと考えてしまう。他人に少し批評されただけで、ひどく非難されたように感じてしまう。
やればやるほど自己評価が下がる。何かをするのが怖くなる。やらなければこれ以上、自分は傷つか
ない。結局、何かに挑戦することを最初からあきらめ、あるいは途中で放棄してしまいます。
突然仕事を辞めてしまったり、何日も家に閉じこもったり、他人から見たら理解できない行動をとる人がいますが、その裏にあるのは、親教のマインドコントロールなのです。常に内心の批判の声に怯えているので、他人のちょっとした言葉がきっかけになって、極端な行動を起こしてしまいます。自殺を図ったり、普段はおとなしそうな人が、突発的に暴力事件を起こすこともあります。
逆に、非常に尊大で威張っていて、誇大妄想を持つ人もいます。これもじつは、健全な自己評価のなさ、健全な自信のなさに由来します。
彼らは、自分の中の「親」とセットになった「幼児」です。幼児はナルシシスティックで、自分の限界を知らず、自分にはなんでも可能で、すべてが自分の思いどおりにいくものだと信じています。
ほとんどの人は成長するにつれ、近所のガキ大将にケンカで負けたり、成績で評価されたり、女の子にふられたりして、適度な挫折を経験しながら、現実の自分が万能ではないことを学習していきます。そんな自分でも十分生きていけるし、そんな自分でも十分愛されることがわかっていくのです。
ところが親教の信者は、まだ自己愛にひたった幼児のままでありたい人たちです。大人としての自分が、そうたいしたことはないとは認めたくありません。他人に、たいしたことのない自分を知られてしまうのが怖いので、必要以上に自分を高く見せようと高慢にふるまいます。
「オレは、他のやつらとは違うんだ」と周囲の人間を無知、無能とバカにし、罵ります。こうして、彼の周りにいてくれる人を選別しているのです。彼の罵りを支持してくれ、「あなたはすばらしい」といってくれる人とだけつき合いたい。そうでなければ不安なのです。自分が世界の中心にいないと不機嫌になってしまう幼児と同じです。
ある程度以上の実力や能力がある人は、社会でもこれで通用する場合がありますが、社会で通用しないと知っている人は、会社では周囲に媚こびて、異性関係や家庭で高慢にふるまうこともあります。社会で傷ついた自尊心を、自分より弱そうな女性や子どもに威張ることで取り戻そうとしている男性はけっこう多いのではないでしょうか。
女性のほうも、「女は男をたてるもの」という世間の期待を取り入れて、こんなガキのような男性に、「お父さまはご立派で」などといっては、そのナルシシズムにエサを与えてあげていることが多いでしょう。
このような倣慢さを身につけてしまった人にとっては、他人に頭を下げたり、謝罪したり、助言を求めるのは至難の業わざなので、自分の態度によって困った事態におちいっても、頑固にこの傲慢さを捨てようとしません。捨てられないのです。
適切なノーがいえない
親教の信者は、ノーをいうのが大変苦手です。ヘタです。自分が拒否したら相手にも拒否される、一度でもノーをいってしまったら、もう見捨てられるような気がするのです。ノーがいえないために、ウソにウソを重ねることもあります。行動にも一貫性がありません。
きっぱりノーをいえずに他人のいいなりになっているうちに、思わぬ事件や犯罪に巻き込まれがちです。はっきりせず曖あい昧まいで、あとから「そんなつもりはなかった」などといって無責任です。また、我慢に我慢を重ねて、大爆発を起こすこともあります。
イヤなことをイヤといい、してもらいたいと思うことをきちんと伝えられないとなれば、結局、人間関係が面倒になってきますので、ひき込もらざるをえなくなる。
彼らの人間関係は、決して親密ではありません。いつもどちらが上でどちらが下かをはかっています。本当の自分が出せず、適度な要求を伝えることもできませんから、人とつき合っていても、その間には高く厚い壁があり、孤独です。実際にひき込もる人もいますし、表面上は社交的でも、心は孤独のカプセルに入っている人もいます。
そうやって自分から他人を遠ざけ、「オレは他人とは違う」といって孤立しながら、寂しがります。寂しいのなら、心の敷居を低くしてありのままの自分で他人とふれ合えばいいのですが、それができません。弱みを見せたらバカにされると思うのです。
対等な関係であれば、弱みを見せ合っても平気なのですが、親教の信者は、相手が「下」で自分が「上」だと思えば、相手をバカにし、いじめて喜ぶ。常に屈辱感を感じているので、自分の屈辱感を晴らす機会をうかがっている。そういう世界観の中で生きていますから、自分も弱みを見せればやられると思い、固い殻でよろっているのです。
また、自分が適正にノーがいえない結果、相手のノーも適正に読みとれなくなっています。拒否されたわけでもないのに「拒否された」と過剰反応したり、逆に、きちんとノーをいわれているのに認めたくなくて、結局相手から手ひどい「ノー」を引き出してしまうこともあります。お互いが気持ちよくつき合える適度な距離をはかり合って、親密な関係をつくっていくことができないのです。