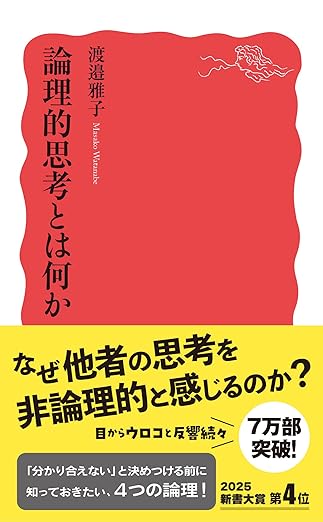なぜ日本の小論文は米国で「採点不可」になる? 文化圏で異なる思考パターン
2025年05月23日 公開

ビジネス書を中心に1冊10分で読める本の要約をお届けしているサービス「flier(フライヤー)」(https://www.flierinc.com/)。こちらで紹介している本の中から、特にワンランク上のビジネスパーソンを目指す方に読んでほしい一冊を、CEOの大賀康史がチョイスします。
今回、紹介するのは『論理的思考とは何か』(渡邉 雅子著、岩波書店)。この本がビジネスパーソンにとってどう重要なのか。何を学ぶべきなのか。詳細に解説する。
論理的思考の概念を一新する
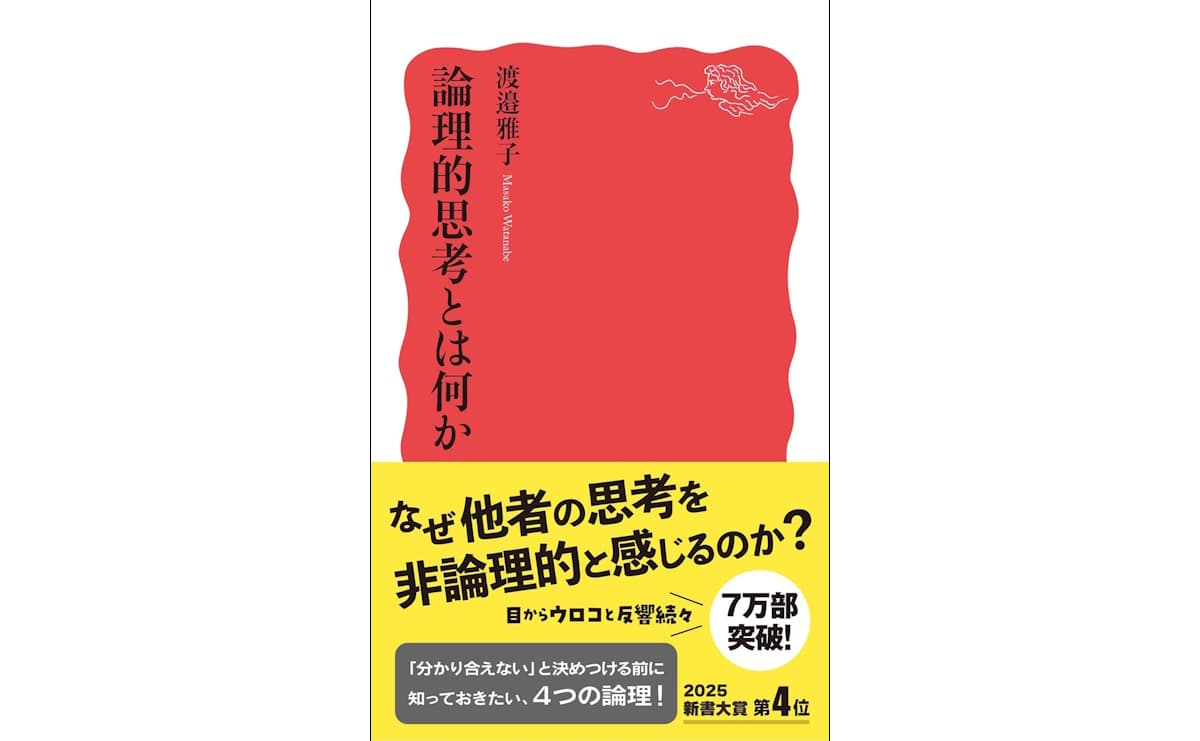
論理的思考は現代のビジネスシーンで必須のスキルの1つと言われています。「頭がいい」「説明がわかりやすい」「説得力がある」という望ましい評価の元にあるのは、まさに論理的思考の力です。
今まで論理的思考について何らかの研修や本で学んできた方は多いはずです。そして、いわゆるピラミッド構造の論理展開を思い浮かべるのは私だけではないでしょう。
まず結論があり、それをサポートする論理や例が3つほど述べられ、再度結論が登場するものが一般的なように思います。しかし、これまでの理解は「論理的思考」に対する偏った見方だった、という衝撃を本書から感じることになります。
文化による論理的思考の違い
ある国でとても優秀な学生が、他の国の大学に行くと、全く論理的でないと言われるそうです。日本の優秀と言われる学生でも、米国の大学で小論文を書くと、採点不可能という評価になってしまうことがあるくらいです。そのような感覚の違いはどうして生じるのでしょうか。
ここで興味深い分析があります。アメリカの応用言語学者のカプランは、長年なぜ留学生は英語力が向上しても、小論文が上達しないのだろうかと考えていました。そこでカプランは30か国以上から来た留学生の小論文を分析しました。そして、論理の流れを図式化すると、言語圏によって形が全く異なっていることがわかったのです。
まず代表的な流れは英語圏のもので、直線的な論理展開を取ります。冒頭で紹介したピラミッド構造の論理だと思っていただければイメージがわくと思います。
次に、ヘブライ語やアラブ語などのセム語圏では類似することがらを詩の対句のように並行させながら展開させていきます。日本を含む東洋では、主題から遠いところから渦巻きのように主題に近づいていく展開をします。この展開方法は私たちにはなじみがありますが、あらためて考えてみると論理的という言葉から遠い存在のようにも思えます。
そしてフランス語に代表されるロマンス語圏では、余談を交え紆余曲折しながら論理が展開されるそうです。そして、極めつけはロシア語圏で、パラグラフの間のつながりがパターン化できないのだそうです。ロシアの独裁色の強い伝統的な政治体制下では、何か明確な結論を出すことが個人として望ましくない、というような背景もあるそうです。
ここまででも、文化圏によって代表的な論理展開に違いがあることは理解できると思います。そして、その違いにより各文化圏が得意なテーマを分岐させていくのだといいます。
論理的思考の4類型
英語圏の直線的な論理展開は経済領域を得意とします。端的に言えば、効率的に最大限の収益を上げることを目的にしています。
そして、英語圏では目的が定まった後の形式合理性を重んじていて、主観的な判断が行いやすいようになっています。たしかに未来を予測することが多い経済領域の判断では、どれだけ精緻に予想しようとしても因数が無数にあって、客観的な正しさは証明できないため、最終的に主観的な判断が主役になるのは納得できます。
フランスでは歴史的に理想の社会の実現に対して、多様な議論をしてきました。政治的な理想は社会福祉や共通善、ルソーの言葉では共同体全体の利益を目指す「一般意志」を追求するものと言われています。その理想に近づくためには、スピード感をもった判断ではなく、慎重に何が共通善なのかを熟考する必要があります。
そのため、テーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼといった弁証法を代表とする議論がなされます。政治領域と同様に哲学領域でもこのような議論は好まれます。こちらは主観ではなく、あくまでも客観的判断となり、目的が定まっていないことから実質合理性を追求します。
そしてイランなどの中東の多くの国では、宗教や法技術領域を得意とします。いわゆる宗教の教義やイデオロギーなどを人間が従うべき絶対的な権威とみなします。イランの作文の結論は、ことわざ・詩の一節・神への感謝が語られることが多いそうです。
つまり、ここで独自の解釈や理解を述べるのではなく、過去正しいと考えられていたことの正しさを確認して文章が終わるのです。宗教や法技術領域では、目的が定まっているため手段を考える形式合理性を追求し、個人ではなく集団的な合理性を追求する客観的判断の姿勢がとられます。
そして、世界の中では日本も独特の論理展開をします。得意とするのは社会領域です。日本の読書感想文では本を読む前の自分の考えと、本の内容を経て、結論として読書体験から得られた成長や今後の心構えが語られることが多いかと思います。そのような形式をとる言語では、社会が統制と秩序を保つために、他者への共感を通して明文化されない緩やかな価値を構成していきます。
そのため、状況に応じて個人が選択する道徳心が求められます。事前に目的が定まっていない実質合理性に従い、主には主体的判断の集合となります。日本で暮らす我々には、納得感のある記載ではないでしょうか。
私たちはどう論理的思考に向き合うのか
世界で大切にされている思考法を俯瞰すると、今まで私たちが考えていた論理的思考に関する大いなる誤解に気づかせてくれます。論理的思考はただ一つの型に従うのではなく、何を目的に議論を展開するかで適切な論理展開が変わる、ということなのです。
それでも気づかされるのは、やはりアメリカ式の論理展開はメッセージが明確なため、複雑な事業環境で迷いがちな経済領域で主流であることは再認識されられたことが一つ。
そしてもう一つは日本社会が世界的に見て安定しているのには、文化的な背景とそれを形成する日本語が得意とする論理展開が寄与している、ということです。
私自身は新卒でコンサルティング会社に勤めたため、社会人になると同時にアメリカ式の論理展開を叩き込まれました。今まで随分それに助けられた面はあるものの、一方でつまずいた時を思い返すと、論理的な明確さで割り切れない複雑な状況や人の感情への配慮だったように思います。
仕事がある程度一人前にできるようになり始めた20代後半から30代前半で、上司の指示と自分が正しいと思うことに折り合いをつけるのかに苦心していたことが思い出されます。
環境に合わせて適切な論理を使い分けられると、ビジネスシーンで柔軟に対応することができそうです。論理性が求められる現代のコミュニケーションに明快な理解と指針が得られる本書は、多くの人にとって有用になるでしょう。本書ははじめの章から最後まで知的刺激にあふれています。ぜひお勧めしたい一冊です。