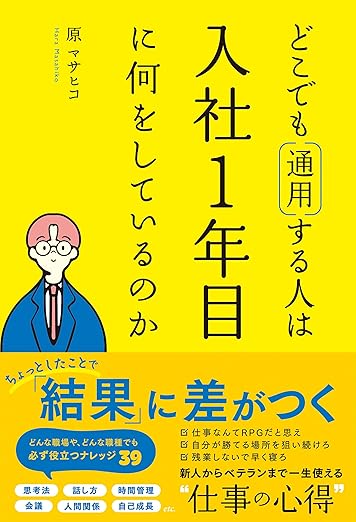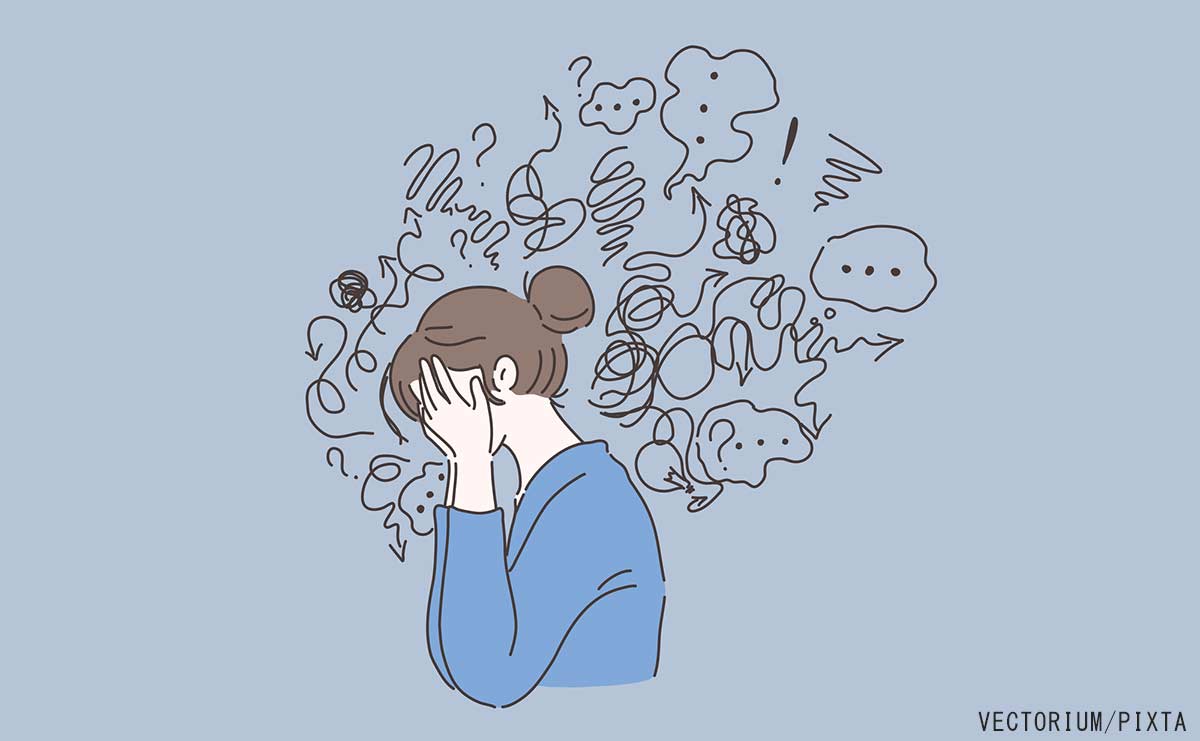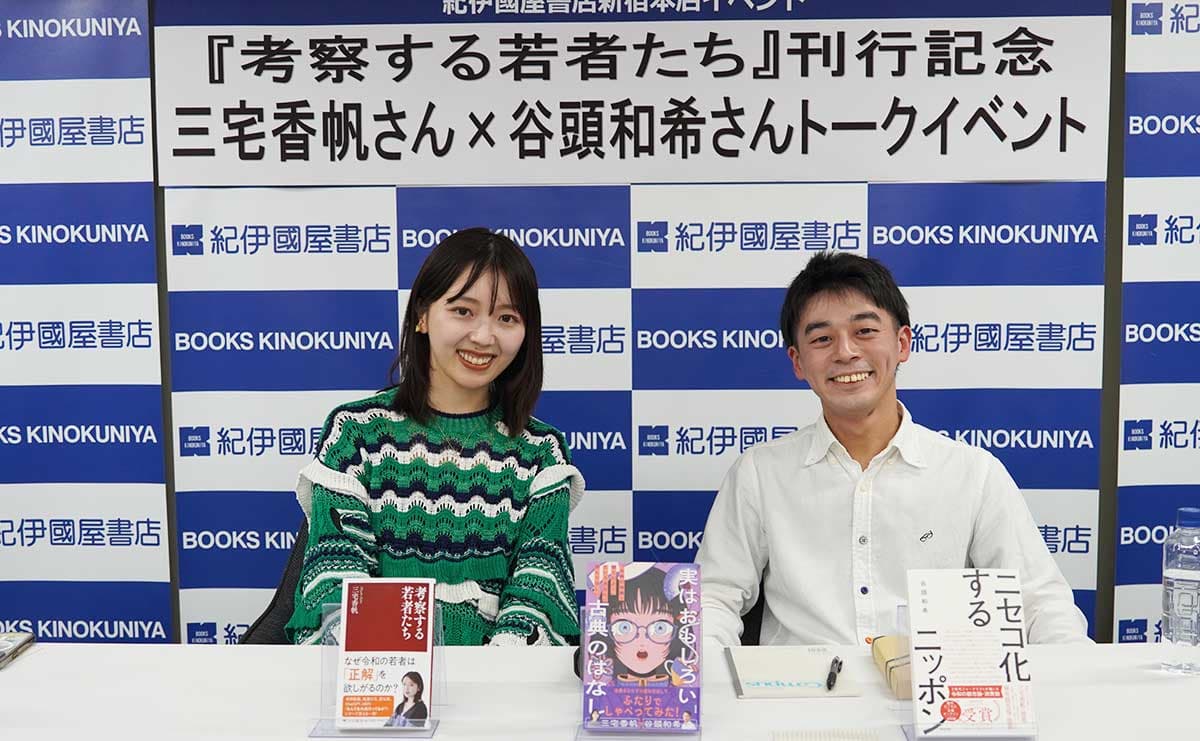就職してから時間がたってくると、さまざまな悩みを抱える人が多くなります。
入社前に抱いていた理想や希望がなかなか実現できなかったり、仕事の忙しさや人間関係に悩むあまり転職を考え始めたり...。そうすると「今とは違う場所でもうまくやっていけるだろうか」と気になってくるものです。
そのような時は、会社のようなビジネスの場ではどのような人材が求められているかをよく考えてみましょう。会社が社員に期待していることは、「成果を出すこと」です。
本稿では、書籍『どこでも通用する人は入社1年目に何をしているのか』より、どんな場所でも成果が出せる人材になるための思考について解説します。
※本稿は、原マサヒコ著『どこでも通用する人は入社1年目に何をしているのか』(総合法令出版)の一部を再編集したものです
飲み会や忘年会で経験すべきこと
何年か前に「忘年会スルー」という言葉がメディアで取り上げられていました。会社で年末に開催される忘年会に、参加しない社員が増えているという話題でした。実際のところ、皆さんはどうでしょうか。「会社の飲み会なんて、わざわざ参加したくない」とか「参加するなら残業手当をつけてほしい」とかいろいろな意見があるかと思います。
個人的には、飲み会や忘年会は自分の意思で判断すれば良いと考えていて、出たほうが良いとも出なくても良いともいえません。会社の方針やその場の雰囲気に従えば良いのではないかと思います。ただ1つ、どうせ飲み会があるなら経験してほしいことがあります。
それは幹事をやるということです。
幹事をこなす能力というのは、仕事にも役立ちます。ですから、そういった意味で一度は経験してほしいと思うのです。幹事に必要な能力とはでは、どのような能力が必要で、どう生かせるのか、具体的に書いてみましょう。
・企画力
会社の飲み会であれば、なんらかの意味があって開催するケースがほとんどです。忘年会なのか新年会なのか送別会なのか歓迎会なのか。そのコンセプトに沿って、どのような飲み会にするのかを考えていかなければいけません。
つまり、企画の"軸"となる部分です。誰が主役になるのか、誰を立てるべきなのか、それによって会場となるお店も変わってきますし、会費も変わってきます。そういった全体の企画力が必要になってくるのです。
・スケジュール調整力
飲み会において難しいのが日程調整です。部署内の飲み会など少人数であれば良いのですが、忘年会など部署をまたぐものになると全員参加が難しかったり、大切な予定と重なっていたりすることが必ずあります。
まず、どのように調整していくかが重要で、誰の予定を優先していくべきかも考えなければいけません。また、参加する人数によって会場も変わってくるので、ここをしっかり合致させないとあとで大変なことになってしまいます。
・ニーズの把握力
飲み会に求めるものは人によって異なります。あくまで例ですが、男性ばかりであれば賑やかで騒げるお店だったり、女性が多かったらお手洗いが綺麗なお店かどうか、座敷ではなくテーブル席が良いのではないかといった配慮も必要です。
また、喫煙者がどれだけいて、嫌煙者がどれだけいるのかも重要です。お酒が飲めない人がいる場合には、ノンアルコールのドリンクメニューが充実しているかどうかも確認しておく必要があるでしょう。このように、参加者が求めるものを事前に把握しておくことも必要になってきます。
・リサーチ力や分析力
優れた幹事は、お店に関する情報に長けているものです。それは日頃からリサーチを欠かさず、気になるお店があったら実際に足を運んで体験しているからです。また、過去に先輩が開催した飲み会の話を聞いてデータを収集しておくというのもポイントになるでしょう。せっかく実績があるわけですから、その情報はストックしておいて今後の参考にすべきです。
・視野の広さ
当日に幹事がすべき仕事は、"気配り"です。誰に挨拶をしてもらうか、料理や飲み物が行きわたっているか、暑そうな人や寒そうな人はいないか、体調の悪そうな人はいないかなど、とにかく気を配ることが重要です。これは、のちに組織をまとめるうえでのマネジメント力を養うトレーニングにもなるはずです。
・予算管理
飲み会では、会費の徴収をスムーズに、明確にする必要があります。お金が絡む話ですので、ここでトラブルになってしまうとせっかくの楽しい飲み会が台無しになってしまいます。上司から多めにもらうという場合も多いですが、スムーズに気持ち良く支払ってもらえるよう、事前に根回しをしておく必要があるでしょう。
このように、箇条書きで書いてみても、さまざまな力が求められることがわかります。しかし、仕事ではなく飲み会ですから、多少失敗しても会社がつぶれるわけではないですし、「新人だから仕方ないね」と大目に見てもらえるはずです。
むしろ、失敗を重ねながら幹事力を養っていくことで、ビジネススキルも身について一石二鳥ではないでしょうか。
他人が嫌がることを積極的に行う意味
入社1年目というのは多くの人がスキルや経験不足のため、1人ひとりを見ても実力にそれほど差はありません。ただ、仕事を任せられるかどうかを飲み会での振る舞いで判断されることが実はよくあります。
飲み会は仕事ではないので、誰もが幹事をやることは嫌がるでしょう。しかし、皆が嫌がることを積極的に引き受けるというのは1つのアピールになるはずです。
皆と同じ仕事をしているのに、自分だけ給料が増えてほしいなどと願うのは虫がいい話ですし、まずありえないことです。やはり、人が嫌がることや避けたいことに積極的に首をつっこんでいくことで経験値が上がり、評価されるようになります。
それは幹事に限った話ではありませんが、「幹事、やってみる?」と聞かれる機会があったら、ぜひこのことを思い出して手を挙げていただきたいと思います。飲み会自体が面白くないものだったとしても、その場をつくり出す準備に意味があるのですから。