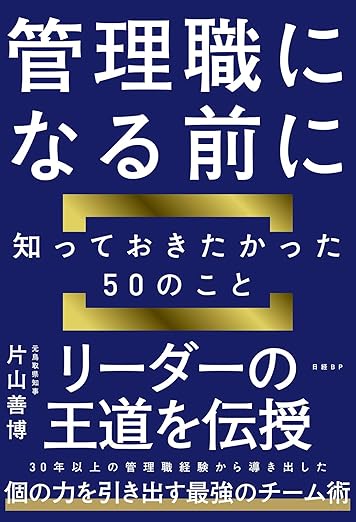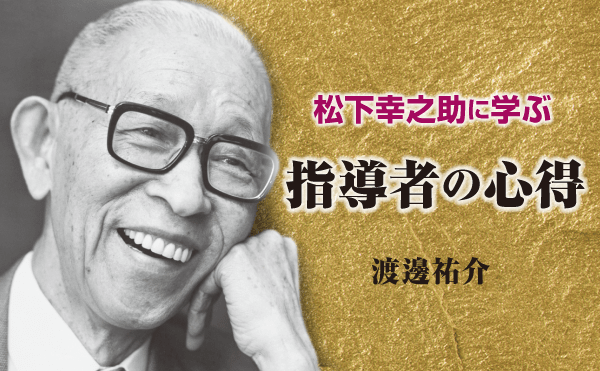厚生労働省の報告によると「管理職に昇進したいと思わない」人は61%にのぼるといわれています。一方で、実際に社会や会社を動かしていくためには、管理職の仕事は必要です。
本稿では、日経クロスウーマンが行った調査、約3000人の現役管理職と管理職経験者に聞いた「これから初めて管理職になる人へのアドバイス」について、「管理職を長年経験できてよかった」と仰る大正大学特任教授で元鳥取県知事、元総務大臣でもある片山善博さんに解説して頂きます。
※本稿は、片山善博著『管理職になる前に知っておきたかった50のこと』(日経BP)を一部抜粋・編集したものです。
アドバイスの上位に入ったけれど
「これから初めて管理職になる人へのアドバイス」では「自分の可能性を信じる」「鈍感力を身に付ける」という内容が上位に入りました。でもこの2つの項目に私はあまり賛同できませんでした。
まずは、「自分の可能性を信じる」という言葉です。これについては、具体的にはこんなメッセージが書き込まれていました。「自分の可能性を信じること」「常に自分には素晴らしい道が開けていると信じてほしい」「チャンスがあればどんどん上を目指すべきだ」など。でも、私はこれらの言葉を読んで、ちょっと自己啓発本を読んでいるような気持ちになりました。
私はときどき書店で自己啓発本をめくってみるのですが、正直、取って付けた感があってピンと来ないんです。「不自然さがあるな」と思えてしまって。「自分の可能性を信じましょう」という表現を聞くと、嘘っぽさを感じます。もっと肩の力を抜いて自然体でやっていれば、こういう言葉は出て来ないのではないでしょうか。
「上を目指す」というのは、「もっと大きい仕事をしてみたい」という意味では、当然出てくる感情だと思います。「今、自分が持っている権限の範囲内だったら、ここまでしかできない。より上の立場になれば、もっと広い視野で、思い切った仕事ができるな」と思うものです。
「自分の可能性を信じる」うんぬんではなく、そういう考え方を持っていればいいのではないでしょうか。そのうえで、チャンスが自分に回ってきたら挑戦すればいいのです。
次の「鈍感力を身に付ける」については、「全員を満足させることはできない。鈍感力も大事」「周りからの雑音に鈍感になり、自分の仕事に徹する」「全員に好かれようとする必要はない」というメッセージが寄せられました。最近の風潮を反映していて分からないでもないですが、やや割り切りが過ぎているように感じます。
そんなに割り切れるものではないですよ。確かに管理職として仕事をしていると、周りから雑音が聞こえてきたり、悪口を言われることはあります。中には誹謗中傷もあるかもしれません。それをいちいち気に病んでいたら仕事になりません。それはその通りなんです。
でも、雑音や悪口の中に真実もあります。ですから、それはやはりいったんくみ取ったほうがいいんです。ワンクッション置いて謙虚な気持ちになって、「雑音として聞き流すもの」と「受け止めて傾聴に値するもの」に仕分けする必要があります。
あまりしゃくし定規に「全く気にしない」と決めないほうがいいです。自分やチームの仕事を第三者の目で見てもらって、意見を聞くことも大事ですから。
耳の痛い指摘には宝が隠されている
例えば役所の場合、住民から何かクレームが来たとします。こういう場合、クレームが届いた部署だけ改善しようとすることがありますが、それではもったいないんです。「ゴキブリは1匹いたら、背後に100匹いると思え」といいますが、それと同じで、1件のクレームをきっかけに、全体の改革につなげることもできます。
知事時代、私はそれを実践しました。県庁の窓口にいろいろなクレームが届き、中には公益通報のようなものもありました。担当職員に整理してもらったところ、「これは調べてみたい」という案件がありました。この後の調べ方にこつがあるのです。
通報の対象になった部署だけ調べると弊害が出ます。「あの課でこんな通報をするのは、あの人しかいないよね」とかね。まだ公益通報者保護法のない時代でしたが、公益通報者を保護する意味で、無関係の部署を含めた5カ所ぐらいの部署を調べていました。
そうしたら最初にクレームが来た部署はガセネタで、たまたま調べたほかの部署では問題が見つかりました。そんな経験をしてからは、「これは」と思うクレームが入ったら、最初から全庁を調査するようにし、その結果、大きな行政改革につながりました。こんなふうに、耳の痛い指摘には宝が隠されている場合が少なくありません。
また、耳の痛いことは、組織の内部から寄せられることもあります。組織の違法行為やコンプライアンス違反に対する批判や内部告発です。これが昨今、自治体や企業で大きな話題になっている公益通報と呼ばれるものです。組織のトップはもとより、管理職はこの問題に対して、公益通報者保護法のルールにのっとって真摯に対応しなければなりません。
通報内容が明るみに出ることで組織全体が信用を失ったり、幹部の誰かを傷つけたりするのを避けようとして、管理職が通報を握りつぶすようなことをしてはいけません。通報が匿名の場合に通報者探しはすべきではなく、通報者を一方的に処分するのもいけません。こうした行為は公益通報者保護法により厳げんに禁止され、もしそれに違反すると、状況によっては組織の破綻につながりかねません。
管理職になろうとする人は、ぜひこの問題に関心を持つようにしてください。