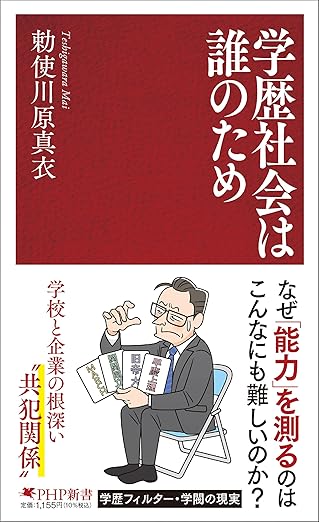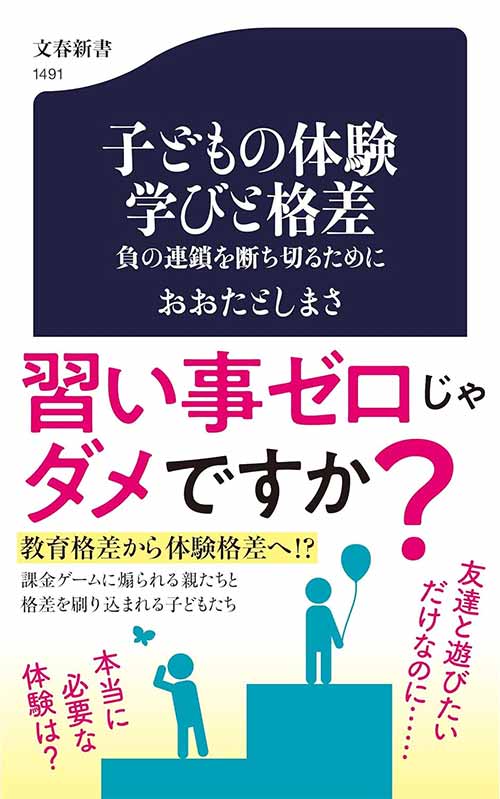「学歴社会」「体験格差」 超能力主義社会で、親が子どもにしてあげられる“声かけ”
2025年06月10日 公開

去る5月29日、紀伊国屋書店新宿本店で、『学歴社会は誰のため』(PHP新書)著者の勅使川原真衣さんと、『子どもの体験 学びと格差』(文春新書)を上梓したおおたとしまささんのトークイベントが開催された。「なぜ親は、子どもに『優秀』になってほしいのか?」と題した本イベントは予約満席、ふたりの話に熱心に耳を傾ける参加者であふれた。学歴社会と子どもの「体験格差」をテーマに、子どもの本当の幸せとは何かを考える。
取材・構成:中西史也(PHP新書編集部)
「異常な威力」を発揮する学歴
「なぜ親は、子どもに『優秀』になってほしいのか」。
本イベントの問いは、身も蓋もないことを言えば、「子どもに苦労してほしくないから、幸せになってほしいから」という一言で終わってしまうかもしれない。
親にとって、自分の子どもが他の子どもよりも「優れてほしい」と思うのは当然だ。一方で、勅使川原さんもおおたさんも、親が子どもに期待して「優秀さ」を求めてしまう心情を理解しながらも、それが本当に子どもの幸せ、ひいてはより良い社会につながるのか、という問題意識をもっている。
親のエゴではなく、本当に子どものためになるための向き合い方とはなんだろう。そう考えながら、ふたりの対話に耳を傾けた。
「そもそも『優秀』という言葉は空虚なんです」と一蹴する勅使川原さん。「誰々は優秀だ」と言うと、何か固定化された「能力」があるように思うが、勅使川原さんは「能力とはつねに揺れ動くもの」と捉える。
勅使川原さんが『学歴社会は誰のため』で、日本の学歴社会に警鐘を鳴らしたのは、まさに「学歴があるならなんか頑張れそうで、能力がある」と一元的に見なすことへの懐疑があるからだ。
おおたさんも、日本において学歴は「“通行手形”のように、異常な威力を発揮する」と指摘する。
親が子どもに「優秀になってほしい」と言うとき、多くの方は「(勉強で)優秀になってほしい」と解釈するのではないだろうか。中高一貫校や進学校に入り、有名大学に進む。そんな「優秀な子」に育てば、大企業に就職して、安定した幸せな生活を手にする可能性が高まる――。学歴が日本でいまだに「異常な威力」を発揮する以上、そう考えるのも無理はないだろう。
「勉強+αの優秀さ」も求められる
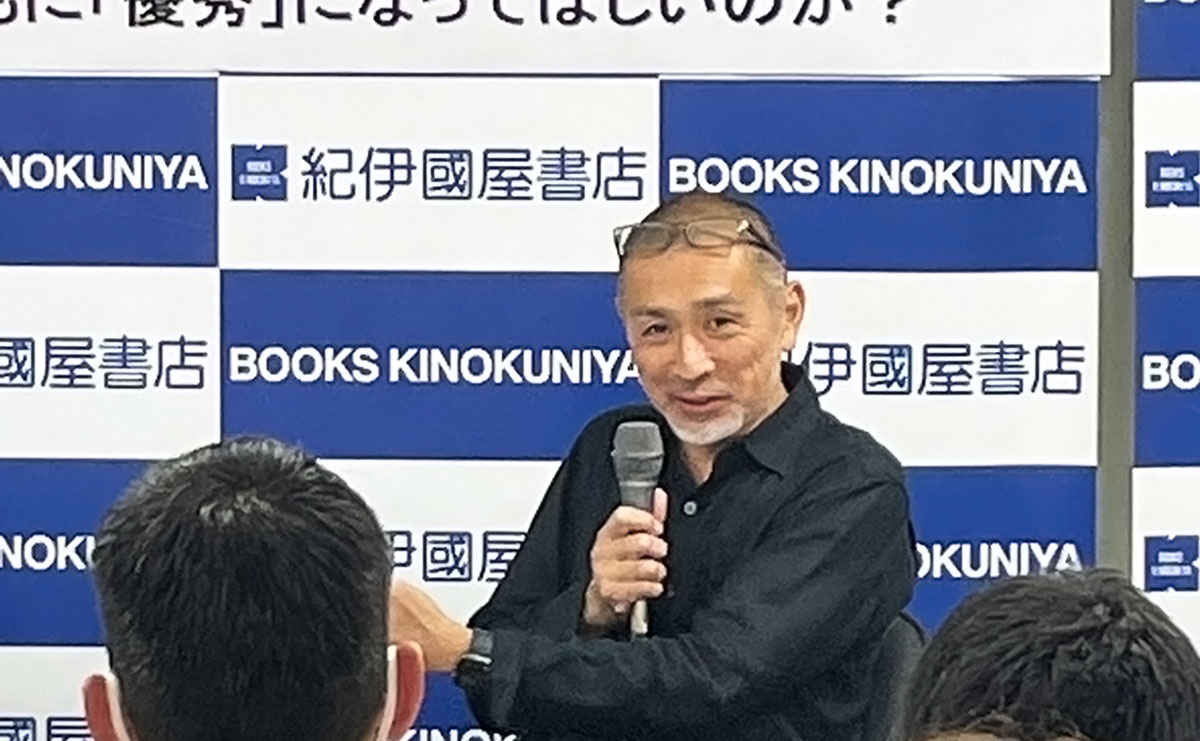
他方で、「優秀さ=勉強」である学歴社会だけならまだましだったと言えるかもしれない。
おおたさんが著書『子どもの体験 学びと格差』で念頭に置くのは、「優秀さ=勉強+α」の社会だ。すなわち、現在の子どもはIQや学力だけではなく、協調性や主体性といった「非認知能力」が求められる。そして「非認知能力」を身につけるためには、習い事や旅行といった「体験」が重要であり、その多寡によって「体験格差」が生じていると言われている。
親の学歴や居住地といった、子どもにはどうしようもない要素でその子どもの教育や学歴が左右されることは「教育格差」と呼ばれたが、いまや格差は「体験」にまで及んでいるのか......。
そこでおおたさんは、「体験格差」という言葉に疑問を投げかける。
「体験を『格差』と言ってしまうこと自体、競争によって順序づけている前提ですよね」
勅使川原さんも、「『格差』と呼ぶことで、有利になるか不利になるかというゲームを内面化している。すると、勝ち続けないといけない、という思考になる」と指摘する。
つまり、「勉強の優秀さ」に紐づく「教育格差」と、「勉強+αの優秀さ」に関わる「体験格差」どちらも、競争によって有利・不利を決め、ひいては将来もらえるお金を左右するゲームという意味で、同じレール上にあると言える。ふたりに言わせれば、「同じ穴のムジナ」だろう。
勉強ができるという「認知能力」、勉強以外もできるという「非認知能力」。このように「能力」が多元化していることは「ハイパーメリトクラシー(超能力主義)」と言われるが、たしかに社会から求められる「能力」は際限なく広がっている気がする。
私はいわゆる「ゆとり教育」を受けてきた世代で、学生時代は詰め込み教育ではダメという意識を植え付けられながら学んできた。就職活動のときはコミュ力(コミュニケーション能力)やリーダーシップの重要性が散々叫ばれた。社会人になると、主体性は当然必要だし、いまやITリテラシー、ファイナンスリテラシー、さらには「言語化力」がないと「仕事ができる人」と見なされない......。
いやいや、求められる能力多すぎ! と言いたくなるが、そうした「能力」の洪水はいまの子ども世代によりいっそう押し寄せてくるのだ。
勅使川原さんとおおたさんが訴えるのは、競争によって有利不利が決まる能力主義のレールの上にいつまでも乗っていていいのか、ということである。「まだ能力主義で消耗してるの?」と言えるかもしれない。
能力主義から解脱した視点
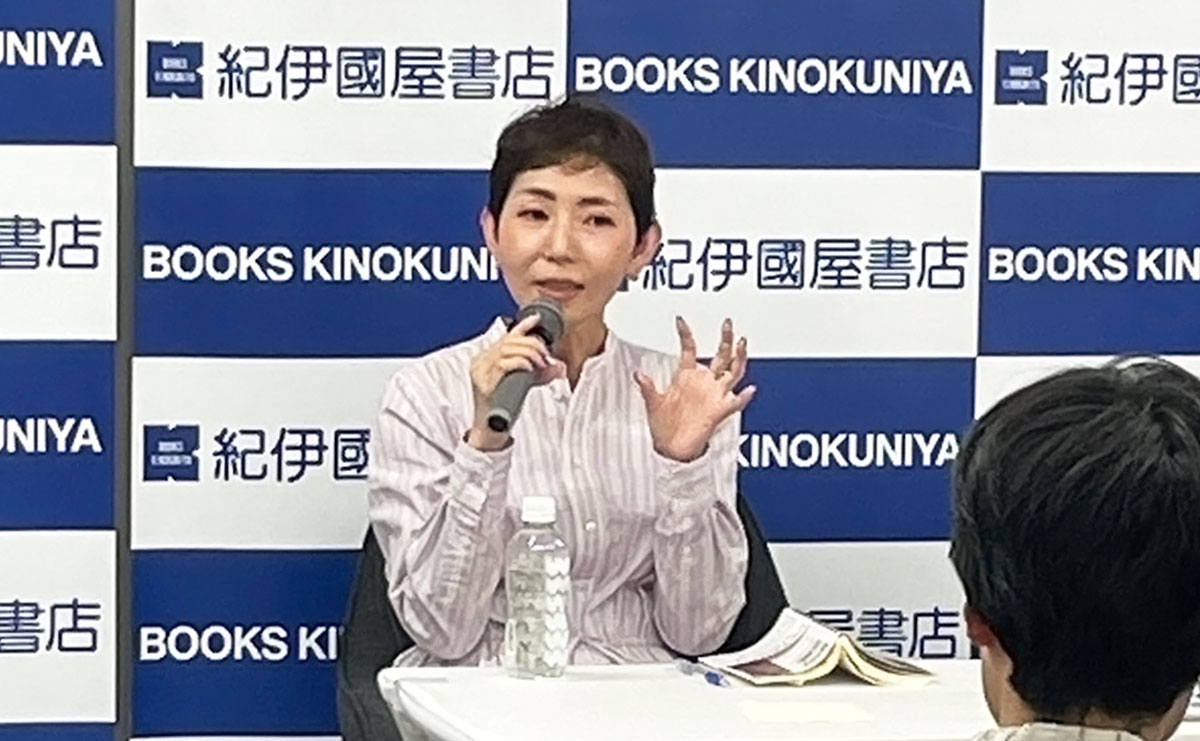
とはいえ、「自分の子どもには負け組になってほしくない、優秀になってほしい」「自分の子どもだけ競争から降りたとして、社会が変わらなければ損をする」と思う方もいるだろう。正直、私もそう思ってしまう。実際、本イベントの最後の質疑応答で、似た趣旨の質問が寄せられた。
ただ、勅使川原さんもおおたさんも、能力主義社会を一朝一夕に変えられると楽観しているわけではない。
勅使川原さん自身いわゆる高学歴で、大手外資コンサルでバリバリの能力主義に身を置き、「自分の子どものことになると、やっぱり受験や学歴は気にしてしまう」と言う。それでも一元的な「能力」で人を見ることにかねてから違和感を抱き、38歳のときに乳がんが見つかった際は「いつまでも競争で勝ち続けることはできない、やっと競争から降りられる」と肩の荷が下りたそうだ。
だから勅使川原さんは、競争ではなく「共創」できる社会をめざしている。個人の「能力」を一元的に捉えて「あの人は優秀だ」「あの人は無能だ」と見なすのではなく、その人の持ち味を活かし、組織をチームとして回していく社会だ。
「自分の子どもが"優秀"になってほしい」と願う親の皆さんに、私が本イベントで得た気づきとして伝えたいことのひとつは、能力主義に基づく競争以外の視点をもってほしいということだ。何を当たり前な......と思われるかもしれない。
でもあえて言えば、能力主義から解脱した視点をもつことで、またその考え方を子どもに共有することで、むしろ能力主義社会でも生きやすいようになるのではないだろうか。「外国語を知らない者は自分自身の言語について何も知らない」と言われるが、「脱能力主義を知らないと、能力主義の"解像度"も上がらないよ」とは言えないか。
当の勅使川原さんも「競争や能力主義社会の前提を疑うことが、あえて言えば"勝ち筋"なのでは」と語る。
それに勅使川原さん自身が痛感されたように、競争でいつまでも勝ち続けるのは難しいし、疲弊するし、何よりしんどい。子どもを熾烈な受験競争に放り込んで仮に「勝てた」として、次は就活、社会人と、競争は延々と続く。
なにも、競争させてはいけない、と言っているわけではない。勅使川原さんが言うように、「競争で勝っている人にとっては、その状態が気持ちいい」。トーク後の質疑応答では、参加者から「結局皆さん、競争が好きなんじゃないでしょうか」という根本的な指摘も飛んできた。
一方で、能力主義に基づく競争以外の世界線を頭の片隅にでも置いておけば、たとえ厳しい競争にさらされても「いざとなれば別のルートもあるし」と少しは気持ちが楽になるのでは、と思うのだ。「こっちの選択肢もあるよ」と、親が子どもに語りかけてもいいはずだ。
子どもに「ビリでラッキーだね!」と言ってみる
うーん、そうは言っても、子どもに「あのね、世の中はハイパーメリトクラシーで大変だけど、じつは別の選択肢もあって......」と言っても伝わりにくいだろう。親が子どもに向き合ううえで、より実践的な方法はあるのか。
そう考えながらふたりの話を聴いていると、おおたさんが興味深いエピソードを語った。
「うちの子どもがあるとき学校のテストで、クラスでビリになったとき、『ビリでラッキーだな!』って言いましたよ。周りの友達が自分よりも"優秀"だったら、いちばん助けてもらえるじゃん、って」。
率直に思った。自分が子どもだったら、そんなふうに言ってくれる親って最高だ、と。
まず、「優秀になれなかった」自分を肯定してくれている。子どもにとって、いや大人だって誰しも、ありのままの自分を肯定してほしいはずだ。
また、「周りに助けてもらえる」という言葉もいい。学校生活でも社会に出てからも、人を「助けてあげられる」ことはもちろん大切だが、「助けてもらえる」ことも同じくらい大事だ。皆さんの周りにもいないだろうか。人に何かを頼んだり、助けてもらったりすることが異常に得意な人(私は苦手なので羨ましい......)。
これを「助けてもらう力」のように「能力」に回収すると、新たな能力主義を生み出してしまい、それこそ同じ穴のムジナだ。
「ビリのままでいいよ、お前はどうせ勝てないし」ではない。たとえビリになっても子どもの存在を肯定し、その子の持ち味を認め、他者との関係性を意識してもらう。
「子どもに"優秀"になってほしい......」と苦闘する親は、子どもの勉学やスポーツの結果が振るわなくとも「むしろラッキーだね! 周りから助けてもらえて最高じゃん」と声をかけることから始めてもいいのではないだろうか。
「いやいや、そんな甘やかしたら子どもが成長しないから......」とどうしても思ってしまうなら、「周りから助けてもらえて最高だね。でも、もしもっと向上したいと思うなら、お父さん(お母さん)も一緒にやるよ」と言ってみてもいいかもしれない。
自分が子どもだったらやっぱり、そんなふうに言ってくれる親は最高だ、と思うから。