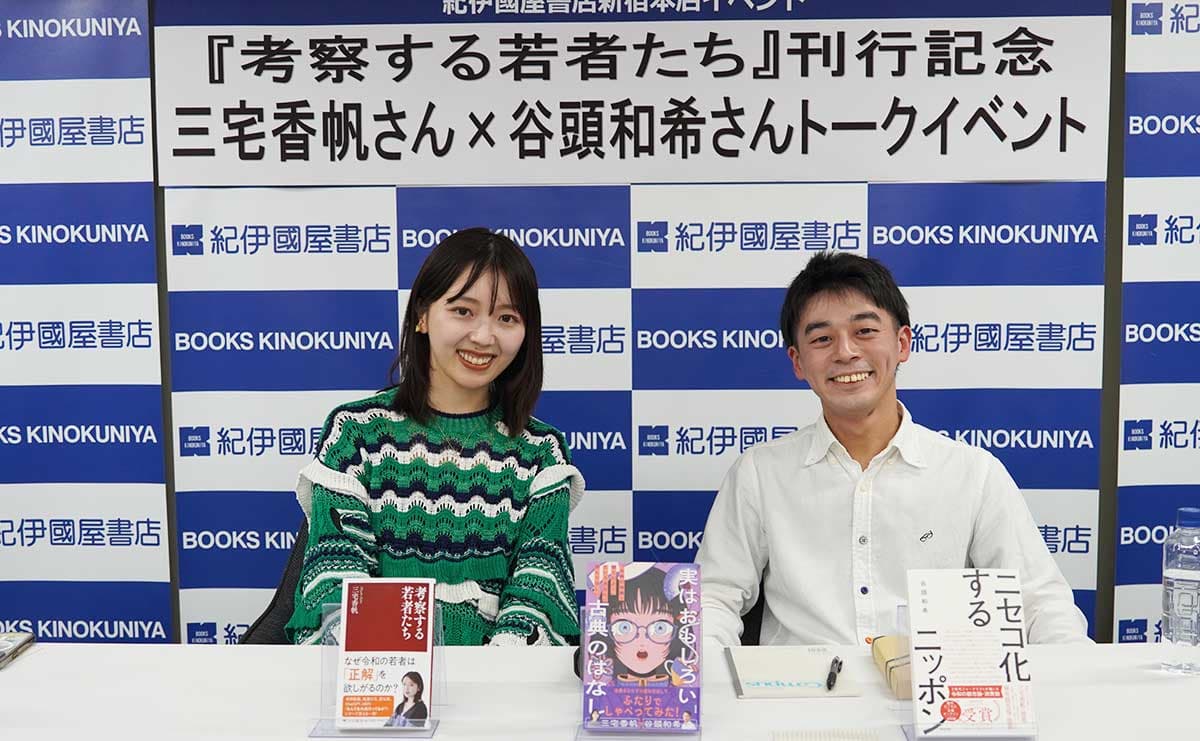ひとつ悩み事が頭に浮かんでくると、それに付随して、いろいろなことを考え始めてしまい、さらに悩みが膨らんでしまう...そんな経験はありませんか。
これに対して、「思考の分離」が、こういった悩みを軽くする、とシリコンバレー発・Sora International Preschool創立者であり、「子どもたちが自ら幸せになる方法」を園にて教える、中内玲子さんは言います。今回、そのような頭の中の混乱をほどく、シンプルな頭と心の整理法について、お伝えします。
悩み事が絶えない人の思考のクセとは?
現代の私たちは、常に何かしらの「悩み」に向き合っています。仕事のこと、家族のこと、人間関係、将来のこと…。特に悩みを抱えやすいと感じる方には、ある共通の“思考のクセ”が見られることがあります。 それは、「問題を必要以上に大きく、複雑にしてしまう」ということです。
◆仕事における例
たとえば、職場で上司から「このレポート、期日を過ぎていたよ」と注意された場面を想像してみてください。 事実は「締切に間に合わなかった」という一点のはずなのに、頭の中では…
「私は仕事ができない人間だ」
「きっと上司は私のことを嫌っているに違いない」
「これからもうまくいかないかも…」
と、本来の問題からどんどん別の方向に思考が展開し、ネガティブな連鎖が始まってしまうことがあります。このような“思考の連鎖”が日常化すると、実際の問題よりも遥かに大きく、そして重く感じてしまい、無意識のうちに自分自身を追い詰めてしまうのです。
◆ 子育てにおける例
家庭では、たとえば子どもが朝なかなか着替えず、毎朝バタバタしてイライラしてしまう、という場面。 ここでも問題の核心は「子どもの準備が遅い」というシンプルなはずなのに、
「また怒ってしまった…私はダメな母親だ」
「この子は将来、自立できないかもしれない」
「夫(パートナー)は全然協力してくれない」
など、一つの出来事から派生した悩みが複数の層となって複雑に混在してしまいます。その結果、「何が本当の問題なのか」が見えにくくなり、対処法も曖昧なまま、怒りや自己嫌悪といった感情だけが強く残ってしまうのです。
では、このような思考のクセを持ち続けていると、私たちの日常に具体的にどのような影響が現れるのでしょうか。
このような思考癖を持っていると、何が起きてしまうのか?
◆仕事における影響
仕事において、"1つの問題"が、まるで雪だるま式に"複数の悩み"へと膨らんでいくと、次のような悪循環が生まれやすくなります。
問題の本質が見えなくなり、どこから手をつけていいかわからなくなる。
具体的な対処法がぼやけてしまい、行動を先延ばしにしてしまう。
小さなストレスが積み重なり、慢性的な疲労感や無力感につながる。
「また同じ失敗をするかもしれない」という不安が強まり、新しい挑戦をためらうようになる。
このようにして、たった一つの小さなミスや指摘がきっかけで自己肯定感が大きく揺らぎ、日々の業務への集中力や判断力にも深刻な影響が出てしまうことがあるのです。
◆子育てにおける影響
子育てにおいては、例えば子どもに対して「ついカッとなって怒ってしまった」という一時的な後悔が、「私は母親(父親)として失格なのでは?」といった深刻な自己否定にまで発展してしまうことがあります。そうなると、親自身が精神的に疲弊し、家庭全体の空気も知らず知らずのうちに重たくなっていきます。
結果として、
子どもが親の顔色をうかがい、話しかけづらくなる。
親も感情的な対応が増え、冷静な対話が難しくなる。
パートナーとの間にも不満が募り、関係がギクシャクしやすくなる。
など、本来は小さなはずの1つの悩みが、家庭内に「複数の根深い問題」となって広がってしまうのです。
このように、思考のクセは仕事や家庭生活において様々な悪影響を引き起こします。では、どうすればこの負の連鎖を断ち切り、目の前の問題をシンプルに捉え直すことができるのでしょうか。その具体的な方法として、次にご紹介したいのが「思考の分離」という考え方です。
1つの問題を“1つのまま”にして解決する「思考分離」のススメ
「思考の分離」とは、文字通り、頭の中でごちゃ混ぜになっている思考や感情を、一つひとつ丁寧に分けて整理するアプローチです。物事を不必要に複雑にせず、できるだけ"1つずつ"の要素に分解して捉えることで、問題解決の糸口を冷静に見つけ出すことを目指します。
◆仕事での思考分離の実践
先ほどの、上司から注意された場面で試してみましょう。
【事実】:(提出物の)締切に間に合わなかった。
【感情】:注意されて悔しかった、申し訳なかった。
【解釈】:(この一度のミスで)上司は私を評価していないかもしれない。
【不安】:今後のキャリアがどうなるか心配だ。
このように、思考や感情を層ごとに客観的に分けてみると、「まず対応すべきは、『締切に間に合わせる』という具体的な行動目標であり、そのための締切管理の方法を見直すことだ」という、やるべきことが明確になります。
例えば、具体的な行動としては、「すべてのタスクを洗い出して細分化し、それぞれに現実的な所要時間とデッドラインを設定する」「手帳やタスク管理アプリに、作業完了日だけでなく作業開始日も記入し、視覚的に管理する」「週の初めや毎朝、タスクの進捗を確認する時間を設け、遅れが出そうなら早めに上司や同僚に相談し、調整する」といった具体的なステップが考えられます。
そして、「感情」や「解釈」「不安」は、それが事実とは異なる可能性を認識し、一度脇に置いておくことで、冷静に本来の問題と向き合えるようになるのです。
◆子育てでの思考分離の実践
子どもが朝、なかなか着替えない場面でも応用できます。
【事実】:子どもが今朝、着替えに時間がかかった。
【感情】:私はイライラした、焦った。
【解釈】:「私の育て方が悪いのかもしれない」というのは、今の感情からくる自分の意味づけ。
【不安】:「この子は将来自立できないかも」というのは、今の状況からくる未来への飛躍した心配。
まず「事実」と、それに対する自分の「感情」を認識する。そして、そこから生まれた「解釈」や「不安」を切り離して考えると、いよいよ「子どもの朝の準備をスムーズにする」という具体的な目標に対する対処法が見えてきます。
例えば、「前日の夜、明日着る服やカバンの中身などを子どもと一緒に選び、手の届く場所にセットしておく」「朝の支度の手順(顔を洗う→着替える→朝ごはんなど)をイラストや写真でリスト化し、壁に貼って、できたらシールを貼るなどゲーム感覚で進められるようにする」「『この服に着替えたら、大好きなアニメの歌をかけようね』といった、小さな楽しみを準備の節目に用意しておく」など、具体的な行動レベルに落ち着き、親子で楽しみながらシンプルに取り組めるようになります。
思考の分離を実践することで、問題の見え方や取り組み方がこのように変わってきます。では、これが習慣になると、さらにどのような良い変化が期待できるのでしょうか。
“思考分離”すると、どのような良いことが起こるのか?
◆仕事において得られる効果
問題の優先順位が明確になり、何から手をつけるべきか迷わず、対応が早くなる。
不要な感情の引きずりが減り、気持ちの切り替えが上手くなる。
他人の言動に過敏に反応したり、深読みしすぎたりすることが減る。
客観的に状況を判断できるようになることで、少しずつ自信を取り戻せる。
◆子育てにおいて得られる効果
「私はダメな親かもしれない…」といった過度な自己否定や罪悪感が減る。
子どもに対して感情的に怒るのではなく、冷静に、そして具体的に対応できるようになる。
親が感情に振り回されないことで、家庭全体の空気が穏やかで安定したものになる。
親の安定感が子どもにも伝わり、子どもも安心して自分の気持ちを表現できるようになる。
「悩みがあること」自体は、決して悪いことではない
「悩みがあること」自体は、決して悪いことではありません。それは私たちが真剣に物事に向き合っている証でもあります。 けれど、その悩みを自分の中で必要以上に重く、そして複雑にしてしまうことで、自分を責めすぎたり、次の一歩が踏み出せなくなったりするのは、とてももったいないことです。
もし今、たくさんの悩みに押しつぶされそうだと感じたら、そんな時こそ、ご自身の頭の中にそっと問いかけてみてください。
「この悩みは、いくつの問題が混ざり合ってできているのだろう?」
思考を丁寧に整理し、分けること。それは、心を軽くし、重荷を下ろすこと。 そして、変化を恐れず「人生を再び動かす力」を自分自身に取り戻すための、もっともシンプルで強力な習慣なのです。