奥の細道、お遍路...なぜ人は歩き続けるのか? 経験者が語る「ロングトレイル」の深い魅力
2025年07月01日 公開 2025年07月03日 更新

真ん中が土屋智哉さん、その右に座るのが中村純貴さん
6月27日、「東京アウトドアショー」のトークイベントに、アウトドアに深く関わり、その魅力を発信し続けている二人が登壇した。三鷹のハイキング専門店「ハイカーズデポ」店主・土屋智哉さんと、アウトドアブランド「山と道」に所属する"JK"こと中村純貴さんだ。
テーマは、ロングトレイル――自然の中を何日もかけて歩く長距離トレイルの魅力、そして「歩く」という行為そのものが持つ根源的な意味について。さらに、軽量装備の哲学「ウルトラライト」にも話題が及び、持ち物の選び方や食料計画といった実践的な知見も語られた。
経験豊富な二人が語る「歩く旅」の本質とは?そのトークの模様をレポートする。
ロングトレイルとは何か?
北米で発祥し、100年以上の歴史をもつロングトレイル。東海岸のバーモント州で生まれたバーモント・ロングトレイルや、アパラチアントレイルといった数千km単位の道が存在し、多くのハイカーたちを魅了してきた。
ロングトレイルが生まれた背景には、都市化や経済成長へのカウンターアクションとして「自然に回帰しよう」という人々の思想があるそう。
「パシフィック・クレスト・トレイル(略称PCT)では、メキシコ国境からカナダ国境を目指して4,000kmを歩きます」と語るのは中村さん。その道のりには自然との対話だけでなく、日々の出会いや偶然の積み重ねも含まれている。
ロングトレイルには距離や時間などの縛りはなく、「1週間歩くこと」をロングトレイルと言う人もいれば「1000キロ以上歩くこと」をそう定義する人もいるといいます。
「ロングトレイルを歩く人は、基本的にひとり。でも、歩くリズムが合う人と自然と一緒になるんです」と中村さんは話す。くっついたり離れたりを繰り返しながら、誰かと歩調を合わせていくうちに、自然と親しい関係性になっていくという。
登山とロングトレイルの違い
「登山とロングトレイルの違いは?」という問いに、土屋さんは「補給の存在」と答えた。
登山が「山に登って歩き切る」行為であるのに対し、ロングトレイルは「山脈から山脈へ歩き、町で食料などを補給しながら、歩き続ける旅」だという。ただ、必ずしも山に入る必要はなく、例えばビーチなど、自然の中を歩き続けることもそれにあたるらしい。
テーマを持って歩くことも面白いと話す。国内でいえば松尾芭蕉の奥の細道を辿ってみたり、アメリカであれば西部開拓の歴史とリンクさせながら歩いてみたり、自由な発想で歩くことを楽しめるのだ。
一方、中村さんはロングトレイルにおいてハイカー同士の出逢いに重きを置いているという。
「最初に歩いたのが、パシフィック・クレスト・トレイルなんですけど、ドイツ人の21歳ぐらいの子と、僕は当時26歳で、ちょっとした挨拶から始まり、一緒に2ヶ月半ぐらい歩くことになりました」
"トレイルファミリー"という造語もあるように、長期間ともに歩いているうちに家族のような関係性になっていくことも、誰かと歩くロングトレイルの醍醐味かもしれない。
「ウルトラライトハイキング」とは何か
食料はどれくらい持ち歩くのか。トレイル中は仕事ができず資金面で厳しいため、基本的には袋麺などの簡単な食事で済ませるという。
「水分を含まない、できるだけ軽量なものを選びます。日本の山小屋に行っても、カップヌードルが販売されていることが多いですよね」と中村さん。
また、現地のスーパーにも立ち寄るため、パンやベーグルなど、安価で軽く、どこでも手に入りやすいものが食料の中心になるという。
「日本を歩くと本当に楽です。コンビニとかやっぱあのフリーズドライ系の食料がものすごい充実しているから」と中村さんは語る。
アメリカでは、日本と比べて山小屋の数が圧倒的に少なく、食料の調達が難しい場面も少なくないという。
ロングトレイルに出るにあたり、仕事はどうしているのか。
「コロナ禍以降はリモートワークも定着し、働き方も変わってきたので、自分が最初に行った約20年前に比べると、休職するとか、社会的にもいろんな体験には価値があると思ってもらえるようになってきていると思う」と土屋さんは話す。
また、リュックの大きさも人によってさまざまだ。中村さんは50リットルのリュックを使用しているが、土屋さんは、最後に歩いたアメリカのトレイルをわずか36リットルのリュックで歩き通した。着替えは一切持たず、着ている服だけで過ごすことで荷物を最小限に抑えているのだという。
必要な容量は、歩く期間やスピードによっても変わってくる。
そうした背景もあり、ハイカーたちの間では荷物の軽量化を追求する「ウルトラライトハイキング」という思想が広がっている。水や食料を除いた装備の重量を4.5kg以内に抑えるのが基本とされるが、その実践者である土屋さんはこう語る。
「持っていくべきものを持っていかないんじゃなくて、長く歩くことにフォーカスを当てているから、その必需品だけに絞る感じだと思います。例えば、キャンプを楽しむためだったら、キャンプ場で楽しむためのものをたくさん持っていくのが、正しいと思うんですね。
一方で長く歩くためには、基本的にテント、寝袋、マット、それから炊事道具と雨具・防寒着、ファーストエイド、ヘッドライト、モバイルバッテリーみたいな感じになると思うんですけど。それから着替えをワンセット持つか持たないかですね。でも『ああ、これで生活できるんだ』って感覚になっていくんです」
過酷に見えるロングトレイルは「楽しむこと」が最優先
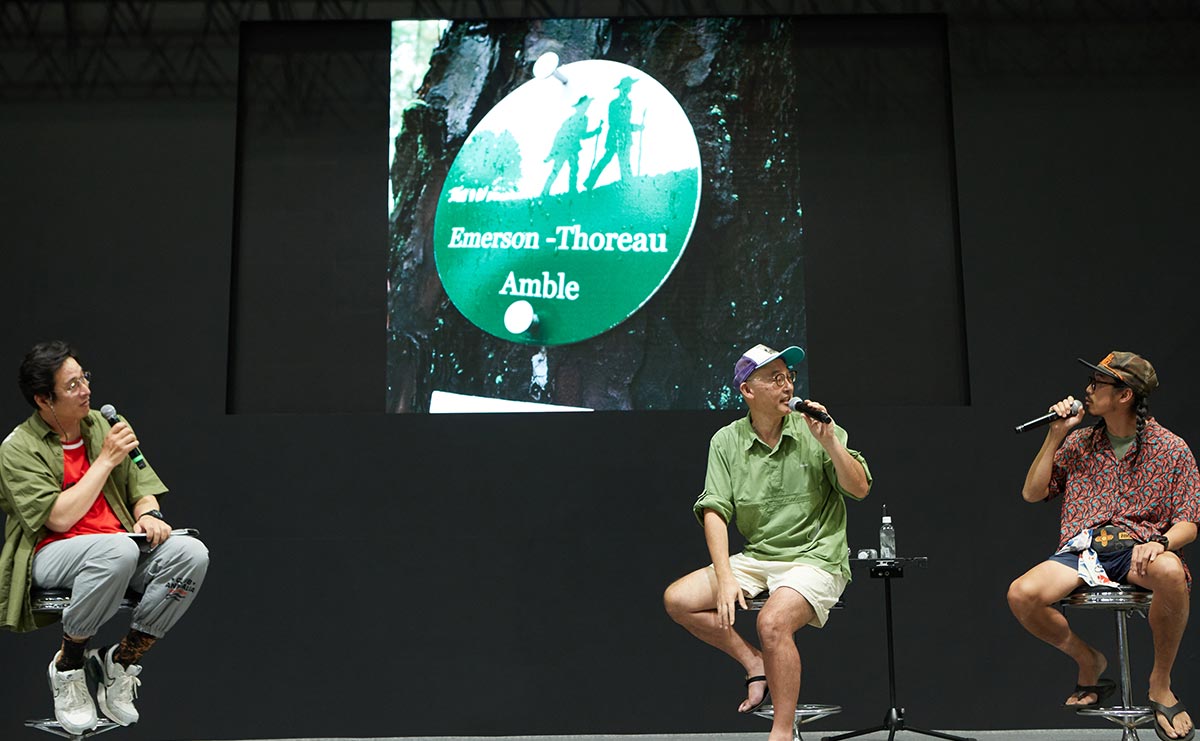
『森の生活』の著者、ヘンリー・デイヴィッド・ソローが暮らした家を、土屋さんが訪れた時の写真。ソローはアウトドアの源流の一つともいわれる
一見すると修行のようにも思えるロングトレイルだが、中村さんは過酷な環境の中で得た気づきをこう話す。
「僕は毎日ラーメンを食べてたんですけど、日常でいうとそんなにおいしいものではないですよね。でも毎日4,50kmぐらい歩いてたりすると、それがとにかく美味しい。たまに贅沢する日なんかは、バターひとかけら入れたり。それだけですごい幸せなんですよね。
普段はいろんなものに囲まれていますけど、実は自分自身が幸せになるのに、たくさんのものいらないんだな、みたいなことに気づきました」
お二人によれば、ロングトレイルの根底にあるのは「楽しむこと」。歩いて国境を越えるという非日常の体験や、圧倒的な自然の美しさを全身で感じられること、そして人との出会いが何よりの魅力だという。体力的に不安があれば、無理せず途中で引き返しても構わない。旅として心から満足できるなら、それで十分なのだ。
最後に、お二人それぞれが初心者におすすめのトレイルコースを教えてくれた。
土屋さんが挙げたのは、長野県飯山市を中心に広がる「信越トレイル」だ。
「もし日本で長く歩いて、山里の景色も見たいっていうなら飯山にある信越トレイルを歩いてみるのがいいんじゃないのかなと。
山道もしっかりと歩けるし、秋山郷っていう、いわゆる日本らしい風景を見ることができるので。距離も120kmくらいなので、(ロングトレイルの)とっかかりとしてはいいんじゃないかなと思います」
一方、中村さんは王道をすすめる。
「初心者の人であれば、"THE"なところだと、やっぱり北アルプスに行くのが一番手っ取り早いんじゃないかなと思います。その登山口行くまではヒッチハイクでいってみるとか、そういうところで旅の要素を入れるっていうのも面白いかなと思います」
ロングトレイルとひと口に言っても、歩く理由や魅力の感じ方は人それぞれだ。美しい景色や人との出会い、そして日常では味わえない"歩く旅"の喜び。ロングトレイルは、そんな体験を通じて、自分自身と深く向き合うきっかけになる旅だ。
















