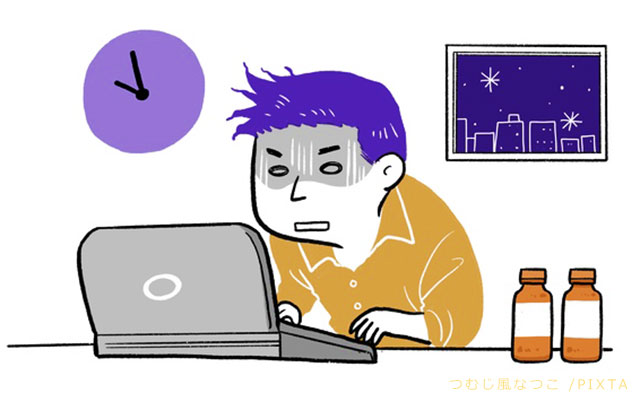テレワークの残酷な現実…居場所を失う「働いているフリ」していただけの社員
2020年07月03日 公開 2024年12月16日 更新

新型コロナウイルス感染拡大、緊急事態宣言期間を経て、一躍注目されるようになったテレワーク。もともと下地があったためスムーズに実行できた企業が脚光を浴びた一方、大半の企業は急な対応を迫られたのが現実だ。紙を使った事務作業や、不慣れなオンラインでのやりとりへの抵抗など、さまざまな理由で導入が進まなかったケースは少なくない。
社会レベルで働き方の移行が進むと、評価される人材の姿もこれまでと変わってくる。そう語るのは、テレワークに必要な基礎知識をまとめた新刊『テレワークをはじめよう』(テレワーク生産性向上研究会 著)で法律監修を務める弁護士の藤井総氏。同氏によれば、テレワークが広まった社会では、優秀な人材の定義が変わるだけでなく、組織に必要とされる人とそうでない人の差が大きくなっていくという。
テレワークが普及した世の中で、評価される人とされない人の違いは何か? 対応できなかった人には、どのような未来が待っているのか? 今回は、これから着実に進行する「人材の二極化」について解説した、藤井氏の特別寄稿を掲載する。
(記事提供:Gihyo.jp)
テレワーク対応に四苦八苦する企業
2020年4月7日に政府から緊急事態宣言が出されたことにより、企業はテレワークの導入を余儀なくされた。
すでに2〜3年前から、東京オリンピック(延期されてしまったが)期間中の混雑緩和や、少子高齢化に伴う地方人材の活用、子育て・介護と仕事の両立、多様な働き方を認めることによる優秀な人材の確保など、さまざまな文脈の中でテレワークの必要性は認識されていた。
今回のコロナ禍においても、就業規則や運用ルールの整備、研修などすでに取り組みを進めていた企業は特に影響を受けなかった一方で、(職種としてテレワークが可能であるにも拘らず)さまざまな理由を並べてテレワークに後ろ向きだった企業は、対応に四苦八苦することになった。
著名な大企業でありながら、感染の危険を承知の上で輪番出社させたり、全社員を自宅待機にしたのはいいが、社員はメールチェックくらいしかできず、事実上、業務が止まってしまった企業もあったようだ。
もっとも、5月25日に首都圏と北海道で緊急事態宣言が解除され、テレワークをしていた人たちが出社を再開できるようになり、そのような企業は胸を撫で下ろしているだろう。
テレワークへの「賛否」 調査の結果は?
そのような中、Googleは約3000人のオフィスワーカーを対象に4月28日〜30日に実施したテレワークの意識調査の結果を発表した。
調査の結果、新型コロナウイルス拡大の懸念が収まった後も、テレワークを「続けたい」「やや続けたい」と答えた人は49.3%で、「続けたくない」「あまり続けたくない」の23.1%を大きく上回ることになった。
同様に、日本生産性本部が1100名の雇用者を対象に5月11日〜13日に実施した意識調査の結果でも、新型コロナウイルス収束後もテレワークを継続したいかについては、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」と答えた人は62.7%だった。
なぜこれだけ多くの人たちからテレワークが支持されたのか。さまざまな調査結果を見るに、通勤ラッシュから解放されたことや、通勤時間が無くなった分プライベートの時間が増えたことなどが歓迎されているようである。しかし、それだけの理由でテレワークを続けたいと考えているなら、考えを改める必要がある。
緊急事態宣言は一旦解除されたものの、再度感染が拡大して医療機関が逼迫する事態になれば再指定はあり得るし、そもそも、新型コロナウィルスに関係なく社会はテレワークに向かって進んでいる。では、今以上にテレワークが進んだ社会では、労働のあり方はどう変化していくのだろうか。
次のページ
テレワークで評価が「下がる人」と「上がる人」の違い