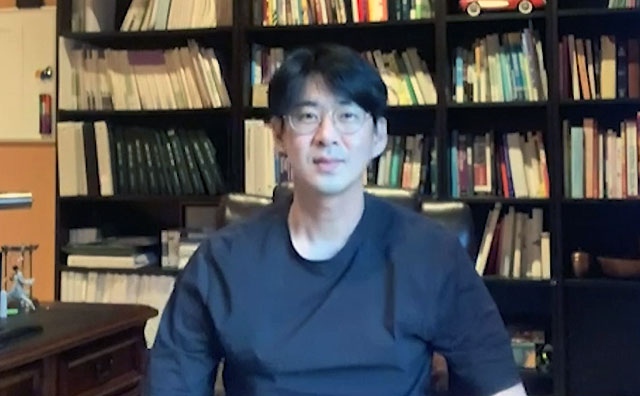「正義」とはトラウマのようなものだ
2008年11月10日 公開 2024年12月16日 更新

この連載は、映画、漫画、小説といった、さまざまなジャンルのフィクション作品を毎回いくつか取り上げ、そこに反映された現代社会の様相を読み解くことが目的である。
それはさしあたり、作品をあえて社会反映論的な視点から解読しようという試みでもある。しかしもちろん、それだけではない。
すぐれた作品は、しばしば時代を先取りする。あたかも作者の自意識を超えるようにして、それは起こるだろう。
自作においてしばしばそうした現象と向き合っ てきた作家の桐野夏生は、虚構のリアリティは「現実」に拮抗しうるという自らの信念を語っている。本連載のタイトルは、直接にはこの桐野氏の発言に想を得たものだ。
そう、いまや虚構は現実なのである。まったく同じ意味で、現実は虚構である、と言い換えてもよい。
私はかつて、次のように書いた。「いまや『現実』はスティーヴン・キングとスティーヴン・ホーキングとの間にある」と。
ホラーとファンタジーの「虚構世界」をこのうえなくリアルに描き出すキングと、「現実世界」を数式によって果てしなく抽象化、すなわち虚構化してみせる ホーキング。
2人のスティーヴンが同じように読まれ、消費される現代にあって、はたして「虚構」と「現実」との間に明瞭な境界線を引きうるものだろうか。
もちろん、答えは「否」である。
「リアル」についても同様のことが指摘できる(【註】ちなみに日本語では慣用的に「リアリティ=現実らしさ」という意味で使用されるが、英語的に は"real"が「現実の、現実らしい」という形容詞であり、"reality"のほうが名詞としての「現実」である。
よって「現実」そのものではない 「現実らしさ」を意図する場合、本論では「リアル」で統一する)。
いまや「リアル」は、精神分析と脳科学との間にある。どういうことだろうか。
精神分析、とりわけ私がしばしば依拠するラカン派のそれは、われわれの「日常的現実」を「想像的なもの」とみなす。些末な話はややこしいので省略するが、 ラカン派のいう「現実」とは、日常語の「現実」とはまったく別の意味をもつ言葉なのだ。
それは絶対に認識不可能でありながら、われわれの生きる「日常的現 実」に対して、つねに影響を及ぼさずにはおかないような次元のことを指している。「意識」に対する「無意識」のような位置づけ、といえば、多少は理解しや すくなるだろうか。
つまり、ラカン派の立場から見れば、さきほど紹介した桐野夏生の言葉はすでに自明の前提なのである。いわゆる「虚構」と「現実」との間に、本質的な区別な ど存在しない。ウソみたいな現実もあれば、現実以上にリアルな虚構も存在する。われわれにその区別を可能にしているのは、端的に「リアルの濃淡」という 「程度の判別」にすぎないのだ。メディア・リテラシーとは、この「リアルの濃淡」に関する判断力を指すと考えて、ほぼ間違いない。
いっぽう脳科学にとっては、あらゆることが「現実」である。
これも解説が必要となるだろう。脳科学者は基本的に、人間の精神活動を、脳内物質の分布やニューロンの発火パターンなどに還元可能であると考える。この発 想なくして「脳科学」は成立しない。ということは、人間にとってあらゆる感覚刺激は、それが虚構由来であれ現実由来であれ、脳に物質的な変化を起こす、と いう点では「現実」なのである。よって、脳科学的に考えても、「虚構」と「現実」の区別は存在しない。
茂木健一郎がかつて随所で引用していた「クオリア」なる概念には、どうやら(将来的には)数量化可能な程度差があるようで、「クオリアのピュアさ」や「強 度」が問われるようだ。つまり脳科学的な視点からは、クオリアの程度をもって「虚構」と「現実」が区分可能であるかもしれないのだが、その可能性につい て、むろん私は懐疑的である。
「リアル」の位相
「現実」と「虚構」の区分が限りなく曖昧化しつつある現在、真に問われるべきは「リアル」の位相 である。もう1度確認しておこう。いまやリアルを担保するものは、ナマの「現実」などではない。さまざまな論者が「現実」そのものよりも「リアル」を論じ つつあるのが、その第1の徴候だ。
大塚英志の言う「まんが・アニメ的リアリズム」、私が指摘した虚構内限定のヒロインである「戦闘美少女」のリアル、東浩紀による「ゲーム的リアリズム」、 いずれもそうした状況を反映した、一次的には「現実」を担保としない、特異なリアルの形式である。
はっきりと明言されているわけではないが、これらの論点に共通するのは、いまや「リアル」を構成するメカニズムが、「何がリアルか」を確認させてくれるような、再帰的コミュニケーション以外には存在しない、という視点だ。
早い話が、いま若者集団でもっともリアルな同一性として流通しているのは「キャラ」である。そう、「キャラ変わった?」「キャラを使い分けてる」「キャラ がかぶるから」などと使用される、場面限定のペルソナとしての「キャラ」。およそ「自己同一性」や「固有性」といった議論からもっとも遠い軽薄な言葉、 「キャラ」。しかしこれこそが、多くの若者が日常を生き抜くために必要とされる「リアル」なのである。
「キャラ」は、ある種の個性であると同時に、きわめて効率的なコミュニケーション・ツールでもある。相互のキャラを認知することで、「関係性」は瞬時に定 まる。そう、キャラとはあらかじめ「関係性」が畳み込まれた記号であり、それはコミュニケーションを介していっそう強化されるのだ。これこそが「キャラの リアル」である。
本来、「キャラ」は、「リアル」の端的でわかりやすい例にすぎない。むしろわれわれはこういうべきなのだ。いまや「リアル」のあらゆる局面が、コミュニケーションを介して構成されつつある、と。
「コミュニケーション」にも「情報」にも、確固たる基盤など存在しないはずだ。しかし人々は、そこに否応なしの「リアル」を見てしまう。その意味で、現代 を「コミュニケーション幻想」と「情報幻想」が覇権を握った時代と見ることもできるだろう。もちろん、「それを指摘する私だけは例外」とはならない。むし ろこの幻想は、「自分だけは幻想のメタレベルに立ち得た」と思い込んだ者をこそ、もっともよく侵すものであるからだ。
すでに理解されるとおり、あらゆる「フィクション」もまた、それ自体が「情報」であり「コミュニケーション」でもある。たとえばこの連載で後日取り上げる 予定の「ケータイ小説」は、それがどれほど軽蔑されバカにされようとも、作品を媒介とした膨大なコミュニケーションが存在する限りにおいて、無視しがたい 「リアル」さをはらむ。いまやいかなる批評も、「美」や「伝統」、「技術」といった基準以上に「リアル」を優先せざるを得ない状況が到来しつつあるのだ。
この連載で私が「フィクション」と向き合う態度は、以上のような現状認識を前提としている。それは「フィクションも時には現実の鏡たりうる」というような 消極的姿勢ではない。「ひょっとすると、フィクションを介してしか、もう現実とは向き合えないのではないか」という不安と切迫感。これこそが、私をして フィクションに向かわせる当のものなのだ。
いささか長すぎる前置きになってしまったが、これでも必要最低限の前提を確認したにすぎない。最後に蛇足を一言つけ加えて終わりにしよう。「虚構と現実を 混同」うんぬんという紋切り型がいまだに存在するが、もし何の留保もなしにこの言い回しを用いるならば、それはいまや、端的な「メディア・リテラシーのな さ」の暴露にすぎない。本連載のタイトルが、そうした態度への挑発を目指してつけられたことはいうまでもない。