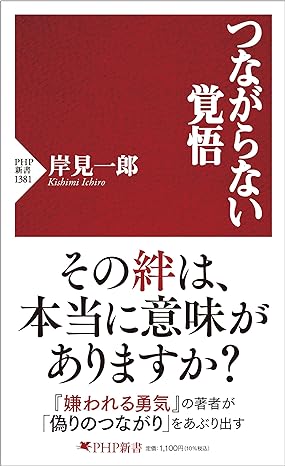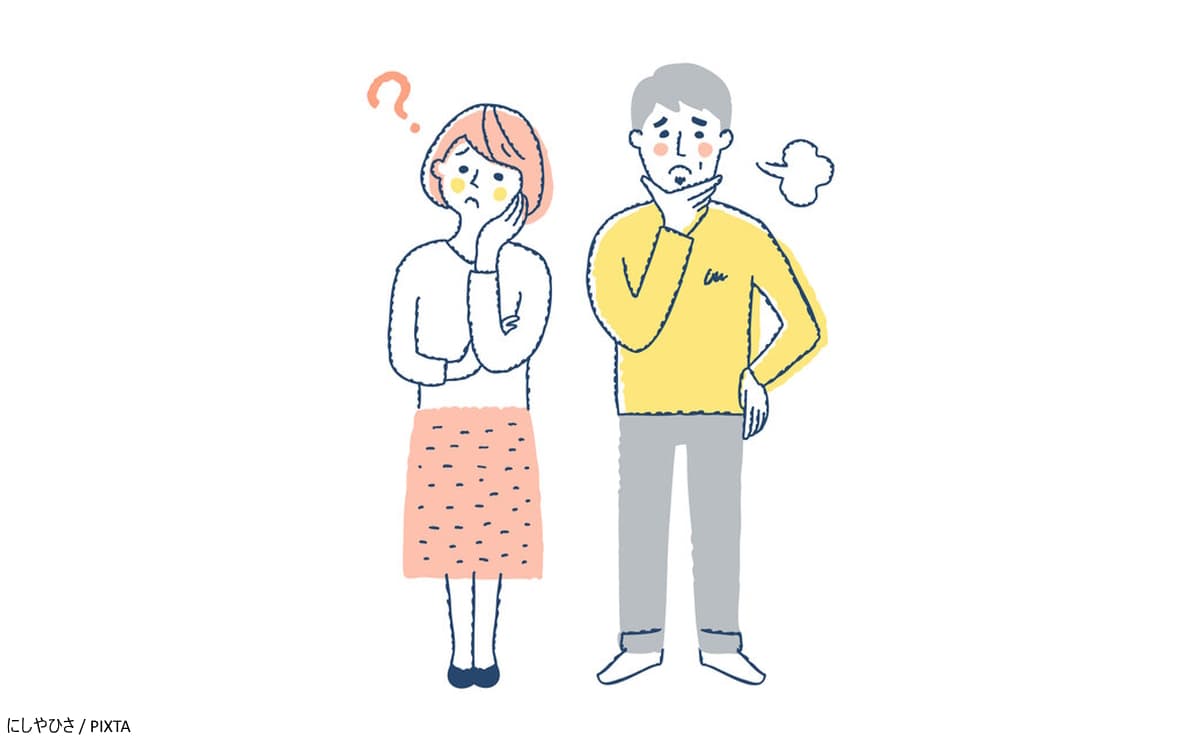多くの人が仕事にまい進し、物事を成し遂げようと努力を重ねている。しかし、何かしらの成果を上げることだけが「幸福」なのか? 生きていく上で本当に大切なことについて、哲学者の岸見一郎氏が語る。
※本稿は、岸見一郎著『つながらない覚悟』(PHP新書)を一部抜粋・編集したものです。
本当に大切なこと
心筋梗塞で倒れ入院した時、看護師さんの一人が私にこんなことを語った。
「ただ助かったで終わる人もおられるのですけどね。でも、これからのことを考えゆっくり休んで、若いのですから、もう一度生き直すつもりで頑張りましょう」
私はその言葉を聞いて、退院してからの人生で何が重要かを考え、生き直す決心をした。
それは端的にいえば、「生きること」である。最近妻を亡くしたばかりだという男性がインタビューに答えているのをテレビ番組で見たことがある。その人は仕事などどうでもよかったと語っていた。仕事と妻との優先順位が変わったのである。
かつて、ある会社の役員研修で講演をしたことがあった。研修というのは講演者の話を聞きたいと思って参加しているわけではないので、その日私が講演した時も、大方の人はつまらなそうに聞いているように見えた。
ところが、「人は働くために生きているのではなく、生きるために働いているのである」と話したところ、多くの人が、急に熱心になり、中には身を乗り出して聞き始めた人もいた。
人は働くために生きているのではないというと、働かなければ食べていけないではないかと反発する人は多い。
たしかにその通りだが、過労で倒れたり、転勤で家族が離れ離れになったりすると、一体何のために働いているかわからなくなる。
会社は社員に会社とつながることを求めるかもしれないが、自分の人生こそが大切であり、つながるべきなのは会社ではない。身を粉にして働くことが幸福とは感じられないのは、真につながるべき人とつながっていないからである。
生きることに価値がある
三木清は、次のようにいっている。
「幸福が存在に関わるのに反して、成功は過程に関わっている」(『人生論ノート』)
何も成し遂げなくても、今生きていることがそのままで幸福で「ある」という意味である。人は生きるために働いているという時の「生きる」というのは、そのまま「幸福に生きる」を意味している。生きていることが幸福であるのであれば、働こうと働くまいとそもそも人は幸福で「ある」。
そうであれば、働いているのに幸福でないというのはおかしい。人生には幸福を犠牲にしてまで成し遂げなければならないというようなことはないからである。研修の時に私の講演を聞いていた役員たちは、皆若い時からずっと身を粉にして働いてきたのだろう。
そのように働いてきたのは、他者との競争に勝って昇進して成功するためだったであろう。実際、競争に勝って成功したのである。会社に入る前も、名門大学に合格するということを目指して一生懸命勉強したのは、成功するためだった。
引用文の後半で、三木は「成功」は過程に関わるといっている。三木のこの言葉の使い方は特別であり、普通の意味とは違う。今生きていることが幸福であるのに対して、成功は何かを成し遂げなければならないという意味である。幸福が今という点であるとしたら、成功は直線、成功するためにはそれに至る過程を経ることが必要である。
問題は、成功するかはわからないし、何かを達成して成功したとしてもそれで終わりにはならないことである。また、次の目標がすぐに現れる。そうすると、成功することが幸福だと考えていた人は束の間の幸福を感じられるかもしれないが、また次の目標を目指して働かなければならなくなる。成功は蜃気楼のようなものである。成功したと思っても、たちまち消え去ってしまう。
そして、瞬く間に定年を迎える。働いて成功を収め続けていた間は自分に価値があると思っていた人が、定年で仕事を辞めると、自分にはもはや価値がないと思うようになる。何かを成し遂げることに自分の価値を見出してきたからである。
ある80歳代の銀行の頭取まで務めた男性が脳梗塞で入院した。その人は身体を動かせなくなり、もはや生きていくことに価値はないと絶望し、「殺せ」と叫び続け家族を困らせた。
もちろん、その人が生涯身を粉にして働き、頭取まで勤め上げた人生に価値がなかったわけではない。しかし、仕事を辞め身体が動かせなくなっても、価値がなくなるわけではなく、生きていることに価値がある。それは働いている時と同じである。仕事をしている時には自分に価値があると思えるだろうが、その時でも働いているから価値があるのではない。
誰もが働けるわけではない。働いていても必ず成功するとは限らない。老齢や病気のために働けなくなることがある。若い人でも病気になり、働けなくなるかもしれない。
だが、そのようなこととは関係なく、何があろうと、生きているだけで自分には価値があり幸福であると感じることができれば、働いていてもいなくても、日々の生活の中で幸福を感じることができる。そして、定年や他の事情で仕事を辞め、その結果、多くの人とのつながりが絶えることになったとしても、そのことで、自分の価値がなくなり不幸になるわけではない。
老後のつながりの強制
しかし、そのように思えず、老後、あるいは定年後も何かをしなければならない、人とつながり、そのためには趣味を持った方がいいと考える人は多い。そのような生き方を否定しようとは思わないが、人とのつながりはあった方がいいと勧められるようなことがあれば、これもつながりの強制である。
地域のコミュニティに入ってみても、もはや肩書がまったく意味を持たないことに馴染めず浮いてしまう。仕事を辞めたからといって、必ず人とのつながりの中に入っていく必要はない。
一度、つながりから解き放たれ、競争や評価から自由になって、ゆっくりどう生きていくかを考えるといい。
私の高校生の時の倫理社会の先生が、仕事を辞めたら、若い時に買いためた本を読むといっていたことをよく覚えている。残念ながら、先生は定年を迎える前に亡くなったので、このような老後を送ることはできなかったのだが。
仕事を辞める前にも2つのことができる。まず、仕事を辞める前でも、現実的には時間などの制約はあるだろうが、やってみたいことがあればためらわずに手がけることである。人とつながるためではない、純粋に好奇心から始めたことがあれば定年を迎えることが不安ではなくなる。
次に、人間の価値は生産性や経済的有用性にあるのではないと知ることである。病気になれば否が応でも考えないわけにはいかないが、病気にならなくても、常識とは違う考え方があることを知っているだけで人生は違ったものになるだろう。